八
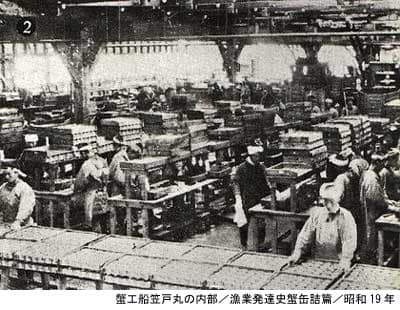 表には何も出さない。気付かれないように手をゆるめて行く。監督がどんなに思いッ切り怒鳴り散らしても、タタキつけて歩いても、口答えもせず「おとなしく」している。それを一日置きに繰りかえす。(初めは、おっかなびっくり、おっかなびっくりでしていたが)――そういうようにして、「サボ」を続けた。水葬のことがあってから、モットその足並が揃(そろ)ってきた
表には何も出さない。気付かれないように手をゆるめて行く。監督がどんなに思いッ切り怒鳴り散らしても、タタキつけて歩いても、口答えもせず「おとなしく」している。それを一日置きに繰りかえす。(初めは、おっかなびっくり、おっかなびっくりでしていたが)――そういうようにして、「サボ」を続けた。水葬のことがあってから、モットその足並が揃(そろ)ってきた
仕事の高は眼の前で減って行った。
中年過ぎた漁夫は、働かされると、一番それが身にこたえるのに、「サボ」にはイヤな顔を見せた。然し内心(!)心配していたことが起らずに、不思議でならなかったが、かえって「サボ」が効(き)いてゆくのを見ると、若い漁夫達の云うように、動きかけてきた。
困ったのは、川崎の船頭だった。彼等は川崎のことでは全責任があり、監督と平漁夫の間に居り、「漁獲高」のことでは、すぐに監督に当って来られた。それで何よりつらかった。結局三分の一だけ「仕方なしに」漁夫の味方をして、後の三分の二は監督の小さい「出店」――その小さい「○」だった。
「それア疲れるさ。工場のようにキチン、キチンと仕事がきまってるわけには行かないんだ。相手は生き物だ。蟹が人間様に都合よく、時間々々に出てきてはくれないしな。仕方がないんだ」――そっくり監督の蓄音機だった。
こんなことがあった。――糞壺で、寝る前に、何かの話が思いがけなく色々の方へ移って行った。その時ひょいと、船頭が威張ったことを云ってしまった。それは別に威張ったことではないが、「平」漁夫にはムッときた。相手の平漁夫が、そして、少し酔っていた。
「何んだって?」いきなり怒鳴った。「手前(てめ)え、何んだ。あまり威張ったことを云わねえ方がええんだで。漁に出たとき、俺達四、五人でお前えを海の中さタタキ落す位朝飯前だんだ。――それッ切りだべよ。カムサツカだど。お前えがどうやって死んだって、誰が分るッて!」
そうは云ったものはいない。それをガラガラな大声でどなり立ててしまった。誰も何も云わない。今まで話していた外のことも、そこでプッつり切れてしまった。
然(しか)し、こういうようなことは、調子よく跳ね上った空元気(からげんき)だけの言葉ではなかった。それは今まで「屈従」しか知らなかった漁夫を、全く思いがけずに背から、とてつもない力で突きのめした。突きのめされて、漁夫は初め戸惑いしたようにウロウロした。それが知られずにいた自分の力だ、ということを知らずに。
――そんなことが「俺達に」出来るんだろうか? 然し成る程出来るんだ。
そう分ると、今度は不思議な魅力になって、反抗的な気持が皆の心に喰い込んで行った。今まで、残酷極まる労働で搾(しぼ)り抜かれていた事が、かえってその為にはこの上ない良い地盤だった。――こうなれば、監督も糞もあったものでない! 皆愉快がった。一旦この気持をつかむと、不意に、懐中電燈を差しつけられたように、自分達の蛆虫(うじむし)そのままの生活がアリアリと見えてきた。
「威張んな、この野郎」この言葉が皆の間で流行(はや)り出した。何かすると「威張んな、この野郎」と云った。別なことにでも、すぐそれを使った。――威張る野郎は、然し漁夫には一人もいなかった。
それと似たことが一度、二度となくある。その度(たび)毎に漁夫達は「分って」行った。そして、それが重なってゆくうちに、そんな事で漁夫達の中から何時(いつ)でも表の方へ押し出されてくる、きまった三、四人が出来てきた。それは誰かが決めたのでなく、本当は又、きまったのでもなかった。ただ、何か起ったり又しなければならなくなったりすると、その三、四人の意見が皆のと一致したし、それで皆もその通り動くようになった。――学生上りが二人程、吃(ども)りの漁夫、「威張んな」の漁夫などがそれだった。
学生が鉛筆をなめ、なめ、一晩中腹這いになって、紙に何か書いていた。――それは学生の「発案」だった。
発案(責任者の図)
A B C
| | |
二人の学生 ┐ ┌雑夫の方一人 国別にして、各々そのうちの餓鬼大将を一人ずつ
│ │川崎船の方二人 各川崎船に二人ずつ
吃りの漁夫 │ │水夫の方一人┐
│ │ │ 水、火夫の諸君
「威張んな」┘ └火夫の方一人┘
A――――→B――――→C→┌全部の┐
←―――― ←―――― ←└諸君 ┘
学生はどんなもんだいと云った。どんな事がAから起ろうが、Cから起ろうが、電気より早く、ぬかりなく「全体の問題」にすることが出来る、と威張った。それが、そして一通り決められた。――実際は、それはそう容易(たやす)くは行われなかったが。
「殺されたくないものは来れ!」 ――その学生上りの得意の宣伝語だった。毛利元就(もうりもとなり)の弓矢を折る話や、内務省かのポスターで見たことのある「綱引き」の例をもってきた。「俺達四、五人いれば、船頭の一人位海の中へタタキ落すなんか朝飯前だ。元気を出すんだ」
「一人と一人じゃ駄目だ。危い。だが、あっちは船長から何からを皆んな入れて十人にならない。ところがこっちは四百人に近い。四百人が一緒になれば、もうこっちのものだ。十人に四百人! 相撲になるなら、やってみろ、だ」そして最後に「殺されたくないものは来れ!」だった。――どんな「ボンクラ」でも「飲んだくれ」でも、自分達が半殺しにされるような生活をさせられていることは分っていたし、(現に、眼の前で殺されてしまった仲間のいることも分っている)それに、苦しまぎれにやったチョコチョコした「サボ」が案外効き目があったので学生上りや吃りのいうことも、よく聞き入れられた。
一週間程前の大嵐で、発動機船がスクリュウを毀(こわ)してしまった。それで修繕のために、雑夫長が下船して、四、五人の漁夫と一緒に陸へ行った。帰ってきたとき、若い漁夫がコッソリ日本文字で印刷した「赤化宣伝」のパンフレットやビラを沢山持ってきた。「日本人が沢山こういうことをやっているよ」と云った。――自分達の賃銀や、労働時間の長さのことや、会社のゴッソリした金儲けのことや、ストライキのことなどが書かれているので、皆は面白がって、お互に読んだり、ワケを聞き合ったりした。然し、中にはそれに書いてある文句に、かえって反撥を感じて、こんな恐ろしいことなんか「日本人」に出来るか、というものがいた。
が、「俺アこれが本当だと思うんだが」と、ビラを持って学生上りのところへ訊(き)きに来た漁夫もいた。
「本当だよ。少し話大きいどもな」
「んだって、こうでもしなかったら、浅川の性(しょ)ッ骨(ぽね)直るかな」と笑った。「それに、彼奴(あいつ)等からはモットひどいめに合わされてるから、これで当り前だべよ!」
漁夫達は、飛んでもないものだ、と云いながら、その「赤化運動」に好奇心を持ち出していた。
嵐の時もそうだが、霧が深くなると、川崎船を呼ぶために、本船では絶え間なしに汽笛を鳴らした。巾広い、牛の啼声(なきごえ)のような汽笛が、水のように濃くこめた霧の中を一時間も二時間もなった。――然しそれでも、うまく帰って来れない川崎船があった。ところが、そんな時、仕事の苦しさからワザと見当を失った振りをして、カムサツカに漂流したものがあった。秘密に時々あった。ロシアの領海内に入って、漁をするようになってから、予(あらかじ)め陸に見当をつけて置くと、案外容易く、その漂流が出来た。その連中も「赤化」のことを聞いてくるものがあった。
――何時でも会社は漁夫を雇うのに細心の注意を払った。募集地の村長さんや、署長さんに頼んで「模範青年」を連れてくる。労働組合などに関心のない、云いなりになる労働者を選ぶ。「抜け目なく」万事好都合に! 然し、蟹工船の「仕事」は、今では丁度逆に、それ等の労働者を団結――組織させようとしていた。いくら「抜け目のない」資本家でも、この不思議な行方までには気付いていなかった。それは、皮肉にも、未組織の労働者、手のつけられない「飲んだくれ」労働者をワザワザ集めて、団結することを教えてくれているようなものだった。


























コメントを残す