七
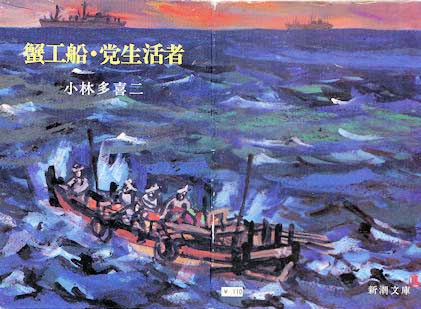 ウインチがガラガラとなって、川崎船が下がってきた。丁度その下に漁夫が四人程居て、ウインチの腕が短いので、下りてくる川崎船をデッキの外側に押してやって、海までそれが下りれるようにしてやっていた。――よく危いことがあった。ボロ船のウインチは、脚気(かっけ)の膝(ひざ)のようにギクシャクとしていた。ワイヤーを巻いている歯車の工合で、グイと片方のワイヤーだけが跛(びっこ)にのびる。川崎船が燻製鰊(くんせいにしん)のように、すっかり斜めにブラ下がってしまうことがある。その時、不意を喰らって、下にいた漁夫がよく怪我(けが)をした。――その朝それがあった。「あッ、危い!」誰か叫んだ。真上からタタキのめされて、下の漁夫の首が胸の中に、杭のように入り込んでしまった。
ウインチがガラガラとなって、川崎船が下がってきた。丁度その下に漁夫が四人程居て、ウインチの腕が短いので、下りてくる川崎船をデッキの外側に押してやって、海までそれが下りれるようにしてやっていた。――よく危いことがあった。ボロ船のウインチは、脚気(かっけ)の膝(ひざ)のようにギクシャクとしていた。ワイヤーを巻いている歯車の工合で、グイと片方のワイヤーだけが跛(びっこ)にのびる。川崎船が燻製鰊(くんせいにしん)のように、すっかり斜めにブラ下がってしまうことがある。その時、不意を喰らって、下にいた漁夫がよく怪我(けが)をした。――その朝それがあった。「あッ、危い!」誰か叫んだ。真上からタタキのめされて、下の漁夫の首が胸の中に、杭のように入り込んでしまった。
漁夫達は船医のところへ抱えこんだ。彼等のうちで、今ではハッキリ監督などに対して「畜生!」と思っている者等は、医者に「診断書」を書いて貰うように頼むことにした。監督は蛇に人間の皮をきせたような奴だから、何んとかキット難くせを「ぬかす」に違いなかった。その時の抗議のために診断書は必要だった。それに船医は割合漁夫や船員に同情を持っていた。
「この船は仕事をして怪我をしたり、病気になったりするよりも、ひッぱたかれたり、たたきのめされたりして怪我したり、病気したりする方が、ずウッと多いんだからねえ」と驚いていた。一々日記につけて、後の証拠にしなければならない、と云っていた。それで、病気や怪我をした漁夫や船員などを割合に親切に見てくれていた。
診断書を作って貰いたいんですけれどもと、一人が切り出した。
初め、吃驚したようだった。
「さあ、診断書はねえ……」
「この通りに書いて下さればいいんですが」
はがゆかった。
「この船では、それを書かせないことになってるんだよ。勝手にそう決めたらしいんだが。……後々のことがあるんでね」
気の短い、吃(ども)りの漁夫が「チェッ!」と舌打ちをしてしまった。
「この前、浅川君になぐられて、耳が聞えなくなった漁夫が来たので、何気なく診断書を書いてやったら、飛んでもないことになってしまってね。――それが何時までも証拠になるんで、浅川君にしちゃね……」
彼等は船医の室を出ながら、船医もやはり其処(そこ)まで行くと、もう「俺達」の味方でなかったことを考えていた。
その漁夫は、然(しか)し「不思議に」どうにか生命を取りとめることが出来た。その代り、日中でもよく何かにつまずいて、のめる程暗い隅(に転がったまま、その漁夫がうなっているのを、何日も何日も聞かされた。
彼が直りかけて、うめき声が皆を苦しめなくなった頃、前から寝たきりになっていた脚気の漁夫が死んでしまった。――二十七だった。東京、日暮里(にっぽり)の周施屋から来たもので、一緒の仲間が十人程いた。然し、監督は次の日の仕事に差支えると云うので、仕事に出ていない「病気のものだけ」で、「お通夜」をさせることにした。
湯灌(ゆかん)をしてやるために、着物を解いてやると、身体からは、胸がムカーッとする臭気がきた。そして無気味な真白い、平べったい虱(しらみ)が周章(あわ)ててゾロゾロと走り出した。鱗形(うろこがた)に垢(あか)のついた身体全体は、まるで松の幹が転がっているようだった。胸は、肋骨(ろっこつ)が一つ一つムキ出しに出ていた。脚気がひどくなってから、自由に歩けなかったので、小便などはその場でもらしたらしく、一面ひどい臭気だった。褌(ふんどし)もシャツも赭黒(あかぐろ)く色が変って、つまみ上げると、硫酸でもかけたように、ボロボロにくずれそうだった。臍(へそ)の窪みには、垢とゴミが一杯につまって、臍は見えなかった。肛門の周(まわ)りには、糞がすっかり乾いて、粘土のようにこびりついていた。
「カムサツカでは死にたくない」――彼は死ぬときそう云ったそうだった。然し、今彼が命を落すというとき、側にキット誰も看(み)てやった者がいなかったかも知れない。そのカムサツカでは誰だって死にきれないだろう。漁夫達はその時の彼の気持を考え、中には声をあげて泣いたものがいた。
湯灌に使うお湯を貰いにゆくと、コックが、「可哀相にな」と云った。「沢山持って行ってくれ。随分、身体が汚れてるべよ」
お湯を持ってくる途中、監督に会った。
「何処へゆくんだ」
「湯灌だよ」
と云うと、
「ぜいたくに使うな」まだ何か云いたげにして通って行った。
帰ってきたとき、その漁夫は、「あの時位、いきなり後ろから彼奴(あいつ)の頭に、お湯をブッかけてやりたくなった時はなかった!」と云った。興奮して、身体をブルブル顫(ふる)わせた。
監督はしつこく廻ってきては、皆の様子を見て行った。――然し、皆は明日居睡(いねむ)りをしても、のめりながら仕事をしても――例の「サボ」をやっても、皆で「お通夜」をしようということにした。そう決った。
八時頃になって、ようやく一通りの用意が出来、線香や蝋燭(ろうそく)をつけて、皆がその前に坐った。監督はとうとう来なかった。船長と船医が、それでも一時間位坐っていた。片言のように――切れ切れに、お経の文句を覚えていた漁夫が「それでいい、心が通じる」そう皆に云われて、お経をあげることになった。お経の間、シーンとしていた。誰か鼻をすすり上げている。終りに近くなるとそれが何人もに殖えて行った。
お経が終ると、一人々々焼香をした。それから坐を崩して、各々一かたまり、一かたまりになった。仲間の死んだことから、生きている――然し、よく考えてみればまるで危く生きている自分達のことに、それ等の話がなった。船長と船医が帰ってから、吃(ども)りの漁夫が線香とローソクの立っている死体の側のテーブルに出て行った。
 「俺はお経は知らない。お経をあげて山田君の霊を慰めてやることは出来ない。然し僕はよく考えて、こう思うんです。山田君はどんなに死にたくなかったべか、とな。――イヤ、本当のことを云えば、どんなに殺されたくなかったか、と。確に山田君は殺されたのです」
「俺はお経は知らない。お経をあげて山田君の霊を慰めてやることは出来ない。然し僕はよく考えて、こう思うんです。山田君はどんなに死にたくなかったべか、とな。――イヤ、本当のことを云えば、どんなに殺されたくなかったか、と。確に山田君は殺されたのです」
聞いている者達は、抑えられたように静かになった。
「では、誰が殺したか? ――云わなくたって分っているべよ! 僕はお経でもって、山田君の霊を慰めてやることは出来ない。然し僕等は、山田君を殺したものの仇(かたき)をとることによって、とることによって、山田君を慰めてやることが出来るのだ。――この事を、今こそ、山田君の霊に僕等は誓わなければならないと思う……」
船員達だった、一番先きに「そうだ」と云ったのは。
蟹の生ッ臭いにおいと人いきれのする「糞壺」の中に線香のかおりが、香水か何かのように、ただよった。九時になると、雑夫が帰って行った。疲れているので、居睡りをしているものは、石の入った俵のように、なかなか起き上らなかった。一寸すると、漁夫達も一人、二人と眠り込んでしまった。――波が出てきた。船が揺れる度(たび)に、ローソクの灯が消えそうに細くなり、又それが明るくなったりした。死体の顔の上にかけてある白木綿が除(と)れそうに動いた。ずった。そこだけを見ていると、ゾッとする不気味さを感じた。――サイドに、波が鳴り出した。
次の朝、八時過ぎまで一仕事をしてから、監督のきめた船員と漁夫だけ四人下へ降りて行った。お経を前の晩の漁夫に読んでもらってから、四人の外に、病気のもの三、四人で、麻袋に死体をつめた。麻袋は新しいものは沢山あったが、監督は、直ぐ海に投げるものに新らしいものを使うなんてぜいたくだ、と云ってきかなかった。線香はもう船には用意がなかった。
「可哀相なもんだ。――これじゃ本当に死にたくなかったべよ」
なかなか曲らない腕を組合せながら、涙を麻袋の中に落した。
「駄目々々。涙をかけると……」
「何んとかして、函館まで持って帰られないものかな。……こら、顔をみれ、カムサツカのしやっこい水さ入りたくねえッて云ってるんでないか。――海さ投げられるなんて、頼りねえな……」
「同じ海でもカムサツカだ。冬になれば――九月過ぎれば、船一艘(そう)も居なくなって、凍ってしまう海だで。北の北の端(はず)れの!」
「ん、ん」――泣いていた。「それによ、こうやって袋に入れるッて云うのに、たった六、七人でな。三、四百人もいるのによ!」
「俺達、死んでからも、碌(ろく)な目に合わないんだ……」
皆は半日でいいから休みにしてくれるように頼んだが、前の日から蟹の大漁で、許されなかった。「私事と公事を混同するな」監督にそう云われた。
監督が「糞壺」の天井から顔だけ出して、
「もういいか」ときいた。
仕方がなく彼等は「いい」と云った。
「じゃ、運ぶんだ」
「んでも、船長さんがその前に弔詞(ちょうじ)を読んでくれることになってるんだよ」
「船長オ? 弔詞イ? ――」嘲(あざ)けるように、「馬鹿! そんな悠長(ゆうちょう)なことしてれるか」
悠長なことはしていられなかった。蟹が甲板に山積みになって、ゴソゴソ爪で床をならしていた。
そして、どんどん運び出されて、鮭(さけ)か鱒(ます)の菰包(こもづつ)みのように無雑作に、船尾につけてある発動機に積み込まれた。
「いいか――?」
「よオ――し……」
発動機がバタバタ動き出した。船尾で水が掻(か)き廻されて、アブクが立った。
「じゃ……」
「じゃ」
「左様なら」
「淋しいけどな――我慢してな」低い声で云っている。
「じゃ、頼んだど!」
本船から、発動機に乗ったものに頼んだ。
「ん、ん、分った」
発動機は沖の方へ離れて行った。
「じゃ、な!……」
「行ってしまった。」
「麻袋の中で、行くのはイヤだ、イヤだってしてるようでな……眼に見えるようだ」
――漁夫が漁から帰ってきた。そして監督の「勝手な」処置をきいた。それを聞くと、怒る前に、自分が――屍体になった自分の身体が、底の暗いカムサツカの海に、そういうように蹴落されでもしたように、ゾッとした。皆はものも云えず、そのままゾロゾロタラップを下りて行った。「分った、分った」口の中でブツブツ云いながら、塩ぬれのドッたりした袢天(はんてん)を脱いだ。














この記事への質問・一言コメントをどうぞ AIコースケと議論しよう!
回答には文字数制限があるため、制限を超えると途中で打ち切られることがあります。