戸村一作:著『小説三里塚』(目次へもどる)
第17話 空港・閣議内定(2)
 「これで木の根、古込、天浪、東峰、天神峯と数えたら、敷地内だけでも三五〇戸以上は、空港にすっぽりとひっかかるよ」
「これで木の根、古込、天浪、東峰、天神峯と数えたら、敷地内だけでも三五〇戸以上は、空港にすっぽりとひっかかるよ」
源二は指折り数えて、部落名を拳げた。
「やはりこれは各部落にも呼びかける必要があるな」と、武治がいうと、それにつれて臼木が口を開いた。
「一刻も早く反対同盟を結成し、まず成田あたりで総決起集会を開いて気勢を上げるんですね。そしてマスコミをうまく利用して……」
「うん、まず発会式か。」
「しかし、人の尻馬に乗っては、空港反対はできねえぞ」
「……そりゃ、そうだよ。地元農民が動かなけりゃ、どんな政党だってどうにもなんめえよ」
「自民党の佐藤政府ですら富里では大失敗したんですからね。ぐずぐずしてる間に二五〇〇人の富里農民が、むしろ旗を立てて県庁に押しかけ、友納をつるし上げたんですから……」
と、臼木が白分の手柄話しでもするかのように、説明した。
「富里の百姓もこれで大したもんだよな!」
「これで三里塚の場合は、奴らも考えてます。二度と失敗は繰り返すなと、やれば電撃戦できますよ。だから富里と違った運動方針を立てる必要があります、みなさん」
という臼木の顔に、一同の視線が向けられた。
「俺あ何もわかんねえがよ、人の屋敷に何んのことわりもなく、土足で乗り込んでくる奴は、空港であろうが、何んであろうがただじゃおけねえ。何やったってかまうめえ」
高橋の叫ぶようなだみ声に一同の視線は臼木から、高橋の顔に移った。彼の言葉に刺激されてか、武治は半ば怒りを込めた口調で切り出した。
「粒々辛苦……二六年の木の根だど……。何もかも血と汗の結晶だ。この土地を奪られてたまるかえっ」
昼の疲れも出てか、こんな激しい武治の言葉にも、こっくりこっくり居眠りする者もあった。
武治は、それにチラと眼をやったかと思うと、起ち上がり、台所から一升壜と湯呑茶碗を拘えて出てきた。みんなの前に茶碗を置くと、それになみなみと冷酒を注いで回った。
農村ではどこでも寄ると触ると、いつも酒はつきものだ。酒が出るとすっかり眠気が覚めて、空港の話から四方山の世間話にまで話は移っていった。そして常日頃無口な者までが喋り出し、普段胸に包んでいた欝憤をぶちまけるので、思わざる喧嘩にまで発展することすらあった。
岩沢辰巳が突然、声を強めていい出した。彼は加藤と一緒で木の根から通っている、船橋競馬場の守衛を務める出稼ぎ農民だった。出稼ぎというよりも、むしろそれが職業化しているといった方がよい。
「伜一三貧乏世盛りとはよくいったもんだ。俺もこの頃はつくづくそう思うよ。嫁に百姓やらせて、毎日てくてく通って働いたって毎月足んねえで追っかけ回されっぱなしだもんな……。いやになっちゃうよ」
彼は湯呑み茶碗を傾けて、やけに冷酒をあおり、また続けた。
「百姓もここで何とか考えねえと、このままでは……」
「このままでは何だよ。岩沢」
大工の高橋がキッと岩沢をみつめて口をはさんだ。
「このままでは借金しょってよ、入植者も、共倒れだよ」
「だからどうしようてんだよ」
高橋も少し酒が回ったせいか、つっけんどんなもののいい方だった。
「……」
岩沢はとまどいながらも、答えた。
「補償――、結局、空港問題も補償によりけりだよ」
「補償だって……何いってんだい。一言の相談もなく百姓を虫けら以下に踏みにじってよ、補償もへったくれもあるもんか」
「このままいったら、下手したらけつの毛羽までひん抜かれちゃうよ」
と、源二が合の手を入れた。
「そりゃ俺だってこの土地は安々手放せねえよ。だけんどよ、時代の流れというものがあって……、今のままでは百姓はやっていけなくなる。やっぱり、切り替えの潮時というものがあるんじゃねえか」
「……じゃ、百姓やめるっていうのか」
と高橋が突っ込んでいくと、岩沢はしどろもどろになった。
「いや、やめるっていうわけじゃねえけどよ……」
「そんなら何だい」
「……」
「そんなことじゃごれからおっぱじまる政府相手の喧嘩にゃ勝てねえぞ。俺も大工だけど嬶に百姓やらしてでも、この土地だけは何んとしてでも手放さねえつもりだ」
今まで黙って頭を垂れて話を聞いていた武治が急に頭をもたげ、やや改った口調でいい出した。
「岩沢さん、実はこの俺も貧乏世盛りだよ。餓鬼が六人もいてよ。でもよ、木の根では家が建ち電燈も灯いて、やっと格好づいたところだ。空港だけは追っ払わねえとな……」
「うん、俺なんか大工でよく富里へ仕事で行ったけどよ、『金は一時、土地は末代』て貼紙が、そこらじゅうにおっ貼ってあったからな」
高橋がいうと、武治がそれに続けた。
「借金で苦しいのは開拓者みんな同んなじだ。ここで土地手放したらどうなる……。二度と土地は手に入んねえど」
岩沢はポケットから煙草を取り出し、火をつけながらそっと呟いた。
「農地死守か……」
岩沢はどっちかというと、一攫千金を夢見る男だった。性格的にも、武治とは対照的だった。だから武治のいう「農地死守」には、少なからず抵抗を感じてならなかった。たとえ、どん底に二六年粒々辛苦の土地であっても、それに対して報いるだけの補償を政府が出すというなら、何も敢えて「農地死守」を唱え、絶対反対する必要もないのではないか。
それに終戦直後の解放地で当時の値にして一〇アール、ピース一個代ぐらいの払下げで、今にしてみればただ同然だ。政府はどのくらいの補償を出すかまだわからないが、要は補償次第である、何もいつまでも木の根の原に巣食って、孫子の代まで百姓を続けるだけが人生ではない。時代の流れに便乗してうまく世渡りするのが上手というものではないか。
木川武治の考えはあまりにも融通性がなく、世間知らずだ。彼のような男は正直者は馬鹿を見るという言葉の見本ではなかろうか。
だから酒の力も手伝って、今夜もそのことが自ずと岩沢の口から漏れたのである。だが今の情勢では部落こぞって空港絶対反対だ。
彼は大工の高橋に言葉尻を把えられて追及され、返答に困った。奥歯にもののはさまったもののいい方しかできず、押し黙らねばならなかった。
ポケットから煙草を取り出し、煙草の煙を輪に巻いて、吐き出した。彼はそれ以外に、なす術を知らなかった。岩沢の心の内では空港に「絶対反対」か、「条件闘争」か、二つの道のどちらを選ぷべきかと、迷っていた。――といって、てんから条件派に与することもできなかった。
「反対同盟と行動をともにするのも、時間の問題だ。そのときによって臨機応変の処置をとればいいのだ。それまで暫くの辛抱だ」
彼は心密かにそう考えると、思わず緊張した。勘づかれてはならないと思ったからである。
だが、岩沢の表情にはどことなく、それを隠し切れないものがあった。
「何だ、岩沢、いつものおめえと違って今夜さっぱり元気がねえじゃねえかよ」
すぐ隣りに座っていた金井が、岩沢の浮かぬ顔を覗き込むようにしていった。彼は急に頭を上げ、金井の肩をボンと叩いて高笑いした。が、それが何かを胡魔化すような動作に見えた。だが、岩沢の心の中は、誰も知ることができなかった。


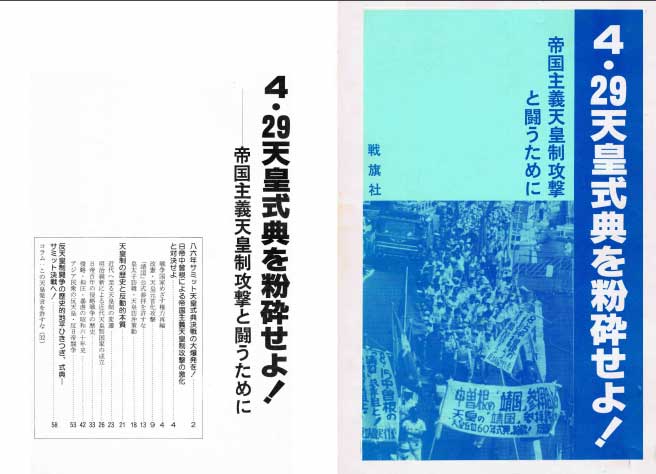
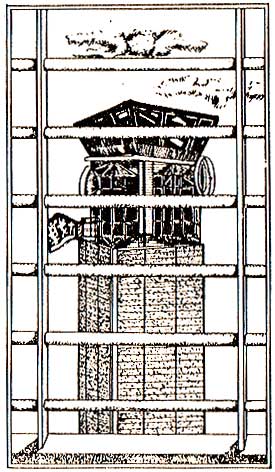
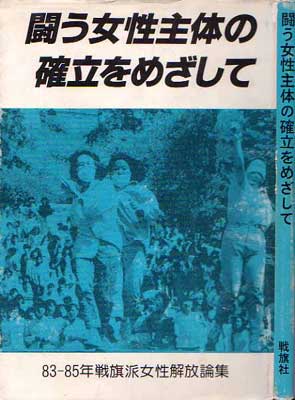










この記事への質問・一言コメントをどうぞ AIコースケと議論しよう!
回答には文字数制限があるため、制限を超えると途中で打ち切られることがあります。