2.スターリン主義批判の原点としてふまえられるべき諸点~スターリン主義批判の系譜
 1956年2月ソ連共産党20回大会で突如なされたフルシチョフによるスターリン暴露は、文字通り全世界のプロレタリアートを震憾させた。スターリンの無謬の神話が音をたてて崩壊していくなかで、ポーランド、ハンガリア労働者階級はソ連への隷属と官僚支配の打破、生活苦からの解放を求めてたちあがり、これに対するソ連軍の戦車による制圧、ハンガリア人民との激突は、ソ連共産党-クレムリン指導下の国際共産主義運動、ひいては共産主義の内実そのものが極めて官僚主義的に歪められたものでしかないことを、全世界の人民の眼に焼きつけた。
1956年2月ソ連共産党20回大会で突如なされたフルシチョフによるスターリン暴露は、文字通り全世界のプロレタリアートを震憾させた。スターリンの無謬の神話が音をたてて崩壊していくなかで、ポーランド、ハンガリア労働者階級はソ連への隷属と官僚支配の打破、生活苦からの解放を求めてたちあがり、これに対するソ連軍の戦車による制圧、ハンガリア人民との激突は、ソ連共産党-クレムリン指導下の国際共産主義運動、ひいては共産主義の内実そのものが極めて官僚主義的に歪められたものでしかないことを、全世界の人民の眼に焼きつけた。
1955年の日本共産党六全協における右転換以来共産党中央との対立関係にあった全学連指導部が中心となり、58年勤評、警職法闘争を闘いぬくなかで、1958年12月第一次共産主義者同盟が結成されて以来、トロツキー主義の強い影響下になされてきたスターリン主義批判は、こうした歴史的過程を反映するなかで、ほぼ以下のような諸点にまとめられるものである。
(1)まず第一に、一国社会主義建設可能論にもとづくマルクス主義の修正に対する批判である。
これはそもそもレーニンが「一国における社会主義革命の完全な勝利は不可能であり、そのためには少くとも、いくつかの先進国の積極的な協力が必要とされる。そしてわがロシアをこの先進国の一つにかぞえることはできないのである」と1918年11月に提起していることを(全集28巻、P115)スターリンが1926年1月、『レーニン主義の基礎』の改訂をなすなかで、「一国での社会主義の勝利の可能性とはどういうことか?それはわが国の内部の力でプロレタリアートと農民とのあいだの矛盾を解決することができる、ということであり、また他の国々のプロレタリアたちの共感と支持をうけていれば、まえもって他の国々でプロレタリア革命が勝利しなくても、わが国でプロレタリアートが権力をにぎって、その権力を完全な社会主義社会の建設のために利用することができるということである」と、いわばなし崩し的に改ざんしていったことへの批判である。
これはさらに中国共産党に対する批判とも絡みあわされる形で、過渡期(プロ独期)と共産主義の第一段階としての社会主義社会が二重うつしにされており、マルクスの『ゴー夕綱領批判』の内容が修正されていること、社会主義社会であるなら国家は死滅しているはずであり、労働証書制が採用され、価値法則も止揚されているはずだといった、端的には対馬忠行の『マルクス主義とスターリン主義』にまとめられる内容として提起される。
つまりマルクス主義の原則的観点からのイデオロギー的逸脱に対する批判である。
(2)第二には世界革命の放棄が、ソ連一国防衛主義として1930年代スペイン革命の放棄、抑圧や、ドイツ革命の挫折をもたらし、中国革命に対してもコミンテルンの誤った指導として、国際共産主義運動の混迷をもたらしてきたこと等の批判である。
 ソ連共産党20回大会における平和共存路線への移行以前から、1928年コミンテルン第9回拡大執行委での社会ファシズム批判や、1935年コミンテルン第7回大会でのディミトロフによる反ファッショ統一戦線の提起など、国際共産主義運動、各国革命に対する指導はまったくジグザグしており、結局は「社会主義の祖国ソ連を防衛せよ」という方針につらぬかれたものであった。
ソ連共産党20回大会における平和共存路線への移行以前から、1928年コミンテルン第9回拡大執行委での社会ファシズム批判や、1935年コミンテルン第7回大会でのディミトロフによる反ファッショ統一戦線の提起など、国際共産主義運動、各国革命に対する指導はまったくジグザグしており、結局は「社会主義の祖国ソ連を防衛せよ」という方針につらぬかれたものであった。
プロレタリア国際主義を内実としてもちあわせぬこの方針は、各国の闘う人民を孤立化させ、ファシスト共の餌食にさせてきたのであり、独ソ不可侵条約の締結などは、ヨーロッパにおける反ナチ・レジスタンスの方向性を喪失させ、ソ連に対する不信をつのらせるだけとなった。
毛沢東が中国人民解放軍をひきいて抗日民族統一戦線を構築し、独自の遊撃戦理論をつくりあげたのも、いわばこうしたコミンテルン指導の方針(オットー・ブラウンの堡塁戦、陣地戦)に対するアンチとしてである。スペイン革命にあってはPOUMに従ったジョージ・オーウエルが『力タロニア讃歌』においてフランコを助ける共産党指導部を糾弾しているし、中核派の野島三郎の『革共同の内戦論』は、どこでもかしこでもスターリン主義者が裏切ったと、それ自体全く正しい指摘だが裏切り史観でつらぬかれる形で書かれている。
(3)第三にはブルジョア議会主義への埋没と二段階戦略の固定化が、ブルジョア体制内化=共存化してしまい、闘う前衛党としてのエトスを喪失させ、ひいては選挙で一票とる運動へと革命運動そのものを矮小化させていることに対する批判の系列である。
 特にこれは日本共産党の現在、つまり日本におけるスターリニストの運動路線に対する批判として展開されてきたものであり、1961年綱領の採択以来、民族民主革命の実現にむけての民族民主統一戦線の形成をという政策要求、制度要求闘争路線が、闘う労働者階級人民と一切結合していないばかりか、むしろ常に体制の左足としての敵対者としてあらわれていることへの指摘といえる。
特にこれは日本共産党の現在、つまり日本におけるスターリニストの運動路線に対する批判として展開されてきたものであり、1961年綱領の採択以来、民族民主革命の実現にむけての民族民主統一戦線の形成をという政策要求、制度要求闘争路線が、闘う労働者階級人民と一切結合していないばかりか、むしろ常に体制の左足としての敵対者としてあらわれていることへの指摘といえる。
ラジカルに闘う者をすべてトロツキスト、暴力主義者の闘争破壊として糾弾し、反トロキャンペーンによって戦線から放逐しようとするそのやり方は、狭山差別裁判糾弾闘争や三里塚成田空港粉砕闘争において、闘う大衆団体(部落解放同盟や三里塚芝山連合空港反対同盟)から糾弾され、人民大衆が共産党から離反する結果をもたらしており、否、そればかりかそうした敵対者をすべて権力の手先よばわりしていく偏狭な体質は、革命的に闘おうとするものは唯一の前衛党であるはずの日本共産党には属しえないという皮肉な結果をもたらしている。
共産主義者同盟のスターリン主義批判の原点はいわばここにあり(=『われらの対立-共産主義者同盟と共産党』佐々木和雄著)、かつ依然として最重要の批判点として現在もある。
(4)第四に党の官僚化、一党独裁によるプロレタリア独裁の歪曲が、複数主義を認めず、ソビエト(議会)の無力化と空洞化をもたらし、党が人民に君臨する専制支配を生み出してきたことへの批判である。
 1920年代の左翼反対派が、書記局を牛耳るスターリンの専制に対する批判としてこれをなして以来、党的に少しでも疎外されたり、あるいは自己の権利運動として革命運動をとらえる部分は、すぐにこれを口にしたがるというように、一方ではブルジョア・アトミズムからのアプローチそのものでしかないアナーキイな傾向をも内包しつつ、しかし1930年代の血の粛清の如きスターリン主義の最も悪しき発現もここに見られるように、政治としてのスターリン主義に対する批判の原点を、これは形づくってきた。
1920年代の左翼反対派が、書記局を牛耳るスターリンの専制に対する批判としてこれをなして以来、党的に少しでも疎外されたり、あるいは自己の権利運動として革命運動をとらえる部分は、すぐにこれを口にしたがるというように、一方ではブルジョア・アトミズムからのアプローチそのものでしかないアナーキイな傾向をも内包しつつ、しかし1930年代の血の粛清の如きスターリン主義の最も悪しき発現もここに見られるように、政治としてのスターリン主義に対する批判の原点を、これは形づくってきた。
党が自己の上に君臨し、専制的な官僚機構が国家をおおい、個人の自由な自己の発現が圧殺されるという印象を持つことは、ブルジョア的個人主義を価値判断の基礎にすえる限り、たしかにこの上ない苦痛であり、個人解放というブルジョア的原理にまっこうから反することであって、マルクス主義者はこの克服をめざす以外ない。
だが同時にこれは近代における機械体系への人間労働の従属だとか、巨大管理機構への個人の従属というブルジョア社会における基本的な社会=人間関係においても同様に問題とされてきたことであって、それとオーバーラップして「自由な個人」が組織を批判することとも絡みあう問題であり、特定の価値判断に立って一個の目的意識の体系をなす党活動においては、一面として排除される以外ない領域もふくまれている。
だから例えば『ソ連における少数意見』での、ロイ・メドヴエーデフの市民的自由の主張という正当な見解や、同じようなものとして見られがちのソルジエニーツインのギリシア正教の昔に帰れ、それがロシアの本来の姿だというような主張は、とても一緒くたには論じられないものである。
言い換えれば官僚主義批判だとか、個人の自由の圧殺とか、党的ヒエラルヒーの批判の内容において、如何なるものを持ちえているかこそが、スターリン主義批判の位相を決定しているのであり、従って政治としてのスターリン主義の克服の問題は、一番つよくこの領域に求められるものであるとわれわれは考える。
(5)第五に民主主義の形骸化、基本的人権の無視、専制的官僚支配が文化的にも停滞をもたらし、スターリンイデオロギーの諸科学への押しつけとして、芸術や科学の自由な発展をもたらしてこなかったという第四の領域とも絡みあう内容での批判。
社会主義リアリズム批判だとか、言語は上部構造に属さないというスターリン言語論に対する批判、ルイゼンコ学説に対する批判など、イデオロギーや芸術などの分野におけるスターリン主義の克服は、トロツキーの『文学と革命』であるとか、黒田寛一、宇野弘蔵、武谷三男、吉本隆明、三浦つとむなど様々な領域の、様々な分野においてなされてきたし、これからもなされていくだろうと思われる。
以上の如き幾多の領域にわたる批判のつみ重ねの中から、日本において例えばスターリニスト・レジーム、スターリニスト革命、スターリニスト政治経済法則などの概念をつき出すことによって、〈反帝・反スタ〉を標榜する革共同や、反社帝のためには日米安保も承認すべきという中共派なども生み出されているわけであり、スターリン主義批判は明確に概念規定されぬまま日本革命的左翼の自明の課題であるかのような体をなしつつある。
われわれはわれわれの観点においてスターリン主義の克服を問題とする時、まずもって以上述べられてきたようなスターリン主義批判の内容は前提的にふまえられるべきことであり、かつ正当な批判の内容であることを確認しなければならない。
そのうえでわれわれにとり基軸的といえるものをとり出し、われわれ独自の方向性を確定していきたい。そのためにも次にスターリン主義の反人民性の最も卑劣な発現となったソビエト・ロシア1930年代の血の粛清に至る歴史的過程を俯瞰し、問題とすべき点を抽出していこう。
3.ロシア1920-30年代歴史過程とそこにおいてふまえられるべき視点
 ごく大ざっぱに問題を見ていくならば、1924年1月のレーニンの死後、1924年5月の第12回党大会でまずトロツキー派が主要な党機関から排除され、つづいて1925年12月の第14回大会をメルクマールにぺトログラード党組織に依拠したジノヴィエフ反対派がスターリンに敗北し、27年9月のトロツキー、ジノヴィエフの最後の抵抗となった合同反対派政綱の提出に対しては、同年11月の中央統制委による両者の共産党からの除名、12月15回党大会での左翼反対派総体の党からの除名という具合に、いわゆる左翼反対派のスターリン・ブハーリンブロックとの党内闘争の歴史は進展する。
ごく大ざっぱに問題を見ていくならば、1924年1月のレーニンの死後、1924年5月の第12回党大会でまずトロツキー派が主要な党機関から排除され、つづいて1925年12月の第14回大会をメルクマールにぺトログラード党組織に依拠したジノヴィエフ反対派がスターリンに敗北し、27年9月のトロツキー、ジノヴィエフの最後の抵抗となった合同反対派政綱の提出に対しては、同年11月の中央統制委による両者の共産党からの除名、12月15回党大会での左翼反対派総体の党からの除名という具合に、いわゆる左翼反対派のスターリン・ブハーリンブロックとの党内闘争の歴史は進展する。
そしてトロツキーが1928年1月アルマ・アタヘ追放されてからのちスターリンの左転換がはじまり、急速なロシアの工業化がさけばれ、28年10月第一次五ヵ年計画(いわゆるゴスプラン計画)の開始にともない右翼反対派、ブハーリン、ルイコフなどが失脚するといった歴史過程を20年代ロシアはたどっている。
ジノヴィエフ、カーメネフなどは除名、シベリア流刑、復党をくり返すが、ドイツにおけるナチの勃興にともないクラーク追放、工業化、電化の達成が確認された、ボリシエヴィキ党の大同団結の大会としての第17回党大会が1934年1月ひらかれてのち、12月のキーロフ暗殺そして36年の第一次モスクワ裁判、ジノヴィエフ、カーメネフの処刑、38年の第三次モスクワ裁判、ブハーリン、ルイコフ処刑、39年独ソ不可侵条約の締結といった、坂をころげるようなスターリン専制の暴虐が、その後の1930年代を形づくっている。
こうした歴史過程を対象化しつつ、スターリン主義の誤謬につき問題をつきだしていこうとするならば、永続革命対一国社会主義、ロシアの工業化をめぐる分岐、そして農業集団化などのロシアにおける社会主義の建設問題が主要論争軸であることがわかる。そして例えば1920年代の論争においては、1917年ロシア革命の成果を防衛しきるという観点において、トロツキーではなくスターリンの方に、実際のロシアの労農大衆に対しては説得力をもった主張が多いということも、対象化されるのである。
 つまり第一に国際革命の待望か、それともロシア一国での社会主義の勝利にむけての苦闘かとしてなされた、トロツキー永続革命をめぐる論争にあっては、トロツキーの主張であるロシアに社会主義を建設するためには、どうしても西欧の社会主義革命が必要であるという純理論的な主旨では、既に1923~4年にはドイツ革命の展望が喪失してしまい、ロシアが孤立せざるをえないという現実的規定との関連において、「世界革命の到来が遅れる運命にあるならば、どういうことになるか?われわれの革命には一筋の希望でもあるだろうか?同志トロツキーは、われわれに全然希望を与えない」(論文『十月革命とロシア共産主義者の戦術』)というスターリンに反論できない。
つまり第一に国際革命の待望か、それともロシア一国での社会主義の勝利にむけての苦闘かとしてなされた、トロツキー永続革命をめぐる論争にあっては、トロツキーの主張であるロシアに社会主義を建設するためには、どうしても西欧の社会主義革命が必要であるという純理論的な主旨では、既に1923~4年にはドイツ革命の展望が喪失してしまい、ロシアが孤立せざるをえないという現実的規定との関連において、「世界革命の到来が遅れる運命にあるならば、どういうことになるか?われわれの革命には一筋の希望でもあるだろうか?同志トロツキーは、われわれに全然希望を与えない」(論文『十月革命とロシア共産主義者の戦術』)というスターリンに反論できない。
「この考えによれば、われわれの革命は唯一の展望、つまり自らの矛盾を含みながら無為単調なる存在を続け、世界的規模の革命を待っている間に革命の根を腐らせてしまうという展望だけをもつ」という具合に、革命の成果を守ろうとするロシアの労農大衆に説得力を持つ形でスターリンがトロツキーを批判し、しかも社会主義の「完全」な勝利は不可能でも、プロ独権力を守りこれを発展させることができれば、「社会主義の勝利の可能性はある」(『レーニン主義の基礎』改訂版)と提出するならば、実際的な政治関係においてシニカルなトロツキーの主張が展望を与えず、しりぞけられる以外ないことはいわば自明となってしまう。
また第二の論争としてのロシアの工業化と農民対策をめぐるトロツキー派の主張は、プレオブラジェンスキー『新しい経済』に表現されるものであるわけだが、それは社会主義の目標の達成のためには社会主義的原始的蓄積が必要であり、急速な工業化は前提である、そのためにはロシア国内の農民に対し政治的外圧により重税をかけることにより、そこからの収奪によって蓄積をとげる以外ないというのが主旨である。
「非社会主義部門からの強制取り立て」のために、プレオブラジェンスキーの考えだしたものは「従価税」であり、商取引きを国家が独占的に支配するなかで、農民の購人、販売に重税を課すという論旨であっては、「レーニンはツアーリズムを完全に一掃するために、プロレタリア革命へ移行するために、農民の革命的能力をくみつくし、農民の革命的エネルギーを利用しつくそうと提案したのに、一方『永続革命』の支持者らはロシア革命で農民が非常に重大な役割をもつことを理解せず、農民の革命的エネルギーの力を過小評価した」(『レーニン主義の基礎』)として、ネップ政策における農民の保護の継続をよびかけたスターリンに実際上対処できない。
スターリンとブロックを組みプレオブラジェンスキーの論敵となったブハーリンに従うならば(=『過渡期の法則性に関する問題によせて』)、(1)工業は市場における価値法則の作用におうじて成長すべきであり、(2)重工業は消費財生産の拡大ののち、その発展につれて間接的に生産財の生産として増大するのであるから、(3)むしろ長期の観点において工業発展の基礎となる個人農を育成すべきなのであって、(4)プレオブラジェンスキーにはこの観点がなく、そもそもプロ独の維持がロシアにあっては農民との同盟によってのみ可能だということを無視している、急激な工業化は必然的に農民の離反をまねき、ロシアのプロ独を崩壊させることになるとして論破されてしまうのである。
つまり実際上のロシアの政治的現実に立脚し、依拠せざるをえない農民層をはぐくむといった観点、あるいはロシアの孤立という現実を認め、なおかつその中で社会主義の勝利のためにがんばる以外ないという視点の提出において、トロツキー派はあまりにも理論主義的であり、小ブルジョア的な理念をそれとして提起しているだけであって、実践的な説得力に欠けていたといわねばならない。
 それはともあれこうした論争系譜をへてのち左派が粉砕されると、1927年~28年の農業危機において穀物の調達率が25%も減少したことなどにたいし、突如スターリンはクラーク(富農)・イデオロギーヘの批判を開始し、重工業化の実現のための農業集団化を提起し、それまでの左派の主張を横取りしてブハーリンら右翼反対派を攻撃しはじめる。
それはともあれこうした論争系譜をへてのち左派が粉砕されると、1927年~28年の農業危機において穀物の調達率が25%も減少したことなどにたいし、突如スターリンはクラーク(富農)・イデオロギーヘの批判を開始し、重工業化の実現のための農業集団化を提起し、それまでの左派の主張を横取りしてブハーリンら右翼反対派を攻撃しはじめる。
ブハーリンは1928年9月『一経済学者のノート』を発表してこれに対抗するわけだが、そこでの主張としては、スターリンの工業化へのトロツキー的転換は「予備積立の必要を無視し、消費物資の不足を解消せず、投資の危険なまでに過大な割合を提案しており」「資本支出に無理がある」、従って「中農、クラークなどの保護政策を継続し」「消費財生産の拡大による重工業化の実現をはかれ」というものであった。
これはいわば従来の左翼反対派に対するスターリン派の主張でもあったわけだが、これに対しスターリンは1926年頃の左翼反対派の主張(例えば十三人宣言として提起されたもの)、(1)労働者無視、農民重視政策への批判、(2)クラーク、中農、貧農といったヒエラルキーが生み出されていることへの対処、(3)労働者の賃金の一般的増大の必要、等を横取りする形で、消費財生産の促進をいう部分を右翼反対派として批判し、ドイツにおけるナチの勝利に対し、戦争の危険が迫っていることへの対処としてのロシアの急速な工業化の実現と、農民のソホーズ、コルホーズヘの集団化、そしてクラークの撲滅運動へ邁進するのである。
いわゆるスターリン主義の発現となった農民へのテロル、強制的な集団化のための政治的暴力の駆使は、この1928年の転換ののち開始される。つまり1928年には「外国帝国主義と体制内部の敵を告発する裁判」が開始され、1930年に勤労農民党や産業党が、1931年にメンシェヴィキが裁判にかけられ流刑に処せられる。クラークのシベリア流刑のはじまりは1931年2月のことであり、農民は自分がクラークでないことを証明するために次々と家畜を殺したという。ジャン・エレンステンの『スターリン現象の歴史』などの資料によれば、1929年、牛6710万頭が1933年には3860万頭へ、馬3070万頭が1660万頭へ、豚2030万頭が1220万頭へ、それぞれ農民自身の手による屠殺で減少してしまったのである。1933年には29年以来のものとして85万人のクラーク流刑者が存在したともいう。
1933年にはかかるごとき強引なゲバルトを駆使しての工業化・電化、農業集団化により28年以来の第一次五ヵ年計画が4年3ヵ月で達成されたとして第二次五ヵ年計画が開始されるわけだが、しかしすべてを人民の敵として圧殺するスターリンのテロルにより、ほぼ1934年1月のロシア共産党17回大会を境として、もはや何のマルクス主義的内実も持ちあわせぬ暗黒支配が以後1953年のスターリンの死までつづくことになるのである。
ちなみに1939年の第18回党大会の代議員数は1827人だが、34年の17回大会より継続した者は全部で35人、わずか2%しかいなかったのである。残りの者は皆おしなべて追放され、流刑されたり、処刑されてしまったのだ。
以上のような歴史過程のとらえかえしをつうじ言えることは何かというならば、第一にいわゆるスターリン主義の政治的発現については、クラークの粛清にみられる農民抑圧のはじまり、つまり右翼反対派批判から第一次五ヵ年計画実施後のテロルの開始を契機としてみるべきであり、しかもテロルによる反対派の圧殺は1934年キーロフ暗殺からのちはじまるわけで、20年代前半や左翼反対派との論争過程一般をスターリン主義として断罪することはできないということである。
別の言いかたをすれば確かに1926年1月、『レーニン主義の基礎』をもつて一国社会主義建設可能論が定式化されるわけだが、そのことをもってただちにスターリン主義の害毒として弾劾しても、それはイデオロギーを断罪するということでしかなく、実践的に何が人民にとり桎梏となり、阻害物となったのかの回答にはならないといえる。
党のテロルが人民に対し向けられ、スターリンの意に反するものがことごとく圧殺されるという歴史のはじまりは17回大会1934年のあとであり、そののちに生じた事態に対しこれをスターリン主義の悪しき発現として批判し、弾劾すべきである。
第二に確認すべきこととして、一国社会主義建設可能論というイデオロギーの提起は、帝国主義に包囲されつつ孤立した社会主義建設を必然化されたロシアの現状にあっては、いわばありうべきことであり、それがマルクス主義理論そのものとしては誤っていたとしても、そこから帰結するものとしてクラークヘのテロルや血の粛清などをくしざし的に批判することはできない。
ロシアの工業化・電化のためにはいずれ農業集団化はなされざるをえなかったわけであり、いわば社会主義的な経済建設のためには必然的な過程であるわけで、だから農業集団化そのものに問題があった等とは絶対にいえない。問題になることはそのやり方の反人民的性格であり、民主的ルールや説得をかいた粗暴なゲバルトによる実施の方法であって、そこにこそスターリン主義の政治的否定面が発現している。
もちろんだからといって一国社会主義建設可能論が肯定されるということにはならず、それ自体スターリン主義の誤りの一つであるわけだが、それを批判することによってスターリン主義を批判した気になっている、対馬忠行や黒田寛一的発想は問題をとりちがえているということなのだ。イデオロギー的基礎を批判すればスターリン主義を内在的に克服したということには絶対ならず、問題は実践面におけるわれわれ自身の政治的発現において、如何にしてスターリン主義的誤りから自由であるのかを問うことにあるのだ。
一国社会主義かそれとも世界革命かというような抽象的次元でのみ線がひかれ、現実的な自分達の行為のもつ抑圧やテロルといったスターリン主義的誤りには目がつぶられていくのだとしたら、何のためのスターリン主義批判なのかの意味を欠くのである。
以上の如き歴史的対象化をつうじて、第三にわれわれはスターリン主義の克服を、近代ブルジョア階級の思想としてのブルジョア個人主義と、その全くの裏返しとしての「全体」主義、あるいは非人間的な合理主義のプロレタリア革命運動内部における発現、つまりブルジョア・イデオロギーの未止揚の問題としてとらえるし、共産主義的な主体形成の実現において克服可能なものとして考える。すなわちブルジョア的主体性の未止揚が政治的に発現した場合、スターリン主義として表現されるのだと問題を設定し、実践的にはそれは、スターリン主義をのりこえた党風、作風の形成としてのみ解決されることだと考えるのである。そこで次にそれらの内容につきわれわれの観点をまとめていこう。
4.スターリン主義の本質規定をめぐる問題
ハンガリー動乱(映画『君の涙ドナウに流れ』より)
これまでの展開からも明らかなように、過渡期における労働者国家の建設過程にあって帝国主義に包囲され、不断に存亡の危機にさらされ、ましてやドイツにおけるブルジョア反革命の最も先鋭な形態としてのファシズムの成立、それとの戦争の必然性といった事態をファクターとすることによって、次第に官僚主義的に歪曲され、プロレタリア的規範を喪失し、まだ思想的にも近代ブルジョア・イデオロギーを克服しきれぬために、ブルジョア・アトミズムのアンチとしての官僚的合理主義思想が人開性そのものの否定として生みだされてくる、そうした過程をたどることによってスターリン主義は1930年代に、労働者階級にその暴威をふるい、しかもそれ以後もなおみずからがつくりあげた政治経済体制を物質的基礎とすることにより、不断に再生産され続け現在もなお存立しつづけているのである。
ここにおいてこの変質したソ連邦に代表されるスターリン主義を如何なるものとして本質規定するのかは大きな問題である。これに対し中国共産党などはこれを「国家独占資本主義」と規定し、「資本主義経済が復活し」「コルホーズなどではブルジョア階級が農民に対し収奪し」「コメコン経済体制をつうじ資本輸出し、新植民地主義をおしすすめている」(『ソ連はいかにして社会帝国主義に変質したのか』1976年上海人民出版社)等といっている。
だが「ソ連の企業は、企業自身が労働者を募集し解雇する権限をもっており、企業と労働者の関係は労働力を売買する関係」だなどといっても、社会的生産手段を私有するブルジョア階級がプロレタリアートの労働力を買い入れ、社会的に必要とされる使用価値の生産をおこない、剰余労働の搾取をなしつつ、私的に利潤を得、かつそれをもとに生産を拡大していくといった資本家的商品経済のメカニズムと類推するには、これらの断言はあまりにも政治的であり、実証力に乏しい。
また、「ソ連の国家が掌握している固定生産基金は全社会の90%以上を占めており、そのほか鉱山、河川、土地等々の天然資源や国民経済の命脈もみな、少数の官僚ブルジョア階級分子が国家の名において独占している。これは最高度の国家独占である」だとか、あるいは「生産経営活動に関する権限は、管理者、企業長および職務分担にもとづいて規定される企業その他の責任者がこれを規定する」と、ソ連の『社会主義国営生産企業条例』にあるから、だから国家資本主義だ等といっても、いずれも労働力の自由な売買と私的利潤の追求にもとづく、資本家的商品経済とそれが同一だという証左にはならない。
われわれの結論を繰りかえせば、官僚主義的に歪曲された労働者党、および官僚主義的に歪曲された「労働者国家」、つまり労働者国家の疎外態の支配的イデオロギーとしてスターリン主義は存在しており、中国などもソ連と同じくそうした範疇に属するものとして規定される。カクマルなどは「スターリニスト・レジーム」としてブルジョア国家とも労働者国家とも異る第三のカテゴリーをつくりだしてしまったが(これに対し中共派はブルジョア国家だと言ってるわけだが)、われわれは世界革命の遅延による孤立化がもたらした労働者国家の変質態としてこれをみる。
つまり現在の中共派などはあきらかにトニー・クリフ『国家独占資本主義論』と同じことをいってるだけにすぎないのだが、官僚層が生産手段の私的独占にもとづき、プロレタリアートの剰余労働を私的に搾取しているということを論証することはできず、「ブルジョア階級と同一だ」といいつつ、官僚を階級(クラス)として立証することはできないでいる。
他方カクマル派などは「現代ソ連邦は、たしかに新しく出現した歴史的存在である。だからといってそれは資本主義でも社会主義でもない新しいカテゴリーでつかまれるべきだということにはならない」(『日本の反スターリン主義運動』1、P538)と一方ではいいつつ、「中国や東ヨーロッパにおけるスターリン主義国家としてのスターリン主義国家の形成-つまりソ連邦の変質を物質的基礎とし、スターリン主義党によって指導されつつ、はじめからスターリン主義国家として形成された」(『資本論以後百年』P220)、「これをわれわれは《スターリニスト政治経済体制》という新しいカテゴリーで把握し表現するのである」(『日本の反スタ』1、P538)等とこれを言い換え、それ自体矛盾した論理を展開している。
 つまるところ本質規定に関しては、問題はソビエト・エリートとよばれる官僚層をいかなるものとして規定しえるのかであり、そこからスターリン主義を如何なる存在として克服しようとするかにあるのだ。
つまるところ本質規定に関しては、問題はソビエト・エリートとよばれる官僚層をいかなるものとして規定しえるのかであり、そこからスターリン主義を如何なる存在として克服しようとするかにあるのだ。
マービン・マシューズによる研究などを参照すると、ソビエト・エリートとよばれる集団は大ざっぱにいって次のような条件を有した部分として区別される。
(1)月450ルーブル(1ルーブルは350円)以上の収人のあるもの、(2)ノーメン・クラトゥーラ、つまり党・国家等の重要職務に任命されるための有資格者名簿に名前が載っていること、(3)各種の特権(海外旅行、住宅、別荘、消費財購人、年金など)へのアクセスを獲得していること。
これらの条件にあてはまるエリートの数は総数25万人いるといわれ、その内訳は、(a)党官僚38%、(b)国家、コムソモール、労組役員24%、(c)軍人、警察官、外交官12%、(d)アカデミー会員など高級知識人17%、(e)ソホーズ議長など企業管理者9%ということになる。
ところがこれらのエリートであったとしてもブルジョア国家のブルジョア階級と比した場合、明白に次のような差異性をもっている。
第一にそもそも彼らが私的に蓄積した富は少く、所得が低いこと、第二にエリート内部に階層的、社会的分化がほとんどみられず、私的な富の蓄積がないこととからんで一位階にとどまっていること、第三に国家の政治システムに依存しており、経済的政治的独立性をもっていないこと、第四に党・国家に従属しており、一代限りであって世襲制ではないことなどである。ここから言えることはエリート層はようするに、国家的な一位階をしめる身分(カースト)にすぎず、生産手段の私的所有による労働力商品の購人をつうじた、剰余価値の生産とその搾取をなしうる階級的存在などとは言いきれないということである。
これを例証するものとしてヘドリック・スミスの『ロシア人』の「第二章 特権階級」中の暴露をあげることができる。そこでは、「全部でおよそ二十人のこのエリートの中核-政治局員と党書記は、手づくりで一台七万五千ドル相当の黒いリムジンの“ジル”に乗る」とか、「ジルに乗るにいたらない第ニグループの高官たちにとって、最も格式の高い車はチャイカ」であるとか、あるいは「地位(ステータス)の高さを示すもっとも大きな特権はモスクワの外にある。指導者とその家族たちは隠れ家のような別荘のある地域全体を持っている」等と、いかにソビエト・エリート層が一般労働者よりめぐまれた待遇をうけているかが例証されている。
だが同時に「解任されると党の慣習は冷酷無比である。ポストがなくなる、これはとりもなおさず、国有の別荘もなくなることを意味する」「彼らが党の階層の中に自分の子息を入れることはできない」「地位であって権力でない」という具合に、あくまでもソビエトの国家システムに依拠した地位にもとづく待遇の差異としてしか特権がないことが示されている。
イストであるはずの政治局員が手作りのジルに乗りたがるのはブルジョア的な貴族趣味に依る嗜好であると批判できても、そのジルは私的に所有されるものではなく国家から借リるだけであり、それらはあくまでステータス・シンボルでしかないのである。
従ってかかるごとき官僚層がブルジョア的に堕落し、プロレタリア的階級性を喪失している、腐敗しているということはいくらでも言えるとしても、中共派のように自分達の都合にあわせて、だから国独資だとか、ブルジョア階級だとかいうことは、マルクス主義的な概念規定だとはいえない。政治的批判の言葉としては位置を持っているとしても、社会科学的な概念としては無理があるのである。
われわれは従って官僚主義的に歪曲され、変質した「労働者国家」の支配的イデオロギーとしてスターリン主義をとらえるし、かかる現実を打破するものとしての補足的政治革命の設定として、スターリン主義との闘いを考える。そしてこのことはブルジョア階級の打倒、プロレタリア政治権力の樹立といったプロレタリア革命の本質的課題とは反スターリン主義のたたかいは位相を異ならせるものであり、いわば世界革命の完遂へむけての特殊的課題であって、戦略的に対象化されるものであったとしても、ブルジョア階級の打倒と同一の地平で直接に論じることはできないものということになる。
〈反帝・反スタ〉も〈反帝・反社帝〉もマルクス主義的な本質規定との関係でいえば全くあいまいであり、誤っており、プロレタリア革命が労働力商品の廃絶をつうじて、生産手段の私的所有を廃止し、社会的共有化をかちとっていくことを内実とする以上、異なる概念の接ぎ木であってうけ入れがたいものなのだ。(なおこれに関しては『過渡期世界の革命』中の「〈反帝・反スタ〉革命論の左翼反対派的限界」P394以下なども参照せよ)
これ等を前提としてふまえるなかで、次にスターリン主義が思想としての近代ブルジョア・イデオロギーを依然未克服であり、その亜種にすぎないという問題につきみていこう。
(次回「思想としてのスターリン主義」に続く)



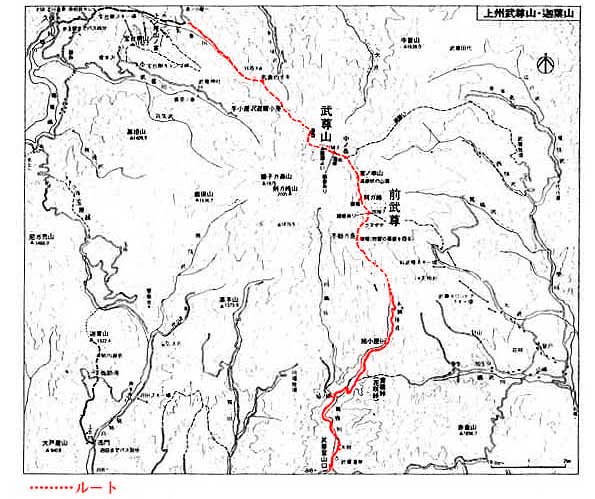





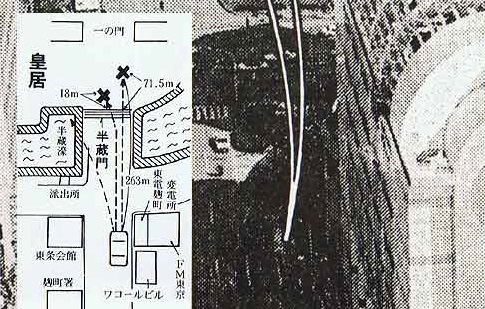






メールでお教えしたかも知れませんが、以下のサイトも参考になりますね。
http://members.jcom.home.ne.jp/nokato/data4.htm
TAMO2さん>
ありがとうございます。実はこの論文を掲載したのは、TAMO2さんのところのリンクで、ご紹介の論文を目にしたことも動機の一つとなっているんです。忘れていたので巻末の参考リンク集に加えておきました。どうか今後ともこの問題についての議論(それも元気になって希望をもてるような)の継続にご協力いただければと思います。
私はスターリン主義批判でいかなる内容を持っているかが、その左翼運動の質を決定していると思います。ついでに言えば、どんな言葉でファシズムを(さらに言うなら共産主義を)批判しているかが右翼や保守運動の質を決定しているとも思う。この点について左右ともにあまりにも無自覚で、戦後民主主義の視点からしか語るべきものをもたないか、せいぜい自分たちが語る「本当の」理想から逸脱した裏切り者だくらいの視点しかありません。まさしく噴飯ものだと思います。
右のファシズム批判も、左のスターリン主義批判も、煎じ詰めればそれは「悪いもの」であって、「自分はそうじゃない」で話が終わってしまっているのが現状です。多少はものがわかった人でも、せいぜい「なんでそんな『悪いもの』が幅をきかしたのかを解明して二度とそういうことがおきないようにしよう」くらいが関の山ではないでしょうか。そこには「もちろん私はそんな『悪いもの』ではありませんよ」という前提があるわけです。
でも実際には、そう言って批判しているはずの様々な社会運動の中でこそ、こういうものは何度も復活というか、今でも厳然として息づいている。そのことに無自覚なのは本人たちだけ。右の人は自分はファシズムとは無縁だと思っているし、理想主義者たちはスターリン主義なんて自分とは関係ないと思っている。
この論文に優れたところがあるとすれば、スターリン主義を「自分の問題」として論じているところでしょうか。次に結論を導き出すために、まず今まで連綿として繰り広げられてきた「スターリン主義批判」の系譜とその内容を歴史的に整理しているところ、最後に、スターリン主義批判の内容を左翼仲間でしか通じないような「マルクスの言っていることと違う」という理論やイデオロギーレベルの神学的な断罪ではなく、現実問題として実践的にスターリン主義の何が人民にとって害悪なのかという視点で書かれているところだと思います。特に最後の視点は、民衆の視点から見れば当たり前のことなのですが、とかく新左翼で繰り広げられがちだった理論主義的な断罪では、結局「俺たちはスターリン主義は関係ない。すでにそれを乗り越えた存在だ」という結論になりがちなので重要な視点だと思います。
このあたりの視点はむしろ現在的には右翼の方にこそ学んでいただきたいと思っています。たとえば戦前の天皇制ファシズムが国家を存亡の危機にまで追い込み、民衆を苦しめたことについて、やり方が悪かったのであって主義や思想は正しかっただの「本当の」右翼思想や天皇制の伝統とは違うだのというレトリックは、この論文で批判されている新左翼のスターリン主義批判に、奇妙なまでに酷似しているんですから。
最後に、もっとも重要な点は、この論文がスターリン主義批判の内容を、理論的な一種のドグマ(教条)とせずに、きわめて実践的な日常の点検、主体形成に求めている点が重要だと思います。すなわち、「この理論を掲げているからすでに俺たちはスターリン主義者ではない」というような、黒田寛一の流れをくむ「反スタを掲げたスターリン主義者」たる人々と自己を画することができる可能性、理論的な作業でスターリン主義と「無縁」になることは絶対にできないし、批判にこそ耳を傾けてその内容を吟味すべきだと言うか、常に永遠の今として自分の中のスターリン主義と向き合い続けるしかないのだということだと思います。
こんばんは。小生は広く暴力の問題として、スターリン主義とファシズムを捉えています。暴力は剥き出しの物理的なものという姿なら脅威は少ない――なぜならあからさまだから――のですが、しかし権力という姿態を取ることにより、底知れぬ脅威を、圧倒的な脅威を与えます。
申し訳ないですが、小生はファシズムを左翼の思想の一つと見なしています。勿論、スターリニズムと同様に、「ありうべき様態」からすれば反対物へ転化したものです(弁証法)。
で、なぜ、反対物に転化するのか。そしてそれは、保守から派生した数々のイデオロギーに基づく思想よりも酷いものになり果てるのか。
ここに三つのキーワードがあると思います。上に書いた「暴力」、そして「権力欲」と「恐怖心」。スターリン主義の場合、きっかけは勿論ロシア革命でレーニンが状況に応じて取った戦時共産主義が発端だと多くの識者に示されています。種籾まで奪うエクス(レーニン)は農業集団化(スターリン)を思い起こさせますし、次々と反ボリシェヴィキに行き着き、内戦およびテロでもって反レーニン・ボリシェヴィキを闘った闘志に対する赤色テロは、スターリンの大粛清を思い出させます。しかし、レーニンが生きた時代の暴力と、スターリンの時代の暴力は違うんですよね。レーニンはファニー・カプランに危うく殺されそうになりましたが、あけっぴろげとも言える「警備」状況でのテロ、あからさまな状況でのテロ。カウンターでカプランは確か2日後に殺され、同時にSR左派もかなり殺されたと記憶します。やるか、やられるか。暴力が戦時共産主義を産み、拡大し、スターリンへの途を掃き清めました。
で、スターリンの時代。こちらの暴力はシステマイズされ、誰の上に降り注ぐか分からない不気味さがあります。いつ、スパイとか人民の敵として粛清されるのか。告発者・密告者は少しでも「敵」よりも優位に立ちたいという「権力欲」から、あるいはこちらのほうが圧倒的に多いのですが告発される前に密告してしまえという「恐怖心」。
マルクス主義は、理想主義的な文脈で語られることが多かった気がします。マルクス自身、あるいはもっと強烈にはレーニン自身が言うように、そのような理想主義的なものは「ナンセンス」なんですが。しかし、理想主義的にこれらが捉えられるならば、「善-悪」二元論に立たざるを得ないし、プロテスタンティズム的なキリスト教解釈が世界の多くを支配している現在、これは「敵は死ね」という、カールシュミットが論じた政治世界を現出します。そうなると、「敵に剥き出しの暴力を行使することは善」と簡単に言えますし、また「敵」規定さレルかもしれないという「恐怖心」も、「敵に対して頑張った」という認められたい心、より多くの敵をやっつけるために他の仲間を自分の絵に従わせたいという「権力欲」が亢進します。マルクス主義者が権力を握ると、殆どがスターリン主義――国家権力だけではなく!――になるのは、こういう心理なのではないでしょうか。それが極限まで進んだのが革マルかな、と。
どれもこれも無縁ではないので、スターリン主義を「外在的」に取り扱う人はスターリン主義を理解できないし、克服することなんか不可能ですね。個人的には、マルクス物象化以前の議論=疎外論を徹底的に踏まえることがマルクス主義者にとって非常に大事だと思っています。観念論者としてのマルクス万歳!!