画像元<菅孝行/貝原浩著「全学連」>
 なんかここんとこ続けてアッテンボローさんやRRさんから「『旗旗』で紹介されました」などという、思わず「わしは朝日新聞かい!」と突っ込みたくなるようなタイトルのトラックバックを続けていただきまして、「そない大袈裟にいわんでも」と思っておったんですが、今度は私のほうが、その気持ちがしみじみわかる事態とあいなりました。
なんかここんとこ続けてアッテンボローさんやRRさんから「『旗旗』で紹介されました」などという、思わず「わしは朝日新聞かい!」と突っ込みたくなるようなタイトルのトラックバックを続けていただきまして、「そない大袈裟にいわんでも」と思っておったんですが、今度は私のほうが、その気持ちがしみじみわかる事態とあいなりました。
黒目さんのサイト「despera」の記事で、私の「天皇制=性器説」がとりあげられてしまいました。前にも書きましたが、黒目さんはかつて右翼青年から左翼(しかも無政府主義系)に転向された方です。左翼と言いましてもいろいろあるわけですが、特に無政府主義系の方は天皇制問題についても熱心に取り組んでおられる方が多いです。しかも右翼側の主張も一通り熟知しておられるわけですから、この問題については到底私なんぞが足元にも及ばない造詣をお持ちのはずだと推察しております。
もともとあのエントリーは、私が最初に「天皇制雑感」という記事を書き、それについてRRさんの保守派サイト「こっちへおいでな」でのエントリーで言及していただき、その内容についてさらに私がコメントしたものです。そこではRRさんの「天皇制は日本の骨格」という説に対して、これを批判するんではなく、その土俵にのっかる形で「いやー、天皇を崇拝している人の精神構造から分析するに、骨というより性器(ちんこ)に近いんではないか」と返したわけです。
そのエントリーに対してRRさんからまた反応がありました。
私がここで鼻ほじりながら書いた稚拙な文章があちらで紹介されてしまいました(滝汗 なんかあれですよ、朝生とか観ながらテレビの前で「そりゃちがうよ」とか軽い気持ちでツッコミ入れていたら突然収録スタジオのゲスト席に座らされた気分ですよ(笑
「旗旗さんで紹介されて 」より
まあ、「鼻ほじりながら書いた稚拙な文章」はお互い様(笑)ですので、私としてはこういうやりとりがけっこう楽しかったりしていたわけです。
ところが、RRさんのほうにしか意識がいってなかったところに、突然黒目さんから「戦後天皇制の政治的機能」というきわめて真面目なタイトルと内容のトラックバックをいただいてしまった。しかもその内容が大変に「ごもっとも」なことでございまして、今度は私が「滝汗」をかくはめになってしまいました。
なんか、「加藤茶に向かって得意になってアドリブでボケていたら、突然いかりや長介に背後から『おまえ何やってんだよ!』と思いっきりスリッパで後頭部をはたかれた新人時代の志村けん」状態。ぼーっとしていたところがいっきに目がさめてしまいましったって。思わずモニターの前で姿勢を正してしまいましたよ。
くわしくは是非とも黒目さんのエントリーを読んでいただきたいのですが、黒目さんは私のエントリーを、天皇制をファロス(男根)崇拝運動みたいなもんだと説明しようとするものであるとされ、「ある種の『天皇主義右翼』と呼ばれる人々にとっての天皇は、まさにファロスそのものであった」「戦前においては、これは一致してい」たが、戦後における「現実の天皇制そのものは(右翼が期待するファロス的天皇像と)著しい乖離を見せているわけであ」って、「この両者を、片方を批判する事でもう一方を定義する事は根本的に間違いではないのか?」ということでした。
さらに
◎このような「ファロス的天皇制」が復活することは機能面、政治効率面からも、ありえない。
◎現実の日本史でも天皇が政治権力を握って政治を行った期間のほうが稀有であり、たかだか明治以降の80年間だけを前提に「天皇制は日本人の骨格である」「ちんこである」などというのはなんの根拠もない。
と続きます。まあいちいち「ごもっともです」としか言えないんで、なんか「あらすじを書いて読書感想文の枚数をかせぐ小学生」状態になってますが。
黒目さんのエントリーを読んで記憶がよみがえってきましたが、私はもともと現役時代には「一木一草天皇制論」を批判しておったなあと。左翼にも「天皇制社会主義」なんていう結構トンデモに思える主張を含めていろいろいるわけですが、その中でも「日本という国家は古来よりその一木一草に天皇制が宿っている」つまりイデオロギー的に大変に根深くて手強い敵であると認識している人が少なからずいたわけです。
これに対して私らは、そうでもないんちゃうんけと。天皇(制)に対するイメージは時代と共に変遷してきたもんであって、明治以前には田舎にいけば天皇の存在そのものを知らない日本人もけっこういたみたいだよと。んで明治政府も初期の頃は「天皇はお稲荷様より偉いんだ」みたいなPRを一生懸命してたんだと。これはいわば「党の主張」であったわけですが、私も「それはそうだろうな」と思います。左右の思想というよりは、ごく自然に考えれば、明治以降の絶対天皇制時代に人造的に作られた天皇(制)イメージをもって、全日本史を通じて流布していたように考えるほうがむしろ不自然であるわけで、それは裏返しの「左翼版皇国史観」だと思います。
私らのいた運動圏は左翼の中でもディープでコアな部分だったし、また、運動が衰退している時に、さらにその中でももろに衰退している組織にいたら、自分の周囲でデモとかに参加している人は全員が「天皇制打倒!」な人ばかりであり、一般世論が「天皇制維持」に賛成だったら、「このままでは自分たちの運動はますます駄目になる」→「なんとかしないといけない」→「しかしどうすればいいのか?壁は厚いぞ!」的になるのはわかります。でも、そんなに深刻に考えこまんでも、日本人ちゅうのは悪くいえばもっとええ加減で、良く言えば柔軟だと思うんですよね。当時の私らみたいに組織が拡大して勢いのある時には、ちょうど年末にクリスマスしたその一週間後には初詣に行くみたいに、「天皇制?別にええんちゃうの」と思っている人が、いくらでも反戦デモに参加してくるわけです。そんで「貴族あれば賎民あり。天皇制に賛成することは差別に賛成することちゃうか?」程度の説明で「そりゃそやな」で、コロッと「天皇制反対」になってしまうという。
ですからねー、やっぱり黒目さんが別のエントリーでおっしゃっている「ある意味、現時点において天皇制を批判する事が政治的にマイナスなのではないかという思いにすらとらわれる。今の右派勢力の伸張は、決して天皇をかついでの登場ではないからだ」というのは正直に言って確かにありました。そういうのは反戦運動で集まってきた人が、今後も反戦を続けていくためには天皇制に反対せなあかんとなったら、簡単に「反対!」となっちまう程度のもんであって、「入り口」のところで反天皇制の踏み絵を踏ませるのは、ある意味「めんどうくさいな~」と。
しかし70年代後半から80年代にかけては「天皇をかついで」の国家への国民統合がいろいろと画策されてきた時期にあたっており、「めんどくさい」とは言ってもおれんかった。一方で戦後に構築されてきた「ソフトな天皇(制)イメージ」をあなどることができないのは事実であって、これがどういう役割を果たすべく作られてきたのか、あるいは現実に果たしているのか、どう対決し、向かい合っていくのか、あんまり簡単に「そりゃそやな」程度ではなく、ちゃんと考えていかなあかんわけです。黒目さんのエントリーのタイトルはそのへんの考察ということですね。
これに対して私のエントリーが全然そのへんの考察をしてない、戦後天皇制の解明になってない、ちゅうか、そういう視点で見た場合には根本的に誤っていると言われてしまえば、その通りだと思うわけです。
実はエントリーの最後にリンク集でつけておきましたけれども、あれを書く前に、たとえば憲法改正で現在第1章にある天皇が第2章に「格下げ」されてしまう「危険」があるが、それは「日本の危機」であるだとか、女性を天皇にしてその子が皇位を継承したら、それは「女系」で世襲されたことになるので、その新天皇以降の天皇は「正統な天皇」ではないことになるだの、ほんとに頭痛くなるというか、もう目まいしそうなほどアナクロな主張ばっかり読んだんですよね。ですからあれは「戦後天皇制の解明」ではなくて、そういう「アナクロな人の頭の中にある天皇制の解明」になっちゃってるわけです。実際にはこういうアナクロな主張は天皇家の方々の立場に立って考えてみても「いいからほっといてくれ、つーか、おまいら黙れ!」ぐらいの勢いでしょうね。
現在のソフト天皇制に対する認識が非常に浅い(ちゅうか理論的に80年代で止まってる)んで、またしても「片方を批判する事でもう一方を定義する」ことになってしまうかもしれませんが、私らの現役時代、具体的には「在位60年式典」や天皇代替りくらいまでですけれども、あの頃に「天皇を担ぎ出してくる人」らってのは、まだ頭の中に「ファロス的天皇制イメージ」を持っていたように思います。それがおよそ「ファロス的」でない今の天皇になって、皇太子の結婚くらいから、「天皇を担ぎ出してくる人」の担ぎ出し方に変化が見られます。まあそれも、従来の「国家への統合」を前面に出して「天皇のお人柄」を背景的な武器にしてたんが、「お人柄」を前面に出して、その着物のすそから「国家への統合」という鎧が見えるというふうに変わった、つまり「1枚目と2枚目を入れ替えた」だけにすぎんのかもしれませんが。
見方を変えれば「陛下のお人柄」を強調しているうちに、「国民の天皇(制)への支持」がそこに集中してしまった。なかなか「国家への忠誠」の結節点とならない。つまり「天皇制存続を支持している人=靖国参拝やイラク戦争も支持」という構図が成立しないという「弱さ」の表れと言えないこともない。もちろん今の段階でこの逆の構図は成立しつつあるんで、油断はできないところですが。
しかしなんやね。まあ「女系がはさまったら正統でなくなる」ちゅう人ほどではないけど、「60年式典」くらいで頭の中が止まってる私もアナクロかもしれんね。
●今までの経過
◇天皇制雑感(旗旗)
◇サイパン慰霊の旅(despera)
◇真面目な左翼の人のblogは面白いぞ★( こっちへおいでな)
◇天皇制=かしこきところ説(旗旗)
◇旗旗さんで紹介されてしまいました(滝汗(こっちへおいでな)
◇戦後天皇制の政治的機能 その1(despera)








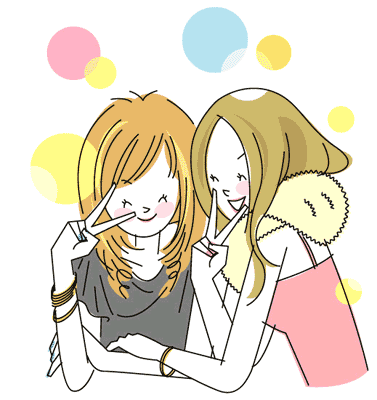





「迷惑ごと対策」のための新約聖書 岩田薫 『住民運動必勝マニ…
すばらしい。みなさんの周りに住む、迷惑住民・迷惑集団たち。高層マンション・騒音問題・道路公害・迷惑施設から、さまざまな公共事業(高速道路・区画整理事業・ダム・新…
ぬあにをおっしゃいますやら(w
私はそもそもは「世の中の悪い事の大体の根元は天皇制なんだ」などと主張しておったわけですが(W。
天皇代替わり期に言われていた「イデオロギー装置論」みたいなんをいっぺん、ちゃんと整理して書いておこうかなと思いまして、その前振りなわけですが。
なんつーのかなあ、左翼のイメージの中では、「軍国主義の復活」というのは、「絶対主義天皇制」復活→特高警察復活→皇軍復活→アジア侵略戦争みたいなセットで、まさに戦前の体制がもう一度復活する、というようなイメージを描いていたと思うのですが、全然はずれやんけ、と。
で、一方で代替わり期にはインチキな「日本文化評論家」がウンカの如く湧いて出て、天皇制イデオロギーを「日本文化」を持ち出して補強するというような事をやっていて。
その辺で、やはり天皇制が具体的にどのように我々に作用しているのか、というのを見ていくしかないんじゃないのかとゆう
そおゆう話なんです。
わははは(笑 タイトル見て机の前で椅子ごと後ろにのけぞって倒れそうになりました(w いやいや意見や知識の交換は楽しいですね。等価交換ではなくてこちらにいただくぶんが圧倒的に多いのは恐縮の極みです(笑
いやん★
いやん★
戦後天皇制の政治的機能 その2
では、天皇制の政治的機能とはなんなのか。
昔していたような議論を思い出しておく事も無益ではなかろう。
だいたい、サヨクの業界というものは「難しい事を言った方が…
これはもう10年前に書いた文章ですけど、少し字句修正をしたのみで再録します。アフガン板他にも書きましたけど、まあ、多分そんなに荒れるほどの反応もないだろうし、右の側からの一つの皇室論として参考になればと。
急いで付け加えておきますが、まあ誤解する人はいないでしょうけど、著者の萩原さんは優れたファンタジー作家で、右翼でも何でもありません。こちらの側はこう読んだ、というだけですので。
書評「空色勾玉」(萩原規子著)徳間書店
「天皇論議からタブーをなくし、開かれた議論をしていこう」鈴木邦男氏のこの勇気ある発言以降、天皇および天皇制議論はかなり自由なものになったかのように見える。特に網野義彦氏、赤坂憲雄氏等優れた歴史学者の研究には学ぶべきことが多い。
そして昭和天皇の崩御のあと、天皇制を論ずるときにすぐ大東亜戦争の責任論に言及する姿勢は、一部の左翼系ジャーナリズムや贖罪史観論者を除いてはきわめて少なくなった。このことを歴史認識の後退や天皇制の風化として危惧する声は左右両翼を問わず存在し、それも確かに一面の真理をついてはいるが、あえて「天皇および天皇制」を、単に明治以降の近代日本の問題と結びつけて考えるのではなく、古代に始まる日本文化の根底を支える『日本史を貫く皇室伝統』としてより広く豊かに語るための場がやっとできたものとして捉えるべきではないだろうか。
今こそ民族派も、「YP・戦後史観」から自由になるだけでなく、プロシャ型近代帝国の影響を強く受けた「明治帝国史観」から解き放たれるべきである。そもそも「天皇問題とは、論理を越えた精神や信仰の問題」「自分の内在の<聖>性を見ることが、即、天皇をおもう心」(「新右翼」鈴木邦男)であり、また天皇及び天皇制が今なお私達の民族的無意識の内に深く水脈として流れる一つの文化的根源であるならば、皇室とその伝統、歴史を語るとき、「漢意」(からごころ)である「論」という形式のみを選ぶべきだはなく、時には「唄・語り=文学」としてうたわれるべきではないだろうか。
児童文学作家、萩原規子氏の「空色勾玉」(徳間書店)は、「天皇制」を文学として表現しえた数少ない作品の一つだ。たしかに古代日本を舞台にした「歴史小説」は他にもある。しかし、その多くは現代人の視点から当時の人物や事件をどう解釈するかという、結局の所司馬遼太郎的な、「現代人から見た歴史」にとどまる。
しかし、たとえ我々から見ればいかに神話や伝説の世界が不思議なものに見えようとも、古代人にとってそれはまさしく「現実」だったのであり、太陽が東の空を昇るのを「神のあらわれ」と観た人の目が、現代の我々よりもより美しいものを感じる力を持っていたかもしれないではないか。この作品には、まだ「神」と「人」と「自然」とが豊かに交信していた古代世界が、その価値観と精神のままに描かれている。
舞台は、「豊藁原の国=古代日本」。生命と光の神・高光輝の大御神をあがめ、その元に統一国家をうちたてようという「輝の宴」と、死と再生の神・闇御津波の大御神につかえ、それぞれの土地の「土地神=土着の神」を守ろうとする「闇の一族=土ぐも」が激しい抗争を繰り広げていた。闇の一族の血を引く少女・狭也は、両親を輝の軍勢に殺されたみなし子。彼女は輝の宮に仕える村で育てられ一五歳の村祭りの夜、楽人として村を訪れた闇の一族に、自分が闇の血を引くものだったことを知らされる。しかし同じ晩、闇の一族を追って村を訪れた輝の宮の王子・月夜王と出会う。気高く美しい王は狭也の憧れだった。王は、狭也を采女(巫女)として都に連れていくことを告げる。この異例のとりたてに狭也は驚き、自分が身分卑しくまた闇の血を引くものであることを言うが、王はそなたの水は清い。まだ闇にも濁らぬままにある。生まれを気にすることはない。係累にこだわるのは、豊葦原の人間の習癖であって、天つ父神のおもんぱかるところではない。」と語る。狭也は幸福の絶頂で憧れの都、まほろばへ向かう。
しかし、都での生活は狭也に疎外と絶望しかもたらさなかった。規律ずくめの毎日、ほかの采女から受ける差別、何よりも苦しかったのは、月夜王の真の愛はもう1人の輝の王子にして姉である照日王にそそがれ、自分には向けられないことを知ったことだった。
さらに決定的だったのは、生まれを隠して都に潜入した闇の氏族の少年・烏彦が、捕らわれて、「形代=犠牲(いけにえ)」にされることを目の当たりにしたことである。永遠の命を持つ「輝の王」=「神」の、一人一人の生命や死をあまりにも軽んずる姿勢に、狭也はやはり自分は闇の一族として生きていくことを決意する。
鳥彦を救い出すために、宮中の奥深い神殿に忍び込んだ狭也は、そこで両手両足を縛られた照日王、月夜王に続くもう一人の王子・稚羽矢に出会う。稚羽矢は輝の王家でありながら、闇の世界に魅かれる「できそこない」として幽閉されていたのだった。狭也と稚羽矢は共に深くつながりあうものを感じる。
「あたしたち、正反対で、とてもよく似てるんだわ。二人とも、一族のわくをこえたものに憧れてしまったのよ。」
二人は神殿の祭壇に収められている「大蛇(おろち)の剣」、稚羽矢以外の誰にも使いこなすことの出来ない危険な魔法の剣の力で都を脱出し、闇の氏族に合流する。ここから「光」と「闇」との戦いは全く新しい展開をむかえることになる。
ストーリーの前半を紹介してみたが、「光」と「闇」の対立という構図は、古代史研究の大テーマの一つである「弥生文化」VS「縄文文化」という構図にそのまま当てはまることは間違いない。しかし、従来の論は、しばしば縄文文明を、国家以前の自然と共存する豊かで自由な文明と美化し、弥生を古代天皇制に連なる農耕文化・権力制度として批判することに終始する傾向があった。これは、余りにも現代の史観(それも密輸入された左派・アナーキズム史観)である。本書の優れているのは、「光=弥生権力」の美しさと気高さを、その残酷さと共に認め、かつ後半のストーリー展開で「光」と「闇」、「神」と「人」、「生」と「死」、「弥生文化」と「縄文文化」が和解・合一していく過程を、日本の国づくりの原点として見事に描き切っていることだ。
そのストーリーの雄大さはとてもここに小さくまとめることを許さないが、「神」と「人」の和解の上に立つ「天皇」ということの意味を、これほど魅力的に考えさせてくれた小説を私は他に知らない。
そして、それぞれの対立に「和解」をもたらす狭也と稚羽矢が、二人とも「一族のできそこない」「夢を見るもの」「孤独なもの」であると言う設定も興味深い。盲目の皇子蝉丸、英雄にして悲劇的人物であるヤマトタケル等、わが国の皇室伝統には、内部にあえて「一族から疎外されるもの」を生み、またその人こそが偉大な事業や文化、芸術の源となるという発想がある。この精神は、古代精神の万華鏡というべき万葉集の編纂姿勢にも現れている。万葉集が、国家に対する反逆者、政治犯として罰せられた皇子や貴族の詩でも無視することなく掲載しているのは、このような人々の死を追悼し、その霊を沈めると共に、反抗者の側、無実の罪で人生を絶たれた側にもまた、国家の「正史」とは違うもう一つの「物語」があることを認め、それを文学の世界に書き留めておこうとしたのだ。
これこそが明治以降の近代天皇制が見失ってしまった、日本伝統の「闇の氏族」の豊かさである。それは単純な「光の権力」だけでなく「権力」を自ら解体する「闇=異端の文化」を生み出す力を持っていたのだ。
この作品に描かれる狭也と稚羽矢、とくに稚羽矢は、老若男女を問わず沢山の読者の共感を呼ぶはずだ。彼は「光の世界」、この現実を力強く生き、処理し、成功していくことよりも、どうしても夢の世界、形なき世界、死の世界に魅力を感じてしまい、「できそこない」として牢につながれる。しかし私達は、一見この現代社会を「光」として生き、「死=闇」を忘れたふりをしていながら、実は心の奥底にもう一人の稚羽矢を幽閉し、無理にでも閉じこめておこうとしているのだ。
「闇」を閉じこめる世界ほど恐ろしいものはない。そういう世界はいつか必ず、閉じこめられることによって歪み切った闇に復讐されることだろう。一九九五年、私達はその一つのあらわれを地下鉄サリン事件で見せつけられることになった。
日本文化の、光と闇を内在させた豊かさと深さ。もう一度それを思い起こすことこそ、日本民族主義の精神的ルネッサンスである。