戸村一作:著『小説三里塚』(目次へもどる)
第10話 旱魃(かんばつ)
 新緑の美しい下総高原の初夏、五月も過ぎると、蒸し暑い夏が回ってきた。
新緑の美しい下総高原の初夏、五月も過ぎると、蒸し暑い夏が回ってきた。
朝早く起きた武治は小屋の前に立って腕を組み、空を見上げた。
「ああ、この空では当分駄目だな」
説子は武治の独言を小屋の中で聞いていた。
「この分じゃ、父ちゃん、落花も里芋もみんな駄目になっちゃうよ」
武治はしばらく空を見渡していたが、しょげた表情で小屋の中に入ってきた。
「説子!もしこの日照りが続いたら、大変だ」
「いつまでも小屋住まいじゃね……それに父ちゃん来年は和年も学校だし、金もかかる一方だし……」
「その先に、このままいけば、日干しだよ」
「父ちゃん、何をやってもうまくいかないもんだわね」
武治は説子の言葉に黙って頭を抱え、頂垂れていた。朝の強い陽射しが、小屋の中まで射し込んできた。光は妙に赤味を帯びて、不気味だった、恵みの太陽が、最大の愁いに変わろうとは……。
ついに二ヵ月も一滴の雨すらなく、開拓地の畑は焼け灰のように乾き切った。軽霧土は風が吹けば空に舞い上がり、赤く天を掩った。
夏が来た。一滴の雨も落ちてこない。武治はひとり夜ふけの星空を仰いで立った。毎夜降るような、星空だ。茫然として自失し、ただ嘆息した。
北総台地一帯を襲った旱魃で、畑作は日に日に干上がっていく。まるで鉄板の上で、煎りつけられるようだ。じりじりと音を立てるように、落花生、里芋、生姜の葉が眼に見えてよじれていく。武治はわが身が焼かれる思いだった。
夜露が降りれば、かろうじて作物たちは、蘇った。だが再び朝がきて、真夏の太陽が頭上に輝き始めると、一たまりもなく凋んでいった。妻とともに荒野を切り開き、種を蒔き、芽生え育った作物――実りの秋を前にしての旱魃だ。政府も県も何ら手を打たなかった。むしろ放置状態だった。
木の根の入植者たちは午後のひと時、例の松林の芝生に円座を作って集まった。その真中に座って武治は、旱魃に対する対策を訴えた。
「みなさん、どうやらこの旱魃も長く続くらしいし、これでいけば開拓地はまず全滅だ。そうなると直接ひびくのは入植者の生活だが、何とかする対策はなかっぺか」
「木川さん、対策って、これどうすることもできめえ。まさか雨を降らせるごともできめえし、それに国や県で特別、開拓地にだけ対策をとるということもあんめぇしな……」
「とにかく、高橋さん、このままいけば今年の作は全滅だ」
高橋裕次は入植者だが本職は大工で、その家族が主として農業を営んでいた。みんな申し合せたように雲一つない青空を見上げて、憂い顔だった。
「全く困ったことだ」
「井戸水も涸れてきたし、田んぽの水までなくなる……、ごんな年は滅多にねえよ」
「全く、八〇年振りとかいうよ」
「今さら、突き抜き井戸を掘って水をかけるということもできめえしな……」
「そりゃできねぇてことあねぇ。県や市がやる気なら何でもできべぇよ」
「陳情してみるか。大勢のカなら木の根の原を起したように何とかなるかもしんねぇぞ」
と、大工の高橋がいった。
「もう今年はここへきちゃ間に合うめぇ。落花生まで葉がよじれっちゃったよ」
「とにかく、百姓に一番大切なもんは何はなくとも水だよ、な、水!」
「うん、そうだ!水が一番大切だということが、身に染みてわかったよ」
「それにこの辺りには川という川はねえし、水を引くにもその源がねえしな……」
「これからの百姓は、農業用水がどうしても必要だな。おっかなくて百姓なんかできっこねえ……」
今まで黙って腕を組んで聞いていた武治が、その時、口を入れた。
「うん、われわれはこれから家を建てて、電気も引かねばならねえが、まず、水の問題が百姓にとっては痛切だ。種下して肥やしやればいいとばっかり思ってたが、大間違いだ」
「そうだよ。今度ぱかりはこの旱魃で身に染みてわかったよ」
「全く天侯次第で百日鉄砲屁一つだ!」
その時、傍から須田カが、声をかけた。
「いや、百姓って大博打を張るようなもんだ。高い肥料や種、それに農薬ぶんまいてよ、雨降んなけりゃペケときてんだからよ」
須田はこの界隈でも知れた博打うちだった。その言葉も彼の体験から、得たものだろう。たしかにそうかも知れぬ。いくら金と労カを費しても、天候次第だから運は天に任せろとでもいうのか――。彼は何もかも投げやりで、武治とは対照的だった。
武治は常日頃、考えていた。
何とか博打農業から脱却し、災害に耐えうる農業形態を作らねば、開拓者の将来はないと――。武治は一同を見回して再びいった。
「たしかに今の百姓の仕事は、須田さんのいうように博打をうつようなものだ。しかしだ、そのままじゃ、百姓は空っ尻になっちゃう。この悪運を共同の力でどう切り開いてゆくかが問題だよ。でねぇと、みんな共倒れだ。まだ掘立小屋で電気も井戸もねぇ。やりてぇことぁいっぱいあるが、まずこの旱魃をどうするかだ」
みんな慎重な面持ちで、武治の顔を見つめた。須田だけは空とぽけた表情で、晴れ渡った空を眺めて、悠然と煙草をくゆらしていた。だが、武治の言葉をきっかけにいろんな意見が出てきた。
「県に対策と補償を陳情したら……」
「いや、この旱魃じゃいくら国だって雨を降らせることはできめぇ、それにすぐ井戸掘ってどうこうということもできめぇ」
「いや、それをやらせるんだよ」
「そうだ、やるもやらねえもねえ、やらせなけりゃ、俺らは干死んじゃうんだから……」
「そんなこといったって無駄だよ。誰が木の根だけにそんなことやるもんか」
「それよりもだな、被害調査させ、補償金をうんととった方が有利だぞ」
「かりに補償金をとったって涙金だ。焼け石に水だよ。誰がそんな金で一年も募らせるもんか」
「それにさっき木川さんがいったように、木の根もこのままではしょうがねえし、まず家造りと電気はどうしてもやらねばなんねえし……」
「もう、この秋頃にはぽつぽつ始めなけりゃ……だから補償金で足んねえとごろは低利の営農資金でも農協からひっぱり出して使うほかあんめえ。それが一番面倒臭くなくて簡単だよ。やはり、この際利用できる金は国であれ、県であれ、どんどんひっぱり出すごとだ」
と、いうのは岩沢倶己だった。彼はあくまで補助金派の中心に立って、武治とは意見が対立し、最後まで噛み合わなかった。
そこで武治は一つの提言をした。
「災害補償や営農資金の利用もいいが、切角、実りの秋を迎えた作物が可哀相だ。みんなで深井戸を掘って、畑に水を引く方法は考えられねえもんかなー」
「しかし、もうここへきちゃどんなに水をかけたって何したって、陽が入っちゃったんだから無駄だよ。この際、岩沢のいうようにこのままで被害補償をとるよりほかあんめえ、これも天災だからなー」
武治の発言に対して二、三の者の意見もあったが、結局旱魃対策に対して何らの積極的な具体案も見出されず、尻切れとんぼのまま解散した。
共同で旱魃対策がやれるかと半ば期待していた武治の失望は大きかった。





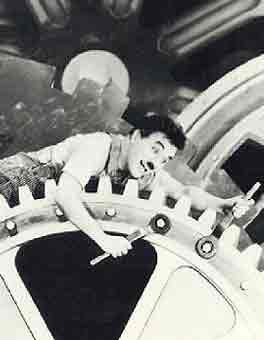








この記事への質問・一言コメントをどうぞ AIコースケと議論しよう!
回答には文字数制限があるため、制限を超えると途中で打ち切られることがあります。