
本書『闘う女性主体の確立をめざして』は1983年2月『理論戦線』17号での論文「『第二の性』をこえる女性解放闘争の方向」(以下、第一論文と略します)提出以来、85年にいたるまで、党内の多くの同志達からよせられてきた女性解放、あるいは女性活動家の主体形成をめぐる諸論文、所感等を再録したものです。
これらの文章は、ほとんどが『闘う労働者』に掲載されたため、現在各地区に残っておらず、そのことが女性解放や女性の主体形成に関する学習・討論を非常に困難なものとさせてきました。また、新たに組織に結集した同志の中には、その過程で提起された諸内容、さらには様々な論争の存在そのものを知らないという同志も生まれています。
ところが、今日われわれをとりまく政治状況は、そうした女性解放についての階級的視点の確立、とりわけ女性活動家がいかにして革命的主体への発展をかちとっていくのかという課題への全党的とりくみを、再度われわれに迫るものとなってきています。
昨年5・7山田宣言以降、日帝のアジア再侵略へむけた治安弾圧型国家再編、その最大の環たる「過激派壊滅作戦」=革命党破壊攻撃の嵐が吹き荒れ、わが同盟にあっても、86年権力の別働隊としての右翼民間反革命による襲撃・白色テロ、87年4・25-6・19-7・11弾圧、無差別強制家宅捜索、あるいは情宣活動の妨害等々として、敵の攻撃は日増しに激化しています。
かかる中にあって、これを打ち返し、戦略的武装を堅持しつつ、武装闘争の遂行と全人民との一層の結合を同時に押し進めることによりプロレタリア日本革命の未来をたぐりよせていくというわが同盟の双肩にかけられた階級的任務は、個々の主体にすさまじいまでの飛躍を問うています。小ブル的理念をふりかざすのではなく、かつまた言われたことをそれとしてこなしていけばいいというものでもない、創造的に自己の任務にとりくみ、そこでの的確な判断と対処をなしうる、まさに革命運動の実践的遂行者としての組織創造的な諸能力の形成が、すべての同志達の課題になっているということです。
そして、わが党・革命勢力を構成する女性同志にとっても、これらの課題に応えることが、男性の同志と同様に要求されていることはいうまでもありません。しかしながら、そのためには歴史的・社会的に特殊な位置におかれてきた女性存在をマルクス主義的にとらえかえし、ブルジョア的な「女らしさ」や「没主体性」として女性に対し強要されているブルジョア・イデオロギーと対決していくことが不可欠なのです。何故なら、80年代後期階級闘争の激動をきりひらくための政治と暴力の主体化、責任性や指導性の獲得という命題は、そのようなブルジョア的「女らしさ」等とは全くもって相容れないものだからです。
こうした観点を再度明らかにし、戦旗派主体形成論の一領域として、女性活動家の主体形成に特殊に要求される内容を再確認していくこと、それが本書刊行の第一の目的です。
また、女性解放論自体のイデオロギー的深化という課題もわれわれの前には存在しています。本書に収録された諸論文はいずれもが党的な結論としての完結性を与えられたものではありません。わが同盟の女性解放論構築へ向けた過渡的位置をなすものとして本書があることをあらかじめふまえた上で、これまでにつくりだされた女性解放に関する理論的諸内容、論争の経緯を本書の学習を通じ対象化してほしいと思います。
そして本書の革命的地平を継承・発展させながらこれを超えるマルクス主義的女性解放論を創出するという党的課題に、是非とも多くの同志諸君が挑戦されることを訴えるものです。そのための資料として本書が活用されること、これが刊行の第二の目的です。
ところで、こんにちの第四インターにあっては、内部分裂の進行が女性解放グループの出現・党内分派結成という事態をひきおこしています(『世界革命』1011号=9月21日号で発表)。とにかく男は敵だ!というようなこの女解グループの主張と、これに何ら党的批判を加えられない中央委員会のみじめな姿のどちらもが、第四インターにおける女性解放論のあまりの貧困性をものがたっています。
この第四インターの惨状を反面教師としてみるとき、われわれは女性解放に関する革命的視点の確立という作業が、ひとり女性の手にのみ委ねられるべきものではなく、まさにレーニン主義党としてのわれわれ総体の課題であることを痛感せざるを得ません。もとより女性の解放が女性自身の決起なくして実現され得ないのは自明のことですが、ブルジョア的「女性」性の発現も他ならぬ男性との関係性の中において表出されるものである以上、人間の普遍的解放へ向けた作業の一環を、男性もまた担うのでなければなりません。
そうした点からいって、本書は革命党の基礎文献として広く全党的に共有化され、斟酌されるべきものであり、本書の出版をつうじ組織的に活発な論議がかわされていくことを願うものです。
本書は、第1部「『理戦』17号論文をめぐる論争」、第2部「女性革命家への飛躍に向けた決意」、第3部「85年『研究ノート』とそれへの批判」、の3部から構成されています。さまざまな見解の提出されてきた経過を明らかにするという本書の性格上、ほとんどを発表の順をおった編年体形式で編集してあり、また内容的には一切の変更を加えていないことを付記しておきたいと思います。
さて、第1部ですが、ここには第一論文をめぐる党内論争、そしてアダチ・グループの須美論文批判に対する反批判、という二つの内容を収録しました。ここでは結論的にいって、須美第一論文の切り拓いた革命的地平を押さえていってほしいと考えます。
83年2月に発表された須美第一論文は、女性活動家の主体形成のあり方について、党的に新たな視点を打ち出しました。そこでの展開は、ボーボワールの『第二の性』に依拠しながら「つくられる性」としての女性の存在を明らかにし、しかしながらマルクス主義者ではないボーボワールには女性解放の現実的方向性をさし示しえなかった、その限界をマルクス主義的観点においてのりこえることが必要だとして、女性に対する抑圧、女性の世界史的敗北の根拠は私有財産の発生=生産と所有の分離からもたらされた母権の転覆にあり、その要因は戦争の生業化である、ゆえに女性解放の方向とはプロレタリア革命との結合による私有財産・国家・単婚家族の止揚、家事・育児労働の社会化にこそあるというものです。
この論旨自体は、要するにボーボワールの問題意識に立脚しながら『単婚と家族』での宮崎杏子(現在の第四インター・ボルシェビキ派、これが書かれた当時は革共同中核派からの分派過程にあった)の内容を展開したというものでしたが、この論文が『単婚と家族』をもこえる地平をきりひらいた点は、宮崎が女性解放論一般として「政治と暴力の奪還」を論じたことに対し、須美論文ではそれを担う担い手の問題を問題にし、「政治と暴力の奪還」にとどまらぬ、女性自身のブルジョア的女性観との内在的対決を通じた「政治と暴力の主体化」を論じたことにあります。そして、まさにこの点こそ、第一論文が党的にも画期的な位置をなした根拠があったのです。
われわれのそれ以前の女性解放に関する論文は、唯一、立原みづほの「女性解放闘争の革命的展開とは何か」(74年、『何を守り何を発展させるべきか』所収)が存在したのみでした。しかし、この論文は主要にはリブ批判を目的として書かれたもので、女性活動家の主体形成を論じたものではありません。また、79年~80年頃に女性活動家の抱える問題が組織的に取り上げられたことがありましたが、これらは七九的陥穽に色濃く規定された論議であり、そこで語られた内容も子育てや家事労働の苦労談にとどまっていました。70年代に活動の中心を担ってきた女性達の多くが一定の年齢に達し、結婚→出産により組織活動の一線から身をひいていく中で、女性活動家にとってはそれが当たり前のことであるかのような風潮が党的にも一般化されていたのです。
こうした組織現実に対し、須美第一論文は、「良き母」になることだけが女性の人生なのではない、女性の「子産み道具化」を女性自身が内在的に止揚していく論理を獲得していかなければならないのだ、と訴えました。すなわち、須美第一論文は、当時の党建設の歴史性・現実性の中ではきわめて革命的な提起をなしたのです。
ところが、この論文の提出は、その受け止め方において党内からの反発をもうみださしめました。その多くは、子持ちの女性活動家からの「子供を産んだことがいけなかったのだろうか。自分はいったいどうすればいいんだろう」という素朴な疑問の形をとっていましたが、これをむしろ子供の存在は革命運動にとって必要なのだ、と積極的に主張したのが、水野あきの「『女性解放闘争の方向』を読んで」です。
水野の主張は、須美論文においては「活動家たらんとする女性がどう闘い続けていくのか」ということと「婦人の組織化をいかにして実現するのか」が混在化されている、そして後者のためにこそ前者はあるのだから、子供の存在は革命運動の中に積極的に位置づけられるべきだ、というものです。「婦人の組織化を考える時に、子供の存在はプロレタリア女性の中にわけいっていくための武器、絶好のチャンスとしてみることはできないでしょうか」「現実の矛盾の中で呻吟する女性達の闘いへの息吹を、子供をもつ女性活動家であるからこそ、階級的に組織していくことができるのではないでしょうか」というのがその論旨でした。
これに対して須美は、「(第一論文の)核心的内容は、女性解放に対する基本的なマルクス主義的観点の整理であり、それを実現していくにあたってまず女性が伝統的に培われてきた内なる受動性や保守性を打破し、歴史性・社会性・階級性を奪還すべく革命的人生を闘いとらねばならないことを訴えた点にある」、ゆえに第一論文には婦人の組織化という問題意識は含まれていない、としたうえで、水野の主張には女性存在に関するマルクス主義的対象化がなく、女性のブルジョア的実存を自己肯定しているにすぎない、とこれをきっぱりと退けました。さらに、「夫婦がお互いに全的に革命運動に身を投じようとする場合、子供は産むべきではない」「女性は『適齢期になったら結婚し、そのうち子供を産んで母になる』というブルジョア的ライフプランを無批判に受け入れてはならず、逆に『家族』や『育児』に対するマルクス主義的観点がしっかりと確立されていなければならない」と、第一論文の視点をより鮮明にさせたのです。
女性革命家としての生き方、実存を高く掲げ抜いた須美と、旧来からの女性活動家のあり方を変えようとしない水野の見解の差は歴然としていました。ゆえにこの論争以降、須美の提起に応え、女性革命家の人生を選びとっていこうとする女性活動家が党内に続々と誕生していくことになったのです。
続く立原の「須美玲子『女性解放』論文によせて」も、「革命運動を担わんとする決意の高さという点において」須美を支持、水野の主張は「子供の存在に意味付与していく」ものでしかないとしました。立原はまた、須美第一論文における党的理論や共同主観の継承性の欠如を指摘しましたが、ここでは問題点の指摘という段階にとどまったため、女性解放論の体系的論述というイデオロギー作業は、それ以降もひき続きわれわれの課題として残されていったわけです。
第1部最後の「レーニン主義党建設から逃亡するアダチ・グループ」という論文は、『女性解放研究』誌上でのアダチの須美論文批判(83年夏)に対する反批判として書かれたものです。大衆迎合・サークル主義のアダチには、女性の革命的主体形成を論じた須美第一論文の意義などさっぱり理解できず、あろうことかこれを「糾弾権の否定」などといいなし、わが同盟への矮小な敵対をおこなってきたのです。本論文においては、このアダチの「差別糾弾主義」の限界性がはっきりと暴き出されています。また、この論文と、前述した『何・何』立原論文の内容の対象化によって、第四インター・女解グループの主張へのわれわれの批判的観点も基本的に確認されることと思います。なお、この論文は第2部に収録したものと時期的に前後していますが、編集の都合上第1部に組み入れました。
第2部は、各地区の先頭で闘う女性活動家からよせられた、『シンデレラ・コンプレックス』(コレット・ダウリング著)と『私にも話させて』(ドミティーラ著)の書評です。『シンデレラ・コンプレックス』は83年、『私にも話させて』は85年暮に、それぞれ党内の多くの同志達に読まれ、その感想をめぐる討論がかわされたものです。
これらの著書の内容については本文の中で詳しく述べられているのでここでは触れませんが、これらの書評は書評という形をとってはいるものの、内容的には女性活動家の主体形成に関する党的提起との関係で書かれており、女性革命家への飛躍という要請が女性同志達にいかに受けとめられていったのかを明らかにするものです。現在、党の第一線を担って闘い抜いている女性同志達が、ブルジョア的女性観と対決し、あるいは第三世界の女性革命家に学びながら、党の要請に真正面から応え抜き、革命戦争の指導者へと自らをつくり変えていこうとした実践的苦闘が、これらの文章から浮かび上がってくるだろうと思います。
これらの文章は論文というような性格のものではありませんが、女性解放一般ではなく、女性活動家の党的主体形成の論理を基軸にすえようという本書刊行の方針から、ここに掲載しました。また、、『シンデレラ・コンプレックス』書評中最後の文章は83年春夏大攻勢の総括として書かれたもので書評ではありませんが、ほぼ同時期の女性の決意が語られているため付け加えておきました。
須美第一論文は、女性革命家への主体的飛躍を訴えたという点で確かに画期的な地平を切り開きましたが、その革命性は子供を産まないことまで決意するというような女性の生き方・実存を論じたという点にあり、イデオロギー的な内容としては多くの不十分性をも有したものでした。ゆえに、女性解放のマルクス主義深化という作業は党的課題として存在し続けていました。こうした中で須美は、自らが第一論文で立脚した宮崎杏子『単婚と家族』を批判的にのりこえることをめざし、女性解放論のイデオロギー的高次化をはたそうとしたのです。
そこで書かれたものが、85年9月『闘う労働者』49号に発表された「研究ノート」でした。ところが、この論文は、第一章を久場嬉子に、第二章を高群逸枝にそれぞれ依拠して書かれたもので、全体としての体系性・整合性を欠くばかりでなく、女性の解放を家事・育児労働からの解放のみに切り縮めてしまい、結論としての『単婚と家族』の批判は『理論戦線』19号松木沢論文からの引用による本多暴力論批判にとどまり何ら宮崎批判とはなりえていない、というふうに、全面的に論理破産したものになってしまったのです。それどころか、宮崎批判中の「疎外家族論の批判」という箇所では「両親-子供というまったくもって自然的な普遍的な関係はどんな時代にも存在する。自分の子供はやはり自分の子であり他人の子ではない」「家族を疎外態たらしめる経済的関係の除去、そのことによって夫婦の自由な愛情と血縁的紐帯のみを結合の根拠とする家族が奪還されていく」などと、家族の止揚・死滅の方向性まで否定してしまったのです。
この「研究ノート」に対しては、党内から多くの批判が上げられました。
「研究ノート」への直接的批判は野平論文、高峰論文によってなされました。野平は「研究ノート」の第一論文からの後退を批判し、家族の止揚の内実を価値法則の止揚との関係でマルクス主義的に明らかにしました。また、高峰は「研究ノート」では『単婚と家族』の内容自体がふまえられていないことを述べ、須美による宮崎批判の限界、革命的主体変革の論理の欠如を批判したのです。
この二つの批判により、「研究ノート」が理論的にも、主体的モメントからいっても、第一論文から大きく後退しており、第一論文のうちだした革命性を水に流すものになっていることがつきだされていったのです。
また、これとは別個の観点から、森下は『単婚と家族』そのものの批判をこころみ、第一論文の地平を継承する女性活動家の主体形成を論じました。仁科論文は、プロレタリア女性存在の対象化を欠く「研究ノート」の女権論的傾向を批判しています。
こうして、須美「研究ノート」は多くの批判を浴び、党的理論としての位置を持つことはできませんでした。しかし、これらの「研究ノート」批判の諸論文もそれぞれが論旨を異ならせており、わが同盟の女性解放論争を完結させるものではありません。
以来、党的に新たな女性解放論は提起されておらず、第3部をこえる理論的内容の創出と女性活動家の実存的飛躍が、現在のわれわれの課題として存在しているのです。
本書に明らかにされた内容は、いずれにしても、わが同盟の中に多くの女性革命家が形成されていく、その闘いのほんの第一歩をしるすものにすぎません。子供がいようがいまいが自己の全実存をかけて帝国主義に立ち向かっていく、そんな第三世界の女性革命家たちに比すならば、われわれがこれまでになしてきたことは、それに向けた決意の打ち固めであり、イデオロギー的な対象化への着手ということであって、女性革命家を形成する前提をつくりだすための闘いであったとさえいえるものです。
こんにち帝国主義の根底的な危機が深まり、戦争と革命の時代の本格的到来が開始されています。わが戦旗・共産同のすべての女性同志は、いまこそ武装し闘う女性革命家への渾身の飛躍を闘いとっていくのでなくてはなりません。不可能を可能とし、なにものをも恐れず突き進む戦旗派魂にかけて、日帝国家権力のあらゆる暴力的弾圧をはねのけ、プロレタリア日本革命の巨大な水路をきりひらこうではありませんか。
1987年10月 『闘う女性主体の確立を目指して』編集委員会

![山村工作隊とは[師匠とバカ助手]](https://bund.jp/wp-content/uploads/2008/09/サムネイル-485x273.jpg)

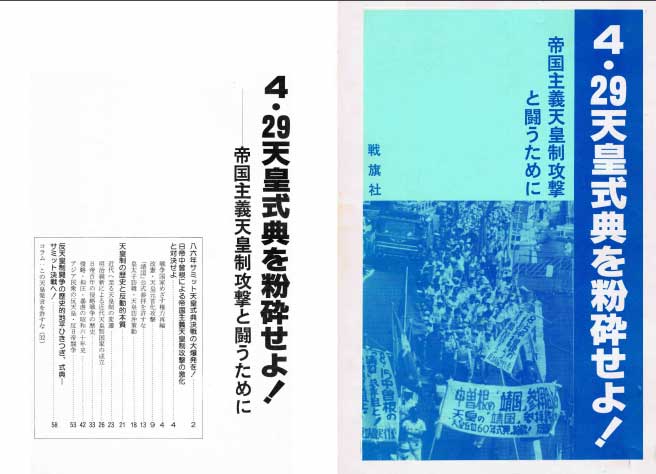


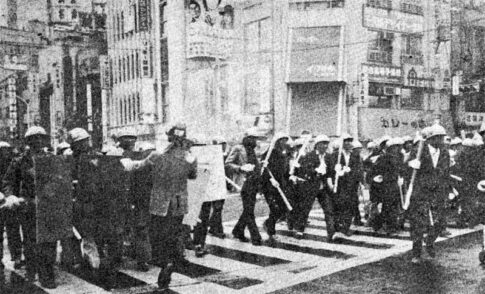







この記事への質問・一言コメントをどうぞ AIコースケと議論しよう!
回答には文字数制限があるため、制限を超えると途中で打ち切られることがあります。