戸村一作:著『小説三里塚』(目次へもどる)
第8回 土地争い
 七月も半ばを過ぎたある朝のことだった。朝霞が立ちこめる麦畑で、武治はいつものように仕事をしていた。
七月も半ばを過ぎたある朝のことだった。朝霞が立ちこめる麦畑で、武治はいつものように仕事をしていた。
突然。
「この野郎ーっ」
「何おーっ」
激しい怒号が霞を裂いて響いた。
思わず、動かす鍬の手を止めて、武治は声の方を見上げた。一人の男が鎌を頭の上に振り上げ、麦畑の中を必死に追いかけていく。そのすぐ先を一人の男が韋駄天のように、逃げていく。二人の足音が、武治の立っている麦畑まで、ドド……ッと地響を伝えてくるようだった。
逃げ手は龍崎伸二で、追っ手は岩沢進だ。二人とも木の根部落の同じ入植者だった。
武治は持っている鍬を放り棄て、岩沢進の後を追って走った。
龍崎は、自分の家に飛び込んだ。かとみると二メートルもある長柄の山刈用大鎌を大上段に振りかざして現われた。刃先が陽を反射して、異様に光り輝いた。
「さあ、こいっ、この野郎」
一瞬、岩沢はギョッとして立ち竦んだ。両膝がガクガク震えるのが武治にも見えた。大鎌を構えて仁王立ちになった龍崎の形相は殺気立ち、身の毛のよだつ思いだった。
龍崎はその構えでじわじわと、岩沢に近づいていく。追手だった岩沢は鎌を持つ手を後に引いたままたじろいで、一歩二歩と後ずさりした。二人の睨み合いは、黙ったまま続いた。二人の距離は、だんだんと狭まっていく。
武治は二人の血相があまりにも険しくて、口を入れる隙もなかった。だがとにかくこのまま捨ててはおけなかった――武治は身の危険も打ち忘れた。
「止めろっ」
武治は二人の間に両手を拡げ、割って入った。
「冷静になって話せばわかる……」
武治は交互に二人の顔を、見つめていった。
龍崎の振り上げた大鎌が、徐々に降り始めた。
「おめえはなー、人の畑に切り込んできたじゃねえかよっ。この盗人野郎っ」
と、龍崎が怒鳴れば、岩沢もそれに応酬した。
「何いってんだい。貴様が俺んちの畑の杭を抜いて、くい込んできたじゃねえかよっ」
「何をっ」
龍崎の大鎌が、またスッと上がった。続いて岩沢も、身構えた。
「まあ、そんな危ねえもんなんか……お互いに怪我したって得はとれねえ。お互いにだ」
武治はわが身の危険も忘れたかのように龍崎に近づき、その手から大鎌を取り返した。
二人の硬直した形相にも、漸く和らぎの表情が見えてきた。お互いに武治の前に、恥入る気色が見えた。
「とにかく、この場は俺に任してくれ。この木の根の原の者がみんな仲良くこれからやろうというのに、今から仲間割れじゃ共倒れになっちゃう」
激昂から覚めて岩沢も鎌を武治に渡した。二人はいくらか正気を取り戻したようだった。それでも、お互いに睨み合いながら右と左に分かれていった。
武治は胸を撫で下し畑から鍬を担いで、小屋に帰った。説子が心配そうな顔で、尋ねた。
「さっき畑の方で大声で怒鳴り合う声が聞こえたけど……」
「うむ、また龍崎と岩沢の土地争いだよ」
「また、やったの」
「やっと今日のところは納まったが、あれですめばいいがな――」
武治は心配そうに顔をしかめた。
同じ巡り合わせでこれからともにここで生きようとする者の中にも、欲望と憎悪が絡み合い、いつも醜聞が絶えなかった。これはひとり龍崎と岩沢だけの争いではなかった。元来、几帳面な性格で部落内のどんな些細な出来事にも責任を感じ、まるで自分ごとのように乗り出してまとめ役を務める武治は、木の根開拓部落の世語役として、常にこうした煩しい人間関係にまで首を突っ込まねばならなかった。
決して彼は単なる「おせっかいや」ではなかった。彼は木の根部落の貴重な存在となって、重宝がられ親しまれていた。そうした彼にさえ「出しゃばりや」という誹りは免れなかったが、彼は人に何といわれても、これはと思ったことには責任を果たさねば自分の気がすまなかった。
「何も人のことかまっていなくたっていいじゃないの……。だから出しゃばりっていわれるのよ」と、説子はよくいった。
妻のいうように小屋の苦しい生活のことを考えれぱ、事実それどころではなかったかも知れない。しかし、武治の頭に絶えずこびりついて離れないものがあった。それは木の根開拓部落をどう作り上げていくかだった。
それにはどうしても入植者同士の心の和がなくてはならぬ。現実は、その全く反対である。武治の思いどおりには、何一つ進まなかったのだ。そればかりか彼の努カでやっと纏まりかけたものまで、些細なことが元でいざこざが起こり、ご破算になる事がたびたびだった。
部落のことに心労すれば労するほど厚い壁に遮られ、将来に向かって部落作りのことを考えると頭が痛くなり、一切放棄して世話役など辞めてしまいたくなることもあった。部落のことを考え、何かことを始めようとすれば、必ずといっていいほどそれを阻むものが現われてきた。それは人間の欲望であり、利已主義だった。
武治は寝床に入ってもまんじりともせず、このことを考えることがあった。次から次へと考えが湧いてきて、なかなか寝つかれなかった。すると翌日の畑仕事に差しつかえて、妻の説子にはきまって小言をいわれた。
木の根には部落の集会所も、なかった。ことあるごとに集まる場は、初めてむしろ旗を立てた松林の芝生だった。寄合いは大概、昼休みを利用してやった。それが長びいてついに半日も過ごしてしまうことさえあった。それでも議事は纏まらなくて、翌日に持ち越すことさえあった。
龍崎と岩沢の争いのあった日から三日目の夜だった。まだ宵の口だったが武治が小屋の脇の便所にいこうとして、外に出た瞬間だった。斜め前に赤々と燃える火の柱が立っているのを見た。暗夜を焦す狼火のような火柱だった。一瞬、武治は茫然とした。が、小屋の中に向かって「おーい、説子火事だっ!」というと、説子が寝間着のまま飛び出してきた。
「あらっ!岩沢さんの小屋じゃないっ」
「俺ちょっと行って見てくる……」
武治は火の柱に向かって、走り出した。
岩沢進の小屋はすでに丸焼けで、辛うじて出した夜具や鍋釜が、暗い周辺に散乱しているばかりだった。岩沢の妻が小屋の燃えるのを見ながら二人の子供を抱えて、闇の中に悄然と立ちつくしていた。岩沢進は佐原の親戚に葬式ができて、朝早くいったまま、まだ帰らなかった。
あちこちの小屋から人々が火を見て駈け寄ってきた頃は、小屋は丸焼けでどうすることもできなかった。武治は放り出されて火のついて燃えている夜具を、足で踏んで消した。彼はそれを担ぐと、岩沢の妻と二人の子供を連れて自分の小屋に帰ってきた。
武治の後からついてきた岩沢親子を見て、説子は意外に思った。武治は背負ってきた夜具を床に下ろした。夜具はきな臭かった。
「岩沢さんの留守の間に小屋が、丸焼けになっちゃったんだ」
「まあ、どうして……やっぱり岩沢さんの家だったの」
「うーむ、どうもつけ火らしい。怪しい」
「つけ火?」
岩沢親子は説子に導かれて小屋の中に入ったが、武治の子供たちがすでに三人寝ていて狭くて上がり場もなかった。説子は子供の寝ている蒲団を片隅にひっぱり寄せて、漸く岩沢親子の寝場所を作ってやった。もじもじしている岩沢の妻を誘って、説子はいった。
「さあ、どうぞ上がって下さい。とんだ災難にあったもんですね」
岩沢の妻は子供の手を曳いて、遠慮勝ちに床に上がった。
その晩、武治の小屋に岩沢親子は泊めて貰ったが、岩沢進は帰らなかった。木の根では電話もなし、連絡の方法もなかった。
翌朝早く佐原から帰った岩沢進は、自分の小屋が、灰になっているのを見て驚いた。そればかりか妻子もいない。武治の家に、親子で世話になったということを聞いて、岩沢は武治の小屋に一目散にひた走った。親子の無事を見た岩沢は、武治に涙を流し、土間に手をついて頭を下げた。
岩沢は妻から、その夜の様子を聞いた。岩沢は爛々と眼を光らせ、龍崎の小屋を見つめて呟いた。
「ようし、野郎、覚えてろ。ただではおかねえ」
それから三日目の夜だった。また怪しい火柱が立った。今度は、龍崎伸二の小屋が丸焼けになった。相次ぐ焼き打ち事件で木の根ばかりでなく、周辺の部落の夜は、戦々兢々とした雰囲気に包まれた。
一見、和やかに見える開拓部落も、一皮剥けば憎悪と嫉妬の縮図を見るようだった。ある者は裸一貫で戦地から、ある者は戦災で丸焼けとなって、三里塚に入植した共通の戦争被害者の身だった。同志としてともに庇い合って生きていくのが本当なのに、事実はその反対だった。人間生来の醜悪な面ばかりが出てきて、武治の理想とするものは何一つ現われてこなかった。
武治は失望し、自信を失なうばかりだった。それでも彼は常に開拓者の自立できる部落作りにはどうしたらいいかと、心悩ますのだった。
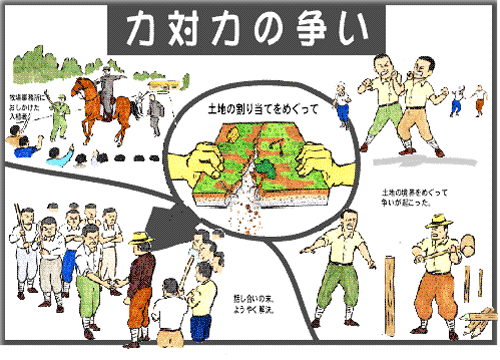
「御料牧場の一部が解放されたものの、すべての人に、生活できるだけの土地がいきわたるということにはなりませんでした。そのため、開拓者のグループ同士の間で、力対力の争いが起きることもありました。当時の新聞記事はそのことを伝えています。また、開拓者の方々におこなった聞き取り調査からも、限られた土地をめぐって、あちこちでもめごとが生じていたことがわかりました。この争いはしばらく続きましたが、最終的には関係者の間で協議がなされ、それぞれの配分が決まりました」
「第一章 開拓」了 目次へもどる














この記事への質問・一言コメントをどうぞ AIコースケと議論しよう!
回答には文字数制限があるため、制限を超えると途中で打ち切られることがあります。