戸村一作:著『小説三里塚』(目次へもどる)
第12話 豪雨(2)
 やがて暑い夏が巡ってきた。
やがて暑い夏が巡ってきた。
去年の旱魃に続く豪雨の恐ろしさが、武治の胸にありありと蘇ってきた。――だが今年は雨も順調に降って土を潤し、作物の「でき」はどこの畑もみんな上々だった。部落の人々も漸く蘇生の喜びを克ちとったような気持で、農閑期の夏を迎えることができた。
木の根部落では開拓以来、初めての夏祭をやることになった。豊作を祝う七夕祭だ。子供も大人もみんな浮き浮きして部落の中央にある広場に集まった。打鳴らす太鼓の周りを浴衣姿の娘や子供が歌いながら、夜ふけまでも踊り狂った。
はずむ太鼓の音がこだまして木の根から田んぼを越え、辺田部落や三里塚の方まで鳴り響いた。朝から上った花火が夜まで鳴り渡って、綺麗な流線が夜空いっぱいに拡がった。子供たちはそのたびに声を張り上げた。七タ祭はいつ終るとも知れず続いた。眠くなった子供は、母親の胸に抱かれて帰っていった。その夜は開拓部落ばかりでなく、菱田の方からも、若い衆たちが集まってきて賑わった。
夏の夕べは打ち水した庭の縁台で、隣りの人とお茶を呑みながらのタ涼み。――夜風に吹かれて軒下の糸瓜が揺れる。蒸し暑い夜は寝苦しく、夜ふかしする晩も多かった。蚊を団扇でバタバタ追う音が聞こえてくる。
真昼は焼けつくような木の根も、夜がふけるに従って冷気が漂い、肌身に染みて爽やかだった。
ある夜、武治が説子と、庭の縁台に腰掛けていると、ひょっこり金城倶輝がやってきた。今夜に限って、金城の例の鼻歌が聞こえなかったから、彼の近づくのも知らずにいた。子供たちは庭の窪地で、螢を追って無心に戯れていた。金城も木の根の武治と同じ、入植者である。彼の出身は沖縄で、天浪には沖縄部落があった。二七歳、まだ独身で、両親が畑仕事をしていたから、千葉市の開拓連合組合の常任として勤めていた。彼は背丈は小作りだが真面目で、多少左翼がかっているところがみえた。武治もどこか違うところがあるなと日頃から思っていた。
金城倶輝は帰りしなに、広い庭の縁台で仲睦まじくタ涼みをしている武治夫婦を見て、ちょっと立ち寄ってみたくなったのだった。
「今晩は……。お揃いで……」
説子は体を縁台の端にずらせて、金城の席を空けた。彼は持っていた鞄を縁台の上にバサリと置いて、腰を下ろした。
「随分遅くなるんだわね。金城さん」
と、説子は労るようにしていった。
「うん、それでも夏はまだいいが、冬は陽が短いから真暗……」
「大変だよな」
と、武治がいうと、金城は眉を顰めていった。
「勤めは辛いですよ、木川さん。本当は家で百姓やった方がいいですが、反別も少ないし……、それにまだ親たちがどうやら働けるでね」
「戦争で沖縄では随分、苦労かけたからね……。本当はもう隠居させてやりたいんだが……」
「早くいい嫁さんでも貰ってね」
「水呑み百姓のところへ来る嫁さんなんか、今時いませんよ。アハ……」
金城は説子に向かって、高笑いした。
「そういえば木の根には娘という娘はいないな。説子」
「父ちゃん、いるにはいるけど、木村さんとこみたいにみんな勤めに出ちゃっているんだよね」
金城は二言三言話して、帰っていった。
それから三日目のタ方だった。彼は帰り際に再び、武治の家を訪れた。話がたまたま農協のことになると、真剣な表情になって切り出した。
「木川さん、県も農協も百姓の味方じゃないよ」
武治は金城の顔を、ただ黙ってみつめた。
「農協は農民を食い物にした体のいい商社ですよ。肥料、農薬、農機具から電気製品、これからは自動車のセールスまでやりかねない。儲け欲一点張りだ。それに農協の組合長や幹部には、遠山も芝山も同じだが、山林を五町歩、一〇町歩持つ地主がいるんだからな」
武治は黙って、頷いた。
「戦後の農地改革もアメリカの占領政策の一環であって、われわれ無産者の解放ではなく、農民は一生働いても、うだつが上がらない」
「うん、昔から胡麻の油と百姓は何とかで……といわれてるからな」
武治の言葉に、傍の説子がからからと笑った。
降るような美しい星空を、北から南へ一つの流星が一際輝きながら、青い尾を曳いて消えていった。金城はそれをチラと見て、再び続けた。
「農協も国の手先機関で、結局農民相手に搾取をしているんだ。農協は取りっぱずれがないから、百姓の欲しがるものは何でもござれ、庭に置いていく。そりゃ秋ともなれば収穫物で回収し、その上預金させ、金に困りゃ高利で貸しつける。農協は一割の高利だよ、木川さん」
立て続けにしゃべる金城の顔をみつめて、武治は思った。自分も千代田農協に借金のあることを、金城は知っているのかと――。事実、武治は利子の支払いには、月々頭を痛めていた矢先だった。
「金城さん、あんたは直戦争体験はねえかもしれねえが、わしは一五年も軍人生活した上で、敗戦、入植者となった。わしも辺田の農家の次男坊で、実家から土地を分けて貰って新宅するカもなかった。そんな関係で作男をしていたが、軍人を志望して海軍に入った。それが敗戦でこうなったが、まさか再び百姓になるとは夢にも……」
「僕の親爺もやはり木川さんと同じで、戦争の犠牲者ですよ。本土よりもひどい犠牲を強いられた上、故郷を追われて木の根にまで流れてきたというのかな……」といって金城は何気なく、武治の家の鴨居に視線を移した。そこにはいつからあったのか一つの額に納まった天皇裕仁と皇后の写真が、麗々しく掲げられていた。金城はそれを見て、全身に虫酸が走る思いだった。直接戦争体験はなくとも、天皇の名で殺された多くの同胞の話を聞かされていたからだ。そればかりか、彼も戦争中は父母に伴われて沖縄の各地を逃げ回り、辛うじて生き延びたという幼い頃の体験をもっていた。
金城は冷え切ったお茶をゴクリと呑むと、音をたてて茶碗を机の上に置いた。そして帰っていった。金城の姿が暗がりに消えると、彼の唄う「ラバウル小唄」が聞こえてきた。武治はそれを追うように、黙って耳を傾けた。なぜか彼の口ずざむ「ラバウル小唄」を聞くと、やるせない感傷に襲われるのだ。あの悲惨な戦争で、外地の露と消え果てた兄や、多くの戦友のことが思い出されるからである。この唄は戦地の武治が何度か、日本から慰問に来た流行歌手によって、聞き馴らされたものだった。
武治が野良仕事を終って風呂に入っていると、いつもきまって伝わってくるものが彼の唄う「ラバウル小唄」である。風呂に入るとなぜか、彼の唄声を待つのが、習慣のような楽しみになっていた。
武治はそれを聞いて、金城が松林のある牧草畑の路を歩いてくるのを知った。声はだんだん近づいて、再ぴ遠くへ去っていく。これは武治が風呂で聞く、姿のない彼の唄声だった。
木の根の夜は静寂だ。耳を澄ませば葉擦れの微かな音さえ聞けるほどの夜である。
すでに金城は去って、その唄声も聞こえないのだが、武治には彼の残した言葉に、ひっかかるものがあった。それは彼の「占領政策の一環」という言葉だった。何か聞き馴れないばかりか、馴染めないもので、なぜか武治の心の奥に引っかかって離れなかった。



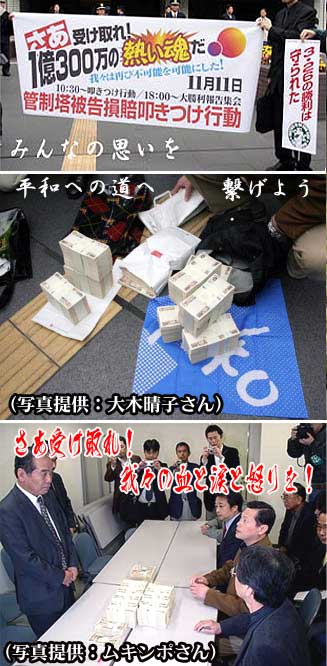










この記事への質問・一言コメントをどうぞ AIコースケと議論しよう!
回答には文字数制限があるため、制限を超えると途中で打ち切られることがあります。