戸村一作:著『小説三里塚』(目次へもどる)
第14話 二六年目の土
 開拓地も今年で丸二六年の春を迎えることになった。陽春の陽を吸った土は黒々と輝き、見るからに畑らしい畑になっていた。その間、幾多の変遷もあったが、最近漸くいくらか百姓として武治も、落着きをみせてきた。
開拓地も今年で丸二六年の春を迎えることになった。陽春の陽を吸った土は黒々と輝き、見るからに畑らしい畑になっていた。その間、幾多の変遷もあったが、最近漸くいくらか百姓として武治も、落着きをみせてきた。
武治と説子の間には、六人の子女が生まれた。子供の養育費や教育費は、開拓者の生活にとっては大きな負担だった。生活は相変わらず苦しかったが、彼は何としても将来、専業農家として自立したかった。いやそれ以前に、いかに苦しくとも二六年、ただ一途に専業農家として生きてきたのだという、誇りを持ち続けてきた。
彼は元来、酒好きで、たまには三里塚の町にやってきて、一杯呑むごとがあった。一杯呑むと褌(ふんどし)一本になって、道路を大声を張り上げて闊歩することがあった。そんな事もあって「木の根の武治」という綽名で、有名になった。彼は百姓の子であるだけに、根っから百姓が好きらしく、そればかりか百姓を馬鹿の一つ覚えのように誇りに思っていた。
武治の年間の作付は麦・落花生・生姜・人参・西瓜、などで、家畜に牛馬と豚はいつも飼育していた。彼の広い庭先には堆肥の山ができていた。彼は冬の農閑期を利用して説子とともに、近隣の山林から落葉を掻き集めた。そして夏は朝飯前に道端などに生い茂る夏草を苅りとった。それをリヤカーで庭に運んで、家畜の排泄物と交互に積み上げた。その大きな堆積が庭先に、山と築かれていた。それは寒い冬の朝など頂きから、火山の噴煙のように白煙を吐いていた。
煙に見えたのは、醗酵する堆肥が吐く蒸気で、むんむんと香ばしい匂いが発散していた。夏の炎天下など武治はよく昼休みのひと時を利用して、台所の流し水を肥柄杓で丹念にかけていた。武治は堆肥のでき具合を、味覚で調べていた。
彼の畑がことのほか、黒々とビロードのように光って柔らかいのは、武治のまめな中耕・培土に加えて、彼の作る堆肥からくる地力によるものだった。
武治は農協から金肥も買ったが、肥料の多くは家畜による厩肥と、落葉や雑草による有機質のものだった。
武治の持論は、家畜と離れて農業はありえないという有畜農業にあった。彼の営農法は有機農法というよりも、有畜農法というべきだ。だが最近の木の根を見てもわかるように、家畜をなくし、堆肥作りを止めて、金肥一点張りの農業に変わっていく傾向が見えてきた。連作に強い落花生までが減収したのは、金肥や農薬の乱用による地カの低下からくるものではなかろうか。
戦後一〇年を過ぎる三〇年頃からだった。あんなに普及したカルチベーター・プラウ、和犂などによる畜力農法は、瞬く間にすたれて牛馬とともに姿を消していった。 長年、家族の一員のように愛され、飼い慣らされた家畜が、博労に売られて屠殺場に運ばれていく情景がよく見られた。
牛馬は作業に慣れると、主人の手綱なしで畦間に作業機を曳いた。時代の流れとはいえ、飼い慣れた家畜と別れるのは、農家の者にとっては何よりも辛かった。
車の行く先はどこか――動物特有の敏感な感覚がそれを知らしめるのか、憂い気に長く尾を曳いて啼く声に、飼主は耐えられなかった。去りゆく車の上から牛は、長年住み慣れた牛小屋を見つめては、頻りと啼くのである。
小型耕運機が農村に普及するに従って、役牛は、博労に買いとられてどこかへ連れ去られていった。
武治は最近、農家の庭先でよく牛馬の売り渡される情景を見かけた。彼自身も日頃飼育した家畜を、博労に売り渡した経験があったから、その場を見ると身近に感じるものがあった。
武治はそんな時、いつも売られていく家畜が、農民の姿に見えてきてならなかった。さらにそれが自分の姿に見えてくるのだった。最近の木の根にも二六年の開拓生活に見限りをつける者、乳牛を売り払って出稼きに出る者などが、ポツポツ目立ってきたからである。
木の根から日増しに消えゆく家畜に開拓農民の末路を見て、武治は何かうら淋しい思いに打ちひしがれた。さんざんこき使われた揚句の果ては、つぶし(肉用)に売られていく家畜――これが百姓というものではなかろうか。武治は売られていく牛馬に託して、農民の身の上を想った。
畜カ時代が過きて耕運機時代がきても、武治の家には相変わらず動物が飼育されていた。武治も人並みに耕運機を入れたが、それによってすぐに家畜が淘汰されるものではなかった。
武治の家畜飼育の目的は単に役畜ばかりでなく、厩肥が農業にはなくてならぬものと考えたからだった。だが一般農家では、耕運機は使う時だけ餌をやればいいが、役畜は年柄年中餌付をしなければならない。不経済だといって、家畜を廃止してしまった。その結果、配合肥料である金肥を、高い金で買わされる始末となった。
政府が無制限に化学製品を使わせた結果、地カが衰え、土壌の機能が破壊された。そればかりか新しい病菌の発生を招き、その抵抗カをますます旺盛にする素地を作っていった。病菌を駆除するために逐次強力な農薬を使うから、それに競うようにして病菌も抵抗カを増して反撃してくるのは、理の当然だった。
まるで馳(いたち)ごっこだ。せっかく強カで新鮮な地カを持つ開拓地も、近代化農業によって破壊されていった。畜力農法は機械化を奨励する農政によって、駆逐されていった。これは農民を低賃金労働者として、土地から切り離すための巧妙な罠だった。





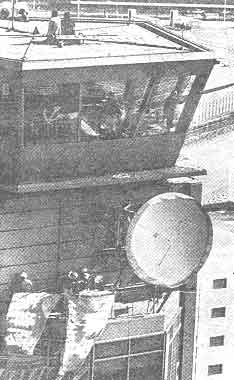








この記事への質問・一言コメントをどうぞ AIコースケと議論しよう!
回答には文字数制限があるため、制限を超えると途中で打ち切られることがあります。