■ 1ページ目にもどる > 戦旗派内部組織総括一覧
三、右派市民運動としての「協商懇」構造の陥穽

ところでわれわれが「連帯する会」構造から訣別し、別個の地平で六〇年代反戦全学連運動や、七〇年代初期全共闘運動にも匹敵する戦闘性と左翼性を有した闘争潮流形成をはからんとする試みは、直接的に反中核、反カクマル、反日共系新左翼・市民・労働運動の結合体である現下の「協商懇」構造=べ平連、共労党、インターの寄り合い世帯がつくり出す右派市民運動の方向に抵触し、それらとの軋轢のうちにわれわれは闘わねばならない必然のもとにおかれている。
別の言い方をすれば、八四年秋冬期の攻防環となった「連帯する会」脱会後の闘争陣形の構築の問題とは、インター、プロ青、赫旗との確執に根を持つだけでなく、彼等が立脚する基本的運動基盤である「協商懇」系列の政治展開に、われわれの総路線が結びつかない結果もたらされる齟齬を表現しているのである。この構造をどうとらえかえし、かつその陥穽を打破していくのかがわれわれに問われているのだ。
八〇年代の今曰、何故に「協商懇」のような運動政治基盤が存在しえているのかといえば、六〇年代の反戦・全学連、七〇年代初期の全共闘運動が、いわゆる新左翼系八派共闘を軸に形成されたものであり、べ平連運動などはそれよりも右の市民潮流として別個のところに存続していたという関係から、六九年四月権力の破防法適用、七二年の連赤によるリンチ殺人事件、そして時期を同じくしての中核・カクマルの内ゲバの開始などの諸条件によって八派共闘が解体し、七〇年七・七華青闘告発にみられるように、情勢の活性化により政治過程に多量に登場した諸階層の政治的利害を全人民的政治闘争で牽引する構造が喪失してしまい、革命的左翼の権威が失墜していく過程において、内ゲバ反対を契機に中核との共闘を絶った第四インター、党的に分裂した共労党系列などが、右にシフトして、べ平連潮流や市民運動との結合をはかっていくことによって、現下のごとき運動政治基盤が作られたことにもとづいている。それが様々な形態をとって今日までヘゲモニーを保持しえてきたということである。
例えば「労働情報」・「連帯する会」・「廃港要求宣言の会」・「日市連」・「パルク」(アジア太平洋資料センター)、雑誌『クライシス』・『新地平』などがその系列に属するわけだが、それらはみな武装闘争とか、ゲリラ・パルチザン戦闘、組織作りにおけるレーニン主義党建設、共産主義的主体形成、闘争の前衛的領導などに対し、一歩距離をおいた位置で市民運動や労働運動を中軸に問題を論じることを特色としている。その中心的イデオローグの役割りを果たしているのが、いいだもも、樋口篤三、白川真澄、武藤一羊、福富節男、前田俊彦、吉川勇一、渡辺勉などであるわけだが、その大半が日共構改派→社革新→共労党の旧政治局員だちなのだ。
われわれ戦旗・共産同は一九七四年七月参院選挙への戸村一作氏の立候補に際し、戸村選挙を支え三里塚闘争の正義を全人民に訴えるために「連帯する会」に参加したのであるが、それは当時中核派の内ゲバヘののめり込みを批判しつつ戦闘的に大衆闘争の領導をおこない、七八年三・二六~五・二〇開港決戦におどり込んでいく勢いのあった第四インターの闘い方が、第二次ブントの「党の革命」、内ゲバヘののめり込みを経てのアダチ分派問題で傷つき、党的再建の途上にあったわれわれをもこえる革命性を有しており、路線的に結合しえたからである。第四インターの変質が始まるのは七八年五・二〇開港阻止決戦後の過程である。
それはともかくこの旧共労党政治局員たちの日共構改系以来の問題把握、政治的観点というものが、第二次ブント以来の世界革命、暴力革命、プロレタリア国際主義の思想を骨格的土壌としたわが同盟の戦略的総路線、発想、政治的思想的観点とどうしてもくい違ってきてしまい、そこに齟齬が生み出されてしまうのが、現在のわれわれを取り巻く情況の根底にあるものなのだ。

党派軍団がいけないとか、戦闘的ジグザグデモもいけない、ゲリラ・パルチザンなどかかわりたくもない、という発想の根源にあるのは、要するにべ平連流の風船デモに買い物帰りの主婦が参加するのが闘いだとする彼等の原基的運動イメージ、或いはロマンチシズムにもとづくものであり、トリアッチ流の労働者の社会参加、権利の拡大を通じての自主管理、ゼネスト革命、議会への進出をテコにしての構造改革路線こそが、発想の根拠となっているのである。
ゆえに八四年秋冬期におけるわが同盟の苦闘、「連帯する会」を脱会したが、それに変わる戦闘的左派潮流の結集に、八月・九月・十二月とアタックしてみたものの成功しえないという現状の突破は、わが同盟が既存のものとして考えてきた運動・政治基盤=「協商懇」構造の内部に六〇年代的な反戦・全学連運動を承認していく左派的潮流形成をはかることにおいてか、或いは全くその枠の外に、別個なところで基盤形成をはかる事に勝利することにおいてのみ、真の打ち返しの道を見い出せるのである。
つまりは「協商懇」系列でがんばりぬき、膨大なエネルギーを費してもオルグを継続し、潮流的となりうるものを見い出し、作りあげていくのか、いっそのこと「協商懇」=熱田派以外の運動基盤に参加し、そこで闘いぬくのかの選択しか、実際上そこには方途のない闘いなのだ。
そしてわが同盟は、度重なる内部討論をつみ重ね、中核派の党派戦争宣言、わが同盟に対する反革命規定などの外的制約をかんがみ、現在の運動系列内部での戦闘的左派潮流の形成と領導以外なしえない実情にあると判断したのである。
八四年秋冬期での共闘的苦闘はそのあらわれである。結局はわれわれ自らが戦闘的左派潮流を領導し、牽引しぬくまでに党的力を増強し、部隊力を高めあげることを決意しながら、一九八四年七月より十二月まで、わが同盟は試行錯誤しつつ、闘いの輪を広げることに全力を注いだのだ。
十二・一六集会における四つの提言と四つの連帯発言は、そうした展望を物質化するための足がかりとなるものである。そしてこれを支えるのは、戦旗・共産同と全革命勢力の単独の力だけでも日本階級闘争に影響力を及ぼすまでのわれわれの力の拡大であり、その前提となるのは単独決起をもってでも、状況を突破していくのだという固い覚悟と党の団結である。
もはやわれわれを取り巻く状況の複雑性に対しては、ただの大衆運動主義、ノンセクト的な非セクト主義、地域主義、学園主義などの、いずれの陥穽におち入ってもこれを突破することはできない。
戦旗・共産同という一個の有機体を構成する各部位、器官、細胞としての己を自覚し、組織として勝利し、党として勝ち抜くために尽力しきる強固な意志の結集は、絶対に必要である。
そして今われわれがこの旧共労党政治局員たちが多大な影響力を与え続ける「協商懇」構造、その大衆運動主義的表現となる「反トマ全国運動」などの枠組において、左からの潮流形成をはからんとする時、そこに何の展望もなく、わが同盟の孤立性だけが存するということでは決してない。
例えば雑誌『インパクション』No.31(八四年九月十五日発行)に天野恵一氏(高田馬場「寅書房」店主、もと中大全中闘)は次のように書いている。
「反トマホークの闘いが多数の人集め自体が自己目的化されるような闘いであってよいわけがないのだ。こういった運動は本当の闘いの大衆化を阻止することはあっても促進することはない」(〈反核〉と「全斗煥・天皇会談」)
「反全来日、反全・反天皇会談という課題は、被害者意識を軸とした反核(反トマホーク)の理念のままでスベリ込めるような課題ではない」(同)
「反トマホーク(反核)の闘いは、反全・天皇会談という課題に横すべりするのではなく、この課題を共有することを通して、被害者ナショナリズムをふるいおとすことを通した大衆化を追求しなければならない」(同)。

また『反天皇制運動資料』Vol2、「全斗煥来日-天皇会談を問う」における対談の中で、十二・一六集会で発言した佐藤達也氏は「反トマの闘いの中心リーダーたちはまったく無自覚だったわけではないけど、結局幅を広げるために、安保とか侵略とかいう問題を前面にかかげようとしない核まきこまれ論のスタイルであった。今回の事態(=全来日阻止闘争)でも、そういう幅を広げる主義でいきたいという部分もいますが、それはダメでしょう。大体幅広く運動する時は、一回左にスタンスを決めてから、それから手を拡げないとダメ。あと中途半端はダメだ」と語っている。
これらの「日韓行動連」や「反天連」に結集する知識人には、佐藤氏が法大のNR出身というように、七〇年代全共闘運動をひとつの原体験としている人々が多く、「協商懇」=「反トマ全国運動」の持つ傾向に対し、きわめて批判的な位置にたつのである。
もちろん現下の彼等の問題意識はそれ以上でも以下でもないものととらえるべぎなのであるが、われわれの闘い方を承認したり、ゲリラ・パルチザンを批判し武装闘争に敵対することの矮小性を認めるぐらいの政治的観点は、充分に保持している。ゆえに運動的に彼等と結合していくことは、九・二~六全来日阻止闘争がそうであったように充分可能であり、又必要である。
われわれに問われていることは、こうした潮流内の分岐の存在に目をとめ、そこにわが同盟の見解を持ち込み、彼らとの政治的合意をできるだけ多くとりつけ、新しい戦闘的潮流の形成にむけ尽力していく、そうした地道な努力の継続である。それ抜きにはわが同盟の共闘関係、潮流形成にむけた前進は閉じられてしまい、われわれは政治的に孤立しきり、マル青同化する以外なくなってしまうであろう。
と同時に、そこには又決断も必要である。
つまり市民運動や戦線運動に幻想を持つのではなく、わが同盟それ自身の発展に展望を見い出し、必要とあれば、必要でなくなるまで単独で闘い抜く覚悟、そうした決断である。
八四年秋冬期、わが同盟はかかる問題のたて方のうちに闘い抜いた。闘争スケジュールが朝令暮改されてしまうジグザグもたしかにあったが、それは新しい潮流形成にまで翼を広げようとし、勇躍飛び立ったわが同盟の共闘創成をめざす苦闘の姿である。
全党全軍の同志・友人諸君は、それをよくわきまえ、わが同盟がおかれている構造を認識し、己の部署で全力を尽くすことを是非ともやりきって欲しい。八五年三月チーム・スピリット粉砕から六月反戦・反核大決起にむけて、きれいごとでは片付かないわが同盟の苦闘はつづく。まなじりを決して闘い抜き必ず勝利をおさめ、なおかつ八四年秋冬期における第四インター、プロ青との対立性の拡大を革命的に止揚する道を、ここでつかみとろうではないか。
いずれにしても問題は「協商懇」運動系列、共労党政治の枠組をわが同盟が如何に突破するのかにあり、そこまで下向した対処をとろうとしない限りどうともならないような位置にわれわれが置かれていること、これをおさえておくことが肝腎である。
参考
(もの書きを目指す人びとへ 岩垂弘)


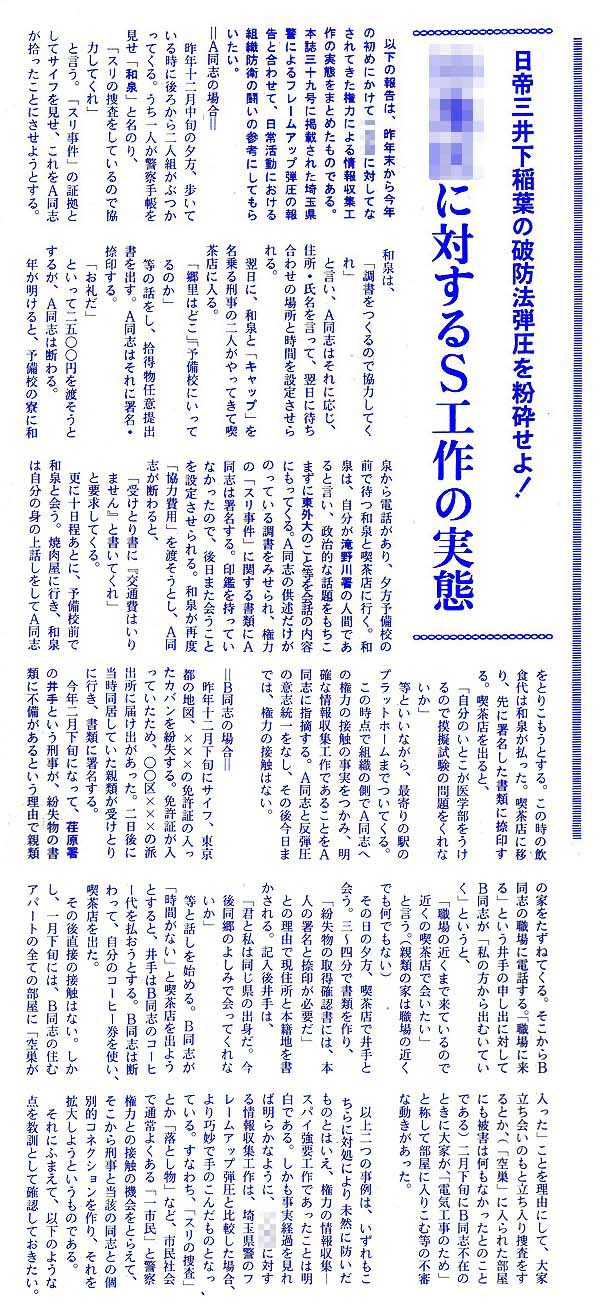


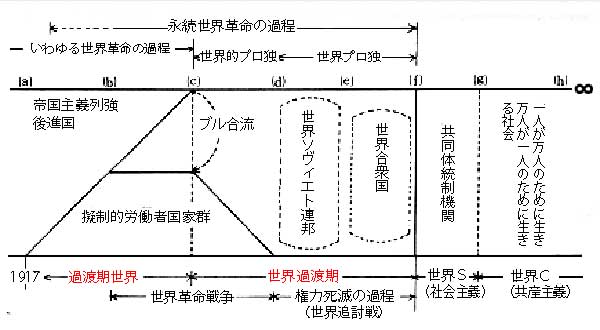








この記事への質問・一言コメントをどうぞ AIコースケと議論しよう!
回答には文字数制限があるため、制限を超えると途中で打ち切られることがあります。