戸村一作:著『小説三里塚』(目次へもどる)
第30話 黄衣の男
 春の日も浅い午後のひと時――戸田の家を訪れた、黄衣の男がいた。彼は東藤行敬といって、戸田とは顔見知りだった。幾度か集会で、一緒になったことがあったからだ。東藤は日本山妙法寺の僧侶として、日頃から平和運動に参加していたので、戸田も彼には一目おいて敬意を払っていた。その東藤の来訪だったので、彼は明るい面持ちで東藤を迎えることができた。
春の日も浅い午後のひと時――戸田の家を訪れた、黄衣の男がいた。彼は東藤行敬といって、戸田とは顔見知りだった。幾度か集会で、一緒になったことがあったからだ。東藤は日本山妙法寺の僧侶として、日頃から平和運動に参加していたので、戸田も彼には一目おいて敬意を払っていた。その東藤の来訪だったので、彼は明るい面持ちで東藤を迎えることができた。
これに対する東藤の態度も、極めて慇懃だった。彼はいつも柔和な表情で、にこやかに人に接する特徴を持っていた。
「戸田さん、私はタベお釈迦さんのお示しをうけまして、焦る気持で今日は三里塚にやって参りました」
彼の声は特徴ある太いだみ声だった。戸田をじーっとみつめて、恭しく合掌し瞑目した。そして静かに眼を開くと、また、その後を続けた。
「私はどうしても空港阻止を祈願して、一週間の断食をしたいのです。どごか空港予定地の中で、適当な所がありましたら……」
東藤の突然の言葉に感激しながらも、暫し返事に困って考えあぐんでいた。その時、戸田の頭に浮かんだものは、つい二日前、岩山部落の手によって完成した、天浪の団結小屋だった。それは四〇〇〇メーター滑走路予定地の中にあった。
折しもそこへ反対同盟で岩山部落の役員、麻生禎和がひょっこり顔を出した。一〇日前戸田に書くのを頼んでおいた部落旗を、取りにきたのだ。あいにくそれは、まだ完成していなかった。
戸田は早速、麻生を東藤行敬に紹介した。麻生は喜んだ。
「先生、岩山はみんな日蓮宗で、六〇戸もあります。お寺は無住で困っています」
東藤は麻生の言葉を聞いて、座敷から廊下に膝を乗り出した。戸田は麻生に東藤の来た理由を、詳しく告げた。麻生は喜び、「岩山部落で建てた団結小屋があるから、先生是非使ってくれ」と、しきりに奨めた。
「先生、まだ木の香がぷんぷんして、誰も入っていないんですよ」
「麻生さん、これはお釈迦さんのお導きです」と、東藤は合掌した。
日蓮宗の僧侶と聞いただけで、麻生は何か得難い人物を得たかのように、有頂点になった。麻生も日蓮宗の信徒だったので、その僧侶が三里塚まで来て、空港阻止のため断食するというのだから、すっかり感激するのも無理はなかった。
その日はそれで東藤は、ひとまず東京に帰っていった。三日目に再び、戸田の家にやってきた東藤は背中に大きなリュックを背負っていた。彼はそのまますぐに、「天浪団結小屋に行くから道を教えてくれ」というので、戸田は早速、寝具と二、三の食器を、妻の澄江に用意させた。それを自動車に積み入れると、東藤を乗せて天浪に向かった。彼を団結小屋に案内すると、その足で木の根の木川武治の家に回った。天浪と木の根は、隣り同志の部落だった。
武治は畑の中にいた。
東藤が天浪で今夜から一週間の断食に入るということを聞いた武治は、すっかり感激してしまい、やりかけた畑仕事を中止してしまった。武治も東藤については、あらかじめ聞いて知っていた。
「天浪には電燈はねえし、坊さんも大変だっぺえ」
「まあ、蝋燭は用意して持っていったよ」
「家には開拓当時使ったランプがあるから、届けてやるべえ。偉い坊さんがあんな淋しい天浪に来て、断食するなんて、もったいねえ……」
武治は天浪の方向を、ちらと見ていった。
武治はその夕方、いつもより早く仕事を切り上げた。自転車の荷がけに大風呂敷に包んだ夜具・茶器・鍋・洗い桶などを積み、ランプを背負い天浪に向かった。
団結小屋に近づくにつれ、太鼓を打つ音が単調に響いてきた。着いてみると東藤は小机の上に蝋燭を点して、その前に端座していた。彼は団扇太鼓を片手に打ち鳴らしながら、読経していた。暫くして読経が終ると太鼓を小机の上に置き、武治に向かって合掌し、丁寧に頭を垂れた。
武治は団結小屋の物置から針金を見つけ出し、それを梁に結びつけると、ランプを吊り下げた。武治がマッチを擦って、点火すると暗い団結小屋の中が、紛(みまが)うように明るくなった。東藤は机の上の蝋燭の火に顔を寄せ、フーッと頬をふくらませて消した。
「先生、ぼろ蒲団ですが、夜はまだ冷えますんで、かけ蒲団を一枚持ってきました」
武治は蒲団を丁寧に畳んで部屋の隅に置くと、東藤の前に座って丁寧に頭を下げた。
「先生、これは憶い出のランプでしてね……」
「ほう……」
「二六年粒々幸苦の血と涙が、このランプには籠っているんですよ。乞食のような格好で掘立て小屋に住んだあの開拓時代が……」
武治はそういう自分の言葉に溺れ、その後がどうも続かなかった。
「ところで木川さん、戸田さんに聞けば、ここは四〇〇〇メーターの真只中ということ……」
「そうです。私のいる木の根は横風の三二〇〇、ここは四〇〇〇滑走賂の真只中です」
「そうですか。木川さん、私はお釈迦様のお示しをうけました。この空港はれっきとした軍事空港です」
武治は眼を丸くし、首を伸ばして、東藤にいざり寄った。
「木川さん、空港阻止のためには、この真只中にどうしても平和塔を建立し、お釈迦様をお祀りする以外に方法はありません」
武治はじーっと東藤の顔をみつめた。
「これは反対同盟のみなさんが協カしてくれれば、必ず実現できます。それを私は信じています。私の今度の断食は、そのためのものです。木川さん」
「先生、それが本当にここに実現できたらもう空港など絶対に……」
「そうです。木川さん」
「わかりました。先生!わしはそのために、生命をかける覚悟はあります。それに先生、この天浪というところは、条件派の多いところで、そのためにも、わしはいつも何かをやらねばと思っていたところで……」
武治は帰るために、立ち上がった。
東藤は武治をおくって外に出た。
天浪の夜は暗い。空を仰げば燦爛(さんらん)と瞬く星空である。春も浅く、夜気が冷く頬を撫でて過ぎる。武治の踏む自転車のペダルの音が、油が切れてかキイキイと暗い中から聞こえてくる。
武治の帰った後の団結小屋は、静寂だ。彼方に見える燈火は条件派の小股由松の家だ。
闘いのポイントともいうべき天浪部落を何とか反対に起ち上がらせたいというのが、武治の唯一の念願だった。そこへ東藤がひょっこり現われて、「平和塔」を建立するというのだから、まるで地獄に仏だった。東藤の来訪は武治にとって、百万の援軍を得たも同然だったのだ。
武治は家に帰るなり、説子に勢い込んで東藤のことについて報告した。
武治はすっかり東藤に心酔し、何か生き仏にでも接したような気持になっていた。東藤は断食明けには、蕎麦粉が要るといった。蕎麦粉をといた湯を飲んで腸を洗ってから、食事をしないと体に支障をきたすという。武治は、方々を自転車で走り回り、遠くまで行って蕎麦粉を捜し求めてきて、東藤に渡した。そして何くれとなく、東藤の身の上の世話をやいた。







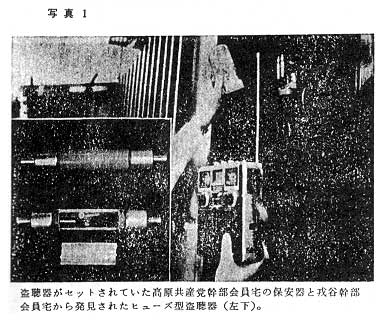






この記事への質問・一言コメントをどうぞ AIコースケと議論しよう!
回答には文字数制限があるため、制限を超えると途中で打ち切られることがあります。