戸村一作:著『小説三里塚』(目次へもどる)
第61話 「土地は売るなよ」(2)

病院はひっそり閑としていた。急患ということで白衣を着た宿直の若い医師が、眼をこすりこすり診察室に入ってきた。ベッドに横たわって悶え苦しむ武治を見下ろし黙っていたが、しばらくすると聴診器をとり耳に当て、心臓の鼓動を診た。そして胸部から腹部にかけて、指で押しては首を捻った。
看護婦に命じて注射を打たせると、武治の苦痛が次第に遠のいていくのが見えた。
医師は説子に向かって、精密検査をしてみなければよくわからないが、多分、心臓障害によるものではないかといった。取りあえず今夜は痛みだけ止めておいて、明日くわしく診察し、レントゲンを撮るからというのだった。
早速、特別の計らいで、個室の病室に入り、寝たが、夜明けにまたも発作が起こった。
一月一三日の朝、九時半だった。繰り返す発作と苦痛の中から、「これが死の苦しみというものか」と、武治は呻くように説子に呟いた。呟く武治の言葉は、気息奄々としていた。見守る家族は慌てふためき、ただおろおろするばかりだった。
武治の苦悶は、何か死を予感するかのように見えた。家族には、医師の動作が生ぬるくて見ていられなかった。
「先生!早く何とかして……」
説子はわななく声で、医師の袖を引くようにして哀願した。黙って頷く医師の態度は、冷静そのものだった。医師の処置によって激痛が取り去られたか、武治の表情がいくらか柔らいだように見えた。
――と、武治の口元から微かに洩れる言葉――見守る者が顔を寄せて、耳を澄ますと、はっきりとそれを聞きとることができた。
「死んでも……土地……売るなよ」
武治の半眼に見開いた眼は、頭を巡らして、静かに病室を見回し、家族一人一人の顔をみつめた。武治の目尻からは、白く光るものが落ちて、ベッドを濡らした。
その時、病室の片隅に蹲って遊んでいた孫の百合子が、武治の枕辺に近づいた。子供心にも何か異様な雰囲気を感じとったのであろう。
「おじいちゃーん、おじいちゃーん!!」
三歳になる孫の百合子が耳元に口をつけて、声を限りに呼んだ――が何の応答もなかった。
「父ちゃーん!」
娘の咲子が父親の体にしがみついて泣いた。妻の説子も泣いた。その悲哀をよそに武治の苦痛の表情は次第に薄れゆき、安楽な面に帰っていった。
「絶対に土地は売るなよ」との一語を最後に、この世の生涯を閉じた。武治は六〇歳だった。
白いベッドの上に無言で横たわる武治――肉体の苦しみばかりか、今はこの世の一切の苦難から解放されて眠る武治は、平安そのものに見えた。苦難のみ多かった武治の生涯も、この日この時をもって終わったのである。
五日前まで天浪の丘で地下壕掘りに精を出した彼は、もうこの世の人ではなくなった。闘いの中の死であった。

彼は開拓当初同志とともに作った、天浪共同墓地の一角に葬られることになった。墓地は空港ターミナルの中心点に位していた。彼の遺言もあって、武治はこの共同墓地に土葬されることになった。家族や親戚の中には火葬にすべきだという反対意見もあったが、弟の源二の主張が通り、一月一五日に土葬されることにきまった。
武治の生前を偲んで.各地から集まった者で、木の根から天浪の共同墓地まで長蛇の葬列が続いた。赤旗の棚曳く葬列の先頭には、弟の源二が歩いた。その源二の姿が、奇妙だった。紋付の羽織袴にヘルメットを被っていた。それは武治の遺した、黒ヘルメットだった。源二にとってのヘルメットは兄の遺志を継ぐ、唯一の象徴だった。路上の周りでは工事に働く労働者らが、手を休め、立ち尽したまま葬列を眺めていた。物陰から出てきた一群の機動隊や私服らが、遠くから葬列を尾行した。

天浪共同墓地は周辺から削り取られて、ポツネンと切り立った丘となって、取り残されていた。ブルドーザーが走り回って、その周辺は見るからに荒寥たる風景だった。かつての天浪開拓部落の様相は、どこにも見当たらず、殺風景な錆色の鉄骨が空しく建っているばかりだった。
墓地に上るとそこには各所に点々と、真新しい赤土の盛り上がっているのが見えた。これは条件派の人々が代替地に移住するに当たって、家族の遺体を自ら掘り取った痕跡だった。後片づけもせず、掘りっぱなしで放置された墓地は、一種凄惨な思いを人に与えた。政府は農民をして、墓あばき人にまで仕立て上げたのである。人が墓をあばき、その遺体を取り去っていった墓地に、武治は今、新しく葬られんとしていた。すでに墓穴は掘られて、傍に赤い土か盛り上っていた。
武治の穴は、墓地の中頃にあった。棺が静かに穴の底に曳き降ろされると、突然、説子と咲子がハンカチで顔を掩い、声を挙げて泣き出した。親戚の誰かが、二人の肩を抱いてもらい泣きするのを見て、みんな悲しみを誘われた。
真新しく盛り上げられた土の上には、一本の墓標が立った。源二がその墓前に額ずき、首を垂れた。源二は墓標に近づき、被っていたヘルメットを脱ぎ、一礼すると墓標の頂きにそれを被せた。
「兄貴!これで本望だろう!」
源二がポツリというと、その眼からは白く光るものが頬を伝って、土の上に落ちた。墓標の傍で学生たちが赤旗を打ち振りつつ、「同志は斃れぬ」と唱い出した。周囲からもそれに和する者もあって、歌声は晴れた冬空に木霊して響いた。説子は涙で曇る眼で、墓標を仰いだ。ヘルメットを被った墓標がまるで武治の姿に見え、それはゆらゆらと揺れて動き出し、説子に近づき語りかけてくるかのようだった。
説子は懐からハンカチを出して、涙を拭いたが、熱い涙はとめどなく溢れて、袖を濡らした。黒い喪服に白いハンカチで涙を拭く説子の姿が痛々しくて、見る者の涙をまたさそった。
打ち振る赤旗のはためきと、低い歌声が地中に染み入るように響いた。
「第八章 地に落ちて」了 目次へもどる









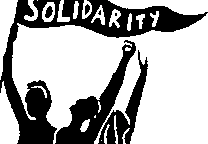





この記事への質問・一言コメントをどうぞ AIコースケと議論しよう!
回答には文字数制限があるため、制限を超えると途中で打ち切られることがあります。