2.なぜ『君主論』を学ぶのか
(1)革命運動における政治の本質性

革命運動の究極的目的は「政治的解放」を超え出たところの「人間的解放」(マルクス『ユダヤ人問題によせて』)であり、政治そのものの止揚をも展望している。だがそのプロセスには政治革命が孕まれており、それ以降のプロレタリア独裁期をも含め、極めて凝縮した「政治の時代」が存在しているのだ。そしてわれわれは今、いっさいを政治革命のために集中する時期に生きている。
この時期に政治革命を認めぬものは、ユー卜ピア主義者以外の何者でもない。サンディカリストやエコロジストなどはこの系列である。政治革命のために当面いっさいの準備をなしていくものこそが、唯一自らをマルクス=レーニン主義者と称しうるものであるのだ。
このように政治とは、革命運動遂行上きわめて重要なモメントを構成しているのである。ところで政治とは、マキァベリがえぐり出していったように、その本質は「力の論理」であり、マックス=ウェーバーの言葉をかりるならば「権力の配分関係に影響をおよぼそうとする努力」(『職業としての政治』)のことである。
したがって、われわれのめざす政治革命が、ブルジョアジーとの絶対戦争を通じたプロレタリア独裁権力の樹立であることと考え合わせるならば、われわれの行使する政治は-言い換えるならばわれわれのはらう「権力の配分関係に影響をおよぼそうとする努力」は、全権力を掌握するところまで究極的に追求されねばならず、それ故そこでは従来の歴史過程における政治以上に極限的な力の発揮と技術の駆使が求められるのである。その一つの頂点をなすものが、武装蜂起を通じたソヴィエト権力の樹立をもってのブルジョアジーとプロレタリアートとのへゲモニー関係の逆転であるのだ。
以上のことからわれわれは、革命運動が政治を必要とするばかりでなく、歴史上かって ないまでに政治が決定的な要因となっていることをふまえることができるだろう。したがって革命的前衛をめざすわれわれにとり、「政治の主体化」は決定的に問われており、これを『君主論』 学習を通じてめざすのでなくてはならないのである。
(2)政治の主体化こそが「勝利する革命党」建設の力ギとなる
革命運動における政治の主体化の本質性もさることながら、今日の階級闘争の激烈化はより一層現実性をもって政治の主体化を焦眉の課題として、わが同盟につきつけている。なぜならば、わが同盟の飛躍的前進にともない、敵日帝国家権力は破防法弾圧をわれわれに集中し、われわれよりも強力な党派は「出る杭は打て」とばかりに、何の根拠もない難くせをつけて党派闘争を激化させてきているからである。
この突破いかんに、われわれが「勝利する革命党」へと脱皮できるのか否かのカギが握られている。そしてそれを可能ならしめる条件は、政治力量の獲得以外ではない。敵権力や他党派による赤裸々なパワー・ポリティクスのひしめく現実の中で、これに打ちひしがれることなく、また足をすくわれることなくわたり合い、勝ちぬいていく中でこそ唯一道は拓けるのである。それはまさに大国の侵略からの解放闘争を、小国どおしのへゲモニ一争奪合戦をなしつつ実現していくといったマキァベリの苦闘そのものであり、それ故に今こそ『君主論』は輝き をもってわれわれに迫ってくるのである。
まさしくわれわれは今だからこそ、政治の主体化わけてもその核心たる「力の論理」の主体化をめざすのでな くてはならない。今この時の努力を回避し、 きれいごとや観念的なおしやべりに逃げこむことは、政治的敗者の道への転落を意味するものでしかない。政治の主体化=力の論理の主体化こそが「勝利する革命党j への関門なのだ。
この関門にもやはり地獄への門と同じくこう書かれているのだ。「いっさいの猜疑を捨てよ、いっさいの怯懦はここに死ぬがよい」(ダンテ『神曲』)と。
すべての同志は勇気と情熱をふるい立たせ、激闘の八六年決戦に躍りこみ、力対力の激突の真只中で政治を実践的にわがものにしなけれはならない。


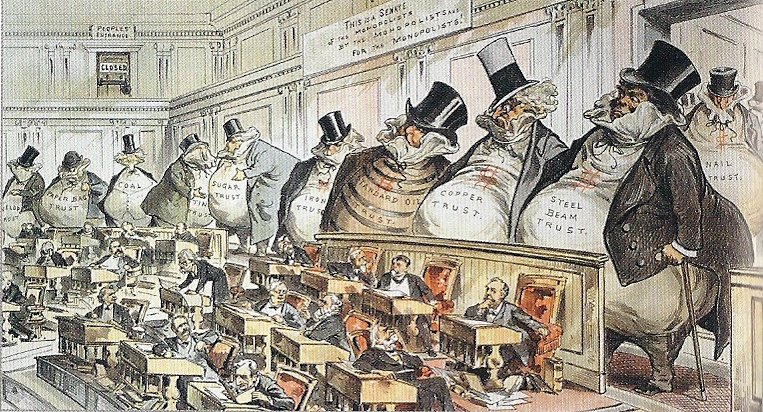
















この記事への質問・一言コメントをどうぞ AIコースケと議論しよう!
回答には文字数制限があるため、制限を超えると途中で打ち切られることがあります。