第一章 開拓
第1話 帰郷(1)
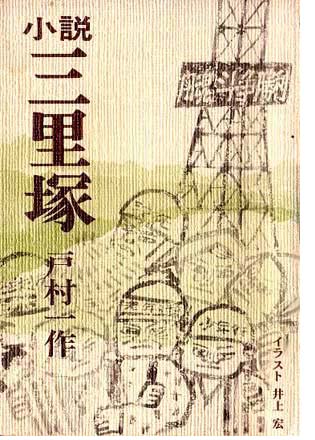 1945年8月15日-ついに日本の敗戦の日が来た。
1945年8月15日-ついに日本の敗戦の日が来た。
木川武治の郷里は芝山町菱田の辺田(へた)部落だった。武治がそこに帰ってきたのは、その年の10月25日だった。
10月といえば農村は農繁期のさなかで、猫の手も借りたいせわしさだった。農繁期の農家はどこを訪ねても空家同然で、留守番といえぱ猫か鶏くらいのものである。
そんな辺田部落に、彼は何の前振れもなく漂然と帰ってきた。軍隊生活が長く、下士官の肩書まで持っていた彼は、敗戦軍人のうらぶれた姿を、郷里に曝したくはなかった。とはいうものの今の武治には、古毛布三枚を担いだ着のみ着のままの敗軍下士官の姿をどうすることもできなかった。
軍隊生活では、たとえ戦時中たりとも、民間に見るような窮乏生活は味わわなかった。そんな彼も一度敗戦となれば、古毛布三枚のみじめな姿とならねばならなかった。
武治は、日本敗れたりといえども、なお軍人としての衿持を持ち続けており、それを象徴するかのように、顔には口髪が、整然と蓄えられていた。それは軍人生活の最後の名残りを止めるかのように、黒々と光って見えた。
久方振りで見る故郷の山河はひとしお懐しく眼に染みて映った。荒んだ彼の心を温かく包み、癒やしてくれるものは、やはり武治を育んでくれた故郷の自然だった。
「ああ、今この俺は生きて故郷の土を踏んだんだ」
武治はそう呟くと、足下の大地を見つめ、何かをたしかめるようにゆっくりと足踏みした。そして、天を仰ぐと、深い息を大気の中に吐いた。
今しがた武治は「ひした」のバス停に降り立ったばかりである。たしかに二〇数年振りで見る故郷の天地である。感慨無量だった。
そこは高台で、彼の生まれた辺田都落を、一望の中に見渡せた。一〇月の空は青く澄んで、刈りとられた二面の田んぼをへだてて、彼方には部落の家並が点々と見下せた。
彼は今まで「生きている」という実感を、ごれほど強くうけたことはなかった。郷土の自然は荒廃した彼を新生せしめる、強大なエネルギーを持っていた。彼は再び母体から生れ出ずるような喜悦をさえ覚えるのだった。
たしかに故郷とは遠くで見たり、聞いたり想ったりすべき処ではないと、じかに肌身に接し、この眼でうけ止めて初めて彼は知ったのだ。
武治の心には郷土を目前にして、新たに誓うものがあった。それは以後何人にも郷土を絶対に侵害させてはならぬという誓いだった。
この日この時の印象は彼の心の奥底に焼きついて、やがて六〇歳を一期(いちご)としてこの世を去るまで離れなかった。そればかりか彼が人生の旅路に疲れ果てて希望を失なった時、いつも心底で蘇り、彼を慰め励ましてくれるものとなった。
眼下の辺田部落は西陽に照り輝いて、血のように燃えていた。夕雲は五色に、そのへりは黄金色に輝き、まるで金環をちりぱめたように見えた。
それをみつめていると、彼は、自分のみすぽらしい敗残の姿が、内側から光り輝いて、いつしか竹取り物語の赫夜姫になったような気がした。そして青竹が真二つに割れ、雲上の人となって天空を飛翔するかのようにすら思われてきた。
武治の両眼が落陽をまともにうけると、キラリと光った。彼の視線は自ずと、森陰のわが家の棟に注がれた。古い昔のままの茅葺屋根が、棚引く夕霞の中に霞んで見えた。あの屋根の下で、少年期から青年時代を過ごしたのだと、武治は思った。
彼の心の奥底には、懐かしい昔が走馬燈のように蘇ってきた。
「昔のままだ!」
武治はそう眩くと一瞬、胸のときめきを覚えた。――と、急に目頭に熱いものがこみあげてきた。そこに住む年老いた母のことが思い出されたからである。老母は長年どんなにか、伜の帰りを待ちわひていたであろう。あの古びた屋根の下で……。
武治は部落に入って、小川を渡った。少年の頃、夏にはよく友だちと素裸になつて泳いだり、雑魚を掬ったりした小川だった。それは一〇年前と同じように澄んで流れていた。
武治は橋の上から、下を覗いた。魚の影は見えなかった。映ったものは毛布を背負ったみすぽらしい彼の姿だけだった。それは静かな流れに映って、揺れて崩れた。
武治は夜も暗くなった頃、辺田部落入りを考えたのだが、成田駅に降り立った頃は、まだ陽も高かったので久し振りで新勝寺の境内をぶらついているうち、行き交う参詣客の中に一人の老婆を発見した。それが武治の母に、よく似ていたから、武治は無性に、家に帰りたくなったのである。彼には今年八八歳の老母が健在で、長いこと武治の帰りを待ちあぐんでいたからだった。息子の帰りを唯一の生き甲斐として今日まで生きながらえてきた老母しずのことだけは、どこにいても一日とて忘れる日はなかった。
焦る気持ちを抑えてはいるが、武治の足はわが家に近づくに従って、自ずと早くなっていったのである。
武治は道端に止って、わが家を見上げた。家には人気もなく、静まり返って音もなかった。
「誰もいないのかな」
武治は見上げたまま、首を捻った。慎重な足どりで、入口の坂を上っていくと、腰をくの字に曲げた老母のしずが、土間を這いつくばうような格好をして、何か片づけものをしているところだった。
しずは武治に気づかず、一生懸命、むしろの上の大豆を笊(ざる)にまとめている。
しずは笊から転げ落ちた一粒の大豆も漏らすまいと曲がった腰を屈め土間に額をつけるようにしては拾い上げ、笊の中に集めていた。
昔の農家はこんなでなかつた。随分せちがらくなったものだと、武治は老母の姿を見て思った。しずは、やっと武治の足音に気づいてか、腰を延ばして外を見上げた。
「ああ、いつもの旦那か。今日は何買いにきただ」
しずは武治を、闇買いに間違えたらしい。このような軍服姿の闇買いや東京からの買出し人が、よくこの部落にも入ってきて、一人留守番をしているしずを相手に、いろいろな食料を漁っては買い集めていくのである。
「おっ母さん!」
武治は敷居を跨ぎながら、叫ぶようにしていった。その声にようやくしずは、息子の武治だとわかったか、ギクリとした。
「武治か?」
しずはもう一度腰を延ばし、武治に近づいていった。
「武治っ」
「おっ母さん」
「武治、おめえよく帰(け)えれたな!」
「よく丈夫でいてくれたな、おっ母さん」
親子の瞼には涙が溢れ出た。二人の眼が曇って、辺りを朦朧とさせた。














この記事への質問・一言コメントをどうぞ AIコースケと議論しよう!
回答には文字数制限があるため、制限を超えると途中で打ち切られることがあります。