Webで読む小林多喜二『蟹工船』
時代は軍靴の足音が近づいていた昭和初期。大正デモクラシーの声もすでに潰えさり、軍国主義・愛国主義が幅をきかせてきた頃である。北洋オホーツクで蟹を獲って缶詰に加工する工場船(蟹工船)の「博光丸」では、今日で言うところの「非正規」の下層労働者たちが働いている。
長時間・低賃金の過酷な労働、「派遣業者」である周旋屋からのピンハネ、労働者を物のようにしか考えずに命さえ使い捨てにする現場監督、やがて労働者たちは過酷な環境に耐えきれず、徐々に一致団結していく。だが、そこに現れたのは……。
この小説は実在の蟹工船「博愛丸」でおこった実話に取材し、作家・小林多喜二が戦前の労働者の現状を活写した代表作だ。初掲は文芸誌『戦旗』。単行本は発禁処分までのほんのわずかの期間に3万5千部を売り上げ、当時の天皇制国家権力を震撼させた。多喜二を恐れた天皇制政府は彼を逮捕し、多喜二は29歳の若さで公安警察に拷問虐殺されることになる。
やがて70年の時を越え、小泉「改革」による若者の非正規労働者化や「働く貧困層」の急拡大、改憲策動など政治の右傾化、愛国主義の蔓延という、当時と酷似した社会状況の中、若者たちの間で「今の私たちに似ている」と口コミで広がって「蟹工船」は再びベストセラーとなり、多数の関連書籍が発売され、再映画化が決定されるなど社会現象となった。
※「白樺文学館多喜二ライブラリー」では『30分で読めるマンガ蟹工船』も全ページ(PDF,40MB)が無料公開されています。
※この作品には、今日の常識からみれば不適切な表現が含まれています。その旨をここに記載した上、今日では使われない歴史上の言葉として、原作のままの形で作品を公開しています。
一
「おい地獄さ行(え)ぐんだで!」
二人はデッキの手すりに寄りかかって、蝸牛(かたつむり)が背のびをしたように延びて、海を抱え込んでいる函館の街を見ていた。 ――漁夫は指元まで吸いつくした煙草を唾と一緒に捨てた。巻煙草はおどけたように、色々にひっくりかえって、高い船腹(サイド)をすれずれに落ちて行った。彼は身体一杯酒臭かった。
赤い太鼓腹を巾広く浮かばしている汽船や、積荷最中らしく海の中から片袖をグイと引張られてでもいるように、思いッ切り片側に傾いているのや、黄色い、太い煙突、大きな鈴のようなヴイ、南京虫のように船と船の間をせわしく縫っているランチ、寒々とざわめいている油煙やパン屑や腐った果物の浮いている何か特別な織物のような波……。風の工合で煙が波とすれずれになびいて、ムッとする石炭の匂いを送った。ウインチのガラガラという音が、時々波を伝って直接(じか)に響いてきた。
この蟹工船博光丸のすぐ手前に、ペンキの剥げた帆船が、へさきの牛の鼻穴のようなところから、錨(いかり)の鎖を下していた、甲板を、マドロス・パイプをくわえた外人が二人同じところを何度も機械人形のように、行ったり来たりしているのが見えた。ロシアの船らしかった。たしかに日本の「蟹工船」に対する監視船だった。
「俺(おい)らもう一文も無え。――糞。こら」
そう云って、身体をずらして寄こした。そしてもう一人の漁夫の手を握って、自分の腰のところへ持って行った。袢天(はんてん)の下のコールテンのズボンのポケットに押しあてた。何か小さい箱らしかった。
一人は黙って、その漁夫の顔をみた。
「ヒヒヒヒ……」と笑って、「花札(はな)よ」と云った。
ボート・デッキで、「将軍」のような恰好(かっこう)をした船長が、ブラブラしながら煙草をのんでいる。はき出す煙が鼻先からすぐ急角度に折れて、ちぎれ飛んだ。底に木を打った草履(ぞうり)をひきずッて、食物バケツをさげた船員が急がしく「おもて」の船室を出入した。――用意はすっかり出来て、もう出るにいいばかりになっていた。
雑夫のいるハッチを上から覗きこむと、薄暗い船底の棚に、巣から顔だけピョコピョコ出す鳥のように、騒ぎ廻っているのが見えた。皆十四、五の少年ばかりだった。
「お前は何処(どこ)だ」
「××町」みんな同じだった。函館の貧民窟の子供ばかりだった。そういうのは、それだけで一かたまりをなしていた。
「あっちの棚は?」
「南部」
「それは?」
「秋田」
それ等は各々棚をちがえていた。
「秋田の何処だ」
膿のような鼻をたらした、眼のふちがあかべをしたようにただれているのが、
「北秋田だんし」と云った。
「百姓か?」
「そんだし」
空気がムンとして、何か果物でも腐ったすッぱい臭気がしていた。漬物を何十樽も蔵(しま)ってある室が、すぐ隣りだったので、「糞」のような臭いも交っていた。
「こんだ親父(おど)抱いて寝てやるど」――漁夫がベラベラ笑った。
薄暗い隅の方で、袢天(はんてん)を着、股引(ももひき)をはいた、風呂敷を三角にかぶった女出面(でめん)らしい母親が、林檎(りんご)の皮をむいて、棚に腹ん這いになっている子供に食わしてやっていた。子供の食うのを見ながら、自分では剥いたぐるぐるの輪になった皮を食っている。何かしゃべったり、子供のそばの小さい風呂敷包みを何度も解いたり、直してやっていた。そういうのが七、八人もいた。誰も送って来てくれるもののいない内地から来た子供達は、時々そっちの方をぬすみ見るように、見ていた。
髪や身体がセメントの粉まみれになっている女が、キャラメルの箱から二粒位ずつ、その附近の子供達に分けてやりながら、
「うちの健吉と仲よく働いてやってけれよ、な」と云っていた。木の根のように不恰好(ぶかっこう)に大きいザラザラした手だった。
子供に鼻をかんでやっているのや、手拭(てぬぐい)で顔をふいてやっているのや、ボソボソ何か云っているのや、あった。
「お前さんどこの子供は、身体はええべものな」
母親同志だった。
「ん、まあ」
「俺どこのア、とても弱いんだ。どうすべかッて思うんだども、何んしろ……」
「それア何処でも、ね」
――二人の漁夫がハッチから甲板へ顔を出すと、ホッとした。不機嫌に、急にだまり合ったまま雑夫の穴より、もっと船首の、梯形(ていけい)の自分達の「巣」に帰った。錨を上げたり、下したりする度に、コンクリート・ミキサの中に投げ込まれたように、皆は跳ね上り、ぶッつかり合わなければならなかった。
薄暗い中で、漁夫は豚のようにゴロゴロしていた、それに豚小屋そっくりの、胸がすぐゲエと来そうな臭いがしていた。
「臭せえ、臭せえ」
「そよ、俺だちだもの。ええ加減、こったら腐りかけた臭いでもすべよ」
赤い臼(うす)のような頭をした漁夫が、一升瓶そのままで、酒を端のかけた茶碗に注いで、鯣(するめ)をムシャムシャやりながら飲んでいた。その横に仰向けにひっくり返って、林檎を食いながら、表紙のボロボロした講談雑誌を見ているのがいた。
四人輪になって飲んでいたのに、まだ飲み足りなかった一人が割り込んで行った。
「……んだべよ。四カ月も海の上だ。もう、これんかやれねべと思って……」
頑丈な身体をしたのが、そう云って、厚い下唇を時々癖のように嘗(な)めながら眼を細めた。
「んで、財布これさ」
干柿のようなべったりした薄い蟇口(がまぐち)を眼の高さに振ってみせた。
「あの白首(ごけ)、身体こったらに小せえくせに、とても上手(うめ)えがったどオ!」
「おい、止せ、止せ!」
「ええ、ええ、やれやれ」
相手はへへへへへと笑った。
「見れ、ほら、感心なもんだ。ん?」酔った眼を丁度向い側の棚の下にすえて、顎(あご)で、「ん!」と一人が云った。
漁夫がその女房に金を渡しているところだった。
「見れ、見れ、なア!」
小さい箱の上に、皺くちゃになった札や銀貨を並べて、二人でそれを数えていた。男は小さい手帖に鉛筆をなめ、なめ何か書いていた。
「見れ。ん!」
「俺にだって嬶(かかあ)や子供はいるんだで」白首(ごけ)のことを話した漁夫が急に怒ったように云った。
そこから少し離れた棚に、宿酔(ふつかよい)の青ぶくれにムクンだ顔をした、頭の前だけを長くした若い漁夫が、
「俺アもう今度こそア船さ来ねえッて思ってたんだけれどもな」と大声で云っていた。「周旋屋に引っ張り廻されて、文無しになってよ。――又、長げえことくたばるめに合わされるんだ」
こっちに背を見せている同じ処から来ているらしい男が、それに何かヒソヒソ云っていた。
ハッチの降口に始め鎌足を見せて、ゴロゴロする大きな昔風の信玄袋を担った男が、梯子(はしご)を下りてきた。床に立ってキョロキョロ見廻わしていたが、空いているのを見付けると、棚に上って来た。
「今日は」と云って、横の男に頭を下げた。顔が何かで染ったように、油じみて、黒かった。「仲間さ入(え)れて貰えます」
後で分ったことだが、この男は、船へ来るすぐ前まで夕張炭坑に七年も坑夫をしていた。それがこの前のガス爆発で、危く死に損ねてから――前に何度かあった事だが――フイと坑夫が恐ろしくなり、鉱山(やま)を下りてしまった。爆発のとき、彼は同じ坑内にトロッコを押して働いていた。トロッコに一杯石炭を積んで、他の人の受持場まで押して行った時だった。彼は百のマグネシウムを瞬間眼の前でたかれたと思った。それと、そして1/500[#「1/500」は分数]秒もちがわず、自分の身体が紙ッ片(きれ)のように何処かへ飛び上ったと思った。何台というトロッコがガスの圧力で、眼の前を空のマッチ箱よりも軽くフッ飛んで行った。それッ切り分らなかった。どの位経(た)ったか、自分のうなった声で眼が開いた。監督や工夫が爆発が他へ及ばないように、坑道に壁を作っていた。彼はその時壁の後から、助ければ助けることの出来る炭坑夫の、一度聞いたら心に縫い込まれでもするように、決して忘れることの出来ない、救いを求める声を「ハッキリ」聞いた。――彼は急に立ち上ると、気が狂ったように、
「駄目だ、駄目だ!」と皆の中に飛びこんで、叫びだした。(彼は前の時は、自分でその壁を作ったことがあった。そのときは何んでもなかったのだったが)
「馬鹿野郎! ここさ火でも移ってみろ、大損だ」
だが、だんだん声の低くなって行くのが分るではないか! 彼は何を思ったのか、手を振ったり、わめいたりして、無茶苦茶に坑道を走り出した。何度ものめったり、坑木に額を打ちつけた。全身ドロと血まみれになった。途中、トロッコの枕木につまずいて、巴投(ともえな)げにでもされたように、レールの上にたたきつけられて、又気を失ってしまった。
その事を聞いていた若い漁夫は、
「さあ、ここだってそう大して変らないが……」と云った。
彼は坑夫独特な、まばゆいような、黄色ッぽく艶(つや)のない眼差(まなざし)を漁夫の上にじっと置いて、黙っていた。
秋田、青森、岩手から来た「百姓の漁夫」のうちでは、大きく安坐(あぐら)をかいて、両手をはすがいに股(また)に差しこんでムシッとしているのや、膝を抱えこんで柱によりかかりながら、無心に皆が酒を飲んでいるのや、勝手にしゃべり合っているのに聞き入っているのがある。――朝暗いうちから畑に出て、それで食えないで、追払われてくる者達だった。長男一人を残して――それでもまだ食えなかった――女は工場の女工に、次男も三男も何処かへ出て働かなければならない。鍋で豆をえるように、余った人間はドシドシ土地からハネ飛ばされて、市に流れて出てきた。彼等はみんな「金を残して」内地(くに)に帰ることを考えている。然(しか)し働いてきて、一度陸を踏む、するとモチを踏みつけた小鳥のように、函館や小樽でバタバタやる。そうすれば、まるッきり簡単に「生れた時」とちっとも変らない赤裸になって、おっぽり出された。内地(くに)へ帰れなくなる。彼等は、身寄りのない雪の北海道で「越年(おつねん)」するために、自分の身体を手鼻位の値で「売らなければならない」――彼等はそれを何度繰りかえしても、出来の悪い子供のように、次の年には又平気で(?)同じことをやってのけた。
菓子折を背負った沖売の女や、薬屋、それに日用品を持った商人が入ってきた。真中の離島のように区切られている所に、それぞれの品物を広げた。皆は四方の棚の上下の寝床から身体を乗り出して、ひやかしたり、笑談(じょうだん)を云った。
「お菓子(がし)めえか、ええ、ねっちゃよ?」
「あッ、もッちょこい!」沖売の女が頓狂(とんきょう)な声を出して、ハネ上った。「人の尻さ手ばやったりして、いけすかない、この男!」
菓子で口をモグモグさせていた男が、皆の視線が自分に集ったことにテレて、ゲラゲラ笑った。
「この女子(あねこ)、可愛(めんこ)いな」
便所から、片側の壁に片手をつきながら、危い足取りで帰ってきた酔払いが、通りすがりに、赤黒くプクンとしている女の頬(ほっ)ぺたをつッついた。
「何んだね」
「怒んなよ。――この女子(あねこ)ば抱いて寝てやるべよ」
そう云って、女におどけた恰好をした。皆が笑った。
「おい饅頭(まんじゅう)、饅頭!」
ずウと隅(すみ)の方から誰か大声で叫んだ。
「ハアイ……」こんな処ではめずらしい女のよく通る澄んだ声で返事をした。「幾(なん)ぼですか?」
「幾(なん)ぼ? 二つもあったら不具(かたわ)だべよ。――お饅頭、お饅頭!」――急にワッと笑い声が起った。
「この前、竹田って男が、あの沖売の女ば無理矢理に誰もいねえどこさ引っ張り込んで行ったんだとよ。んだけ、面白いんでないか。何んぼ、どうやっても駄目だって云うんだ……」酔った若い男だった。「……猿又(さるまた)はいてるんだとよ。竹田がいきなりそれを力一杯にさき取ってしまったんだども、まだ下にはいてるッて云うんでねか。――三枚もはいてたとよ……」男が頸(くび)を縮めて笑い出した。
その男は冬の間はゴム靴会社の職工だった。春になり仕事が無くなると、カムサツカへ出稼ぎに出た。どっちの仕事も「季節労働」なので、(北海道の仕事は殆(ほと)んどそれだった)イザ夜業となると、ブッ続けに続けられた。「もう三年も生きれたら有難い」と云っていた。粗製ゴムのような、死んだ色の膚をしていた。
漁夫の仲間には、北海道の奥地の開墾地や、鉄道敷設の土工部屋へ「蛸(たこ)」に売られたことのあるものや、各地を食いつめた「渡り者」や、酒だけ飲めば何もかもなく、ただそれでいいものなどがいた。青森辺の善良な村長さんに選ばれてきた「何も知らない」「木の根ッこのように」正直な百姓もその中に交っている。――そして、こういうてんでんばらばらのもの等を集めることが、雇うものにとって、この上なく都合のいいことだった。(函館の労働組合は蟹工船、カムサツカ行の漁夫のなかに組織者を入れることに死物狂いになっていた。青森、秋田の組合などとも連絡をとって。――それを何より恐れていた)
糊(のり)のついた真白い、上衣(うわぎ)の丈の短い服を着た給仕(ボーイ)が、「とも」のサロンに、ビール、果物、洋酒のコップを持って、忙しく往き来していた。サロンには、「会社のオッかない人、船長、監督、それにカムサツカで警備の任に当る駆逐艦の御大(おんたい)、水上警察の署長さん、海員組合の折鞄(おりかばん)」がいた。
「畜生、ガブガブ飲むったら、ありゃしない」――給仕はふくれかえっていた。
漁夫の「穴」に、浜なすのような電気がついた。煙草の煙や人いきれで、空気が濁って、臭く、穴全体がそのまま「糞壺(くそつぼ)」だった。区切られた寝床にゴロゴロしている人間が、蛆虫(うじむし)のようにうごめいて見えた。――漁業監督を先頭に、船長、工場代表、雑夫長がハッチを下りて入って来た。船長は先のハネ上っている髭を気にして、始終ハンカチで上唇を撫でつけた。通路には、林檎やバナナの皮、グジョグジョした高丈(たかじょう)、鞋(わらじ)、飯粒のこびりついている薄皮などが捨ててあった。流れの止った泥溝(どぶ)だった。監督はじろりそれを見ながら、無遠慮に唾をはいた。――どれも飲んで来たらしく、顔を赤くしていた。
「一寸(ちょっと)云って置く」監督が土方の棒頭(ぼうがしら)のように頑丈(がんじょう)な身体で、片足を寝床の仕切りの上にかけて、楊子(ようじ)で口をモグモグさせながら、時々歯にはさまったものを、トットッと飛ばして、口を切った。
「分ってるものもあるだろうが、云うまでもなくこの蟹工船の事業は、ただ単にだ、一会社の儲仕事(もうけしごと)と見るべきではなくて、国際上の一大問題なのだ。我々が――我々日本帝国人民が偉いか、露助が偉いか。一騎打ちの戦いなんだ。それに若(も)し、若しもだ。そんな事は絶対にあるべき筈(はず)がないが、負けるようなことがあったら、睾丸(きんたま)をブラ下げた日本男児は腹でも切って、カムサツカの海の中にブチ落ちることだ。身体が小さくたって、野呂間な露助に負けてたまるもんじゃない。
「それに、我カムサツカの漁業は蟹罐詰ばかりでなく、鮭(さけ)、鱒(ます)と共に、国際的に云ってだ、他の国とは比らべもならない優秀な地位を保っており、又日本国内の行き詰った人口問題、食糧問題に対して、重大な使命を持っているのだ。こんな事をしゃべったって、お前等には分りもしないだろうが、ともかくだ、日本帝国の大きな使命のために、俺達は命を的に、北海の荒波をつッ切って行くのだということを知ってて貰わにゃならない。だからこそ、あっちへ行っても始終我帝国の軍艦が我々を守っていてくれることになっているのだ。……それを今流行(はや)りの露助の真似をして、飛んでもないことをケシかけるものがあるとしたら、それこそ、取りも直さず日本帝国を売るものだ。こんな事は無い筈だが、よッく覚えておいて貰うことにする……」
監督は酔いざめのくさめを何度もした。
酔払った駆逐艦の御大はバネ仕掛の人形のようなギクシャクした足取りで、待たしてあるランチに乗るために、タラップを下りて行った。水兵が上と下から、カントン袋に入れた石ころみたいな艦長を抱えて、殆んど持てあましてしまった。手を振ったり、足をふんばったり、勝手なことをわめく艦長のために、水兵は何度も真正面(まとも)から自分の顔に「唾」を吹きかけられた。
「表じゃ、何んとか、かんとか偉いこと云ってこの態(ざま)なんだ」
艦長をのせてしまって、一人がタラップのおどり場からロープを外しながら、ちらっと艦長の方を見て、低い声で云った。
「やっちまうか?!……」
二人は一寸息をのんだ、が……声を合せて笑い出した。







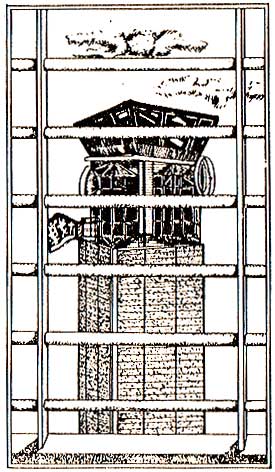








この記事への質問・一言コメントをどうぞ AIコースケと議論しよう!
回答には文字数制限があるため、制限を超えると途中で打ち切られることがあります。