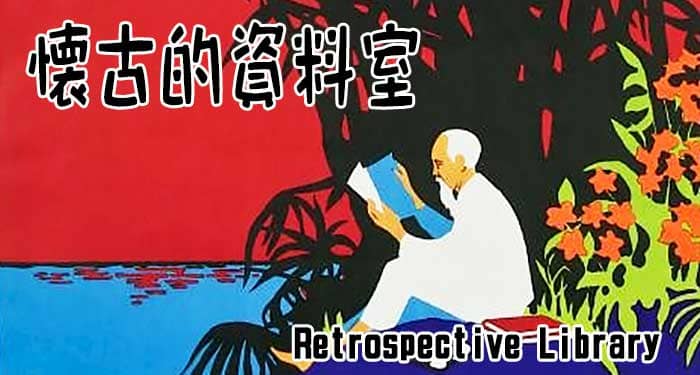Contents -このページの目次-
未分類・整理中
■ 三里塚空港反対同盟 石井武さんを悼む
■ 成田空港管制塔占拠事件(Wikipediaより)
■ 歴史の瞬間に立って-60年安保闘争の記録
■ 60年安保闘争年表
■ 日本赤軍とは何か-これだけは知ってほしいこと
■ 機動隊のガス銃使用に関する国会質疑議事録
小説三里塚
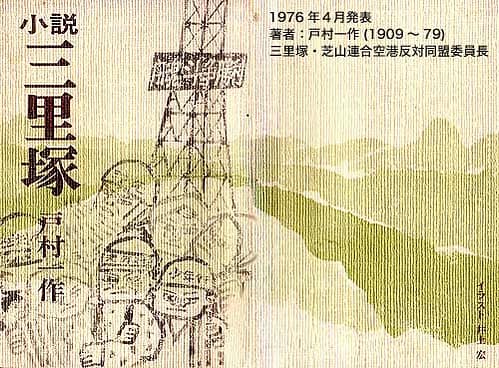
左翼思想入門の入門

どうして左翼はあんなことを言ったり、あんな行動をとるのか?
左派の皆さんの実践と、右派の皆さんの批判のお供に。
- やなせたかし『アンパンマン』論ー『共産主義』ってどんなもの?
- ウルトラマンと『革命無罪』-左翼が「何でも反対」の理由
- 菊池桃子と『左翼魂』-どんな人間のことを『左翼』と呼ぶのか?
- マルクス『賃労働と資本』ノート
- レーニン『帝国主義論』ノート
カテゴリ:左翼的発想の研究 アーカイブ
過激派への100の質問(連載中)

「100問100答」形式で、いわゆる「過激派」に対して一般市民から討論の際によくよせられる質問とそれへの回答をまとめたコンパクトなFAQ(連載中)。
主体性論・哲学論

ソ連や中国の現状、内ゲバやセクト主義の跋扈、それへの反発として市民主義やエコロジー路線の台頭。その中で左翼運動やそれを担う主体について考え続けた論考。
戦争論・政治論

戦旗派内部組織総括文書

世が世なら絶対に公開されることのなかった戦旗・共産主義者同盟の組織内文書。
特に同時期に活動していた他党派や市民団体などの活動家諸氏は必見。
戦旗派写真集(連載中)

戦旗派写真集目次ページ
お世話になったサイト様一覧
「戦旗派」についての解説(戦旗派写真集の掲載にあたって)
1971~73(戦旗派第一期建設)
1974~75(第二期建設開始)
1976~79(三里塚開港阻止決戦)
1980~85
1986~90
活動家マニュアル集(連載中)

これであなたも活動家!? 旧戦旗・共産主義者同盟で提起されていた活動家のマニュアル群。一般の方々が言論弾圧から身を守る際の参考に。
総論編
日常活動編
反弾圧編
組織活動編
参考資料
2chブントスレ保管庫(連載中)

かつて2ちゃねる共産板の名物スレだった「ブント(戦旗)スレ」を資料として保管
小説・エッセイ

勤労青年山の会

元戦旗派活動家にとって、活動とは別の忘れがたい思い出。それは一年中山に登り続けたことだった!
特集:上州武尊山行
- 武尊山 組織山行の背景事情(草加耕助)
- 概要・全体総括
- 参加者個人手記(1)「椅子にあわせて足を切る」
- 参加者個人手記(2)「私は山が嫌いだ」
- 参加者個人手記(3)「女性隊のリーダーに選ばれて」
- 参加者個人手記(4)「それは雪山の入門書の購入から始まった」
[Sponsor Ad]