Webで読む佐藤紅緑『ああ玉杯に花うけて』
本作の一部には差別的な表現、または戦争やファシズムを支えるイデオロギーを宣伝する表現など、今日の常識からみれば明らかに不適切な表現が含まれている箇所があります。 その旨をここに記載した上、作品公開時の時代的な限界性を読者自身が認識し学ぶ意義も考慮し、今日では使われない歴史上の言葉として、原作のままの形で作品を公開しています。ご了承ください。
一

豆腐屋のチビ公はいまたんぼのあぜを伝ってつぎの町へ急ぎつつある。さわやかな春の朝日が森をはなれて黄金の光の雨を緑の麦畑に、黄色な菜畑に、げんげさくくれないの田に降らす、あぜの草は夜露からめざめて軽やかに頭を上げる、すみれは薄紫の扉(と)を開き、たんぽぽはオレンジ色の冠をささげる。堰の水はちょろちょろ音立てて田へ落ちると、かえるはこれからなきだす準備にとりかかっている。
チビ公は肩のてんびん棒にぶらさげた両方のおけをくるりとまわした。そうしてしばらく景色に見とれた。堤の上にかっと朝日をうけてうきだしている村の屋根屋根、火の見やぐら、役場の窓、白い土蔵、それらはいまねむりから活動に向かって歓喜の声をあげているかのよう、ところどころに立つ炊煙(すいえん)はのどかに風にゆれて林をめぐり、お宮の背後(うしろ)へなびき、それからうっとりとかすむ空のエメラルド色にまぎれゆく。
そこの畠にはえんどうの花、そらまめの花がさきみだれてる中にこつとしてねぎの坊主がつっ立っている。いつもここまでくるとチビ公の背中が暖かくなる。春とはいえども暁(あかつき)は寒い、奥歯をかみしめかみしめチビ公は豆腐をおけに移して家をでなければならないのである。町の人々が朝飯がすんだあとでは一丁の豆腐も売れない、どうしても六時にはひとまわりせねばならぬのだ。
だが、このねぎ畑のところへくるとかれはいつも足が進まなくなる、ねぎ畑のつぎは広い麦畑で、そのつぎには生け垣があって二つの土蔵があって、がちょうの叫び声がきこえる、それはこの町の医者の家である。
医者がいつの年からこの家に住んだのかは今年十五歳になるチビ公の知らないところだ、伯父の話ではチビ公の父が巨財を投じてこの家を建てたのだが、父は政党にむちゅうになってすべての財産をなくなしてしまった、父が死んでからかれは母とともに一人の伯父の厄介になった、それはかれの二歳のときである。
「しっかりしろよ、おまえのお父さまはえらい人なんだぞ」
伯父はチビ公をつれてこのねぎ畑で昔の話をした。それからというものはチビ公はいつもねぎ畑に立ってそのことを考えるのであった。
「この家をとりかえしてお母さんを入れてやりたい」今日もかれはこう思った、がかれはゆかねばならない、荷を肩に負うて一足二足よろめいてやっとふみとどまる。
かれは十五ではあるがいたってちいさい、村ではかれを千三(せんぞう)と呼ぶ人はない、チビ公のあだ名でとおっている、かれはチビ公といわれるのが非常にいやであった、が人よりもちびなのだからしかたがない、来年になったら大きくなるだろうと、そればかりを楽しみにしていた、が来年になっても大きくならない、それでもう一つ来年を待っているのであった。
かれがこのあぜ道に立っているとき、おりおりいうにいわれぬ侮辱を受けることがある。それは役場の助役の子で阪井巌(さかいいわお)というのがかれを見るとぶんなぐるのである。もちろん巌はだれを見てもなぐる、かれは喧嘩が強くてむこう見ずで、いつでも身体に生きずが絶えない。
かれは小学校でチビ公と同級であった、小学校時代にはチビ公はいつも首席であったが巌は一度落第してきたにかかわらず末席であった。かれはいつもへびをふところに入れて友達をおどかしたり、女生徒を走らしたり、そうしておわりにはそれをさいて食うのであった。
「やい、おめえはできると思っていばってるんだろう、やい、このへびを食ってみろ」
かれはすべての者にこういってつっかかった、かれはいま中学校へ通っている、豆腐おけをかついだチビ公は彼を見ると遠くへさけていた、だがどうかするとかれは途中でばったりあうことがある。
「てめえはいつ見てもちいせえな、少し大きくしてやろうか」
かれはチビ公の両耳をつかんで、ぐっと上へ引きあげ、足が地上から五寸もはなれたところで、どしんと下へおろす。これにはチビ公もまったく閉口した。
かれが今町の入り口へさしかかると向こうから巌がやってきた、かれは頭に鉢巻きをして柔道のけいこ着を着ていた。チビ公ははっと思って小路にはいろうとすると巌がよびとめた。

「やいチビ、逃げるのかきさま」
「逃げやしません」
「豆腐をくれ」
「はい」
チビ公は不安そうに顔を見あげた。
「いかほど?」
「食えるだけ食うんだよ、おれは朝飯前に柔道のけいこをしてきたから腹がへってたまらない、焼き豆腐があるか」
「はい」
チビ公が蓋をあけると巌はすぐ手をつっこんだ、それから焼き豆腐をつかみあげて皮ばかりぺろぺろと食べて中身を大地にすてた。
「皮はうまいな」
「そうですか」とチビ公はしかたなしにいった。
「もう一つ」
かれは三つの焼き豆腐の皮を食べおわって、ぬれた手をチビ公の頭でふいた。
「銭はこのつぎだよ」
「はい」
「用がないからゆけよ、おれはここで八百屋の豊公(とよこう)を待っているんだ、あいつおれの犬に石をほうりやがったからここでいもをぶんどってやるんだ」
チビ公はやっと虎口をのがれて町へはいった、そうして悲しくらっぱをふいた。らっぱをふく口元に涙がはてしなくこぼれた。
どうしてあんなやつにこうまで侮辱されなきゃならないんだろう、あいつは学校でなんにもできないのだ、おやじが役場の助役だからいばってるんだ、金があるから中学校へゆける、親があるから中学校へゆける。それなのにおれは金もない親もない。なぐられてもだまっていなきゃならない、生涯豆腐をかついでらっぱをふかなきゃならない。
かれの胸は憤怒に燃えた、かれはだまって歩きつづけた。
「おい豆腐屋、売るのか売らないのか、らっぱを落としたのか」
職人風の男が二人、こういってわらってすぎた。チビ公はらっぱをふいた、その音はいかにも悲しそうにひびいた。町にはちらちら中学生が登校する姿が見えだした、それは大抵去年まで自分と同級の生徒であった。チビ公は鳥打帽のひさしを深くして通りすぎた。
「おはよう青木君」と明るい声がきこえた。
「お早う」とチビ公はふりかえっていった、声をかけたのは昔の学友柳光一(やなぎこういち)という少年であった、柳は黒い制服をきちんと着て肩に草色の雑嚢(ざつのう)をかけ、手に長くまいた画用紙を持っていた。

かれはいかなるときでもチビ公にあうとこう声をかける、かれは小学校にあるときにはいつもチビ公と席を争うていた、双方とも勉強家であるが、たがいにその学力をきそうていた、これといって親密にしたわけでもないが、光一の態度は昔もいまもかわらなかった、一方が中学生となり一方は豆腐屋となっても。
「ぼくはね、きみを時計にしてるんだよ」と光一はいった。「きみに逢った時には非常に早いし、きみにあわなかったときにはおそいんだ」
「そうですか」
「重たいだろうね、きみ」
光一はチビ公の荷を見やっていった。
「なあになれましたから」
「そうかね」と、光一はチビ公の顔をしみじみと見やって、「ひまがあったら遊びにきてくれたまえね、ぼくのところにはいろいろな雑誌があるから、ぼくはきみにあげようと思ってとっておいてあるよ」
「ありがとう」
「じゃ失敬」
チビ公は光一にわかれた、なんとなくうれしいようななつかしいような思いはむらむらと胸にわいた、でかれはらっぱをふいた、らっぱはほがらかにひびいた。
と一旦わかれた光一は大急ぎに走りもどった。
「このつぎの日曜にね、ぼくの誕生日だから、昼からでも……晩からでも遊びにきてくれたまえね」
「そうですか……しかし」とチビ公はもじもじした。
「かまわないだろ、日曜だから……」
「ああ、そうだけれども」
「いいからね、遠慮せずとも、ぼくは昔の友達にみんなきてもらうんだ」
「じゃゆきましょう」
光一はふたたび走って去った。雑嚢を片手にかかえ、片手に画用紙を持ち両ひじをわきにぴったりと着けて姿勢正して走りゆく。
それを見送ってチビ公は昔小学校時代のことをまざまざと思いだした。なんとなく光一の前途にはその名のごとく光があふれてるように見える、学問ができて体力が十分で品行がよくて、人望がある、ああいう人はいまにりっぱな学者になるだろう。そこでかれはまたらっぱをふいた、嚠喨(りゅうりょう)たる音は町中にひびいた。
チビ公が売りきれるまで町を歩いてるその日の十二時ごろ、中学校の校庭で巌はものほしそうにみんなが昼飯を食っているのをながめていた、かれは大抵十時ごろに昼の弁当を食ってしまうので正午(ひる)になるとまたもや空腹を感ずるのであった。
そういうときにはかならずだれかに喧嘩をふきかけてその弁当を掠奪するのである。自分の弁当を食うよりは掠奪のほうがはるかにうまい。
「みんな集まれい」とかれはどなった。だが何人も集まらなかった、いつものこととて生徒等はこそこそと木立ちの陰にかくれた。
「へびの芸当だ」とかれはいった、そうしてポケットから青大将をだした。
「そもそもこれは漢の沛公が函谷関を越ゆるときに二つに斬った白蛇の子孫でござい」
調子面白くはやしたてたので人々は少しずつ遠くから見ていた。少年等はまた始まったといわぬばかりに眉をしかめていた。
「おいしゃもじ!」とかれは背後を向いて飯を食ってる一人の少年をよんだ、しゃもじはおわりの一口をぐっとのみこんで走ってきた、かれはやせて敏捷そうな少年だが、頭は扇のように開いてほおが細いので友達はしゃもじというあだ名をつけた。かれは身体も気も弱いので、いつでも強そうな人の子分になって手先に使われている。
「おい口上をいえ」と巌がいった。
「なんの?」
「へびに芸をさせるんだ」
「よしきた……そもそもこれは漢の沛公が二つに斬った白蛇の子孫でござい」
調子おもしろくはやしたてたので人々は少しずつ集まりかけた。
「さあさあ、ごろうじろ、ごろうじろ」
しゃもじの調子にのって巌はへびをひたいに巻きつけ、ほおをはわし、首に巻き、右のそで口から左のそで口から中央のふところから自由自在になわのごとくあやなした。
「うまいぞうまいぞ」と喝采するものがある。最後にかれはへびを一まとめにして口の中へ入れた。人々は驚いてさかんに喝采した。
「おいどうだ」
かれはへびを口からはきだしてからみんなにいった。
「うまいうまい」
「みんな見たか」
「うまいぞ」
「見たものは弁当をだせ」
人々はだまって顔を見合った、そうして後列の方からそろそろと逃げかけた。
「おい、こらッ」
いまにぎり飯を食いながら逃げようとする一人の少年の口元めがけてへびを投げた。少年はにぎり飯を落とした。

「つぎはだれだ」
かれは器械体操のたなの下にうずくまってる少年の弁当をのぞいた、弁当の中には玉子焼きとさけとあった。
「うまそうだな」
かれは手を伸ばしてそれを食った。そして半分をしゃもじにやった。
「つぎは?」
もうだれもいなかった、投げられたへびはぐんにゃりと弱っていた。かれはそれを拾うと裏の林の方へ急いだ。そこには多くの生徒が群れていた、かれらの大部分は水田に糸をたれてかえるをつっていた。その他の者は木陰木陰に腰をおろして雑誌を読んだり、宿題を解いたりしていた。巌はずらりとかれらを見まわした、これというやつがあったら喧嘩をしてやろう。
だがあいにく弱そうなやつばかりで相手とするにたらぬ、そこでかれは木の下に立って一同を見おろしていた。
かれの胸はいつも元気がみちみちている、かれは毎朝眼がさめるとうれしさを感ずる、学校へいって多くの学生をなぐったりけとばしたり、自由に使役したりするのがさらにうれしい。
かれはいろいろな冒険談を読んだり、英雄の歴史を読んだりした、そうしてロビンソンやクライブやナポレオンや秀吉は自分ににていると思った。
「クライブは不良少年で親ももてあました、それでインドへ追いやられて会社の腰弁になってるうちに自分の手腕をふるってついにインドを英国のものにしてしまった、おれもどこかへ追いだされたら、一つの国を占領して日本の領土を拡張しよう」
こういう考えは毎日のようにおこった、かれは実際喧嘩に強いところをもって見ると、クライブになりうる資格があると自信している。
「おれは英雄だ」
かれはナポレオンになろうと思ったときには胸のところに座蒲団を入れて反身(そりみ)になって歩いた。秀吉になろうと思った時にはおそろしく目をむきだしてさるのごとくに歯を出して歩く。
かれの子分のしゃもじは国定忠治や清水の次郎長がすきであった、かれはまき舌でものをいうのがじょうずで、博徒の挨拶を暗記していた。
「おれはおまえのような下卑たやつはきらいだ」と巌がしゃもじにいった。
「何が下卑てる?」
「国定忠治だの次郎長だの、博徒じゃないか、尻をまくって外を歩くような下卑たやつはおれの仲間にゃされない」
「じゃどうすればいいんだ」
「おれは秀吉だからお前は加藤か小西になれよ」
かれはとうとうしゃもじを加藤清正にしてしまった。だがこの清正はいたって弱虫でいつも同級生になぐられている。大抵の喧嘩は加藤しゃもじの守から発生する、しゃもじがなぐられて巌に報告すると巌は復讐してくれるのである。
いずれの中学校でも一番生意気で横暴なのは三年生である、四年五年は分別が定まり、自重心も生ずるとともに年少者をあわれむ心もできるが、三年はちょうど新兵が二年兵になったように、年少者に対して傲慢であるとともに年長者に対しても傲慢である。
浦和中学の三年生と二年生はいつも仲が悪かった、年少の悲しさは戦いのあるたびに二年が負けた、巌はいつもそれを憤慨したがやはりかなわなかった。
「二年の名誉にかかわるぞ」
かれはこういいいいした、かれはいま木の下に立って群童を見おろしているうちに、なにしろ五人分の弁当を食った腹加減はばかに重く、背中を春日に照らされてとろとろと眠くなった。でかれは木の根に腰をおろして眠った。
「やあ生蕃(せいばん)が眠ってらあ」
学生どもはこういいあった。生蕃とは巌のあだ名である、かれは色黒く目大きく頭の毛がちぢれていた、それからかれはおどろくべき厚みのあるくちびるをもっていた。
うとうととなったかと思うと巌は犬のほえる声を聞いた。はじめは普通の声で、それは学生等の混雑した話し声や足音とともに夢のような調節(ハーモニー)をなしていたが、突然犬の声は憤怒と変じた。巌ははっと目を開いた。もうすべての学生が犬の周囲に集まっていた。
二年生の手塚という医者の子が鹿毛(しかげ)のポインターをしっかりとおさえていた、するとそれと向きあって三年の細井という学生は大きな赤毛のブルドッグの首環をつかんでいた。
「そっちへつれていってくれ」と手塚が当惑らしくいった。
「おまえの方から先に逃げろ」と三年の細井がいった。
「やらせろ、やらせろ、おもしろいぞ」としゃもじが中間にはいっていった。犬と犬とが顔を見あったときまたほえあった。
「やれやれやれ」と一年が叫びだした。
「やるならやろう」と三年がいった。
「よせよ」人々を押しわけて光一が進みでた、かれは手に代数の筆記帳を持っていた。
「やらせろ」と双方が叫んだ。
「つまらないじゃないか、犬と犬とを喧嘩させたところでおもしろくもなんともないよ、見たまえ犬がかわいそうじゃないか、犬には喧嘩の意志がないのだよ」
「降参するならゆるしてやろう」と三年がいった。
「降参とかなんとか、そんなことをいうから喧嘩になるんだ」と光一はいった。
「だっておまえの方で、かなわないからやめてくれといったじゃないか」
「かなうのかなわないのという問題じゃないよ、ただね、つまらないことは……」
「なにを?」
三年の群れからライオンとあだ名された木俣(きまた)という学生がおどりだした。
木俣といえば全校を通じて戦慄せぬものがない、かれは柔道がすでに三段で小相撲のように肥って腕力は抜群である、かれは鉄棒に両手をくっつけてぶらさがり、そのまま反動もつけずにひじを立ててぬっくとひざまでせりあげるので有名である。柔道のじまんばかりでなく剣道もじまんで、どうかすると短刀をふところにしのばせたり、小刀をポケットにかくしたりしている。
木俣がおどりだしたので人々は沈黙した。
「おじぎをしたらゆるしてやるよ、なあおい」
とかれは同級生をふりかえっていった。
「三遍まわっておじぎしろ」
光一はもうこの人達にかかりあうことの愚を知ったのでひきさがろうとした。
「逃げるかッ」
木俣は光一の手首をたたいた、筆記帳は地上に落ちて、さっとページをひるがえした。光一はだまってそれを拾いあげしずかに人群れをでた。むろんかれは平素人と争うたことがないのであった。
「弱いやつだ」
三年生は嘲笑した。
「いったいこの犬はだれの犬だ」と木俣はいった。人々は手塚の顔を見た。
「ぼくのだ」
「てめえに似て臆病だな」
「なにをいってるんだ」と手塚は負けおしみをいった。
「二年生は犬まで弱虫だということよ」
三年生は声をそろえてわらった。二年生はたがいに顔を見あったがなにもいう者はなかった。
「やっしいやっしい」と木俣はブルドッグのしりをたたいた。赤犬はおそろしい声をだして突進した、鹿毛(しかげ)は少ししりごみしたがこのときしゃもじがその首環を引いて赤犬の鼻に鼻をつきあてた、こうなると鹿毛もだまっていない、疾風のごとく赤犬にたちかかった、赤は前足で受け止めて鹿毛の首筋の横にかみついた、かまれじと鹿毛は体をかわして赤の耳をねらった。一離一合(いちりいちごう)! 殺気があふれた。
二、三度同じことをくりかえして双方たがいに下手をねらって首を地にすえた。
「やっしいやっしい」
両軍の応援は次第に熱した。このとき二年生は歓喜の声をあげた。のそりのそり眠そうな目をこすりながら生蕃がやってきたからである。
「生蕃がきた」
「たのむぞ」
「やってくれ」
声々が起こった。生蕃は一言もいわずに敵軍をジロリと見やったとき、ライオンがまた同じくジロリとかれを見た。二年の名誉を負うて立つ生蕃!三年の王たるライオン!正にこれ山雨きたらんとして風楼に満つるの概。
犬の方は一向にはかどらなかった、かれらはたがいにうなり合ったが、その声は急に稀薄になった、そうして双方歩み寄ってかぎ合った。多分かれらはこう申しあわしたであろう。
「この腕白どもに扇動されておたがいにうらみもないものが喧嘩したところで実につまらない、シナを見てもわかることだが、英国やアメリカやロシアにしりを押されて南北たがいに戦争している、こんな割りにあわない話はないんだよ」
赤は鹿毛の耳をなめると鹿毛は赤のしっぽをなめた。
犬が妥協したにかかわらず、人間の方は反対に興奮が加わった。
「やあ逃げやがった」と三年がわらった。
「赤が逃げた」と二年がわらった。
「もう一ぺんやろうか」と細井がいった。
「ああやるとも」と手塚がいった、元来生蕃は手塚をすかなかった、手塚は医者の子でなかなか勢力があり智恵と弁才がある、が、生蕃はどうしても親しむ気になれなかった。
ふたたび犬がひきだされた、しゃもじと細井は犬と犬との鼻をつきあてた。「シナの時勢にかんがみておたがいに和睦したのにきさまはなんだ」と鹿毛がいった。
「和睦もへちまもあるものか、きさまはおれの貴重な鼻をガンと打ったね」
「きさまが先に打ったじゃないか」
「いやきさまが先だ」
「さあこい」
「こい」
「ワン」
「ワンワン」
すべて戦争なるものは気をもって勝敗がわかれるのである、兵の多少にあらず武器の利鈍にあらず、士気旺盛なるものは勝ち、後ろさびしいものは負ける、とくに犬の喧嘩をもってしかりとする、犬のたよるところはただ主人にある、声援が強ければ犬が強くなる、ゆえに犬を戦わさんとすればまず主人同士が戦わねばならぬ。
三年と二年! 双方の陣に一道の殺気陰々として相格し相摩した。
「おい」と木俣は巌にいった。
「犬に喧嘩をさせるのか、人間がやるのか」
「両方だ」と巌は重い口調でいった。
「うむ、いいことをいった、わすれるなよ」と木俣はいった。このときおそろしい犬の格闘が始まった。

犬はもう憤怒に熱狂した、いましも赤はその扁平な鼻を地上にたれておおかみのごとき両耳をきっと立てた、かれの醜悪なる面はますます獰猛を加えてその前肢を低くしりを高く、背中にらんらんたる力こぶを隆起してじりじりとつめよる。
鹿毛はその広い胸をぐっとひきしめて耳を後方へぴたりとさか立てた。かれは尋常ならぬ敵と見てまず前足をつっぱり、あと足を低くしてあごを前方につき出した。かれは赤が第一に耳をめがけてくることを知っていた、でかれはもし敵がとんできたら前足で一撃を食わしよろめくところを喉にかみつこうと考えた。四つの目は黄金色に輝いて歯は雪のごとく白く、赤と鹿毛の毛波はきらきらと輝いた。八つの足はたがいに大地にしっかりとくいこみ双方の尾は棒のごとく屹立した。尾は犬の聯隊旗である。
「やっしいやっしい」
人間どもの叫喚は刻一刻に熱した、二つの犬は隙を見あって一合二合三合、四合目にがっきと組んで立ちあがった。このとき木俣の身体がひらりとおどりでて右足高く鹿毛の横腹に飛ぶよと見るまもあらず、巌のこぶしが早く木俣のえりにかかった。
「えいッ」
声とともにしし王の足が宙にひるがえってばったり地上にたおれた。
「いけッ」
二年生はこれに気を得て突進した。
「くるなッ」
巌がこうさけんだ、かれは倒れた敵をおさえつけようともせずだまって見ていた、かれは木俣の寝業をおそれたのである、木俣の十八番は寝業である。
「生意気な」
木俣は立ちあがってたけりじしのごとく巌を襲うた、捕えられては巌は七分の損である、かれは十七歳、これは十五歳、柔道においても段がちがう、だが柔道や剣術と実戦とは別個のことである。喧嘩になれた巌は進みくる木俣を右に透(すか)しざまに片手の目つぶしを食わした。木俣のあっとひるんだ拍子に巌は左へ回って向こうずねをけとばした。
「畜生」
木俣は片ひざをついた、がこのときかれの手は早くもポケットに入った、一挺の角柄(つのえ)の小刀がその手にきらりと輝いた。
「刃物をもって……卑劣なやつ」
巌の憤怒は絶頂に達した、およそ学生の喧嘩は双方木剣をもって戦うことを第一とし、格闘を第二とする、刀刃(とうじん)や銃器をもってすることは下劣であり醜悪であり、学生としてよわいするにたらざることとしている、これ古来学生の武士道すなわち学生道である。
「殺されてもかまわん」と生蕃は決心した。かれの赤銅色の顔の皮膚は緊張してその厚いくちびるは朱のごとく赤くなった。
「さあ、こい」
木俣は再度の失敗にもう気が顛倒(てんとう)してきた。かれはいまここで生蕃を殺さなければふたたび世人に顔向けがならないと思った。かれは波濤(はとう)にたてがみをふるうししのごとくまっしぐらに突進した、小刀は人々の目を射た、敵も味方も恐怖に打たれて何人もとめようともせずに両人の命がけの勝負を見ていた。
生蕃は右にかわし左にかわしてたくみに敵の手をくぐりぬけ、敵の足元のみだれるのを待っていた、だが木俣は心にあせりながらもからだにみだれはなかった、かれは縦横に生蕃を追いつめた。そこは学校の垣根である、歩(ほ)一歩(いっぽ)に詰められた生蕃は後ろを垣にさえぎられた。
「しまった」とかれは思った、だが、逃げることは絶対にきらいである。敵を垣根におびきよせ自分が開放の地位に立つ方が利益だと思った、しかしかれのこの方策はあやまった、敵をして方向を転換させるべく、そこに大きな障害がある、かれの右に三尺ばかりの扁平な石があるのに気がつかなかった。

「畜生!」
ライオンは声とともに生蕃の肩先めがけて飛びこんだ。ひらりと身をかわしたが生蕃は石につまずいてばたりとたおれた。
「あっ!」
二年生は一せいに叫んだ、ライオンは生蕃の上に疾風のごとくおどりあがった。とこのとき非常な迅速(すばや)さをもって垣根の横からライオンの足元に飛びこんだものがある、ライオンはそれにつまずいてたおれた、かれの手には小刀がやはり光っていた。
飛びこんだ学生はライオンにつまずかした上で起きあがってライオンをだきしめた、ライオンはやたらに小刀をふってかれをつこうとした。
「しめたッ」
起きあがった生蕃は背後からライオンののどをしめた。ライオンはぐったりとまいってしまった。
「けがしなかったか、柳君」と生蕃はまっさおな顔をしていった。
「なんでもないよ」
光一は手からしたたる血汐をハンケチでふいていた。
「早いことをするな」
「柳にあんな勇気があったのか」
同級生はあっけに取られてささやきあった。双方ともふたたび戦う気もなくなった、犬はいつのまにか戦いをやめて逃げてしまった。
五分間の後、木俣は回気した。生蕃と光一は水を飲ませて介抱した。
「今日はやられた」と木俣はいった。
「明日もやられるよ」と生蕃がいった。
「いずれね」
「堂々とこいよ」
木俣は去った、三年生が去った、二年生ははじめてときの声をあげた。
「きみのおかげだよ」と生蕃はしみじみと光一にいった。「きみは強いんだね」
「いやぼくは弱いよ」
「そうじゃない、あの場合きみがライオンのまたぐらへ飛びこんでくれなかったら、ぼくはあの小刀で一つきにされるところだったんだ」と生蕃がいった。
「もしぼくがつかれて死んだらきみはどうするつもりだ」と光一は友の顔をのぞくようにしていった。
「君が死んだらか」と生蕃はいった。「おれも死ぬよ」
「そうしてぼくを殺した木俣も生きていられないとすれば……三人だ……三人死ぬことになる、つまらないと思わんか」
「うむ」
生蕃はしばらく考えたが、やがて大きな声でわらいだした。
「おまえおれに喧嘩をよさせようと思ってるんだろう、それだけはいけない」
同級生は一度にわっとわらいだした。
「だが柳」と生蕃はまたいった。「ぼくはきみに頭があがらなくなったね」





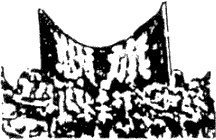


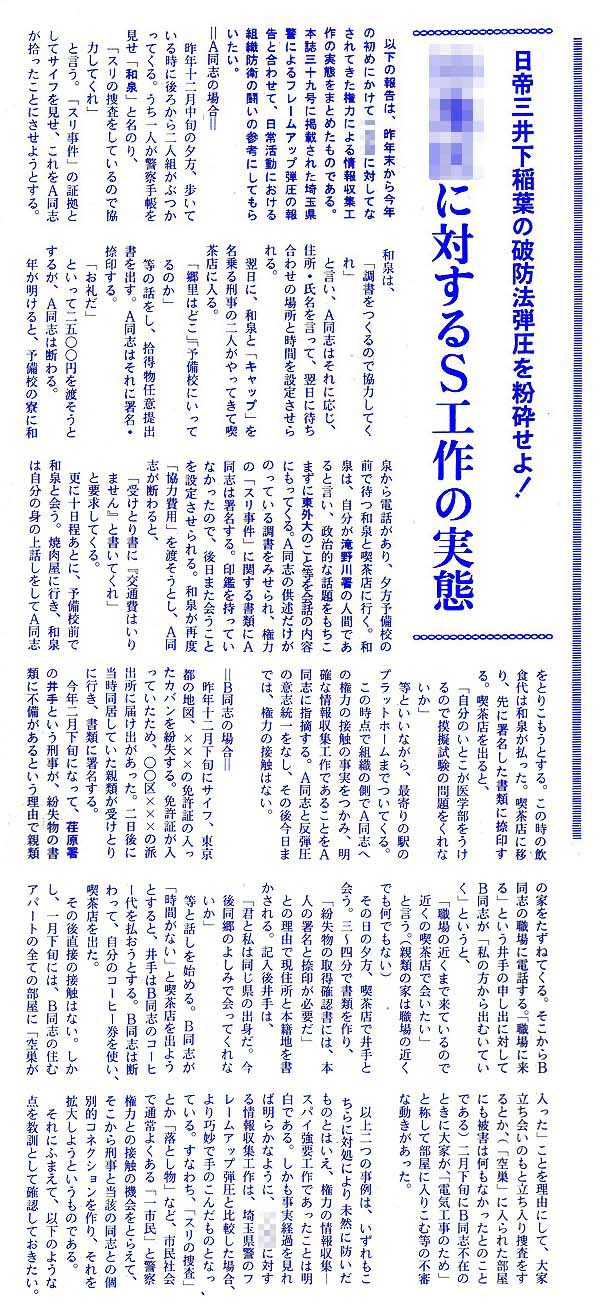





この記事への質問・一言コメントをどうぞ AIコースケと議論しよう!
回答には文字数制限があるため、制限を超えると途中で打ち切られることがあります。