現代ファシズム論序説- 目次 > 懐古的資料室のトップにもどる
1.一九二〇~三〇年代のファシズム認識
イ.ファシズム研究の主体的立場

われわれがファシズムの研究を開始するにあたって、まず最初につきあたるのは、現代におけるファシズム概念の多様化という事態である。すなわちファシズムを「金融資本の暴力的支配形態」(ディミドロフ)一般に解消してしまう傾向や、あるいは反革命一般をその暴力性を唯一の根拠にファシズムでくくってしまわんとする、いわば「何でもファシズム」論が横行し、ファシズムの特性の解明そのものが阻害されている傾向があるのである。
事実、社会科学者の一部には「ファシズム」を社会科学的概念からはずしてしまおうと主張するものもあるし、さらに滑稽な事には、現代のファシスト共自身が、己れをファシストとして認識していないという事実すらある(それはまた、主観的には自らの正義性を信じつつ、歴史のくず箱へと真一文字に突撃しつつあるファシスト共の悲喜劇性を雄弁に物語っているのであるが)。
しかしながら、当然にもわれわれは、「ファシズムなるものはない」とする立場にも、いわんや「何でもファシズム」論にも組みしはしない。
何故ならば(序で述べた如く)かかるファシズム概念の多様化こそ、ほかならぬドイツ共産党の敗北の真の要因、ファシズムに対する無理解、なかんずくファシズムに対する革命運動の敗北への無理解=主体的総括の欠如によってもたらされているからである。
したがってまた、われわれがファシズムを論じる時、その諸特性を述べることよりも、むしろ共産主義運動の敗北という歴史的事実を媒介とした主体的総括をなすものとして、それは語られねばならず、なかんずくコミンテルンのファシズム認識の変遷過程(社会ファシズム論)と、これに一貫して批判を試みんとしたトロッキーのファシズム認識の検討から出発せねばならないのである。
以上、われわれのファシズム研究に対する主体的立場を明らかにした上で、コミンテルンのファシズム認識を、歴史的過程を追いながらみていくことにする。
[Sponsor Ad]
ロ.コミンテルンのファシズム認識
1)コミンテルン第四回大会
一九一七年のロシア革命の勝利は、またたくまに全世界を震憾させ、その炎はドイツを起点に全ヨーロッパに拡がるかの如き様相を呈した。かかるなかで一九一九年三月にコミンテルン創設大会が克ちとられ、その苦難の歩みが開始されることになる。
ところが、前年十一月のキール軍港水兵の蜂起によって開始されたドイツ革命は、周知の如く、ドイツ社会民主党(SPD)の裏切りと、国防軍グレーナーらの反革命策動の中で後退を余儀なくされ、さらにスパルタクス団(後のドイツ共産党=KPD)による時期尚早の武装蜂起が、ローザ・ルクセンブルグ、カール・リープクネヒトらを虐殺される中で鎮圧されるに至り、結局中途で挫折を契したのであった。
第一次世界大戦への突入による、第二インターナショナルの崩壊と、それに次ぐこの社会民主主義者の裏切り行為は、コミンテルンをして、革命連動の最大の阻害物は社民であり、これといかに闘うのかということが、最重要課題であるという認識が広範に共有されることになる。
かかる情勢の中で、一九二二年十月二八日、かつてはイタリア社会党最左派の一人であり、のちにファシストに転向したムッソリーニ率いるファシスト党がローマに進軍し、二日後ムッソリーニ首班の政権が成立した。
このファシズムの歴史への初登場に対し、コミンテルン第四回世界大会(一九一一二年十月~十一月)において、いちはやくファシズムが問題とされた。

たとえば大会における「イタリアの労働者、農民への訴え」は次のように言う。
「ファシストは何よりも地主の手中にある武器であるが……直接闘争では、反動的な学生層や復員将校、単純な盗人どもと並んで勤労者、農業プロレタリアート、農民の一部からなる大隊を擁している。」
しかしながら、ファシストはいかなる綱領や確固とした統一的階級基盤もないのだから、すぐに滅び去るだろう、というのがそこでの最終的な結論となっている。
したがってまた、ファシストの登場を阻止しえなかったこと=「イタリアの同志の責任」は、むしろ「ブルジョアジーの幇助者を党内から追放しなかった点にある」(ジノーヴィエフ)とされたのであった。
これに対して、トロツキー派のカール・ラデックは、まずもって「問題は、ファシズムの勝利が如何にして可能であったか」にあると主張し、より主体的な分析を試みるのであった。
そしてファシズムを、巨大な小ブルの党、民主主義の敵対物と断じ、さらにそれは支配者の政策を体現するものではあるが、広汎な大衆を引き込んでいることへの注意を喚起した。さらにその根拠こそ「共産主義が世界革命の時代の開始以来蒙った最大の敗北」にあるとし、それがファシズムが共産主義運動にかわって何か新しいものをもたらすかの如き幻想の創出を許したと指摘するのである。
ところがラデックは、ここまで来ながらそれ以上主体の切開にはむかわずに、こうした敗北をつくりだしたものこそイタリア社会党=社民であり、要するにこれとの闘争が第一義だと結論づけてしまうのである。
結局のところコミンテルン第四回大会におけるファシズム認識とは、その小ブルを吸収しうる急進性を指摘し、なおかつ部分的にはそれを主体的に切開せんと試みつつも、ファシズムに対するコミュニズムの大衆運動上の一定の敗北としてはとらえることができず、むしろ一切の責任を社民に転嫁してしまうものでしかないのであった。
これこそが萌芽的にあらわれた「ファシスト過小評価」の実態であり、後年の「社会ファシズム」論の原形に他ならない。しかもかかる認識は、実にナチス政権によるドイツ共産党(KPD)の壊滅という大敗北を経た、コミンテルン第七回大会(一九三五年)まで、基本的に受け継がれていくのである。
2)ドイツ十月蜂起の挫折
一九二三年初順に勃発した、ドイツの賠償履行を求めるフランス・ベルギー軍によるルール地方の占領と、この時期ドイツ資本主義をみまった絶望的なインフレーション(同年十二月には1ドル=四兆二千億マルク!)という事態の中で、一切の悪はヴェルサイユにあり、と掲げたナチ(国家社会主義ドイツ労働者党、詳細は2のロを参照せよ)と、「ルール川でポワンカレー(仏)を、シュプレー川でクーノ(独)を打倒せよ」と訴えたKPDは、一挙にその勢力を増大させた。

ところがこのスローガン、したがって戦略をめぐってKPDは深刻な対立を内包することになった。すなわち、このスローガンを掲げつつ、実質的には反仏闘争を展開せんとした中央派(ブランドラー、タールハイマー、およびラデック)に対し、左派(テールマン、およびジノーヴィエフ)が、むしろ主要敵は内部におり、自国ブルジョアジー打倒にむけて内乱を組織すべきであるとし、中央派は「ナショナル・ボリシェヴィズム」であるという、それ自身はまったく正しい批判を展開した(ちなみにトロツキーもこの立場にあった)。
これに対してあくまでも反仏闘争を主軸にせんとした中央派の意図は、ナチに抗して、中間層ないし新中間層を獲得することにあった。
とりわけコミンテルン内において一人抜きんでてファシズムと小ブルの関係を指摘してきたラデックは、この時期ファシズムを、資本主義経済とブルジョア国家の崩壊過程における特徴的現象と規定した。そこでの中間層の分解と没落にファシズムの最も深い根があり、それだけにファシズムは反資本主義的言辞を表して小ブル層をひきつける、危険な反革命勢力として認識しており、これとの対決の必要性を痛感していたのである。
あるいはまた、ラデックと行動を共にしていた、クララ・ツェトキーンは、ファシズムを単なる軍事的テロととらえることに警告を発し、政治的・イデオロギー的把握の必要を説くと共に、「ロシア共産党を除く」各国共産党の認識不足による責任を指摘するという、より主体的な認識をもっていたのであった。
ところが、かかるラデックらがうち出した対ナチ戦術は、たとえばフランス占領軍に抵抗して銃殺に処せられたナチ党員、シュラーゲタの行為を英雄的であると絶賛し、「国民の大義が国家の大義とされるなら、国家の大義は国民の大義となる」とナショナリスティックにぶちあげることによって、「自らの貧困化とドイツの奴隷化に抗して闘うファシズムの小ブル的部分に、KPDこそが真の味方であることを宣伝する」というものであった(いわゆる「シュラーゲタ演説」)。
これに対して左派は、ラデックの如き問題意識は一切待ちあわせなかった。その意味では、実は「ナショナル・ボリシェヴィズム」と「ファシスト過小評価」はメダルの表裏としてあったのである。
それでは両派の対立はいかにして決着がついたのであろうか。
九月二六日、政府はフランスヘの「受動的抵抗」の停止を宣言、これに対するKPD、ナチ等々の反発を予想して全土戒厳令をしいた。
これに対してKPDは、ジノーヴィエフらの強硬な主張の下に、十月武装蜂起へと向かう。しかしこの蜂起は、またしてもSPDのエーベルトと、軍部のゼークトらによって機先を制せられ、他方でブランドラーら中央派が蜂起そのものを時期尚早として、早々にこの指令を撤回したことによって、不発に帰したのであった。
ここに至ってKPDは、左派を中心に再び激しいSPD批判を開始する。
それと同時に、党内においては「ブルジョアジーを支えるもう一方の翼としてのSPD」に対する「過小評価」こそが敗北の要因とされ、一方では中央派が蜂起に消極性をしめしたことが批判の対象となり、ラデックがその責任者として失脚したのをはじめ、中央派は左派に屈していくのであった。
一方でまたファシズム認識においても、十一月にミュンヘンで蜂起したナチが、惨めな敗北を喫することによって(一時的に)政治舞台から姿を消したことも手伝って、その小ブルを吸収しえた力への評価は減少し、ただ大ブルジョアジーのとる独裁形式の一形態としてのみ強調されるに至った。

それよりもむしろ「もう一方の翼」=SPDに対する闘いこそが緊要であるとされ、「社会ファシズム」論への傾斜に拍車がかかっていく。(尚、十月蜂起の挫折とトロツキーの関係については、次節の2を参照せよ)
3)資本主義の相対的安定期の中で
一九二四年のドーズ案に基づくアメリカ資本のドイツヘの導入は、瀕死の状態にあったドイツ資本主義を何とか復活せしめ、これを契機としつつ、資本主義各国経済は一定の小康をとりもどすことになる。いわゆる資本主義の相対的安定期の到来である。

この時期、コミンテルンは「ファシスト過小評価」そしてその裏返しとしての「社会ファシズム」論への傾斜を、いよいよ決定的なものとしつつあった。
何故ならば、相対的安定期の到来に伴なって、絶望的経済状態につきおとされていた小ブルの多くもまた、その経済生活の安定をとりもどしていたため、小ブルに依拠したファシズム運動はすでに歴史の遺物となったかの如く認識されたからである。
無論、よくよく考えてみるならば、相対的安定期の崩壊が訪れるやいなや、かかる運動が再興されるのは理の当然であり、たとえナチ等々が現象的には姿を消したにせよ、それを歴史の遺物などと認識することは当然排されて然るべきであった筈だが、結局ファシズムの問題を主体的にとらえ返すことを知らないコミンテルンは、一九二三年に至る貴重な経験を無造作にくず箱へと投げ捨ててしまったのであった。
こうした傾向は、必然的に現存するファシズム、すなわち「イタリアにおけるファシスト独裁」に対しても、徹底した「過小評価」、戦略的表現としては待機的な楽観主義をとることになる。すなわち、「イタリアのファシスト独裁は、矛盾に充ちた政治体制であるが故に、もがけばもがく程に矛盾を拡大し、やがて崩壊するだろう」という主張がそれである。
これと一対のものとして「しかし社会民主主義は、反革命的役割において、ファシズムよりもはるかに危険である」(クーシネン)という主張がくり返され、いよいよ「社会ファシズム」論の「完成」へとむかった。
そしてそれは、一九二八年七月~九月にかけておこなわれたコミンテルン第六回大会を経て、完全に定式化されるに至るのである。相対的安定期の末期に行なわれたこの大会は、はからずもいわば「ファシズム重視派」にとって最後の登場の場となった。

その内の一人、ブハーリンは次のように述べている。
「第一に、社会民主主義は一片の疑いもなく社会ファシズム的傾向がある。第二にこれは傾向であってなんら完結された過程ではない。いや社会民主主義とファシズムをごたまぜにするのはばかげたことだ」そして「われわれがSPD系の労働者に働きかける可能性はあるが、ファシズムに関しては断じてそのようなことはない」として、社民とファシズムの相違を強調するのである。
これに対し(ブハーリンの提起を無視したかの如く)テールマンはいう。
「相対的な資本主義的安定の内的・外的諸矛盾が、社会民主主義の本質と発展にも反映されているのは興味深いことである。改良主義の社会ファシズムヘの発展は、さまざまの国々でさまざまな実例により説明できる現象である。」
ここにわれわれは、大会そのものでは噴出しなかったコミンテルンの内的対立をみてとることができる。すなわちそれはKPD内の対立に等しく、ファシズムの認識をめぐって、そしてこれと一対のものとしてある社民の認識をめぐっての対立なのであった。
ブハーリンはその後の彼の論文の中で「ファシズムは小市民大衆を自らの側に引きよせ一部の小ブルジョア、さらに時として一部の労働者階級をも買収する……ブルジョアジーが大衆なしには支配しえない国、すなわち内乱の要素が熟しつつある国では、ブルジョアジーはファシズムの方法に活路を求める」とファシズムを分析してみせる。
しかし前出のラデックに等しく、ブハーリンもまたかかるファシズムのエネルギーの根拠がどこにあるのか、これ以上認識を深めることができず、結局「それは社民の裏切りのためなのだ」とするスターリン、KPD左派らが一貫して主張する立場に屈してしまう。
要するに総じてコミンテルン内において、より深くファシズムを認識した部分は、路線的なジグザグ性を内包しており、「社民をたたけ」という一貫性の前に何らなす術をもたなかったのである。そしてそこにこそ「ファシスト過小評価」の本質があった。
4)ドイツ共産党対ナチ
一九二九年四月、突如としてブハーリンが失脚せられ、これとともにKPD中央派に対する「右翼偏向」批判が開始される(トロツキー、ラデックは二七年に党を追放された)。これとともに前年から激化していた労働運動が五月一日~五日市街戦へと発展し、またしてもSPDと結託したゼークト軍部との激突が起こった。
コミンテルンは、ブルジョアジーがこれをひとつの「結節点」として、もはや「社会ファシスト独裁」すなわち「機関銃によって補完され、民主主義の名において試みられる労働者欺瞞」に活路を求めだしているとし、社会民主主義の「社会ファシスト」としての本質を暴露することによって、SPDの影響下にある労働者をKPDの側に獲得することを緊急の任務として提起した。
とりわけ「社会民主主義=『社会ファシズム』、とくにその左派の本質を徹底的に暴露し、労働者大衆をその影響下からひき離さねばならない」(マヌィーリスキー)、すなわちSPD左派との決裂、闘争が全面的に主張されるにいたり、これをもって「社会ファシズム」論は完全に定式化された。それがまた反対派に対する「右翼偏向」批判と密接のものとしてあったのは言うまでもない。
もっともこの「社会ファシズム」論は、なお多少のジグザグを経ることになる。
一九二九年八月、ドーズ案に次ぐヤング案がドイツに押しつけられ、さらに同年末からはじまった世界恐慌の波がドイツにも及ぶことによって、階級情勢は再び激動の坩堝と化した。

この激動期に、ドイツ国民のナショナリスティックな感情を見事に吸収しつつ、ナチが大進撃を開始する。このダイナミズムに充ちたナチの進撃は、コミンテルン、とりわけKPDをして再びファシズムを無視しえないものとした。
たとえばKPDのゲルバーは「われわれが社会ファシズムにすっかり集中してファシズムの波の発展をややなおざりにし、特にヤング案反対闘争で一定の立遅れがあったというわが党の主体的誤り」がナチの躍進を許したという。しかし彼はまた、ファシストのデマゴギーはすでに限界にきているので、これまでの闘いを押し進めれば両翼のファシズムに有効に対抗しうる(二正面闘争論)と、相変わらず楽観論に終始するのであった。
しかし、ゲルバーの予想に反してナチは躍進を続け、もはや楽観が許されなくなる中で、八月二十四日、KPDはナチを当面する最も強力で危険な敵と認識しつつ、「ドイツ人民の国民的および社会的解放のための綱領宣言」をうち出す。(事実上の「社会ファシズム」論の後退)
その主旨は、ナチの主張はすべてデマゴギーであり「プロレタリアート独裁の鉄槌のみが、ヤング案と国民的抑圧の鎖を打ち砕くことができる。労働者階級の社会革命のみがドイツの国民的問題を解決することができる。」というもので、さらに綱領としては「掠奪的なヴェルサイユ条約、ヤング案の破棄、国際的債務および賠償の帳消し、工場経営、銀行、大商業、土地の無償没収」等々がかかげられた。
かかる中で九月に選挙が行なわれ、KPD、ナチ共に大躍進をなしとげた。とりわけKPDが主にSPDの票を奪ったのに対し、ナチはSPDの票のみならす、他の保守党ないし浮動票の大半を吸収することによってその議席を一挙に12から108に伸ばし、一躍SPDに次ぐ議会第2党へとのしあがったのである。
ここに至っていよいよKPDはナチヘの危機感を深め、SPD系労働者、および中間層をもまき込んだ反ファシズム闘争同盟を結成、「人民革命」路線をうち出した。
だが翌年(一九三一年)に至るや、この「人民革命」路線は忽然と姿を消し、三~四月のコミンテルンの声明ではかつての「二正面闘争論」ぐらいまで後戻りした路線が提起された。
恐らくは、「ファシスト過小評価」に対する警鐘を乱打し、「社共による反ナチ統一戦線の結成」を必死に叫んでいたトロツキーヘの対処が働いたためであろうが、このようにしてKPDにとっては半ば強制的に押しつけられた「社会ファシズム」論は、さらにKPDが当初は反対していたファシスト連合によるプロイセン政府(SPD系)弾劾国民投票へのこれもコミンテルンの示唆による参加(KPDとナチによる反SPD統一戦線の実現!)と、その不発によるSPD内KPDシンパの一挙的喪失という事態を経、この大失態を正当化する強弁の中で「社民に主要打撃を!」という「社会ファシズム」論 の大合唱へと高まっていくのである。
その後もKPD内から度々わきおこってくるSPDとの反ナチ統一戦線への動きは、常にコミンテルンによって「修正」され、一方ナチに対しては「ファシストは政権をとればすぐに瓦壊し、国家社会主義の高揚は共産党が継承することになろう」(テールマン)という、あたかもファシストの政権奪取を容認するかのごとき敗北主義的な傾向さえ生まれたのであった。

かくしてKPDは、待機主義と敗北主義という死装束を身にまとい、なおかつ楽観的に「社民をたたけ!」と叫びながら地獄への進撃を続け、ナチ政権下の翌年二月二八日、ナチの謀略による国会議事堂放火事件を機に(ついにナチに一太刀もあびせることなく)一挙に潰滅させられてしまったのであった。
5)敗北の後に

「社会ファシズム」論に忠実に従ったKPDがナチに潰滅せられ、一夜の内に四千名におよぶ革命家が逮捕され、虐殺あるいは強制収容所に送られるという悲惨な大敗北を蒙った後も、未だ暫くコミンテルンは「社会ファシズム」論にしがみついていた。
たとえば同年末の第十三回執行委員会総会において、スターリンはファシズムに関して「金融資本の最も反動的、排外主義的かつ帝国主義的な分子の公然たるテロ独裁」として、後年ディミドロフが主要敵として定式化する、その反革命性の強調が登場しつつも、なお「敗戦国ドイツにおいて、ナショナリズム、排外主義が巨大な力となったこと、および一九一八年のドイツ革命の挫折以来、SPDが一貫してブルジョアジーを助けてきたこと」を挙げるのみで、大敗北の主体的総括は一切なされなかった。
しかしながら、政権を掌握したナチによってSPDもまた解散させられ、最早「社民主要打撃」論が全くの空念仏にすぎないことが誰の目にも明らかとなるなかで、コミンテルンは漸く路線転換をはかる。それがかのコミンテルン第七回大会(一九三五年七~九月)においてディミドロフによって提起された「人民戦線」戦術に他ならない。
しかしそこにおけるファシズム認識も、かつてスターリンが述べた「金融資本の…公然たるテロ独裁」というものであり、結局ファシズムに対する真の認識=敗北の主体的総括は一切なされなかった。
したがって「人民戦線」戦術もまた(主体的総括の不在故に)「社民主要打撃」論の単なる裏返しとして提起されたにすぎず、共産主義運動はこれ以後より一層の敗北(ヨーロッパ革命運動の総破産)へとむかうのである。
行論の関係上、「人民戦線」への批判は他稿へ譲らざるをえないが、これに対する批判もまた「社民主要打撃」論の陥穽のみならず、一九二〇~三〇年代の国際共産主義運動の敗北の主体的総括をもとにしてなされねばならぬことを指摘して先にすすむこととしたい。
6)コミンテルンの限界
さて長きにわたって見てきた如く、ファシズム認識におけるコミンテルンの限界が、要するにファシズムが何であるかさっばり分からなかったこと、あるいは問題を主体的に設定せぬが故に、分かろうとしなかったことにあることは最早明白であろう。
あえて再度ここで整理するならば、コミンテルンはファシズムを「社会ファシズム」と共にブルジョアジーが利用する2つの支配形態の内の一つとして定式化はしたものの、よもやそれが人民の支持を集め、急成長しうるなどとは思ってみることもできず、さらに万が一「社民の裏切りのため」にそれが成長し、政権獲得に至るにせよ、すぐにも瓦壊するものとしてしかとらえられなかったのである。
したがってコミンテルンのこの限界は、単にファシストの暴力性、反革命性に対する「過小評価」としてあったのではなく、むしろ人民の支持を一時にせよ集中しうるファシストのエネルギーに対する「過小評価」としてこそあったのであり、翻えせばファシストとの競合にせり敗ける己れの陥穽への無自覚、まさにその意味での主体的総括の欠如にあるのであった。
以上を踏まえた上で、次にわれわれは、かかるコミンテルンに対して己れを左翼反対派として位置付け、コミンテルンの「ファシスト過小評価」に警鐘を乱打し続けたトロツキーのファシズム認識についてみていこう。
果たしてトロツキーは、真にファシズムを看破しえたのであろうか?
[Sponsor Ad]
ハ.トロツキーのファシズム認識
1)トロツキーとスターリン
コミンテルンのファシズム認識=全くの無理解に対する一貫した批判として展開されたトロツキーのファシズム論は、一方でまたコミンテルン内における権力闘争、とりわけトロツキー対スターリンとしてなされた論争の不可欠の一環をなしていることは周知の事実である。
ここで若干触れるならば、永続革命対一国社会主義を軸とし、ロシアにおける経済建設をめぐるプレオブラジェンスキー対ブハーリン間のいわゆるプレ=ブハ論争等々として展開されたこのたたかいは、プレオブラジェンスキーの若干の混乱(社会主義的原始蓄積論等)を考慮にいれたにせよ、なおトロツキー派が理論的にいえば原則的であり、正しいことをそれとして主張しながらも、現実的にはほぼ全面的にスターリン派に敗北していくという過程を経るのであった。
換言するならば、トロツキーはいわば論理的整合性をもって「粗暴なグルジア人」=スターリンに対抗しえたのみであり、生きた政治の問題、すなわち己れの主張にいかに大衆を動員していくのかという点に関しては、むしろスターリンの方か優れていたと言いうるのである。
したがって、われわれがトロツキーのファシズム認識を分析するにあたっても、かかるトロツキーの本質的な限界を踏まえておく必要があるだろう。
2)「十月の教訓」
前節の(2)「ドイツ十月蜂起の挫折」の中で、われわれはファシズムに対してより深い認識をしめしたトロツキー派のラデックが「ナショナル・ボリシェヴィズム」へと陥り、やがて失脚される過程をみてきた。
それではこの「十月」の事態をトロツキーその人はいかにとらえたのか。
「十月」を前にしたトロツキーは、党内においてももっとも強硬に武装蜂起を主張しており、その期日を歴史的な日である十月七日に合わせるよう提起さえしていた。したがって当然にもラデックらには批判的であり、その意味ではKPD左派、ジノーヴィエフらと立場を等しくしていたのである。
ところがトロッキーの追い落しを狙うジノーヴィエフは、十月の敗北の後、ラデック=トロツキーというシューマをデッチ上げ、串刺し的な批判を展開する。(当時のロシア共産党内における権力闘争は、スターリン、ジノーヴィエフ、カメーネフらの「トロイカ」ブロックにブハーリンを加えた政治局内絶対的多数派対トロツキーとして進行していた)
こうした中でトロツキーは、ジノーヴィエフヘの反論の意をも含めて、敗北の総括を論文「十月の教訓」(一九二四年)によって提起する。
そこにおいてトロツキーは、ロシア十月革命の過程をこと細かに分析してみせることによって、暗にこれとドイツの十月をアナロジーさせつつ、ロシア十月革命が祖国敗北主義の下に「一日先んじても早すぎ、一日ためらっても遅すぎる」その日を逸することなく武装蜂起に成功したのに対し、ドイツにおいてはKPD中央が革命的情勢の到来を見ぬくことができず、蜂起の準備を怠ったが故に敗北を喫したと結論する。
とりわけKPDのナショナリズムヘの屈服に対しては、「現実の革命的条件のもとで、民主主義を支持する立場をとることは、その理論的帰結にまでつきつめれば『未成熟』を理由に社会主義に反対することであり、政治的にはプロレタリアートの立場から小ブルジョアジーのそれに移行することに他ならない。それは国民革命の立場への移行に他ならない」と鋭く指摘し、武装蜂起に対する日和見主義が、祖国擁護主義と密接に絡みあっていることを暴露するのである。
さらにまたトロツキーは、ロシア革命の過程において、他ならぬジノーヴィエフ、カメーネフらがたびたび祖国擁護主義に陥って武装蜂起に反対したことを随所で指摘し、要するに「武装蜂起などできるわけがないと主張していた日和見主義者は君達だったではないか!」と激昂しつつ、さらに返す刀で「いずれにしてもわれわれは、ドイツの十月の挫折をもたらした政策を正当化するためになされている傾向的な結論(十月の「退却」は正しかったとするKPD中央派の主張のこと―筆者注)を絶対に拒否しなければならない」と、ラデックらをも一刀両断してしまい、かかる所業をもって、いわば自らの正当性を全面に押しだしているのである。
それではトロツキーはこの「十月の教訓」の中で何か間違ったことを言っているだろうか、否、断じて否である。トロツキーは全くもって正しいことを原則的かつ徹底的に語っている。だかしかしそうであるか故に、われわれは声を大にしてこう言わねばならない。――確かにトロツキーはすぐれている。すなわちその陥穽を誰にも気づかせぬ程にすぐれているのだ、と。
何故なら、確かに「十月の教訓」そのものは一字一句たりとて誤っているとは言えないが、しかしそもそもロシアの十月と、ドイツの十月を同一線的にアナロジーさせるやり方そのものに無理があることをわれわれは知っているからだ。
すなわちロシア十月に至る過程においては日露戦争でのロシアの敗北に次ぐ第一次大戦への強引な参戦によって、多くの労働者、農民、なかんずく兵士の間に反戦意識が強く存在していたのに対し、ドイツにおいては、フランスのルール占領と激化するインフレーションの中で、一切の悪はヴェルサイユにある、そしてこの「悲劇的な国民的隷属」を打ち破ることにこそ自らの未来があるとする国民意識が高揚していたのであり、何よりもかかる意識の最も中心的な担い手である没落せる中間層(とりわけロシアにはなかった新中間層-なおこれ以後中間層という指摘はかかる新中間層を含むものとして理解されたい)を吸収し、進撃を続けるナチらファシストの存在があったのである。
そしてまた、かかる情勢の中で、たたかわんとすることにこそ、ラデックらの苦悩はあったのであり、ナショナリズムヘの屈服も、ここから派生したのであった。
ところがトロッキーは、そもそもファシズムのファの字もないロシアの十月に問題を横すべりさせ、いわば自分の土俵の上で、ラデックらを「トロイカ」と共に断罪してしまう。これではいくら「正しい」批判をなしえたにせよ、それにかわる方向性=現実に武装蜂起を遂行するための方策は、何らうちだされていないといわざるをえない。
われわれはここから次のことを結論できる。すなわちドイツの「十月」におけるトロッキ―もまた、何故の敗北であったのか、とりわけ何故ラデックらがナショナリズムヘと走ったのか、何ら主体的に総括することを知らず、もっばら原則論に終始するのみであったということ、そうであるが故にトロツキーもまたファシズムの分析に向かいえず、徹底した「ファシスト過小評価」のとりことなっていたということである。まさに「十月の教訓」はその紋章として、われわれの前に横たわっているのだ。
3)「社会ファシズム」論批判
原則をそれとしてしか語らないトロツキーの限界性と、それ故の「ファシスト過小評価」をこれまでわれわれは明らかにしてきた。だが一九三〇年代、ナチが再度の進撃を開始したこの時期のトロツキーはどうであったのか、コミンテルンの「ファシスト過小評価」に警鐘を乱打していたものこそトロツキーではなかったのか。
周知の如くトロツキーは、今日「社会ファシズム論批判」として一括されている数々の論文の中で、さながら機関銃の如く、敗北へと邁進するコミンテルン―KPDに批判をあびせかけた。そしてそれにもかかわらず「社民をたたけ!」と繰返していたコミンテルン―KPDが、あたかもトロツキーの「予言」に合致するかの如く、「血の海」に沈められたことは前節でみた通りである。
それではトロツキーのこの時期のコミンテルン批判は「ファシスト過小評価」の本質をついていたのだろうか。多少引用の過多に陥るやもしれぬが、ともあれトロツキーその人の言葉に耳を傾けてみよう。
「今日ブルジョア議会政体の主な代表となっている社会民主主義は、労働者に依存している。一方ファシズムの方は、小ブルジョアジーに拠りどころを求めている・・・社会民主主義の主要な活動の場は議会にある。ファシズムの体制は議会主義の破壊に基礎をおいている。しかし独占ブルジョアジーにとっては、議会主義政体もファシズム政体も、自らの支配のための異った道具としか見えない。」
「議会主義によって隠蔽されたブルジョア独裁の『正常な』軍事、警察的手段が、社会の平衡を保つ上で不十分になったときに、ファシズムの時代が訪れる。ブルジョアジーはファシズムという出先機関を使って、激怒している小ブルジョアジー大衆、最下級層の一部、道徳的退廃に陥ったルンペン・プロレタリアートなどの、金融資本自身が絶望と憤怒の中に落しこんでいる無数の人間を動員する」
「ファシズムの勝利は、金融資本による直接的かつ瞬間的な、あらゆる統括、指導、教育などの組織や機関の独占にゆきつく」
「まず労働者組織を破壊し、プロレタリアートを無気力の中に落しこみ、かくして、大衆の深奥へ浸透しながら、プロレタリアートの行いうる独自の組織化を妨げることを目的とした。組織体制を作り上げること・・・。そこにこそファシズム体制の本質が存在する。」(『次は何か』一九三二年)
要するにトロツキーは、ファシズムを社民とともに大ブルジョアジーのとりうる支配形態の一つであるとするコミンテルンの大ワクにしたがいつつ、しかし社民が労働者に依拠し、議会主義の上に成り立っているのに対し、ファシズムは小ブルに依拠し、反議会主義によって成り立つという差異を有していること、したがってブルジョアジーにとって議会主義に限界がきた時に、社民にとってかえられるものとしてあることを指摘しているのである。
そしてまたかかるファシズムの急増の要因は、ブルジョアジーが社民からファシズムヘの重点移行への動揺を開始したことと同時に、「深刻な社会的危機が小ブルジョア大衆を、その平衡状態からはじき出している事実と、まさに現在の状勢において、人民大衆にとって、革命的案内者として現われねばならない革命党の不在、という事実」にあり、それ故「反革命的絶望がプロレタリアートの多くの階層までも、小ブルジョアジーに引きつけてしまうほど強く、小ブルジョアジーを包みこんでしまっている」(「共産主義インターナシーナルの転換とドイツの情勢」一九三〇年)ことにあるとする。
ところが、トロツキーによれば、コミンテルン―KPDは、社民とファシズムを「社会ファシズム」の名の下に同列に扱うことによって、社民よりもファシズムの方がドイツの真の危機となっていることを見ぬけず、「社会民主主義にとって問題は、プロレタリア革命から資本主義を防衛することよりも、むしろファシズムからブルジョア議会主義的体制を守ることにある」にもかかわらず、この対立を利用しようとせず、さらには社民の反革命性をより重視することによって「労働者階級に、反ファシズム闘争という任務は二次的任務であり、別に早急なことでもない。また、それは、自然に達成されてしまうだろう、と信じ込ませねばならない」ところまで堕落している。
しかしながら「プロレタリアートが、犯罪的な受動性によって、ファシストが権力を握るのをなすがままにしておくならば、ファシストの権力掌握の後に、その同じプロレタリアートが、急激にその受動性から立ちあがり『すべてを掃蕩してしまう』などということは全く望む余地がない」(以上「次は何か)より)
いうまでもなく、これがトロツキーによる「社会ファシズム」論批判の骨子であるが、再度整理するなら、コミンテルンはブルジョアジーが社民を捨てファシズムを選択しつつあることを「過小評価」しており、この立場を捨てて、社民をまき込んだ反ファシズム統一戦線を結成すべきだとするのがトロツキーの主張の全てなのである。
この主張は確かに一面においては全く正しい。すなわちコミンテルンのファシズムに対する無防備を批判する点においてはである。しかしながらわれわれは、トロツキーはそれ以上一歩も出ていないことを見てとらねばならない。何故ならば情勢認識においてのみトロツキーはコミンテルンよりもすぐれていたのであって、社民ないしファシストに関する規定においては何らコミンテルンのワクを出ていないし、またファシストの現象論的認識においてもブハーリン等のそれを決して上まわっているとはいいがたく、さらに主体的切開という点に関していえば、むしろラデックやクララ・ツェトキーンの方がすぐれていたといえるからだ。
要するにトロツキーは、ファシズムの進撃の要因を分析するには至らず、むしろその根拠をKPDの無能力さに還元してしまい、そこから「ファシズムがその魅力を保つことかできるのは、プロレタリア勢力が分散し…ドイツ人民を勝利に導けなくなっているときだけ」「労働者階級の革命的統一戦線は、すでにそれ自体として、ファシズムに対する、致命的な政治的打撃となる」(『生産の労働者管理について』一九三一年)と、あまりにも楽観的に結論してしまうのである。
したがって再度ここでおさえるならば、トロツキーの展開したコミンテルン批判=「ファシスト過小評価」批判とは、単にブルジョアジーが社民からファシズムにのりうつったことを指摘しているにすぎないといっても過言ではなく、ファシストが何故大衆的な基盤を確立しえたのか、したがって何故共産主義運動が敗北したのかという点に関する分析はスッポリ欠落していたのであり、その意味ではまさにトロツキー自身もまた「ファシスト過小評価」の陥穽の中にあったことをわれわれは、確認せねばならないのだ。
4)トロツキーの限界
それでは、コミンテルンに対してファシズムヘの警戒を促していたトロツキーは、何故かかる陥穽から逃れることかできなかったのであろうか。
一言で言うならばそれは、トロツキーが一貫して、言わば「スターリニスト裏切り史観」とでも言うべきものに陥っていたからに他ならない。
というのは、トロツキーは、レーニン死後の第三インターナショナル内における権力闘争を通じて、スターリン派を筆頭に、常に様々な部分のマルクス主義の原則の歪曲に抗してたたかい続けねばならなかった。あたかも、刈りとっても刈りとってもニョキニョキとはえてくる雑草の如きエピゴーネンとの、この孤立無援のたたかいは、トロツキーをして、一切の敗北の要因をマルクス主義の原則の逸脱や、「スターリニスト官僚の裏切り」に還元してしまう傾向をいわば必然化させ、それ故、ファシストに対する主体的分析に至ることができなかった。
それはまた、あたかもエンゲルス死後のSPD内において、修正主義を掲げたベルンシュタインに対抗し、マルクス主義を擁護せんとしたカウツキーが、修正主義と共に、マルクスの予期しえなかった金融資本主義段階への移行に関するベルンシュタインの提起をも刈り取ってしまった事実を想起させるがごとくである。
すなわち、あくまでも原則をそれとして貫かんとしたトロツキーは、たとえばラデックらのファシズム認識の芽をも、彼らのナショナリズムヘの屈服と共に摘みとってしまい、結局終始一貫してファシストそのものにあの鋭い眼光をむけることはなかったのである。まさにここにこそトロツキーの陥穽はあったのだ。
したがってまたわれわれは、次のように言わねばならない。
すなわち、マルクス主義の原則をそれとして守りぬかんとしたがゆえにトロツキ-の混乱はあり、その陥穽を誰にも気づかせない程にすぐれていたトロツキーの革命的情念を継承せんとする主体的苦闘は、逆にその意味においてこそ、トロツキーヘの教条であっては断じてならず、むしろ総体としてのトロツキーの敗北をこそ真に主体的切開の対象として措定せねばならないということである。
まさにかかる観点からわれわれは、いずれにせよ、未だあまりにも浅薄なわれわれのトロツキー研究を堀りさげていく必要があるだろうが、それは他稿に譲るとして、ここでは問題提起にとどめ、先をいそぐことにしよう。
[Sponsor Ad]
ニ.現代ファシズム論の問題点
われわれは本章の(イ)「ファシズム研究の主体的立場」において、これまでのファシズム論が一九二〇~三〇年代の敗北に対する主体的総括としてなされてこなかったが故に不毛であったことを指摘してきた。
そうであるか故にわれわれは、コミンテルンのファシズム認識の変遷過程から出発し、これに一貫して批判をなさんとしてきたトロツキーのファシズム認識を追認してきたわけだが、その結果われわれは、次の如き過程的結論を手にするに至った。
すなわち(既にトロツキー批判においても触れた如く)これまでの一九二〇~三〇年代の敗北に対する主体的総括の欠除とは、まさにトロツキーヘの教条=「スターリニスト裏切り史観」によってもたらされているということである。
たとえば、日本トロツキズムの草分け、対島忠行は『社会ファシズム論批判』(現代思潮社版)の解説の中で次の如く語っている。
「社共の反ナチ統一戦線を通ずる『分進合撃』と『攻勢防御』、このトロツキーの主張が実践に移されていたらどうであろうか、ナチズムの勝利を防衛し、のみならず―かつてマルクス・エングルスは『恐慌は政治的変革における最も強力な損秤の一つ』であるとみたのであるが、それが実現されていたのではないか」
要するにここでもその主旨は「スターリニストが裏切らなければ勝てたのではないか」ということであり、翻していえば、敗北が敗北として認識されていないことの自己暴露に他ならないのである。そしてこれこそまさに対島忠行に限らず、わが革命的左翼の大半を占める通説となっているのではあるまいか。
しかしながら(残念なことに)真実の歴史はそのようには語っていない。むしろこれまで見てきた如く、一九二〇~三〇年代の敗北の要因とは、「スターリニストの裏切り」のみならず、トロツキーをも合めて、ファシストを真に認識しえなかったことにこそ存在するのである。
そうであるが放にこそわれわれは、トロツキーの教条に陥り、いわば「反スタめがね」によって目先を曇らされることを断固として拒否し、あくまでも国際共産主義運動の敗北を真に己れのものとしてうけとめ、主体的な総括をなすものとしてファシズム論を語らねばならないことを、執拗なまでに強調しておく必要があるのだ。
何故ならば、敗北の要因をスターリンの裏切りに還元してしまうやり方は、そもそもファシズムの登場を社民の責任へと還元し、何ら主体を省みることのなかったスターリニストと、それ故の「社民主要打撃」論の域を一歩もでないことを意味するのであり、結局そのいきつく先はスターリン主義の逆立ちとしてまさに裏返しの「社会ファシズム」論、すなわち一方の翼を「ファシスト主要打撃」論とし、他方の翼を「スターリニスト主要打撃」論とするそれに転落する以外ないからである。
われわれは、このような立場では何ら帝国主義そのものに打撃を与えることができないばかりか、むしろたたかいの混乱を増大させるにすぎないのだということを、肝に銘じておく必要がある。
そしてそれはまた、われわれのスターリン主義に対する問題の立て方にも通ずるものであることにここで留意を促しておきたい。
すなわちわれわれは、昨年、わが同盟戦旗・共産同の戦略的スローガンの豊富化、なかんずく「革命運動のスターリン主義的歪曲を克服せよ!」という提起をなすにあたって、「スターリン主義克服論文」を提起し、その中で革共同に象徴されるスターリン主義の外在的対象化に批判を加え、単にスターリンに対する指弾にとどまることなく(トロツキーのスターリンに対する敗北の必然性をも踏まええつつ)あくまでも革命的実践の中で内在的に克服する対象としてスターリン主義を措定すべく主張してきた。
その意味では、一九二〇~三〇年代総括もまた、スターリン主義による国際共産主義運動の混迷を、階級闘争の前進の中で克服することによってのみなされなければならないことは、いわば前提的な命題である。
したがってその際、一九二〇~三〇年代の敗北が、スターリン主義とそれを乗り超えることができなかったトロツキーによる敗北としてある以上、これを克服する視点もまたスターリン主義の陥穽をいかに克服していくのかという立場に立脚したものでなければならないことは言をまたない。
すなわちスターリン主義=近代ブルジョア主義の未克服の政治的表現ということを踏まえた上で、思想的にファシズムヘの敗北をとらえかえさねばならないということである。
以上、本章を通じてわれわれは、漸々にしてわれわれ自身のファシズム研究に対する主体的立場と、それに基く視座を確立しえたものと考える。これをバネにファシズムヘメスを入れるのが次章の課題である。




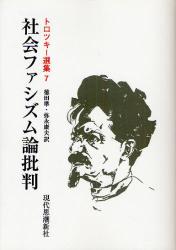

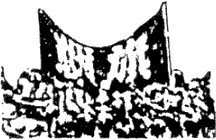











この記事への質問・一言コメントをどうぞ AIコースケと議論しよう!
回答には文字数制限があるため、制限を超えると途中で打ち切られることがあります。