九
監督は周章(あわ)て出した。
漁期の過ぎてゆくその毎年の割に比べて、蟹の高はハッキリ減っていた。他の船の様子をきいてみても、昨年よりはもっと成績がいいらしかった。二千函(ばこ)は遅れている。――監督は、これではもう今までのように「お釈迦様」のようにしていたって駄目だ、と思った。
本船は移動することにした。監督は絶えず無線電信を盗みきかせ、他の船の網でもかまわずドンドン上げさせた。二十浬(かいり)ほど南下して、最初に上げた渋網には、蟹がモリモリと網の目に足をひっかけて、かかっていた。たしかに××丸のものだった。
「君のお陰だ」と、彼は監督らしくなく、局長の肩をたたいた。
網を上げているところを見付けられて、発動機が放々の態(てい)で逃げてくることもあった。他船の網を手当り次第に上げるようになって、仕事が尻上りに忙しくなった。
仕事を少しでも怠けたと見るときには大焼きを入れる。
組をなして怠けたものにはカムサツカ体操をさせる。
罰として賃銀棒引き、函館へ帰ったら、警察に引き渡す。
いやしくも監督に対し、少しの反抗を示すときは銃殺されるものと思うべし。
浅川監督
雑夫長
この大きなビラが工場の降り口に貼られた。監督は弾をつめッ放しにしたピストルを始終持っていた。飛んでもない時に、皆の仕事をしている頭の上で、鴎(かもめ)や船の何処(どこ)かに見当をつけて、「示威運動」のように打った。ギョッとする漁夫を見て、ニヤニヤ笑った。それは全く何かの拍子に「本当」に打ち殺されそうな不気味な感じを皆にひらめかした。
 水夫、火夫も完全に動員された。勝手に使いまわされた。船長はそれに対して一言も云えなかった。船長は「看板」になってさえいれば、それで立派な一役だった。前にあったことだった――領海内に入って漁をするために、船を入れるように船長が強要された。船長は船長としての公の立場から、それを犯すことは出来ないと頑張った。
水夫、火夫も完全に動員された。勝手に使いまわされた。船長はそれに対して一言も云えなかった。船長は「看板」になってさえいれば、それで立派な一役だった。前にあったことだった――領海内に入って漁をするために、船を入れるように船長が強要された。船長は船長としての公の立場から、それを犯すことは出来ないと頑張った。
「勝手にしやがれ!」「頼まないや!」と云って、監督等が自分達で、船を領海内に転錨(てんびょう)さしてしまった。ところが、それが露国の監視船に見付けられて、追跡された。そして訊問(じんもん)になり、自分がしどろもどろになると、「卑怯」にも退却してしまった。「そういう一切のことは、船としては勿論(もちろん)船長がお答えすべきですから……」無理矢理に押しつけてしまった。全く、この看板は、だから必要だった。それだけでよかった。
そのことがあってから、船長は船を函館に帰そうと何辺も思った。が、それをそうさせない力が――資本家の力が、やっぱり船長をつかんでいた。
「この船全体が会社のものなんだ、分ったか!」ウァハハハハハと、口を三角にゆがめて、背のびするように、無遠慮に大きく笑った。
――「糞壺」に帰ってくると、吃(ども)りの漁夫は仰向けにでんぐり返った。残念で、残念で、たまらなかった。漁夫達は、彼や学生などの方を気の毒そうに見るが、何も云えない程ぐッしゃりつぶされてしまっていた。学生の作った組織も反古(ほご)のように、役に立たなかった。――それでも学生は割合に元気を保っていた。
「何かあったら跳ね起きるんだ。その代り、その何かをうまくつかむことだ」と云った。
「これでも跳ね起きられるかな」――威張んなの漁夫だった。
「かな――? 馬鹿。こっちは人数が多いんだ。恐れることはないさ。それに彼奴等が無茶なことをすればする程、今のうちこそ内へ、内へとこもっているが、火薬よりも強い不平と不満が皆の心の中に、つまりにいいだけつまっているんだ。――俺はそいつを頼りにしているんだ」
「道具立てはいいな」威張んなは「糞壺」の中をグルグル見廻して、
「そんな奴等がいるかな。どれも、これも…………」
愚痴ッぽく云った。
「俺達から愚痴ッぽかったら――もう、最後だよ」
「見れ、お前えだけだ、元気のええのア。――今度事件起こしてみれ、生命(いのち)がけだ」
学生は暗い顔をした。「そうさ……」と云った。
監督は手下を連れて、夜三回まわってきた。三、四人固まっていると、怒鳴りつけた。それでも、まだ足りなく、秘密に自分の手下を「糞壺」に寝らせた。
――「鎖」が、ただ、眼に見えないだけの違いだった。皆の足は歩くときには、吋太(インチぶと)の鎖を現実に後に引きずッているように重かった。
「俺ア、キット殺されるべよ」
「ん。んでも、どうせ殺されるッて分ったら、その時アやるよ」
芝浦の漁夫が、
「馬鹿!」と、横から怒鳴りつけた。「殺されるッて分ったら? 馬鹿ア、何時(いつ)だ、それア。――今、殺されているんでねえか。小刻みによ。彼奴等はな、上手なんだ。ピストルは今にもうつように、何時でも持っているが、なかなかそんなヘマはしないんだ。あれア「手」なんだ。――分るか。彼奴等は、俺達を殺せば、自分等の方で損するんだ。目的は――本当の目的は、俺達をウンと働かせて、締木(しめぎ)にかけて、ギイギイ搾り上げて、しこたま儲けることなんだ。そいつを今俺達は毎日やられてるんだ。――どうだ、この滅茶苦茶は。まるで蚕に食われている桑の葉のように、俺達の身体が殺されているんだ」
「んだな!」
「んだな、も糞もあるもんか」厚い掌(てのひら)に、煙草の火を転がした。「ま、待ってくれ、今に、畜生!」
あまり南下して、身体(がら)の小さい女蟹ばかり多くなったので、場所を北の方へ移動することになった。それで皆は残業をさせられて、少し早目に(久し振りに!)仕事が終った。
皆が「糞壺」に降りて来た。
「元気ねえな」芝浦だった。
「こら、足ば見てけれや。ガク、ガクッて、段ば降りれなくなったで」
「気の毒だ。それでもまだ一生懸命働いてやろうッてんだから」
「誰が! ――仕方ねんだべよ」
芝浦が笑った。「殺される時も、仕方がねえか」
「…………」
「まあ、このまま行けば、お前ここ四、五日だな」
相手は拍手に、イヤな顔をして、黄色ッぽくムクンだ片方の頬(ほお)と眼蓋(まぶた)をゆがめた。そして、だまって自分の棚のところへ行くと、端へ膝から下の足をブラ下げて、関節を掌刀(てがたな)でたたいた。
――下で、芝浦が手を振りながら、しゃべっていた。吃(ども)りが、身体をゆすりながら、相槌(あいづち)を打った。
「……いいか、まア仮りに金持が金を出して作ったから、船があるとしてもいいさ。水夫と火夫がいなかったら動くか。蟹が海の底に何億っているさ。仮りにだ、色々な仕度(したく)をして、此処まで出掛けてくるのに、金持が金をだせたからとしてもいいさ。俺達が働かなかったら、一匹の蟹だって、金持の懐に入って行くか。いいか、俺達がこの一夏ここで働いて、それで一体どの位金が入ってくる。ところが、金持はこの船一艘で純手取り四、五十万円ッて金をせしめるんだ。――さあ、んだら、その金の出所だ。無から有は生ぜじだ。――分るか。なア、皆んな俺達の力さ。――んだから、そう今にもお陀仏するような不景気な面(つら)してるなって云うんだ。うんと威張るんだ。底の底のことになれば、うそでない、あっちの方が俺達をおッかながってるんだ。ビクビクすんな。
水夫と火夫がいなかったら、船は動かないんだ。――労働者が働かねば、ビタ一文だって、金持の懐にゃ入らないんだ。さっき云った船を買ったり、道具を用意したり、仕度をする金も、やっぱり他の労働者が血をしぼって、儲けさせてやった――俺達からしぼり取って行きやがった金なんだ。――金持と俺達とは親と子なんだ……」
監督が入ってきた。
皆ドマついた恰好(かっこう)で、ゴソゴソし出した。




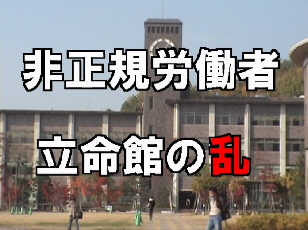
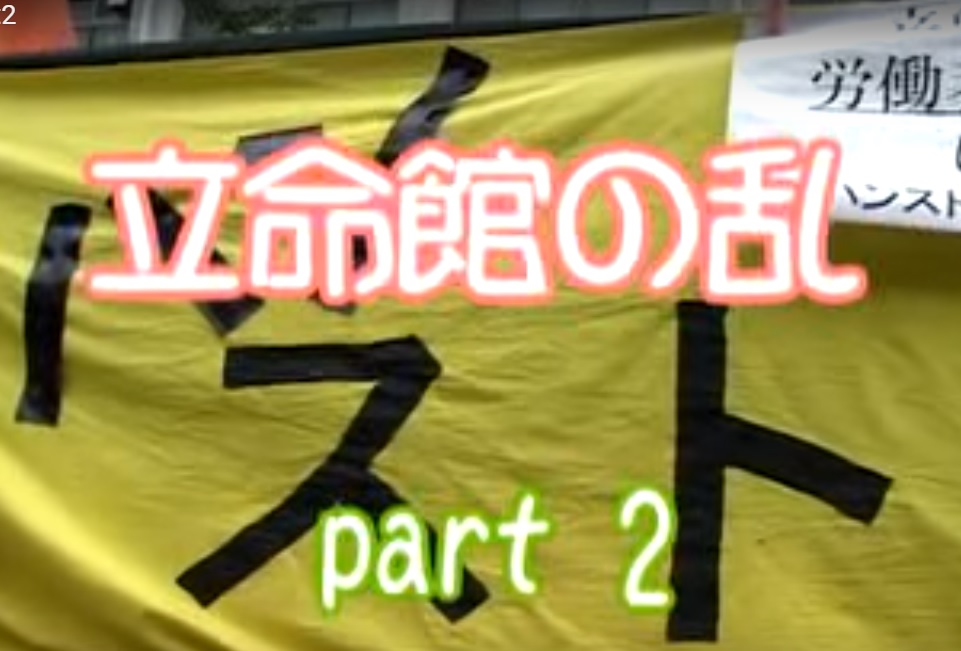












この記事への質問・一言コメントをどうぞ AIコースケと議論しよう!
回答には文字数制限があるため、制限を超えると途中で打ち切られることがあります。