第53話 静子(1)
六月のある日――武治の家の前の坂を下ってくる女性がいた。リュックを背負ったスラックスの軽装で――。彼女は誰の紹介もなく、ひょっこり武治の家を訪ねてきた。こうした学生などはいつものことだから、武治は何とも思わず、喜んで迎え入れた。
彼女はリュックを廊下にゴトリと下ろし、やっと寛げたという風情――スラックスのポケットからハンカチを出し、額の汗を拭いた。
「しばらく泊めて頂いて畑仕事を……。わたしお茶の水女子大の学生で山本静子です」という初対面の挨拶は、今まできたどの学生よりも不躾けだった。
彼女は三里塚十字路でバスを降り、まず戸田委員長の家で道を尋ね、木の根まで歩いてきたという。
「泊まるところはいくらでもあるが、百姓仕事は辛いよ」
「大丈夫よ、わたし群馬の田舎の農家育ちですもの……」
彼女は武治の顔をみつめ、「粘り強く闘っている三里塚の農民に一度は会いたいと、かねがね思っていたが、今日は会えて嬉しい」といって、さも嬉しそうな表情で張りのいい胸に両の掌を当てた。
武治は若い静子にペコリと頭を下げて、ニッコリした。
「本当のところ、わたしは農民から学びたいんです。木川さん……」
静子は当分武治の家で、畑仕事を手伝うことなり、午後からは早速、持ってきた仕事着に着替え、武治に従いて畑に出た。が、どう見ても武治の眼には、彼女が農家育ちとはいっても、野良仕事の経験があまりないとしか、映らなかった。でも「学びにきた」という静子の言葉には武治の心も動かされたし、見たところそれは嘘ではなさそうだ。
山本静子がなぜ木の根に入ろうとしたかには、一つの理由があった。学内闘争で静子は「民青」にいた関係、「日共」が三里塚で犯したという裏切り行為を数回にわたって、他のセクトの学生から糾弾されたことがある。彼女はそれに対して、頑強に反発した。しかしその後自分でも日共の動向に疑惑を覚え、今は「民青」から去っていた。
そうした関係で、一度は是非とも現地に行って、その事実を確かめたいと思っていた。それが今日ようやく、実現できたのである。だがそのことについてはいきなり初対面の武治に持ち出すよりも、一応秘めておいて、後でゆっくり腰を据えて訊きただそうと思っていた。
武治は武治で、静子が農家の出身だと聞いて、少なからず親しみを覚えた。そればかりか、静子がわが娘のように見えてならなかった。それに自分の息子、娘が持ち合わせていない殊勝なものを、彼女は持っているような気がしてならなかった。「今時、よくもこんな殊勝な娘がいたものだ」と思って、武治は彼女の横顔をチラと盗み見た。彼女には二一歳とも見えぬあどけなさが、その面影に漂っていた。
静子は長い睫毛のつぶらな瞳で、じーっと武治をみつめていった。
「私は百姓のお手伝いではなく、闘いのためなら木の根に住みついてもいいと思います」
武治は黙って、頷いた。静子の言葉がどこまで信じるに足りるか、彼にはわからなかった。だが、彼女の言葉には武治を魅了するカがあったことはたしかだった。
静子の「学びにきた」という言葉の意味は、彼女の真撃な言動によって明らかにされた。
「こんな娘がわが娘だったら……。いやそれよりも息子の嫁になってくれたらな……」と、武治は心密かに思うのだった。
「木川さん、日共について聞かせて下さい」
突然の言葉に武治はとまどった。だが一部始終、語った。一〇月一〇日の駒井野の強制測量のときのこと、平和塔の話などを例に、日共の三里塚闘争に対するありのままを話して聞かせた。
静子の胸の内側から怒りが、ときめきとともに、ドーッと込み上げてきた。
日共の裏切行為は、たしかな事実だったのか!静子の全身の怒りが、炎となって燃え上がった。このまま木の根に居据わって、武治の片腕となってわが身を闘いに投げ出したい衡動に駈られた。
静子は話を聞きながらも武治に従いて、忙しく畑仕事の手を動かした。静子の情熱は、武治の心に伝わった。一面識もなかった彼女に、こうも自分の心が伝わるものかと武治も不思議に思った。静子は無心に白い手を動かし続けていた。武治はそれがいとおしく思えてならなかった。
「私は木川さんさえよかったら、ここにこのまま居てもいいと思うのです」
「こんなところでよかったら……山本さん、いつまでもいて下さいよ」
「私も田舎育ちでこうした所にくると、何かほっとするのです。これでも母に従いて野良仕事を手伝ったこともあるのですからね……。私は昔の三里塚は知りませんが、こんな素晴らしい所を空港にするなんて……」
「全く……。毎日腹が立ってしょうがねえですよ」
「私だって腹が立つんですから、まして木川さんだったら……」
静子は手を休めて、じーっと武治の顔をみつめた。武治は静子を誘って、傍の木陰に憩った。
「すぐあすこに見えるのは弟の源二の家ですよ。立入り測量の日には全身糞だらけになって、杭打ちの阻止を……」
「ああ、あれテレビで見たわ!」
「あの日、糞を被ったのが、わしの弟の源二で、わしら兄弟は八郎の家と合わせて、この木の根に三軒あるんですよ」
「兄弟三人で闘うなんて素晴らしいわね」
静子にそう励まされると、武治も乗気になり、時を忘れて「三日戦争」の話を語り続けた。静子の顔は紅潮し、やがて不思議な凛々しさが漲っていった。彼女と語していると武治の心は仄々した明るささえ覚えるのだった。これは彼女の若々しさのもたらすものだろうか。――武治は彼女のあどけない顔をみつめて、不思議でならなかった。
武治は一刻でも長く彼女と語りたい気持でいっぱいだった。そして、一時も多く、彼女をここに引き留めておきたかった。






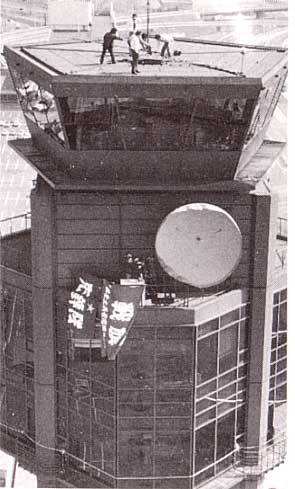








この記事への質問・一言コメントをどうぞ AIコースケと議論しよう!
回答には文字数制限があるため、制限を超えると途中で打ち切られることがあります。