
by 味岡 修
[Sponsor Ad]
左翼総括の方法論的アプローチ
「左翼」総括の難しさ
以前、1968年から50年目(2018年)の節目を迎えることになるというので、左翼の現在と未来についての議論が起こるだろうと言われたことがあった。そういう期待があったというべきかもしれない。1968年は新左翼が主軸となって反戦闘争や大学闘争が頂点にあった時期だからである。
1968年新宿での反戦闘争は60年代の反戦闘争の頂点であったし、1969年初めの東大安田講堂の攻防戦は大学闘争(全共闘運動)の最後というべき位置にあった。そして、その後は内ゲバや連合赤軍事件もあり、左翼運動は衰退を余儀なくされ現在に至ってきた。だから、50年を経てこの時期の闘争があらためて対象化されるだろうという期待と願望があった。
実際にこの期待は『続・全共闘白書』などとなってあらわれたが、未完のものというべきものでしかなかった。僕も自分の主宰している雑誌(『流砂』)に「左翼は再生されるのだろうか」という一文を書いたが、納得がいったものを書けたとは思えなかった。総括〈対象化〉の方法も含めた再検討がいるということを痛切に感じながら、現在にいたっている。
歴史の中に総括しようとする方法に興味
『真説日本左翼史~戦後左派の源流』は戦後(1945年)から1960年安保闘争までの戦後左翼史を対象にしていて、1960年代を主導した新左翼は次に扱われることになっているのだが、日本の左翼史を歴史的な射程で総括しようと試みていて、とても興味を引かれた。僕は1968年の事件を念頭に置きながら、新左翼の総括を試みていた時に、これは伝統的左翼(新左翼に対する旧左翼の総称)の総括を含めなければならない、と思っていたこともあるからかもしれない。

この本の表題とでもいうように掲げられている「『左翼』は何を達成し、なぜ失敗したのか」という事を明瞭にすることは自分もなすべきことだと思っている。左翼の言説は概ねリベラルな言説に変動しているのが現状だが、他方で共産党(伝統的左翼)も中核派も革マル派(新左翼)も残っている。佐藤はそれらがよみがえるかもしれないことを懸念している。悲劇的な事態を演じた左翼が同じことを繰り返すかもしれないという懸念であるが、僕はそういうことはないと思っている。
左翼を存在せしめた現実の矛盾とそれをただそうとする運動は現実に存在している。反体制や反国家権力の運動は、規模はともかく存在しており、それが左翼的なのものの存続を可能にしている。だからと言って、左翼的な存在がかつてのように蘇り、ヘゲモニー(主導権)をにぎることはないと思う。伝統的左翼も、新左翼もその思想(理念)はかつての運動の中で試されたのであり、その中で無効がいいわたされたのであり、思想的には死に体としてあるのが現状であるからだ。
思想(理念)は意識的に解体され、再生されなければ甦ることはないし、伝統的左翼も新左翼も組織を保持している面々にはそのような思想力があるとは思えない。左翼が限界というか、無効性を刻印された事態を超えていくには、左翼的なものを存在せしめた歴史(近代)の総括が必要だし、その中での自己解体と再生の営みが不可欠だからである。
これは現在の存在し、未来において広がることが予測される現状に反抗する反体制、反国家権力の運動に理論構成と言語表現を与えることになろう。若い世代の白井聰(「武器としての『資本論』」など)や斎藤幸平(「人新世の『資本論』」など)の登場はそういう一つだが、それらは新左翼も含めた伝統的左翼の言説とは別のところに位置していることはたしかである。
[Sponsor Ad]
敗戦による左翼(社共)の復活過程
「戦前左翼の復活」としての登場

この本(上巻)は1945年(終戦)の年から1960年安保闘争までの左翼の歴史を扱っているのだが、それまでは日本共産党と日本社会党が大きな位置を左翼の中で占めていた。1960年安保闘争を契機に新左翼といわれるものが登場し、やがては大きな位置をしめる。
伝統的左翼として共産党と日本社会党は戦後の左翼として大きな位置をしめるが、これは1920年代30年代にかけて最盛期にあった戦前の左翼の復活版と言えなくはない。大正末期から昭和のはじめにかけて左翼運動は全盛期にあったが、これは戦争への足音の中で消されるか、沈黙を余儀なくされた。
この左翼は敗戦を契機に復活した。これは戦争を主導した右翼や保守が政治的力を失ったからである。敗戦において日本は国体の護持を条件にしたが、これは国内での旧体制派の支配を目論むものであったが、敗戦が和平派によって推進されたように、戦時期に主導力を持っていた政治家は力を失ってもいたのである。戦争期に抑え込まれていた左翼は敗戦期に復活するのである。
独自の戦後改革の構想がなかった左翼
日本共産党は戦前に獄につながれていた人たち(徳田球一や志賀義雄や宮本顕治ら)が復活をさせる。これにはおもしろいエピソードがあり、アメリカ軍が彼らを解放したということであり、もしもこれが日本人の手でなされたのであれば、その後の共産党は違った存在になっていたかも知れないということである。事実、本書で書かれているように日本共産党はアメリカ占領軍を解放軍として規定し、その後の混迷の要因にもなる。
アメリカ占領軍は初期占領政策として、非軍事化と民主化を柱にして、農地改革や憲法改正などを行う。戦後改革である。これは日本の戦争態勢と戦ったアメリカ軍が勝利の結果として押し付けて来たものであるし、ある意味では日本人が敗戦革命としてやるべきことを取り上げたものだともいえる。やがてこのアメリカの初期占領政策は変更され、日本の最軍備や憲法改正の要求になる。また、日本の官僚支配を通じた天皇の利用も明確になった。
日本共産党が戦後の初期に取ったアメリカ占領軍の規定は謎に満ちてはいるが、フアシズム政権を枢軸とする国と戦った連合国が戦後を支配する体制となったことを考えれば、不思議ではなかったとも言える。戦後の世界体制は戦勝国の世界体制であり、冷戦が激化しなければ、米ソが対立的ではなかったとすれば、アメリカ占領軍の政策を共産党が支持する必然性はあったからである。
このことは日本共産党が戦後における独自の国家構想を持ち得ていなかったことを意味する。よく話題になることだが、共産党は憲法改正時に憲法9条に反対したということがある。国家は自衛の軍を持つことは当たり前のこととして反対した日本共産党は戦力保持を禁じる憲法9条に反対したのだ。これは戦争と国家についての日本共産党の考えを代表していたのである。
憲法9条は誰が発案したか今でも話題になるが、「戦争」についての方向を提示していた。これに対する日本共産党の態度は彼等の戦争観を示すのであるが、「戦争」について敗戦が提示していたものへの、日本共産党のあり様を示していたと言える。
「戦争」に対する左翼の態度の曖昧さ
戦前体制への批判が左翼復活の源泉だった
敗戦がもたらした大きな問題は占領軍による国家支配(統治)であるが、日本国民にとっての問題はどのような国家統治体制を取るかという事であり、その中心には戦争に対する対応があった。何故なら、敗戦までの日本は戦争を国家の中心において、国家体制を構築してきたからである。俗に「富国強兵」政策といわれるが、強兵こそが中心にあったのである。「国体」という統治体制も戦争を軸にした体制から生まれたのである。
この国家のあり方に敗戦は疑念を生みださせたのであり、「こんな戦争は嫌だ」という国民意識を広範に生んだのである。国民にはアメリカ占領軍の日本統治(支配)よりも戦争の方向が重要だったのである。このことはアメリカの占領政策の一つとして日本の非軍事化(憲法9条)が国民に支持され、存続してきた理由である。
戦争を中心に置かない国家は可能かという問題が、この時に浮上した。国家の中心に戦争を置かない国家は可能かというこの問題は、敗戦国としての日本国民を強く支配した事柄であったが、戦勝国が構想した戦後国家とはズレのあるものだった。何故なら、戦勝国はファシズムや帝国主義の戦争には反対であったが、戦争そのものには反対ではなかったからだ。
戦前の左翼はかつての日本の戦争とその下での統治体制で壊滅するほどの強圧を受けたのだが、戦後左翼はこの戦前の統治体制への批判によって復活した。今は、読売新聞の統率者である渡邊恒雄が戦後に日本共産党に入り活動したことはよく知られている。彼は戦争と軍部の独裁体制に反抗したのである。このことはかつての特攻隊員であった若者が共産党(左翼)に身を投じたことと同じである。
戦前革命派の出身ゆえの戦後意識とのズレ
しかし、復活した左翼(日本共産党や日本社会党)には戦前に革命を志向して活動した歴史がある。日本共産党は講座派として、日本社会党は労農派として活動し、戦前は獄につながれた、沈黙を余儀なくされた面々がいた。彼らが日本共産党や社会党の中心にいたのである。
日本共産党の面々は先に紹介したのであるが、日本社会党には山川均や向坂逸郎などがいた。この本では講座派や労農派のことが詳しく紹介されているが、最近の若い人たちには参考になることかもしれない。
かつて戦前に革命運動の活動家としてあり、戦後に復活した面々にとって、また彼らが指導した日本共産党や日本社会党にとって、戦争についての態度をどう決めたかは最大の問題だった。というのは戦争に対する国民の意識こそが、戦後の左翼の基盤であり、それを生かしたものだったからだ。
しかし、戦前に革命運動の展開者であり、戦後に指導的役割を果たした面々の戦争についての考え(理念)には曖昧というか、限界があったのではないのだろうか。もっと端的にいえば、戦争についての国民の意識と彼等の理論や言語表現には誤差があり、国民の意識に基盤を持ちながらそれを生かしきれなかった要因ではないだろうか。
[Sponsor Ad]
最後まで国民意識によりそい続けたことで延命
支配層による戦後改革の否定と修正
戦後の日本は、ともかく戦後のアメリカ占領軍の非軍事化と民主化という方針を受け入れ出発した。日本の支配層はそれを受け入れながら、それを批判する動きを生み出した。それは戦争を国家の主権的なものとして復権させる動きであり、民主化を行きすぎとして修正させようとする動きである。この本でも言われている「歴史の逆コース」である。
これにはアメリカ占領軍の非軍事化と民主化の修正が背景にあった。戦後の15年(1945年の敗戦から、1960年の安保闘争までは)はアメリカ軍の占領軍の戦後改革の修正の動きが顕著だった。憲法改正はその中心に置かれていたが、戦争の復権と統治体制の国家主義化である。これは保守派や右翼の動きと言ってよかったのであるが、左翼はそれらに対する反対闘争を展開した。この反体制的、反国家権力の運動は国家権力の暴走を防ぐという意味でその役割を果たしたと言える。
左翼による革命理念もまた現実の中で破綻
それならば、戦後の左翼であった日本共産党や日本社会党自身は、戦後体制に対してどうだったのだろうか。日本共産党にはアメリカ軍解放軍規定から1952年の軍事路路線、それを全否定しての議会主義革命にいたるまで、路線の紆余屈性はあるが、彼等の革命政党としての出自から規定された革命理念が現実に試されることでその空想性と非現実性が露呈していく歴史だったように思う。
彼らはその歴史に向かい合わないできたと思えるが、そこに悲劇性があるように思う。二段階戦略をはじめとする革命戦略が非現実的で空想的だったのである。戦争について、自由と民主主義について本当に向かい合うのではなく、彼等の革命思想がそれらの前で破綻していく歴史だったように思う。
にもかかわらず日本共産党は生き延びている。その秘密は理念よりも人々の反抗的、反逆的な意識によりそう、そこから離れないという反体制、反権力運動の伝統から身に着けた知恵にあるのではないのか。ここは注目してみておくべきところだ。
本書で日本社会党には「反戦平和」という評価が与えられているが、これは妥当な事のように思う。反戦平和というのは多分に曖昧なところが含まれており、本来ならそれは反戦というより「非戦」とでも言いかえるべきものだ。そこには「戦争をしない」とか「反戦争」とかが明瞭にされない問題が含まれてはいたが、それでも戦後のある時期に日本社会党がぎりぎりの所まで「反戦平和」という態度を貫いたことは評価しておいていいことだと思う。
本書は誰も顧みようとしない戦後左翼を歴史の中に取り上げているのは貴重だが、やはり「左翼という存在」を検証するならば、1960年以降の新左翼が重要だ。次の本を期待したい。
本書の紹介と目次ー出版社サイトよりー
真説 日本左翼史
戦後左派の源流 1945-1960 (講談社現代新書)
 | 真説 日本左翼史 戦後左派の源流 1945─1960 (講談社現代新書) 新品価格 |
日本の左翼は何を達成し、なぜ失敗したのか?
ーー忘れられた近現代史をたどり、未来の分岐点に求められる「左翼の思考」を検証する壮大なプロジェクト。
深刻化する貧困と格差、忍び寄る戦争の危機、アメリカで叫ばれる社会主義(ソーシャリズム)。これらはすべて、【左翼の論点】そのものである!
激怒の時代を生き抜くために、今こそ「左の教養」を再検討するべき時が来たーー。
◇◇◇◇◇
戦後復興期に、共産党や社会党が国民に支持された時代があったことは、今や忘れられようとしている。学生運動や過激化する新左翼の内ゲバは、左翼の危険性を歴史に刻印した。そしてソ連崩壊後、左翼の思考そのものが歴史の遺物として葬り去られようとしている。
しかし、これだけ格差が深刻化している今、必ず左翼が論じてきた問題が再浮上してくる。今こそ、日本近現代史から忘れられた「左翼史」を検証しなければならない。
「日本の近現代史を通じて登場した様々な左翼政党やそれに関わった人たちの行い、思想について整理する作業を誰かがやっておかなければ日本の左翼の実像が後世に正確な形で伝わらなくなってしまう。私や池上さんは、その作業を行うことができる最後の世代だと思います。」(佐藤優)
【本書の目次】
序章 「左翼史」を学ぶ意義
第1章 戦後左派の巨人たち(1945~1946年)
第2章 左派の躍進を支持した占領統治下の日本(1946~1950年)
第3章 社会党の拡大・分裂と「スターリン批判」の衝撃(1951~1959年)
第4章 「新左翼」誕生への道程(1960年~)
【本書の構成】
◇日本共産党の本質は今も「革命政党」
◇社会党栄光と凋落の背景
◇アメリカで社会主義が支持を集める理由
◇野坂参三「愛される共産党」の意図
◇宮本顕治はなぜ非転向を貫けたか
◇テロが歴史を変えた「風流夢譚事件」
◇労農派・向坂逸郎の抵抗の方法論
◇「共産党的弁証法」という欺瞞
◇労働歌と軍歌の奇妙な共通点
◇共産党の分裂を招いた「所感派」と「国際派」
◇毛沢東を模倣した「山村工作隊」
◇知識人を驚愕させた「スターリン批判」
◇天才兄弟と称された上田耕一郎と不破哲三
◇黒田寛一と「人間革命」の共通点
◇現在の社民党は「右翼社民」
……ほか
 |
真説 日本左翼史 戦後左派の源流 1945─1960 (講談社現代新書) 新品価格 |
 |
激動 日本左翼史 学生運動と過激派 1960-1972 (講談社現代新書 2643) 新品価格 |
 |
漂流 日本左翼史 理想なき左派の混迷 1972-2022 (講談社現代新書) 新品価格 |
 |
新しい左翼入門 相克の運動史は超えられるか (講談社現代新書) 新品価格 |







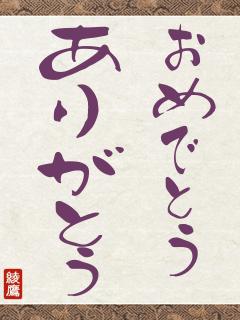






左翼時代、史的唯物論などを見ればわかる通り「左翼は物事を対象化することができるのが強み(特徴)」と言われたことを思い出しました。
右翼は物事を対象化することでできず、歴史的なものであるはずの自己のイデオロギーや道徳、その時々の社会を、何かしら永久不変な真理のようにしか考えられない。せいぜいが昔の野蛮から理想への直線的な発展として、自己を正当化するだけであると。
なるほど三上さんがこの本に抱いた興味としては、左翼はいつのまにか、自分自身をも含めて歴史的な存在にすぎないという認識対象化、その発想の強みを失い、歴史的な存在としての対象化の中に、自分の存在を含めることができなくなっていたという気づきなのかなと思いました。それは興味深いです。
よくスターリン主義者への批判として、マルクスの聖典化や硬直した教条主義、ほとんど宗教団体みたいな自己絶対化があげられていましたが、そういうことがおこってしまう根本的なところなのかなと。単に現象的なところだけで批判していても、いつのまにか自分自身がそうなってしまうのですね。
今更なことなんでしょうけど、あらためて勉強になったと思います。一度読んでみます。
連投失礼。
私はネトウヨ系保守というのは、運動的に言えば昔の左翼運動のマンガ的な劣化コピー、その悪いところだけを集めた裏返しだと思っているのですが、書評中にあった、二段階革命戦略その他のあまりの空理空論という部分で、またそれを思い出しました。
たとえば「日本国憲法無効論」とか「日韓断交」とか「外国人排斥」とかの主張。スローガンだけでなく、いろいろと「分析」してみせたり、経過措置から事後の対策まで、得々として書いている人もいたりして、論理的に一応文章としては(その文章の中では)破綻なく筋が通っているんですよね。ある意味ブログ的というか。そこが(悪い意味で)非常に左翼的。
なるほどね、と思いました。人の振り見て我が振り直せってやつですね。