4.『君主論』の批判点=その階級的性格

われわれはこれまで『君主論』を貫く「政治」の核心点について学んできたわけだが、そのためにも批判点に関しては一応タナ上げにしてきたのである。だが誰が読んでも『君主論』の具体的内容が、直ちに革命運動に適用できる代物ではないことははっきりとすることだろう。 では『君主論』は一言でいって何が問題なのか。それは本書の階級的性格であり、それにもとづく政治目的に他ならない。
マキァベリの政治目的は、フランスをはじめとする大国支配を打ち破り、イタリアの統一をかちとり、イタリアの近代的中央集権国家への道を切り拓くことにあった。それをメディチ家といった一封建領主に託したのである
すなわち封建領主を活用しながら、ブルジョア革命を遂行していくことがマキァベリの戦略であったと言いうる。
われわれの政治目的が、プロレタリア階級の独裁を通じた階級社会そのものの廃絶=共産主義社会の実現であることと比するとき、双方の決定的な違い階級的非和 解性ははっきりするだろう。
こうした相違は自ずと双方の政策の内容をまったく異ったものとさせる。すなわち『君主論』にあっては侵略 政策と民衆抑圧政策は基軸中の基軸であり、これをもって国の領土を拡大し、民衆から収奪し、国(=支配者)を富ませることがめざされたのである。だがわれわれは こうしたことを阻止し、打ち破るためにこそたたかうのであって、双方の政策は水と油の関係にあるのだといえる。
ともあれ政治は武器と同じく技術(手段)の体系である以上、極言すれば、その使い方一つで反革命的なものにもなり、革命的なものにもなるのである。ただいずれにせよ言えることは、「武器の使い方を習得し、武器の使い方に練達し武器をもつことにつとめないような被抑圧階級…は、抑圧され、虐待され、奴隸としてとりあつかわれる値うちしかない」(レーニン『プロレタリア革命の軍事綱領』)のと同じように、「政治の使い方」を習得しない階級に未来はないであろうということである
したがって、革命的な前衛をめざすわれわれは、労働者階級の未来に対して勝利を保証する責任を負っており、それ故政治を主体化する義務を負っていると言わなくてはならない。
ただそこで留意しなければならないのは、「策士策に溺れる」がごとく、技術面にばかり目がいき、自らの階級的立脚点を見失うようなことがあってはならないということである。そのためにも『君主論』主体化に向けた前提として、マキァベリに対する階級的批判の視座ははっきりと保持しておく必要があるのだといえよう。
5.スターリン主義的政治の克服
(1)近代政治の先駆者としてのマキァベリの革命性それゆえの限界性

マキァベリは古代、中世と続いた従来の政治が宗教や倫理、道徳などと未分化であった情況を突破し、政治が 自立した力の論理であることをあばき出していった。それはまた自立した学問としての「政治学」を生み出す下地を作ったということでもある。
まさに「それでも地球は動く」と、キリスト教的宇宙観に真向うから異議を唱えたガリレオ=ガリレイが、近代自然科学の先駆者であったように、マキァベリこそが近代政治(学)の先駆者として、政治思想史に革命的な地平を切り拓いたのである。これらは中世末期に芽ばえ、次の時代に実を結ぶ「近代合理主義」の萠芽に他ならない。
こうした時代の背景を下部構造的に見るならば、それは教会権力による封建支配に対抗し、商人たちが商業活動の自由を要求し勃興してきた時代である。かかるムーヴメン卜が、金もうけのためには「神をも恐れぬ」近代資本主義の源泉でもあるのだ。
こうした資本主義の創生を背景として生まれた「近代合理主義」思想は、資本主義の発展とともに資本家的生産様式を支える精神的バックボーンとして、一つの時代を包みこんでいく。なぜならば資本主義とは、自然から人間にいたる万物を商品化せしめ、資本の増殖のための 手段へと化していく、巨大な合理化のシステムであるからだ
こうしたいわゆる「目的合理性」の貫徹は、近代化の目安となるものである。そしてこれは当然にも政治の場面にあっても極限的に徹底化されるのである。現代政治におけるいわゆる「マキァベリズム」の徹底化である。
ところでわれわれのめざすプロレタリア革命は、こうした近代資本主義社会総体を転覆させることを目的としているのであるわけだから、本質的にはマキァベリで始まる「近代政治」をもその否定の対象としているのはいかにも当然のことである。ただそのプロセスにあっては、 政治は決定的に重要なモメントであることはすでに確認したとおりである。
すなわち政治ないしは近代政治は、あくまでも否定の否定の対象であるということだ。いうまでもなく革命の手段(技術)は、武器をも含めてすべて近代資本主義社会の遺産であり、近代政治もまた例外ではないからだ。だからパワー・ポリティクスそれ自体をアナキストやエコロジストのごとくに、近代主義だとして退けてしまうのはまったく子供じみた空論であり、間題にならない。
しかしながらこれとは逆に、「否定の否定jの論理をま ったく無視しきり、手段の体系=目的合理性のとりこに なってしまった場合、それはブルジョア近代合理主義へ の思想的屈服以外ではない。端的な例として、「革命」の 大義名分さえかかげるならば核軍拡さえ辞さず、民生の向上と銘うてばブルジョア的企業経営方式の全面導入を もなしていくというソ連や中国の今日的あり方がそうで ある。その場合、革命の「力」をブルジョア社会の「力」と等しく「武力」や「生産力」に一面化してしまっているのである。
したがって問題とされるべきは、パワーポリティクスの安直な否定ではもちろんなく、「力(パワー)」の内容に対して思想的切開を加えていくこと、そのことがマキァベリから始まる近代政治が、政治の合理的核心をつかまえるとともに、これと反比例してそぎ落としてしまった領域を再度復権していくことにつながるのではないかと考えられる。
まさにこの近代的「そぎ落とし」の延長線上に、近代政治の枠を一歩も出ずにこれを再生産しているのが、スターリン主義的政治なのである。スターリン主義的政治にあっては、ブルジョア的パワー・ポリティクスがアルファでありかつオメガなのだ。そして革命運動にとりもっとも大事なこと、すなわち「民心の動員」といったファクターをスターリン主義者たちは踏みにじっているのである。
(2)大義に立脚した政治の大道を

以上のことからわれわれは、共産主義運動における近代政治の内在的乗りこえこそが、スターリン主義的政治を克服するものであるということがでぎる。
スターリン主義とは、理論的にいって、ロシア革命後のヨーロッパ革命の挫折に端を発し、帝国主義列強の包囲下での重圧の中で、世界革命の放棄と一国社会主義建設を路線化していったヨシフ=スターリンの革命戦略を本質的にはさすわけであるが、これを理論的に否定すれば、スターリン主義批判が実現できたかのごとく考えるのは、革命運動とは無縁な観念論者のあさはかさ以外ではない。
現に日本の反スタの元祖カクマルは、最も反スタ理論を体系化したと称し、その思い込みだけで生きている党派であるが、実践的には反スタどころか真正スターリン主義者も驚くばかりの反革命党派へと純化している。また反スタ派のもう一方の極にある中核派にあっても、三里塚闘争に顕著なように、一党独裁的なセクト主義的体質と内ゲバ主義へののめり込みといった傾向におち込んでおり、決してスターリン主義を実践的な政治展開においてのりこえているとは言いがたい。
われわれがスターリン主義を考える場合、戦略的な世界革命の放棄といったことと共に、政治展開における民心からの離反といった内容性について対象化しなくてはならない。わけても今日、スターリン主義者によるアフガン人民やポーランド人民、エチオピア人民に対する蛮行が、共産主義運動の名を汚している中で、そのことは決定的に重要である。この汚名をそそがない以上、共産主義運動の未来はないからだ。
それゆえ今日われわれに、実践的な政治展開において民心と結合していくこと、民衆の大義を実現していく、いわば「魂にふれる革命」を追求していくことが求められているのである。
強固な中央集権体制によって成り立つ近代ブルジョア社会を打倒する力は、やはり中央集権を有した強固かつ合理的なシステムによって成り立つ組織の力によるしかないことはレーニン主義の常識であるわけだが、そうした合理的なシステム化のみに一面化、一元化してしまった場合に誤りが生じうる。なぜならば、民衆の解放を望む心は、メンタルなものをどこまでも物質的なもの、合理的なもの、機能的なものへと還元していく近代的な合理化において生ずる人間の疎外からの脱却を求めているからである。
したがって革命党派の近代合理主義的な政治展開、組織建設への一面化は、民心の離反と党の官僚 主義化を生み出す根拠となるのだ。人間にとって「理性」の占める位置は大きい。だが人間はそれだけで生きているわけではなく、合理主義者のカントでさえ指摘しているように、人間は知(理性)・情 ・意を兼ね備えた動物なのである。つまり、情・意といったいわば「非合理」的側面をも内包しない限り、人間をとりあつかう仕事である政治は成功しないのである。
わけても民衆は即時的すなわち自然発生的には非合理が優位に立つ。地域的には西洋から離れれば離れるほどそうした傾向が強まる。こうした傾向に迎合することなく、政治展開のうちに あくまでもそうしたことを配慮し続けるポリシーを保持しつづけることの中に、スターリン主義的政治の内在的克服のキー・ポイントは存するのである。そうした配慮のうちに、あくまでも人民的な大義にそって政策展開をなしていくことこそが求められるのだといえよう。それはまた、結局のところマキァベリの射程内においてしか成り立っていない、スターリン主義をも含む近代政治を根底から止揚するカギと言ってもよいだろう。
(3)アジア革命に学ぶことの重要性
さて、それではそうしたことをわれわれは、現実の歴史の中から学ぶことができるのだろうか。できる。そうした内容性をもっとも豊富に提起した革命として、毛沢東の中国革命が存在する。
毛沢東の情勢分析におけるリアリズムは、彼の『抗日戦争における戦略問題』での、どこまでも客観的に敵=日帝を分析し評価しようとする冷静な理性的=科学的態度とその主客の攻防におけるパワー・ポリティクスの読みの鋭どさにおいてきわだっているといえるが、ここで問題としたいのは、そうした合理的=科学的態度と併存する形で存在する、あくまでも「人の要素を第一」(『四つの第一』)におくといった毛沢東の革命的政治家としてのポリシーについてである。これは、彼の政治展開においても徹底した大衆路線として表現されている
ところでこれは、毛沢東個人にのみ属する政治展開の流儀であるわけではない。否、むしろもっともオーソドックスにマルクス主義の本質的命題を、政治展開の中で継承したものであるといえよう。すなわちマルクス主義 は、政治革命をそのプロセスに内包しつつも、本質的には政治をも止揚することを射程に収めた〈人間解放〉の 思想であり〈人間革命〉のプロパーであるからだ。これこそまさに古くて新しい共産主義革命の命題なのである。
したがって共産主義者は、政治が手段(技術)の体系であることは与件としつつも、その手段の選択において常に民心に対する配慮が介在しなければならず、あくまでも民衆の大義にそって政策を実現しなければならないのだ。政治における倫理主義は戒めながらも、同時に人民的・階級的モラルにそってたたかいは展開されるべきなのである。
こうしたことは確かに経験的・資質的領域に大きく左右されるものであり、政治的現場との緊張関係・バランス感覚の結晶でしかないものとも言えるのだが、かかる困難性に正面から挑んでいかない限り、スターリン主義の内在的克服はありえないものといえる。その意味で、毛沢東の中国革命をはじめとするアジア革命に、学ぶベき点が多く存在しているのである。まさにそうした観点性にたち、この間われわれが主体化してきたスターリン主義の内在的克服の継承・発展が、本論の主旨である 「政治の主体化」とともにおし進められるべきであるといえる。


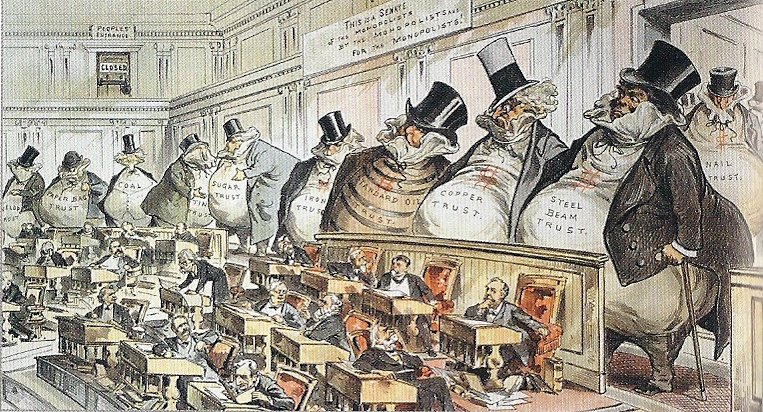
















この記事への質問・一言コメントをどうぞ AIコースケと議論しよう!
回答には文字数制限があるため、制限を超えると途中で打ち切られることがあります。