現代ファシズム論序説- 目次 > 懐古的資料室のトップにもどる
2.ファシズムとは何か
イ.みすごされてきたものは何か
コミンテルンないしトロツキーが陥った「ファシスト過小評価」の構造、したがって「みすごされてきたものは何か」という問いから出発するのが本章の課題である。
ところで今一度ここで押えておきたいのだが、この「みすごされてきたもの」は、言うまでもなくコミンテルンないしトロツキーに限らず現在においてもなお放置されたままとなっているのである。
それは本質的には主体的総括の欠如であることは前述の通りであるが、現象的にみるならば、ナチによる五百万人余りのユダヤ人虐殺をはじめ、ファシストの史上類をみない犯罪行為が明らかになっている現在、「ファシストが実は極悪反動であった」という認識はあまねく拡まっており、そのファシストが急成長しえた要因もまた、ヒトラー個人の天才的といわれた演説等々による大衆操作=デマゴギーの絶妙なる駆使などに卑少化されてしまう傾向が拍車をかけているからであろう。
無論われわれは、「嘘はできるだけ大きな方がよい」とか「嘘も百遍繰返せば真実となる」などと豪語したヒトラーの、デマゴーグとしての側面を看過するわけではない。
しかし史実として、かのナチこそ、ヘーゲルやマルクスを生みだしたドイツに十数年に亘って君臨したのであって、しかも社会科学者の中に占めるユダヤ人の比率が高かったにもかかわらず、多くの知識人さえ吸収しえたのであった。
かかる事実を見すえる時、われわれはナチズムの本質を、デマゴギー一般に解消する方法を戒めねばならない。たとえどれ程絶妙に駆使されたデマゴギーであるにせよ、それだけでは人民の支持を集めることはできず、まさにコミンテルンがそう考えた如く、急成長しえたにせよ、すぐにも瓦壊してしかるべきだった筈である。そうでなかった以上、ナチの急成長の背景には、それなりの根拠があった筈なのである。
そしてそのことは、他ならぬ今日のファシスト共の本質を暴露する上でも非常に重要である。というのは彼らとてファシズム=極悪という認識をもっており、己れをファシズムとは違うものとして理解しているからである。そしてそこにこそ、フアシスト共自身をも含めて「みすごされてきたもの」は介在するのである。

したがってわれわれは、ファシストが急成長しえた要因を、その発生史的端諸にまでさかのぼって分析していく必要がある。とりわけナチの登場過程とその政治主張の分析から開始することとしよう。
[Sponsor Ad]
ロ.国家社会主義ドイツ労働者党
1)ナチ登場の背景
前章の(ロ)においても触れた如く、一九一八年のドイツ十一月革命は、SPDの裏切りによって挫折を余義なくされた。とりわけ国防軍グレーナーに手をさしのべたSPDエーベルトの反革命策動は、潰滅的といってもいい程の打撃をうけていたドイツ反革命=王侯・貴族、ユンカー、大ブルジョアジーに復活の契機を与え、これが自らの権威をたてに、戦争帰りのあてのない兵士を反革命義勇軍に結集させることによって、スパルタクス団をはじめとする革命的労働者、兵士の蜂起を鎮圧させたのである。
そしてこのようにして出来あがった革命の残骸=ドイツ反革命とSPDの妥協の産物こそ、ワイマール共和国なのであった。そしてこのワイマール共和国こそ、ナチをはじめさまざまな右翼ファシストを発生させる土壌となったのである。
すなわち、今や復活した反革命共は、自分たちの責任を放棄し、その政策の帰結としてあるヴェルサイユ条約体制や、異常なまでのインフレーションの勃発によってまきおこった中間層を中心とする危機感や憤激を「ドイツが敗けたのは、ドイツ軍が闘っている時に、後から匕首で刺すものがいたからだ」と自らが負うべき責任を反戦勢力に転嫁して、没落する中間層の怒りを「十一月の犯罪者」=革命的労働者、ならびにSPDに向けさせることに成功した。そのことがまた、ヴェルサイユ体制、そしてその「責任者」たちのワイマール共和国こそが敵だとする、徹底した反共主義に根ざしたファシスト勢力の形成をも促したのである。

それと同時に(前述の如く)KPDが中間層をひきつける有効な戦術を打ち出しえず。あるいは一九二三年の蜂起が惨めな散発に帰したことによって、多くの中間層が最早KPDには何の魅力をも見い出せず、ファシズムの側へと傾斜していったのであった。
かかる情勢の中、ナチは、右翼勢力の極少一派としてその呪われた歩みをはじめ、ワイマールという土壌の上で、着実に成長していくのであった。
2)ナチの政治主張

一九一九年九月、ヒトラーを第七番目の党員としてむかえたドイツ労働者党は、翌年四月、党の名称を「国家社会主義ドイツ労働者党(NSDAP)」と改称し、ついで二一年七月にヒトラーを指導者としてその体制を固めた。いわずと知れたナチの誕生である。
それに先立つ二〇年二月、同党は二五ケ条の綱領を打ち出し、その政治的立場を明確にした。後年まで(徐々に空洞化されていったにせよ)受け継がれたこのナチの政治主張はおよそ次のようなものである。
1、諸国民の自決権に基き、大ドイツ国家にむかっての総てのドイツ人の結合。
2、ヴェルサイユ、ならびにサン=ジェルマン条約の廃棄。
3、過剰入口の移住のために領土と土地(植民地)を要求。
4、ドイツ国の国家公民たるものは、ドイツ的血統者たる者に限られる。
5、ユダヤ人は単に客員としてのみドイツ国内に生活する権利を有する。
6、ユダヤ人は国家の立法、及び執行の決定権から排除される。
11、労働なき、及び勤労なき所得の廃止、利子奴隷制の打破。
12、戦時利得の没収。
13、すでに社会化せられたる総ての営業=トラストの国有化、大企業の利益配当への参加。
16、大百貨店を即時市町村有化し、且つこれを小生産者へ廉価で貸与し、総べての小生産者を最も敏感に顧慮すべきことを要求し、もって健全なる中産等族を創設してこれを維持する。
17、民族的欲求に適合せる土地制度の改革、公共的必要の目的のための土地の無償没収に関する法令の制定、地代の廃止、及びあらゆる土地投機の抑制。
18、一般国民的犯罪人、投機業者、奸商等は、宗教及び人種のいかんを問わず之を死刑に処す。
これらをさらに傾向的に分類するならば、凡そ次の三点に要約することができるだろう。
すなわちまず第一に血統主義的ともいえる民族主義と国家主義(1~4)、第二に反ユダヤ主義(5、6)、第三にいわば小ブル的「社会主義」=「反資本主義」(11~18)である。
ただし第二の反ユダヤ主義に関しては、もともとヨーロッパに伝統的に存在していた反ユダヤ感情が、一方では国粋主義と、他方では「反資本主義」と結びついたもの(ユダヤ人に金融業者が比較的多かったことから、ユダヤ人=奸商というシェーマがデッチ上げられた)であることに踏まえるならば、まさにナチの政治的立場とは、その党名の如く、「国家-社会主義」そのものであったといえるであろう。
さて、以上がナチの政治主張のガイストであるわけだが、われわれははやくもここに、「みすごされてきたもの」の存在を知ることができる。それは「国家社会主義」の「社会主義」の側面である。
綱領をみれば一目瞭然であるように、少なくともこの面におけるナチの主張はコミンテルンが言うような「大ブルジョアジーの支配の道具」にはとてもならない代物ばかりである。何故ならばそこに展開されているのは、中間層の利害に立脚した上での、徹底した「反資本主義」的立場に他ならないからだ。無論ここでいう「反資本主義」は、われわれの展開するそれとは全く異なり、単に大ブルジョアジーに対する小ブルの反発を体現しているものに他ならないわけだが、それにしてもかかる「ラディカル」な主張に中間層の多くが魅了されたことは首肯けるだろう。
そして重要なことは、これらの主張は少くとも初期においては、ヒトラーをも含めて大真面目に語られていたし、事実として初期のナチは大ブルジョアジーとの結びつきを有してはおらず、純然たる小ブルの党として存在していたということである。
したがってこれらの主張を「デマゴギー」として一蹴せんとしたKPDは、すでにそれ自体として敗北を内包していたといえるだろうし、かかるナチの「社会主義」的側面を「過小評価」したが故に、大衆運動、とりわけ中間層の獲得戦での敗北も必然化されたのである。
それはともあれ、われわれは次に、ナチが掲げたこの「社会主義」がどの様に変質していったのかを見ていこう。
3)ナチ党左派

「国家社会主義」の旗を翻えして階級情勢に飛び出し、一躍大衆的基盤をつかむにいたったナチは、二三年十一月、ミュンヘン蜂起を企てて惨めな敗北を喫し、解党へと追いこまれた(ヒトラーは優雅な獄中生活へ)。
これをターニング・ポイントとして党体制の再編にむかったナチは、はやくも変質を開始する。
まず、そもそもが王侯・貴族、ユンカー、大ブルジョアジーの拠点としてあったドイツ南部、バイエルンを出発点としていたヒトラーらは、もはや「社会主義」が頭打ちになりつつあることに気づき、支配層との提携の必要性を認識するにおよんで、国家主義・民族主義、そしてまた反ユダヤ主義への傾斜を開始する。
ところがこれに対して、ドイツ北西部の中間層にジリジリと基盤を拡大させていたグレゴール・シュトラッサー、オットー・シュトラッサー兄弟を旗頭とした部分は、むしろより「社会主義」への傾斜を強め、ヒトラー派に対してナチ党左派を形成するに至るのである。そして「反資本主義」闘争の前進の為には労働者階級との同盟が必要であるとさえ主張し、ヒトラー派(主流派・右派)と激しい党内闘争を展開するのであった。

まず一九二五年、王族の財産没収問題について両派の第一回目の衝突が起こる。
そもそもこれは、KPDの提出した王族の財産没収要求が、SPDをもまき込んだ一大闘争へと発展したものであるが、この大高揚に対して左派は、KPD、SPDと共に戦列に加わることを通じて労働者階級内への基盤形成を画策すべく主張した。
これに対して、既に支配階層への接近をはかりつつあったヒトラーは「とんでもないことだ」と激怒し、左派の全面的統制にのりだしたのである。
この闘争は、当初的には左派の優位に進められたものの、一時はヒトラーの除名すら叫んでいたゲッペルスらが寝返りをうったことなどによってシュトラッサー兄弟が孤立化し、結局ヒトラー派の勝利に終ったのであった。
がそれにしても、この時期の左派の「左傾化」はすさまじいものがある。ゲッペルスなどは日記の中で次のような言葉を残している。いわく「われわれと共産党とが互いの頭をたたきあっているのはひどい話だと思う…場合によってはわれわれは共産党の主だった連中と手をつないでいけるのではあるまいか」
われわれはかかるゲッペルスの言葉などによって、左派内部にはかなりKPDにシンパシーをもつ部分さえ生まれつつあったことを推測することができる。その意味ではラデックの「シュラーゲタ演説」は、一定彼の意をとげていたといえるであろう。(無論そこには「ナショナリズムのカテゴリーにおいて」という注釈がつくのだが…)
さて一度は左派の敗北として終結したナチ党党内闘争は、階級情勢が流動化しはじめた一九二九年末から再び激化しはじめる。
この年八月に行なわれたナチ党党大会において、左派は「西欧金融資本」からドイツの国民的解放を得るために、ソ連との戦術的同盟の必要があること、並びに土地ないし重要産業の社会化を目指す階級闘争の開始を主張しはじめた。
さらに翌年に至っては、兄グレゴールよりも一層、「社会主義者」であったオットー・シュトラッサーは、ヒトラーが「反動的資本家と結んでいること」を暴露、ヒトラーは「資本家的」であり「ファシスト的」であると糾弾することをもって、公然と叛旗を翻えしたのである。

さらにヒトラーに出頭を命じられた彼は、逆にヒトラーに対して「徹底的な革命、資本主義への反対、真の社会主義、(ブルジョアジーとの)連立政権の拒否、ソ連を攻撃しない」という五項目の要求をつきつけ、とっくに「社会主義」を捨て去っていたヒトラーがこれをにべもなくはねつけるや「真の社会主義者はナチ党を離れる」と声明して、ついにナチを脱党。「革命的国家社会主義闘争団=黒色戦線」を結成するに至ったのであった。
だがしかし、こうしたオットーの反乱は、何よりも兄のグレゴールが動かなかったことによって党の分裂にはいたらず、またしてもヒトラー派の勝利に終った。(黒色戦線はその後いたずらに分裂をくりかえして自壊した)
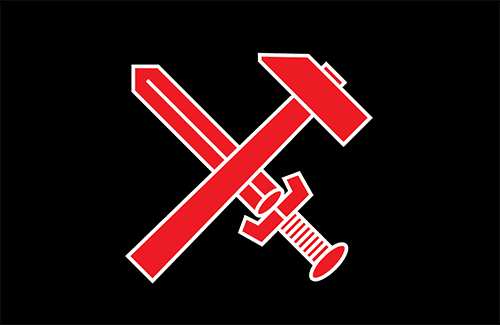
もっとも党内には突撃隊(SA)をはじめとして未だ多くのシュトラッサー兄弟に同情的な部分が存在し、ヒトラーは政権掌握後のいわゆるSAの粛清(隊長のレーム以下一千名余りを処刑、またこのどさくさにまぎれてグレゴールらも殺害した)まで苦しめられ続けることになる。
とりわけ党内に残った左派は、「ナチス労働者闘争団」を結成して一九三〇年のKPD指導下の労働者ストライキを積極的に支持し、あるいは同年十月の国会においては「一切の利子率を四分までに制限、銀行と株式取引の大立物、および東部のすべてのユダヤ人の全財産の無償没収、大銀行の国有化」を案として提出するなど、なお「社会主義」的闘争を展開したのである。(ちなみにこの政策案は、ヒトラーがおおあわてで撤回させたのちに、そっくりそのままKPDによって再提起された)
以上、われわれはナチ党左派の動向についてみてきたが、ナチの政権奪取そのものが「社会主義」の空洞化において成り立っていたにせよ、かかる「社会主義者」の奮闘こそが、ナチズムが知識人、文化人、あるいは労働者に浸透していく上で、非常に大きなエネルギーを発揮したことは否定すべくもないであろう。
とりわけ左派によって結成された「ナチス労働者闘争団」は三〇年以後急速に細胞数を増加させ、当初は技術労働者、官吏等が中心であったものが徐々に一般労働者をも組織するに至り、皮肉にも左派の屈服ののち、ナチが労働者をその配下に統制するための不可欠の要素となったのであった。
さらに若干付記するならば、これら左派の人々はヒトラーらの主張する血統的民族主義には概して冷淡であり、むしろ被抑圧民族のインターナショナルを志向していたとも言われ、ドイツの帝国主義的政策にはしばしば反対の意を表わにさえしたという。
しかるにKPD、いやトロツキーをも含めて、コミュニストの側からこれらナチ党左派の主張に対する批判は1度たりとて行なわれたことはなかった。コミュニストが行なったのは、ヒトラーが大ブルジョアジーと結託していることの暴露と、ナチの主張は「すべてがデマゴギー」とするレッテル貼りばかりで、結局これらナチ党左派の主張する「社会主義」の虚構性は、何ら指摘されることがなかったのである。
それどころかKPDの政治主張が、ナチ党左派の主張と(それがデマゴギーでないとするなら)多くの共通点を有していたのであり、そもそもKPDの主張自体が真に社会主義といいうるのかどうか、甚だ疑問に充ちたものでしかなかったのであって、「デマだ」以外に批判のしようがなかったとも言える(この点に関してはⅢの(イ)を参照せよ)。そしてそこにこそ「ファシスト過小評価」の本質はあったのであるが、けだしこれでは敗北も必然的であったといえよう。
4)ナチの「擬似革命性」
われわれはこれまでナチズム=「国家社会主義」の「社会主義」の側面についてみてきたが、それではヒトラーらを中心とする「国家」の側面はどうであったろうか。
われわれはそこにも「みすごされてきたもの」を見てとることができる。
すなわちナチが主張した「国家主義」とは、翻えせば反ワイマール体制であり、ブルジョア民主主義、議会主義に対する真向からの挑戦であり、それ自身が「ラディカル」な様相を呈していたからである。
そもそも革命の挫折の後に大ブルジョアジーとSPDの妥協の産物として出発したワイマール体制は、第一次大戦の責任者が不明確なままに存在していたし、何よりも戦争への加担者であったSPD自身、官僚的自己保身に窮々とする有様であった。
こうした中で右翼がデッチ上げた「十一月の犯罪者」=ワイマールの使徒達こそが敗戦の責任者だとする主張は、他ならぬSPDの振る舞いによって一定の説得力をもったし、かかる中で反ヴェルサイユ=反ワイマールというシェ-マが成り立っていたのである。
さらにかの絶望的なインフレーシーンは、ワイマール首脳陣達の無能ぶりをさらけだすものとして結果し、(もっともブルジョアジーとSPDの妥協の産物たるワイマールが、インフレを打解する能力などもちあわせぬことは当然なのであるが)とりわけ倹約に勤め、質素な生活を本位としつつ、誠実な「愛国心」をもち続けてきた中間層、とりわけその下層の人々を絶望感の中にたたき込んだ。
一方何度も指摘する如く、これら没落する中間層に対してKPDが何ら有効な戦術を示さないことも手伝って、これらの層は行き場を失ない、新たな価値観を求めていた人々を、ワイマールに対する憎悪と共に、唯一の出口としてのドイツ・ロマン主義へと誘っていたのである。
かかる中で「栄光あるドイツ民族」の旗をうちふり、なおかつ「議会で無能なおしゃべりを続けているワイマールの売国奴をたたき出せ」と「ラディカル」に主張したナチの姿は、そもそも議会から閉め出されていたこれらの人々のもつ行動力=行き場のなくなったエネルギーを吸収するに充分だった。しかもそれは単に己れの利害のみでなく「ドイツ民族」の危機を救うという「利己主義」を超えた「正義性」によって支えられたが故に、大衆の積極的な政治的決起を生みだしえたのであった。
まさにナチは「国家主義・民族主義」の旗の下に、中間層大衆に徹底して依拠し、その主体的な決起を克ちとる絶妙ともいえる手腕を有していたといえよう。
さて(3)(4)を通じてわれわれは、ナテズム=「国家社会主義」を解剖しつつ、「みすごされてきたもの」を暴きたててきたが、ここで注意を促しておきたいのは、ナチズムはあくまでも「国家社会主義」としてとらえるべきであって、何かしら「国家主義」と「社会主義」を悟性的に切断してとらえてはならないということである。
ここまでは行論の関係上かかる手法を止むを得ずとしたまでであって現実にはナチ党両派がそれぞれ体現していったこれらの政治主張は、あるいは反発し、あるいは相互浸透しつつ、まさに総体としてナチズムというダイナミックな大衆運動を創出していたからである。
左派の屈服の後も、けっして「社会主義」的側面が全面的に消滅したわけではないし、あるいはヒトラーにすれば、資本家との結託はあくまでもその利用として、いわば上からの関わりとしてなされたのであった(その意味では、ヒトラー個人からナチを解釈せんとする試みは当然にも排されねばならない)。
そしていずれにせよそれらは、「現体制」の変革を「ラディカル 」に主張し、しかも変革の主体を大衆においていたことがおさえられねばならない。まさにこの「ラディカル」な側面、西川正雄氏の規定にしたがうならば「擬似革命性」といいうるものこそ、ナチズムの原動力となっていたのである。
以上によりわれわれは「みすごされてきたものは何か」という問いに対する一定の結論を提起することができるだろう。
すなわちコミンテルン―KPDが、あるいはトロツキーが、否、今もってなお「みすごされて」いるものこそ、かかるナチズムの「擬似革命性」の本質は何か、という点にあるということである。
そしてその解明は、単に政治主張のレべルにとどまらず、思想的な問題としてなされねばならない。このことを踏まえた上で、われわれはいよいよ本章の核心であるファシズムの思想的解明に立ち向かおう。
[Sponsor Ad]
ハ.思想としてのファシズム
1)「擬似革命性」の本質とは
今日、ファシズムが掲げた唯一のイデオロギーが「全体主義」と呼称されるものであったことは周知の事実となっている。
ところがこの「全体主義」は、多くの場合、系統的な体系を有していなかったことや、あるいは全く非合理的な血統主義等によって粉飾されていたため、いや何より多くの者がこの思想にとりつかれたという事実を忘れよう忘れようという作業しかなされてこなかったために、思想的な考察の対象として措定する作業がなされてこなかった。
そもそも「擬似革命性」すらが「みすごされてきた」ことを考えるとき、その根拠としてある「全体主義」思想が、一笑に付すべき対象として扱われてきたことも、いわば必然といいうるだろう。しかしこの「全体主義」こそがファシズムの原動力となり、なおかつ一九二〇~三〇年代の共産主義運動にうち克ったものに他ならないのである。
別の言い方をすれば一九二〇~三〇年代の敗北の要因とは、現象的には「擬似革命性」への「過小評価」として、そしてより本質的には「全体主義」に対するイデオロギー的敗北としてあったことがおさえられねばならないのだ。
したがって「擬似革命性で蔽われたファシストの本性=反革命性を見失うな」とここで本論の帰結とすることもまた、われわれは慎重に回避する必要があるであろう。
何故ならば(このスローガン自身は全面的に正しいのであるが)そこでわれわれの考察を打ち切ってしまうならば、「擬似革命性」=「反革命のマヌバー」=「デマゴギー」という域をけっしてでることはなく、結局「擬似革命性」そのものにメスが入れることができないからである。
重要なことは、「擬似革命性」のイデオロギー的根拠を分析し解体し、もって国際共産主義運動のイデオロギー的陥穽をも揚棄していくことにこそあるのだ。
われわれは、あまりにも同じことの重複にばかり陥っているという指摘を免れぬやも知れぬが、しかしあくまでもこの一点にこそ一切合財がかかっていることを主張しておきたい。
2)全体主義とは何か
次に「全体主義」の解明に移ろう。そもそも「全体主義」とは一体何なのだろうか。
一言で述べるならばそれは―語義どうり―「個人主義」のアンチとして定立したものである。したがってそれは、ブルジョア個人主義、ブルジョア民主主義に対する直感的否定の変物として成立せるものに他ならない。
この場合、言うまでもなくブルジョア個人主義=近代個人主義とは、思想的にはデカルトの「我惟う、故に我在り(Cogito, ergo sum)」から出発し、政治的にはフランス大革命として表現された「自由、平等、博愛」を獲得する闘争としてあらわれたそれである。
さらにより本質的には、中世封建社会に対して資本家的商品経済が浸透し、封建的紐帯=封建的共同体を内部的に解体することをもって、封建制の成員としてのみ存在していた諸個人を、等価値交換の主体におきかえ、アトム化していく過程を通じて不可避的に生じたものに他ならない。
したがってかかる下部構造的変革によって形成されてくる諸個人の意識は、「自由競争」の原理に根ざした個人の利己心の追及=貨幣の蓄積へとむかい、それ故自己以外の他在あるいは己れの身体までもが、おしなべて資本の価値増殖の単なる手段として立ちあらわれてくるとともに、国家ないし社会とは、これら諸個人の代数的総和として、換言すれば諸個人の経済的営為を保障する風袋としてのみ登場するのである。
そしてまた、このようにして形成されるブルジョア的生産諸関係は、諸個人にとっては「倒錯せる物の世界」=「物による諸個人の支配」として感性的に把握されるとともに、かかる「物の世界」に対する直感的な否定や反発の意識が生じる(いわゆるニヒリズム、ぺシミズム、あるいは坊主主義、絶対者願望などはここから生まれてくる)。
そしてまさにこれらの意識=直感的反発を吸収し、なおかつ単なるニヒリズムにとどまらず、 非合理主義的な 「生の哲学」よって裏打ちされることによって、崩壊せる「共同体」を再構築せんとするものこそ、全体主義のイデオロギー的原泉に他ならない。
すなわちブルジョア社会の思想的原理であるブルジョア個人主義、近代合理主義、そしてまた政治的原理であるブルジョア民主主義と代議制議会主義に対して、全体=国家・民族を対置し、もってこれを「超克」せんとするもの、それこそが「全体主義」の本質に他ならないのである。
したがってまたこの全体主義イデオロギーの主張する核心点は、第一に「個」の利益に対する「全体」=国家・民族の利益を優先し、「個」の「全体」に対する無条件の献身ないし服従を要求することにある。たとえば、今日右翼ファシスト共が「戦後民主主義の中で、国民はたくさんの利益を得た。しかし権利の主張ばかり相変わらず続き、国家への義務がなおざりにされている」と叫ぶのはその好例といえよう。
そして第二に『生の哲学』に立脚した「全体」の存続のための対外侵略の肯定(たとえばナチ党綱領第三条=「過剰人口の移住のために領土と土地を要求する」等々)、すなわち「全体」に対する他在としての他国家、他民族との積極的な闘争の主張がそれである。
さらに第三に(第一の点とも関連するわけだが)単に現にある国家・民族の防衛にとどまらず。土着のエトスとして存在せる「崩壊した民族共同体」の再構築を目指すことである。たとえば、ナチがドイツロマン主義に立脚し、神聖ローマ帝国を継承するものとして「ドイツ第三帝国」の構築を主張したことなどがそれである。したがってそれはまた、それぞれ個々の民族の特性に根ざしたものであり、「ところ変われば品変わる」ということもおさえておく必要があるだろう。
以上が「全体主義」のガイストである。次はようやく俎上にのった「全体主義」を解体していこう!
3)全体主義と資本の論理
ブルジョア社会を上から下まで貫く「近代主義」「個人主義」への直感的な否定から、これを「超克」するものとして主張されたものが全体主義であった。
一方で周知の如くマルクスもまた、前述したブルジョア社会=倒錯せる物の世界に対する直感的否定から出発した。それもけっして「近代主義」の最先端からではなく、ドイツ・ロマン主義を跳躍台としつつ「ヒューマニズム」をパトスとして彼の歩みは開始されたのである。
こうして生みだされたものが『ヘーゲル法哲学批判序説』『ユダヤ人問題によせて』等々一連の著作であることは言をまたない。さらにマルクスは『経済学=哲学草稿』による「疎外された労働」をへて、『ドイツ・イデオロギー』において、その哲学的世界観を確立するにいたるのである。
それではマルクスは「個」と「全体(類)」の関係をいかにとらえようとしたのだろうか。
この点に関する若きマルクスの主張の核心、それを文字通り一言で言うならば「個即類」ということである。すなわちマルクスは、そもそも個と類を慢性的に分離する思考方法そのものを排し、まさに個と類の統一を目指したのである。
それでは「類」とは何なのか、「社会」とは何なのか、マルクスはかく語る。「社会は諸個人から成り立っているのではない。社会とはこれら諸個人が相互にかかわり合っている諸関連、諸関係の総体としてあるのだ。」(「経済学批判要綱」)
かかる視座を確立した上で、マルクスは経済学をメスとして近代市民社会=ブルジョア社会を解剖し、それが資本の論理に貫抜かれたゲゼルシャフトに他ならないことを暴露しつつ、これの揚棄としての高次のゲマインシャフト=共産主義社会の実現を主張したのであった。
それではこれに対して全体主義はどうであったろうか。
このイデオロギーがブルジョア個人主義の直感的否定そのものとして定立していることは、先にもみた通りであるが、この際「個」に先立つものとして主張されている「全体」とは、まさに「全体なるもの」(ホッブスのリバイアサンてはないが)あたかもそれ自身として生命を有し、何かしら自存的な形象物として存在せるものの如くとらえられているのである。それ故この「全体」=国家・民族は神秘主義的なヴェールにくるまれた、それこそ「神聖ニシテ犯ス可カラザル」ものとして登場する。
しかし(マルクスが正しくも指摘した如く)社会ないし国家が、諸個人の総和として存立するものではないことと全く同様に、「国家なるもの」、「社会なるもの」が存在しているわけではけっしてないのであり、それはあくまでも「諸個人の諸関係の総体」として存在するものに他ならないのである。
したがって、いくら「国家」「民族」なるものを神妙な顔をしてふりまわしたにせよ、現存するそれら「諸個人の諸関係」が資本家的商品経済として存在している以上、それは資本の論理に根ざしたゲゼルシャフトであり、けっして全体主義が(主観的には)目指す、ゲマインシャフト=民族共同体などでは存在しえないのだ。
同時にまた資本家的商品経済が世界市場を媒介として存在する以上、(孤立した原始共産制社会ならいざ知らず)そもそも民族=種族が主体となった共同体などありえよう筈がないのである。
しかるに全体主義は、虚構の「全体」をかかげつつ、ゲゼルシャフトでしかないそれをゲマインシャフトとして主張ないし錯覚しているために、結局は資本の論理に我知らずからめとられ、挙句の果てには「個人に対する全体の優位」を唱えつつ、実は彼らにとっても最も愛すべき筈であるところの「国民」「民族」を資本の論理=支配階級の利害のために、その祭壇へと献上してしまうものが全体主義なのである。
まさに「地獄への道は善意で敷きつめられている」という言葉は、全体主義の熱烈な信奉者のためにあるのだ!
4)国家社会主義の本質とは何か
次にわれわれは、主観的にはブルジョア個人主義故の苦悩の「超克」を目指しつつも、資本の論理の忠実な下僕として登場した全体主義がふりかざした「国家社会主義」の旗の本質についてみていこう。
結論を先んじて述べるならば、資本の論理をポールとしたこの旗に刻まれているのは、「国家社会主義」ではなく実は「国家独占資本主義」の八字に他ならないということである。要するにそもそも資本主義社会の根底的な揚棄なくして主張された「社会主義化」とは、つまるところ国家独占資本主義の基礎づけに帰するものでしかなかったのだ。
周知の如く、第一次世界大戦とその渦中に勝ちとられたロシア革命、及びそれが全世界にもたらした激励は、資本主義をして、その体制の大幅な変更を余儀なくさせた。
それこそ国家権力の経済過程への介入、したがって経済外的強制をもってしての有効需要の創出を通じた予防反革命=恐慌の回避、ないしは恐慌からの自動回復をまたない、強制的“回復”の画策を本質とする、国家独占資本主義の登場に他ならない。
それは金融資本主義段階=帝国主義段階に突入した資本主義が、固定資本の増大やカルテル等々の出現による価値法則、人口法則の錯乱、あるいは利潤率均等化法則の未貫徹などを通じつつ、自らの存続のために不可避的に生みだしえた傾向といいうるかもしれない。
それはともあれ(国独資の本質規定は他稿に譲るとして)いずれにせよ何らかの形で国家が経済界に介入するという事態は、資本家階級を総体として防衛するものとしてあったにもかかわらず、帝国主義段階に至っても未だに自由競争の理念を信じ、チープガバメント(小さな政府)を理想としていた資本家達によって猛烈な反発をうけたのであった。
そもそも自らを資本家階級の一員として認識するどころか、常に生存競争にあけくれている資本家共にとってみればそれも当然といえようか。
たとえば今日、国独資政策の指標として名高いアメリカのニューディール政策にしろ、いわゆる「ケインズ革命」にしろ、当初は憎悪をもってむかえられたのである。
それどころか、資本の部分的国有化をも含む国独資政策は、資本家共にとってはまさに「ボリシェヴィズム」が押しよせてきた、とさえみえたし、その意味で「社会主義」的政策としてそれは受けとめられたのであった。
それでは「国家社会主義」の信奉者=ファシストの側はどうであったろうか。
これまで通りドイツを例にとるならば、彼らにとって、絶望的なインフレーションや仏・ベルギーによるルール地方の占領という「国家的民族的危機」の中で、その責任の一端を担っているものこそ、奸商=悪どい大資本家達(それはまた「良い資本家」と対概念であることに留意せよ)なのであった。
したがってこれらに対して「利子奴隷制の打破」(ナチ党綱領第十一条)を要求し、「トラストの国有化」(同十二条)を実現し、「もって健全なる中産等族を創設してこれを維持する」(同十六条)ものこそが「社会主義」としてうちだされていたのである。
しかしながらかかる諸要求こそ(資本主義の根底的揚棄なしにゲゼルシャフトリッヒな関係をそのままに提起されたことを考えるとき)まさに国独資政策に合致したものであり、ファシストや資本家共の主観からさえもはずれながら、まさしく資本家階級を防衛するものであった。
ただここで留意を促しておきたいのは、ファシズムの主張が客観的には国独資を基礎づけるものであったにせよ、ファシズム=国独資とすることはできないということである。
たとえばニューディール政策を(資本家共の怨念も手伝ってか)アメリカのファシズムの現れとみる傾向すらあるようだが、ファシズム、あるいは全体主義が国独資に対応するイデオロギーであるにせよ、両者はあくまでも明確に分けて論じられねばならない。
何故ならばファシズムの原動力とは、近代に対する直感的否定の意識にあるのであり、これを推進力として結果的に国独資へと帰結するところに「国家社会主義」の本質はあるからである。
これに対してニュディール政策はかかるエネルギーの介在をみることができない。
それは第二次大戦を前にしてブルジョア自由主義の守護者として己れを体現したアメリカ帝国主義が、まさにそれ故参戦意識をなかなか創出しえず、日帝によるパールハーバー奇襲を事前に察知しながらこれを容認し「Remember PearlHarbor」というスローガンの下に人民を戦争に動員するという苦肉の策に出ざるをえなかったことなどに、最もよく表現されているといえよう。
よもやケインズをファシストの頭目と考えるむきもないと思うが、この点を見失ってしまえば、われわれはふり出しにもどりかねないのである。
それはともあれ、われわれはついにファシズムのイデオロギー的本質を解体するに至ったことを確認できるだろう。
これをステップとしつつ、漸く一九二〇~三〇年代の敗北の真の総括と、それに基いて現代におけるファシズムとの闘いを、戦略論的に明らかにするものこそが次章=本稿の終章の課題に他ならない。
[Sponsor Ad]
ニ.体制としてのファシズム

本章においてわれわれは、「みすごされてきたものは何か」という問を発しつつ、「ファシズムとは何か」ということを追求してきた。よってわれわれは次章に移る前に、この問の答を完結させておく必要があるであろう。
しかしここで目指すものは社会科学的概念規定としてファシズムを明確化させることではない。何故ならば、再三再四指摘してきた如く、運動主体としてのわれわれにとってのファシズム論とは、一九二〇~三〇年代の主体的総括としてあるからであり、とりわけそのための方法論序説たる本稿においては、敗北の要因と、その揚棄の方向性を充たしうるものさえ把握できれば、一応はそれで事たりるからである。そしてそのための鍵は既にこれまでの作業を通じてわれわれの手中にされるに至った。
すなわち本来なら変革の隊列に参加しうる小ブル大衆ないしプロレタリアートを、支配者たる資本の論理に帰存させるイデオロギー、及びそれに基いた運動として、われわれは「ファシズムとは何か」という問に対する一応の解答とするのである。
無論われわれは、けっして社会科学的概念規定としてファシズムを明確化する作業がわれわれの闘いの役に立たないなどとは言わないが、むしろかかる点に関しては学者諸君の答を待つとすることにして、ここではあくまでも行論の必要上に限って、不十分な点を補っておきたい。
われわれはこれまで、もっぱらナチを中心に扱ってきたが、それがあくまでもファシズムのドイツ的形態としてあることは指摘するまでもないだろう。
しかも、ことドイツに限ってみたにせよ、ナチズムのみをファシズムとして捉えることはできない、というのはファシズムの本質が資本の論理にからめとられるものである以上、まさに資本の側からの策動と合致するとき、ファシズムは体制としての完結をみるのだからである。
すなわち多かれ少なかれ「上からのファッショ化と下からのファッショ化の結合」(丸山真男)としてそれは成立するのであり、再び西川正雄氏の規定を援用するならば「権威主義的反動」と「擬似革命性」の結合によってこそファシズム体制は確立するのである。
たとえばドイツ、イタリア、オーストリア等々においてはいうまでもなく下からのファッショ化が主動となったのに対し、日本、ポーランドなどは上からのファッショ化が主動となった。
とりわけ日本の場合、そもそも近代市民社会がまだ確立しえず、封建的様相を多くもちあわせていたために、いわば上からのなし崩し的なファッショ化が進行しえたのであった。「擬似革命派」としてあった、北一輝らを中心とする「皇道派」は、基本的には二・二六事件後の粛清によって潰滅したが、かかる「皇道派」の行動が、日帝のアジア侵略の引金となったことは今日よくしられるところである。
ただし「皇道派」に対する「統制派」が「権威主義的反動」の本隊としてあったわけではなく、むしろ中間派的なものとしてその存在はとらえうるであろう。いずれにせよ日本型ファシズムに関しては、早急に研究の深化をなさねばならないだろう。
以上のことを補足して、本章を閉じるものとする。




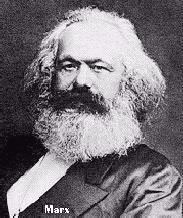


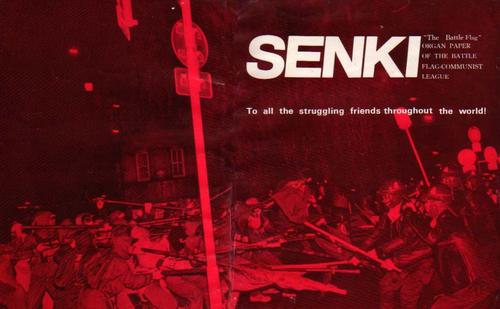















この記事への質問・一言コメントをどうぞ AIコースケと議論しよう!
回答には文字数制限があるため、制限を超えると途中で打ち切られることがあります。