本作の一部には差別的な表現、または戦争やファシズムを支えるイデオロギーを宣伝する表現など、今日の常識からみれば明らかに不適切な表現が含まれている箇所があります。 その旨をここに記載した上、作品公開時の時代的な限界性を読者自身が認識し学ぶ意義も考慮し、今日では使われない歴史上の言葉として、原作のままの形で作品を公開しています。ご了承ください。
七

お宮のいちょうが黄色になればあぜにはすすき、水引き、たでの花、露草などが薄日をたよりにさきみだれて、その下をゆくちょろちょろ水の音に秋が深くなりゆく。
役場の火事については町の人はなにもいわなくなった、阪井猛太は助役をやめてせがれの巌と共に川越の方へうつった、中学校には新しい校長がきた。浦和の町は太平である。
チビ公はやはり一日も休まずに豆腐を売りまわった、それでも一家のまずしさは以前とかわりがなかった、かれは毎日らっぱをふいて町々を歩いているうちにいくどとなく昔の小学校友達にあうのである、中には光一のようにやさしい言葉をかけてくれるものもあるが、多くは顔をそむけて通るのである。チビ公としても先方の体面をはばかってそしらぬ顔をせねばならぬこともあった。
とくにかれの心を悲しませるものは小学校時代にいつも先生にしかられていた不成績の子が、りっぱな中学生の服装で雑嚢(ざつのう)を肩にかけ徽章のついた帽子を輝かして行くのを見たときである。
「金持ちの家に生まれれば出来ない子でも大学までいける、貧乏人の子は学校へもいけない、かれらが学士になり博士になるときにもおれはやはり豆腐屋でいるだろう」
こう思うとなさけないような気が胸一ぱいになる。
「学校へいきたいな」
かれの帰り道は県庁の横手の小川の堤である、かれは堤の露草をふみふみぐったりと顔をたれて同じことをくりかえしくりかえし考えるのであった。
ときとしてかれは師範学校の裏手を通る、寄宿舎には灯影が並んでおりおりわかやかな唱歌の声が聞こえる。
「官費でいいから学校へゆきたい」
こうも考える、だがかれはすぐそれをうちけす。かれの目の前に伯父覚平の老顔がありありと見えるのである。
「おれが働かなきゃ、みなが食べていけない」
そこでかれは夕闇に残る西雲の微明に向かってらっぱをふく。らっぱの音は遠くの森にひびき、近くのわらやねに反響してわが胸に悲しい思いをうちかえす。
ある日伯父の覚平は突然かれにこういった。
「千三、おまえ学校へゆきたいだろうな」
「いいえ」とチビ公は答えた。
「おれだっておめえを豆腐屋にしたくないんだ、なあ千三、そのうちになんとかするから辛抱してくれ、そのかわりに夜学へいったらどうか、昼のつかれで眠たかろうが、一心にやればやれないこともなかろう」
「夜学にいってもいいんですか」
千三の目は喜びに輝いた。
「夜学だけならかまわないよ、お宮の近くに夜学の先生があるだろう」
「黙々先生ですか」
「うむ、かわり者だがなかなかえらい人だって評判だよ」
「こわいな」と千三は思わずいった。
黙々先生といえば本名の篠原浩蔵(しのはらこうぞう)をいわなくとも浦和の人はだれでも知っている。先生はいま五十五、六歳、まだ老人という歳でもないが、頭とひげは雪のように白くそれと共に左の眉に二寸ばかり長い毛が一本つきでている、おこるときにはこの長い毛が上に動き、わらうときには下にたれる、町の人はこの毛をもって先生の機嫌のバロメーターにしている。
先生の履歴について町の人はくわしく知らなかった、ある人はかつて文部省の参事官であったといい、ある人は地方の長官であったといい、ある人はまた馬賊の頭目であったともいう、真偽はわからぬがかれは熊谷(くまがや)の豪族の子孫であることだけはあきらかであり、また帝国大学初期の卒業者であることもあきらかである、なんのために官職を辞して浦和に帰臥(きが)したのか、それらの点についてはかれは一度も人に語ったことはない。
かれが浦和に帰ったのは十年前である、そのときは独身であったが人のすすめによって後妻を迎えた、だがかれは朝から晩まで家にあるときには読書ばかりしている、妻がなにをいっても「うんうん」とうなずくばかりでなにもいわない。で妻はかれに詰問した。
「あなたなにかいってください」
「うん」
「うんだけではいけません」
「うん」
「あなたはなにもおっしゃることがないんですか」
「うん」
「なにか用事があるでしょう」
「うん」
「ご飯はどうなさるの?」
「うん」
「めしあがらないんですか」
「うん」
妻はあきれて三日目に離縁した。かれはその小さな軒に英漢数教授という看板をだした。妻にものをいわない人だから生徒に対しても、ものをいわないだろうと人々はあやぶんだが、一旦講義にとりかかるとまったくそれと反対であった。
最初の一、二年は生徒が少なかったが、年を経るにしたがって次第に増加した。かれには月謝の制定がない、五円もあれば五十銭もある、米や豆やいもなどを持ってくるものもある、独身の先生だからだというので魚を贈る人がいたって少ない、そこで先生はおりおり一竿(かん)を肩にして河へつりにゆく、一尾のふなもつれないときには町で魚を買ってそのあぎとをはりにつらぬき揚々として肩に荷うて帰る、ときにはあじ、ときにはいわし、時にはたこ、ときには塩ざけの切り身!
「先生! つれましたか?」と人が問えば先生は軽く答える。
「うん」
「はりにひっかかってるのはかまぼこじゃありませんか」
「かまぼこは魚なり」
千三は子どものときからなんとなく黙々先生がこわかった。しかしかれとして学問をするにはこの私塾より他にはない。
翌日千三は夕飯をすまして黙々先生をたずねた、そこにはもう五、六の学生がいた、それは中学の二年生もあれば五年生もあり、またひげの生えた人もあり、百姓もあれば商家のでっちもある。千三がはいったときちょうど小学校の教師がむずかしい漢文を読んでいた。
「いかんいかん」と先生はどなった。「もっと声を大きくして漢文は朗々として吟ずべきものだ、語尾をはっきりせんのは心が臆しているからだ、聖賢の書を読むになんのやましいところがある、この家がこわれるような声で読め」
教師はまっかな顔をして大きな声で読んだ、先生はだまって聞いていた。
「よしっ、きみは子弟を教育するんだ、とかくに今日の学校は朗読法をないがしろにするきらいがある、大切なことだぜ」
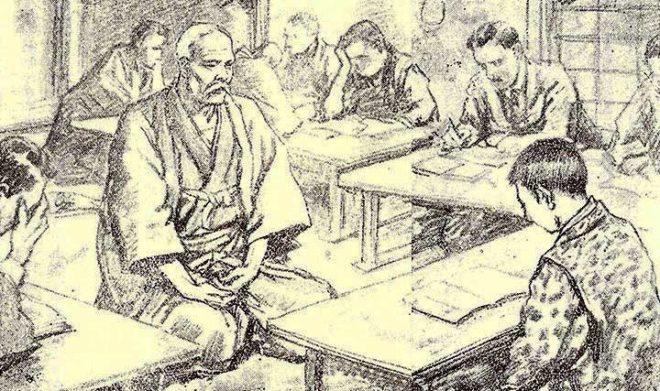
先生はひょろ長いやせた首を伸ばして末座にちぢまっている千三を見おろした。
「きみ、ここへきたまえ」
「はあ」
「きみの名は?」
「青木千三です」
「うむ、なにをやるか」
「英漢数です」
「よしッ、これを読んでみい」
先生は一冊の本を千三の前へ投げだした。それは黒茶色の表紙の着いた日本とじであった。標箋(ひょうせん)に大学と書いてある。
「これをですか」
千三は中学校一、二年生の国語漢文読本をおそわるつもりであった、いま大学という書を見て急におどろいた。大学という本の名を知ったのもはじめてである。
「うむ」
「どこを読むのですか」
「どこでもいい」
千三は中をひらいた。むずかしい漢字が並んだばかりでどう読んでいいのかわからない。
「読めません」とかれはいった。
「読める字だけ読め」
「湯(ゆ)……曰(いわく)……日(ひ)……新(しん)……日(ひ)……日(ひ)……新(しん)又(また)日(ひ)新(しん)」
千三は読める字だけを読んだ、汗がひたいににじんで胸が波のごとくおどる。
「よし、よく読んだ」と先生は微笑して、「その意味はなんだ」
「わかりません」
「考えてみい」
千三は考えこんだ。
「これは毎日毎日お湯へはいって新しくなれというのでしょう」
「えらい!」
先生は思わず叫んだ、そうして千三の顔をじっと見つめながら読みくだした。
「湯(とう)の盤(ばん)の銘(めい)に曰(いわ)く、まことに日に新たにせば日々に新たにし又日に新たにせん……こう読むのだ」
「はあ」
「湯はお湯でない、王様の名だ、盤はたらいだ、たらいに格言をほりつけたのだ、人間は毎日顔を洗い口をすすいでわが身を新たにするごとく、その心をも毎日毎日洗いきよめて新たな気持ちにならなければならん、とこういうのだ、だがきみの解釈は字句において間違いがあるが大体の意義において間違いはない、書を読むに文字を読むものがある、そんなやつは帳面づけや詩人などになるがいい。また文字に拘泥せずにその大意をにぎる人がある、それが本当の活眼をもって活書を読むものだ、よいか、文字を知らないのは決して恥でない、意味を知らないのが恥辱だぞ」
こういって先生はつぎの少年に向かった。
「日本の歴史中に悪い人物はたれか」
いろいろな声が一度にでた。
「弓削道鏡です」
「蘇我入鹿です」
「足利尊氏です」
「源頼朝です」
「頼朝はどうして悪いか」と先生が口をいれた。
「武力をもって皇室の大権をおかしました」
「うん、それから」
武田信玄というものがある。
「信玄はどうして」
「親を幽閉して国をうばいました」
「うん」
「徳川家康!」
「どうして?」
「皇室に無礼を働きました」
「うん、それで、きみらはなにをもって悪い人物、よい人物を区別するか」
「君には不忠、親に不孝なるものは、他にどんなよいことをしても悪い人物です、忠孝の士は他に欠点があってもよい人物です」
「よしッ、それでよい」先生は、いかにも快然といった。
先生の教えるところはつねにこういう風なのであった、先生はどんな事件に対してもかならずはっきりした判断をさせるのであった、たとえそれが間違いであっても、それを臆面なく告白すれば先生が喜ぶ。
千三はその日から毎夜先生のもとへ通うた、先生はまた地理と歴史の関係をもっとも精密に教えてくれた、それは普通の中学校ではきわめてゆるがせにしていることであった、中学校では地理の先生と歴史の先生とべつな人であるのが多い、そのために密接な二つの関係が分離されてしまうが、黙々先生は歴史の進行とともに地理を展開させた、神武以来大和は発祥の地になっている、そこで先生は大和の地理を教える、同時に大和に活躍した人物の伝記や逸話等を教える。学生の頭にはその人とその地とその時代が深くきざまれる。
先生は代数や幾何を教えるにもすべてその方法で、決してまわりくどい術語を用いたり、強いて頭を混惑させるような問題を提供したりしなかった。その英語のごときもいちいち漢文の文法と対照した、そのために生徒は英漢の文法を一度に知ることができた。
先生はいかなる場合にも虚偽と臆病をきらった。臆病は虚偽の基である、かれは講義をなしつつあるあいだに突然こういうときがある。
「眠い人があるか」
「あります」と千三が手をあげた。
「庭に出て水をあびてこい」
先生は千三の正直が気にいった。
冬がきた、正月も間近になる、せめて母に新しく綿のはいったもの一枚でも着せてやりたい、こういう考えから千三は一生懸命に働いた、しかも通学は一晩も休まなかった、かれは先生の家をでるとすぐぐらぐら眠りながら家へ帰る夜が多かった。
と、災厄はつぎからつぎへと起こる、ある夜かれが家へ帰ると母が麻糸つなぎをやっていた、いくらにもならないのだが、彼女はいくらかでも働かねば正月を迎えることができないのであった。
「ただいま」
千三は勢いよく声をかけた。
「お帰り、寒かったろう」と母は火鉢の火をかきたてた、灰の中にはわずかにほたるのような光が見えた、外はひゅうひゅう風がうなっている。
「寒いなあ」と千三は思わずいった。
「お待ちよ。いま消し炭を持ってくるから」
母は麻糸をかたよせてたとうとした。
「おや」
母は立てなかった。
「おや」
母はふたたびいって立とうとしたが顔がさっと青くなって後ろに倒れた。
「お母さん」
千三はだき起こそうとした。母の目は上の方へつった。
「お母さん」
声におどろいて伯父夫婦が起きてきた。千三は早速手塚医師のもとへかけつけた。元来かれは手塚のもとへいくのを好まなかった、しかし火急の場合、他へ走ることもできなかった。

粉雪まじりの師走の風が電線にうなっていた、町はもう寝しずまって、風呂屋から流れてくる下水の湯気がどぶ板のすきまから、もやもやといてついた地面をはっていた。
「今晩は……今晩は……」
千三は手塚の門をたたいた。
音がない。
「今晩は!」
かれは声をかぎりに呼び力をかぎりにたたいた。奥にはまだ人の声がする。
「どうしたんだろう」
千三は手塚なる医者が金持ちには幇間(ほうかん)のごとくちやほやするが、貧乏人にはきわめて冷淡だという人のうわさを思いだした、それと同時にこの深夜に来診を請うと、ずいぶん少なからぬお礼をださねばなるまいが、それもできずにむやみと門をたたくのはいかにも厚かましいことだと考えたりした。
やっとのことで書生の声がした。
「どなた?」
「豆腐屋の青木ですが、母が急病ですからどうかちょっとおいでを願いたいんです」
「はああ――」とみょうに気のぬけた返事が聞こえた。「豆腐屋の……青木?」
「はい」
「先生は風邪気(かぜけ)でおやすみですから……どうですかうかがってみましょう」
「どうぞお願いします、急病ですから」
千三は暗い門前でしずかに耳をそばだてた、奥で碁石をくずす音がちゃらちゃらと聞こえる。
「なんだ、碁を打ってるのにおやすみだなんて」
こう千三は思った。とふたたび小さな窓が開いた。
「ただいま伺います」
「ありがとうございます」と千三は思わず大きな声でいった。
「どうぞ、よろしく、ありがとうございます」
千三は一足先に家へ帰った、母はまだ正体がない。
「冷えたんだから足をあたためるがいい」
こう伯父がいった。伯母はただうろうろして仏壇に灯をともしたりしている、千三はすぐ火をおこしかけた。そこへ車の音がした。
「どうもごくろうさまで……どうぞ」
くぐりの戸をはいってきたのは手塚医師でなくて代診の森という男である。この森というのは、ずいぶん古くから手塚の薬局にいるが、代診として患者を往診した事はきわめてまれである、千三はいつも森が白い薬局服を着て往来でキャッチボールをやってるのを見ているのではなはだおぼつかなく思った。
「先生が風邪気(かぜけ)なんで……」
森はこういってずんずん奥へあがりこんだ、かれはその外套と帽子を車夫にわたした、それから眼鏡をちょっと鼻の上へせりあげて病人を見やった。
「どんなに悪いんですか、ああん?」
かれはお美代の腕をとって脈をしらべた。それから発病の模様を聞きながら聴診器を胸にあてたり、眼瞼(まぶた)をひっくりかえしてみたりした、その態度はいかにもおちつきはらっている。これがおりおり玄関で手塚と腕押しをしたりしゃちほこ立ちをしたり、近所の子どもをからかったりする人とは思えない。門口で車夫がしきりにせきばらいをしている、それは「寒くてたまらないからいい加減にして帰ってくれ」というかのごとく見えた。
「はあん……これは脳貧血ですな、ああん、たいしたことはありません、頭寒足熱ですかな、足をあたためて頭をひやして安眠させるといいです、ああん、薬は散薬と水薬……ああん、すぐでよろしい」
かれはこういって先生から借りて来た鞄を取り上げて室(へや)を出た。
「おい、幸吉!」
幸吉とは車夫の名である、かれはいつも朝と晩に尻はしょりをして幸吉とふたりで門前に水をまいているのである。書生と車夫は同じくこれ奉公人仲間、いわば同階級である。それがいま傲然と呼び捨てにされたので幸吉たるもの胸中いささかおだやかでない、かれはだまって答えなかった。
「おい幸吉! なにをしとるかッ、ああん」
「早くゆきましょうよ森さん」と幸吉は業腹まぎれにいった。
「こらッ外套と帽子をおくれ、ああん」
森は外へ出た、車の走る音が聞こえた、寒さは寒し不平は不平なり、おそらく幸吉、車もくつがえれとばかり走ったことであろう。
車におくれじと千三も走った、かれが医者の玄関に着いたとき、奥ではやはり囲碁の音が聞こえていた。
母の病状はそれ以上に進まなかった。が、さりとて床をでることはできなかった。
「明日になったら起きられるだろう」
こう母はいった、だが翌日も起きられなかった。病弱な彼女が寒さをおかして毎日毎夜内職を働いたその疲れがつもりつもって脳(のう)におよんだのである。千三は豆腐をかついで町まわりの帰りしなに手塚の家へよって薬をもらうのであった、最初薬は二日分ずつであったが、母のお美代はそれをこばんだ。
「じきになおるから、一日分ずつでいい、二日分もらっても無駄になるから」
これはいかにも道理ある言葉であった、どういうわけか医者は二日分ずつの薬をくれる、それも一つはかならず胃の薬である、金持ちの家は薬代にも困らぬが、まずしき家では一日分の薬価は一日分の米代に相当する。お美代は毎日薬を飲むたびにもったいないといった。
ある日千三は帰って母にこういった。
「お母さん、手塚の家の天井は格子になって一つ一つに絵を貼ってあります、絹にかいたきれいな絵!」
「あれを見たかえ」と母は病いにおとろえた目を向けてさびしくいった。「あれは応接室だったんです、お父さんが支那風が好きだったから」
「そう?」
「あの隣の室(へや)のもう一つ隣の室(へや)は茶室風でおまえがそこで生まれたのです、萩の天井です、床の間には……」
母の声はハタとやんだ、彼女は目をうっとりさせて昔その夫が世にありしときの全盛な生活を回想したのであった。
「あのときには女中が五人、書生が三人……」
睫毛(まつげ)を伝うて玉の露がほろりとこぼれる。
「お母さん!つまらないことをいうのはよしてください、ぼくはいまにあれ以上の家を建ててあげます」
「そうそう、そうだね」
母はさびしくわらった、千三はたまらなく苦しくなった、いままで胸の底におさえつけておいた憂欝がむらむらと雲のごとくわいた。かれは薬をもらいに医者の家へゆく、支那風の天井の下に小さく座っていると例の憂欝がひしひしとせまってくる。
「ああここがおれの生まれたところなんだ、おれが生まれたときに手塚の親父がぺこぺこ頭をさげて見舞いにきたんだ、それがいまそいつに占領されてあべこべにおれの方が頭をさげて薬をもらいにきてる」
ある日かれはこんなことを考えながら門をはいろうとするとそこで代診森君が手塚とキャッチボールをしていた。
「そらこんどはドロップだぞ」
手塚は得意になって球をにぎりかえてモーションをつけた。
「よしきた」
森君はへっぴり腰になって片足を浮かしてかまえた、もし足にあたりそうな球がきたら片足をあげて逃がそうという腹なのである。
「さあこい」
「よしッ」
球は大地をたたいて横の塀を打ちさらにおどりあがって千三の豆腐おけを打ち、ころころとどぶの方へころがった。
「おい豆腐屋! 早く球をとれよ」手塚がさけんだ。
「はッ」
千三はおけをかついだまま球をおっかけた、おけの水はだぶだぶと波をおどらして蓋も包丁も大地に落ちた。
「やあやあ勇敢勇敢」と森君は喝采した、千三は球が石のどぶ端を伝って泥の中へ落ちこもうとするやつをやっとおさえようとした、てんびん棒が土塀にがたんとつきあたったと思うとかれははねかえされて豆腐おけもろとも尻餅(しりもち)をついた。豆腐は魚の如くはねて地上に散った。
「ばかだね、おけを置いて走ればいいんだ、ばかッ」
手塚はこういって自分でどぶどろの中から球をつまみあげ、いきなり千三のおけの中で球を洗った。
「それは困ります」と千三は訴えるようにいった。
「豆腐代を払ったら文句がないだろう」
手塚はわらって奥へひっこんだ。
「待てッ」と千三は呼(よ)びとめようとしたがじっと下くちびるをかんだ。
「いま手塚と喧嘩をすれば母の薬をもらうことができなくなる」

かれの目から熱い涙がわきでた。人間の貴重な食料品! そのおけの中にどぶどろにまみれた球をつっこんで洗うなんてあまりの乱暴である。だが貧乏の悲しさ、かれと争うことはできない。
どれだけないたかしれない。かれはもうらっぱをふく力もなくなった。
「おれはだめだ」
かれはこう考えた、どんなに勉強してもやはり金持ちにはかなわない。
「おれと伯父さんは夜の目も寝ずに豆腐を作る、だがそれを食うものは金持ちだ、作ったおれ達の口にはいるのはそのあまりかすのおからだけだ、学問はやめよう」
かれはがっかりして家へ帰った、かれは黙々先生の夜学を休んで早く寝床にはいった。翌朝起きて町へでた。もうかれの考えは全然いままでとかわってしまった。かれは町々のりっぱな商店、会社、銀行それらを見るとそれがすべてのろわしきものとなった。
「あいつらは悪いことをして金をためていばってるんだ、あいつらはおれ達の血と汗をしぼり取る鬼共だ」
その夜も夜学を休んだ、その翌日も……。
「おれがチビだからみんながおれをばかにしてるんだ、おれが貧乏だからみんながおれをばかにしてるんだ」
かれの母はかれが夜学へもいかなくなったのを見て心配そうにたずねた。
「千三、おまえ今夜も休むの?」
「ああ」
「どうしてだ」
「ゆきたくないからゆきません」
かれの声はつっけんどんであった、母は悲しそうな目でかれを見やったなりなにもいわなかった、千三は夜具の中に首をつっこんでから心の中で母にあやまった。
「お母さん堪忍してください、ぼくは自分で自分をどうすることもできないのです」
このすさんだ心持ちが五日も六日もつづいた、とある日かれは夕日に向かってらっぱをふきもてゆくと突然かれの背後(うしろ)からよびとめるものがある。
「おい青木!」
夕方の町は人通りがひんぱんである、あまりに大きな声なので往来の人は立ちどまった。
「おい、青木!」
千三がふりかえるとそれは黙々先生であった、先生は肩につりざおを荷ない、片手に炭だわらをかかえている、たわらの底からいものしっぽがこぼれそうにぶらぶらしている。
「おい、君のおけの上にこれを載せてくれ」
千三はだまって一礼した。先生は炭だわらをおけの上に載せ、そのまま自分の肩を入れて歩きだした。
「先生! ぼくがかついでお宅まで持ってゆきます」
と千三がいった。
「いやかまわん、おれについてこい」
ひょろ長い先生のおけをかついだ影法師が夕日にかっきりと地上に映った。
「きみは病気か」
「いいえ」
「どうしてこない?」
「なんだかいやになりました」
「そうか」
先生はそれについてなにもいわなかった。
黙々先生がいもだわらを載せた豆腐をにない、そのそばに豆腐屋のチビ公がついてゆくのを見て町の人々はみんな笑いだした。ふたりは黙々塾へ着いた。
「はいれ」と先生はてんびんをおろしてからいった。
「はい」
もう日が暮れかけて家の中は薄暗かった、千三はわらじをぬいで縁端(えんばた)に座った。先生はだまって七輪を取りだし、それに粉炭をくべてなべをかけ、七、八本のいもをそのままほうりこんだ。
「洗ってまいりましょうか」
「洗わんほうがうまいぞ」
こういってから先生はふたたび立って書棚を探したがやがて二、三枚の紙つづりを千三の前においた。
「おい、これを見い、わしはきみに見せようと思って書いておいたのだ」
「なんですか」
「きみの先祖からの由緒書きだ」
「はあ」
千三は由緒書きなるものはなんであるかを知らなかった、でかれはそれをひらいた。
「村上天皇の皇子(おうじ)中務卿(なかつかさきょう)具平親王(ともひらしんのう)」
千三は最初の一段高く記した一行を読んでびっくりした。
「先生なんですか、これは」
「あとを読め」
「右大臣師房卿(もろふさきょう)――後一条天皇のときはじめて源朝臣(みなもとあそん)の姓を賜わる」
「へんなものですね」
先生は七輪の火をふいたので火の粉がぱちぱちと散った。
「――雅家(まさいえ)、北畠(きたばたけ)と号す――北畠親房(きたばたけちかふさ)その子顕家(あきいえ)、顕信(あきのぶ)、顕能(あきよし)の三子と共に南朝無二の忠臣、楠公(なんこう)父子と比肩すべきもの、神皇正統記(じんのうしょうとうき)を著わして皇国の正統をあきらかにす」
「北畠親房(きたばたけちかふさ)を知ってるか」
「よくは知りません、歴史で少しばかり」
「日本第一の忠臣を知らんか、そのあとを読め」
「親房(ちかふさ)の第二子顕信(あきのぶ)の子守親(もりちか)、陸奥守に任ぜらる……その孫武蔵に住み相模(さがみ)扇ヶ谷に転ず、上杉家に仕う、上杉家滅ぶるにおよび姓を扇に改め後青木に改む、……青木竜平――長男千三……チビ公と称す、懦弱(だじゃく)取るに足らず……」
なべのいもは湯気を立ててふたはおどりあがった。先生はじっと千三の顔を見つめた。
「どうだ」
「先生!」
「きみの父祖は南朝の忠臣だ、きみの血の中に祖先の血が活きてるはずだ、きみの精神のうちに祖先の魂が残ってるはずだ、君は選ばれたる国民だ、大切な身体だ、日本になくてはならない身体だ、そうは思わんか」
「先生!」
「なにもいうことはない、祖先の名をはずかしめないように奮発するか」
「先生」
「それとも生涯豆腐屋でくちはてるか」
「先生! 私は……」
「なにもいうな、さあいもを食ってから返事をしろ」
先生はいものなべをおろした、庭はすでに暮れて落ち葉がさらさらと鳴る、七輪の火が風に吹かれてぱっと燃えあがると白髪白髯(はくぜん)の黙々先生の顔とはりさけるようにすずしい目をみひらいた少年の赤い顔とが暗の中に浮きだして見える。


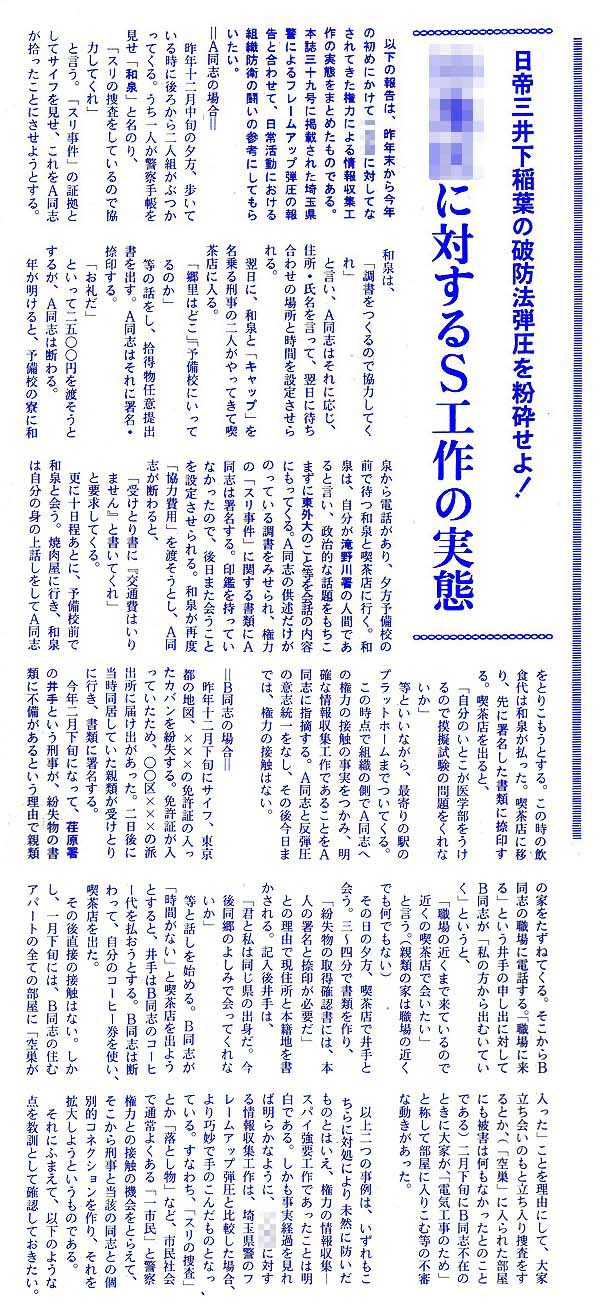












この記事への質問・一言コメントをどうぞ AIコースケと議論しよう!
回答には文字数制限があるため、制限を超えると途中で打ち切られることがあります。