六
小原捕手(こはらほしゅ)はいつもよりはやく目をさましそれから十杯のつるべ水を浴び心身をきよめてから屋根にあがって朝日をおがんだ。これはいかなる厳冬といえども一度も休んだことのないかれの日課である。冷水によって眠気と惰気(だき)とをはらい、さわやかな朝日をおがんで清新な英気を受ける。
だがこの日はいつもより悲しかった、全校生徒の歎願があったにかかわらず久保井校長の転任をひるがえすことができなかった。
今日は校長がいよいよ浦和を去る日である。
大急ぎで朝飯をすましかれはすぐ柳の家をたずねた、柳もまた小原をたずねようと家をでかけたところであった。
「いよいよだめだね」と柳はいった、平素温和なかれに似ずこの日はさっと顔を染めて一抹悲憤の気が顔にあふれていた。
「しかたがないよ」と小原はいった。ふたりは朝日の光が縦に流れる町を東に向かって歩いた。
「ところでね君」と小原はしばらくあっていった。
「今日の見送りだがね、もし生徒が軽々しくさわぎだすようなことがあると、校長先生がぼくらを扇動したと疑られるから、この点だけはどうしてもつつしまなきゃならんよ」
「ぼくもそう思ったからきみに相談しようと思ってでかけたんだ」
「そうか、そうか」と小原はおとならしくうなずいて、「一番猛烈なのは三年だからね、ぼくは昨夜もおそくまで歩きまわって説法したよ、二年は君にたのむよ、いいか、どうしてもわかれなきゃならないものならぼくらは静粛に校長を見送ろうじゃないか」
「ぼくもそう思うよ」
「じゃそのつもりでやってくれ、だが三年はどうかな」
小原はしきりに三年のことを心配していた、いずれの中学校でも一番御(ぎょ)しがたいのは三年生である、一年二年はまだ子供らしい点がある、四年五年になると、そろそろ思慮分別ができる、ひとり三年は単純であるかわりに元気が溌剌(はつらつ)として常軌を逸する、しかも有名な木俣ライオンが牛耳をとっている、校長転任の披露があってからライオンは十ぴきのへびを町役場へ放そうと計画しているといううわさを聞いた、また校長を見送ってからその足で県庁や役場を襲おうという計画もあると聞いている。
小原にはかれらの気持ちは十分にわかっていた、かれらがそんなことをせずとも、小原自身がまっさきになって暴動を起こしたいのである、だがかれは校長の熱烈な演説と、そのいわんとしていわざる満腹の不平をしのんで、学生は学生らしくすべしという訓戒をたれた敬虔な態度を見ると、竹やりむしろ旗の暴動よりも、静粛の方がどれだけりっぱかしれないという溶々(ようよう)大海のごとき寛濶(かんかつ)な気持ちが全身にみなぎった。かれははじめて校長先生の偉大さがわかった。先生はなんの抵抗もせずにこの地方の教育界の将来のために喜んで十字架についたのである、先生は浦和の町人(まちびと)がかならずその不正不義を反省するときがくると自信しているのだ。
小原はこういうことを柳に語った。
「ねえきみ、ぼくにはよく先生の気持ちがわかった、それはね、ぼくが捕手(キャッチャ)をやってるからだよ、捕手(キャッチャ)は決して自分だけのことを考えちゃいかんのだ、全体のことを……みんなのことを第一に考えなけりゃならない、ちょうど校長は捕手(キャッチャ)のようなものだからね」
「そうかね」
柳はひどく感慨にうたれていった。そうして口の中で、「みんなのことみんなのこと」とくりかえした。
ふたりは停車場へゆくとはや東から西から南から北から見送りの生徒が三々五々集まりつつあった。昨日の申しあわせで生徒はことごとく和服で集まることになっていた、白がすりに小倉のはかま、手ぬぐいを左の腰にさげて、ほおばのげたをがらがら引きずるさまがめずらしいので、町の人々はなにごとがはじまったかとあやしんだ。
集まるものはことごとく少壮の士、ふきだしそうな血は全身におどっている、その欝勃(うつぼつ)たる客気はなにものかにふれると爆発する、しかも今や涙をもって慈父のごとく敬愛する校長とわかれんとするのである。危険は刻々にせまってくる。かれらはなにを見てもさわいだ。馬が荷車をひいて走ったといっては喝采し、おばあさんが転んだといっては喝采し、巡査が饅頭(まんじゅう)を食っているのを見ては喝采した。
小原はきわめて手際よくかれらを鎮撫(ちんぶ)した、かれは平素沈黙であるかわりにこういうときにはわれ鐘のような声で一同を制するのであった。野球試合のときどんな難戦におちいってもかれはマスクをぬぎ両手をあげて「しっかりやれよ」と叫ぶと、三軍の元気にわかに振粛(しんしゅく)するのであった。
かれは一同を広場の片側に整列させた、何人(なんびと)も彼の命にそむくものはなかった、がしかし人々の悲痛と憤怒はどうしてもおさえきることはできなかった。一年を制すれば二年が騒ぎだし、二年を制すればまた一年がくずれる、さすがに四年五年は粛然として涙をのんでいる。
これらの動揺の波濤(はとう)の中をくぐりぬけて小原は東西にかけずりまわった、かれは帽子をぬいでそれを目標にふりふり叫んだ。その単衣(ひとえ)は汗にびしょぬれていた、かれはひたいから雨のごとく伝わり落ちる汗を手ぬぐいで拭き拭きした。

このさわぎのうちに人々は一層不安の念を起こしたのは三年生の全部が見えないことであった。
「三年がこない」
口から口に伝わって人々はののしりたてた。
「三年のやつは不埓(ふらち)だ」
だがこのののしりはすぐ一種の反撥的な喝采とかわった。
「三年は全部結束してつぎの駅の蕨(わらび)で校長を見送るらしい」
「いや赤羽まで校長と同車する計画だ」
この報知はたしかに人々の胸をうった、とまた飛報がきた。
「カトレット先生が辞表をだしたそうだ、漢文の先生は校長を見送ってから辞職するそうだ」
このうわさはますます一同の神経をいらだたせた。
「学校を焼いてしまえ」
だれいうとなくこの声が非常な力をもって伝播(でんぱ)した。
「しずかにしたまえ、諸君、決して軽々しいことをしてくれるな」
小原は血眼になって叫びまわった、とこのとき三年生は調神社(つきのみやじんじゃ)に集まって何事かを計画しているといううわさがたった。
「いってみる」と小原はいった。「柳君、しばらくたのむぜ」
かれはげたをぬぎすててはだしになった、そうしてはかまを高くかかげて走りだした。
この熱烈な小原の誠意に何人(なんぴと)も感歎せぬものはなかった。
「おれもゆく」
「おれも……」
後藤という投手と浜井という三塁手はすぐにつづいた。
「学校の体面を思えばこそ小原も浜井も後藤もあのとおりに奔走してるんだ、諸君はどう思うか」
柳がこういったとき一同は沈黙した。
「ああありがたいものは先輩だ」と柳はつくづく感じた。
ものの二十分とたたぬうちに町のあなたにさっと土ほこりがたった。大通りの曲がり角から三年生の一隊があらわれた、かれらはちょうど送葬の人のごとくうちしおれてだまっていた、そのまっさきに木俣ライオンが長い旗ざおをになっていた、旗には「浦和に正義なし」と大書せるものがあったが、小原の強硬な忠告によってそれをまくことにした、かれらはいずれもいずれも暗涙にむせんで歯をくいしばっていた。
「たのむぞ木俣、なあおい」
小原はライオンの肩をたたいてしきりになだめると、木俣はもうねこのごとく柔順になって、おわりにはひとり群をはなれて人陰でないていた。
純粋無垢な鏡のごとき青年、澄徹(ちょうてつ)清水のごとき学生! それは神武以来任侠の熱血をもって名ある関東男児のとうとき伝統である。この伝統を無視して正義を迫害した政党者流に対する公憤は神のごとき学生の胸に勃発した。
かかるさわぎがあろうとは夢にも思わなかった久保井校長は、五人の子と夫人と、女中とそれから八十にあまるひとりの老母と共にあらわれた。
「やあ、これは……」
かれは両側に整列した生徒を見やって立ちどまった。生徒はひとりとして顔をあげ得なかった、水々とした黒い頭、生気のみなぎる首筋が、糸を引いたようにまっすぐにならぶ、そのわかやかな胸には万斛(ばんこく)の血が高波をおどらしている。
校長はほっとして立ちどまったまま動かない。かれはなにかいおうとしたが涙がのどにつまっていえなかった。かれは全校生徒がかくまで自分を慕ってくれるとは思わなかった。
生徒はやはりなんにもいわなかった。かれらはこの厳粛な刹那(せつな)において、校長と自分の霊魂がふれあったような気がした。
「ありがとう、どうもありがとう」
校長の口からこういう低い声がもれた。実際校長の心持ちは千万言を費やすよりもありがとうの一語につきているのであった、かれはいま九百の青少年から人間としてもっとも美しい精霊を感受することができたのであった。
かれはこういってから老母の手をとってなにやらささやいた。老母は雪のような白髪頭をまっすぐに起こして一同を見まわした、その気高くきざんだ顔のしわじわが波のようにふるえると、あわててハンケチをふところからだして顔にあてた。
こらえこらえた悲しみは大河の決するごとく場内にあふれだした。ライオンはおどりでて叫んだ。
「やれッ」
一同は校歌をうたいだした。
いつ先生が汽車に乗ったか、乗ったときにどんな風であったか、それをつまびらかに知ってるものはなかった、一同がプラットホームへ流れでたときにはや汽車が動きだした。
「久保井先生万歳」
熱狂の声が怒濤のごとく起こった。
窓から半身をだした校長の顔はわかやかに輝いた。かれは両手を高くあげて声のあらんかぎりに叫んだ。
「浦和中学バンザアイ」
「久保井先生バンザアイ」
もう汽車は見えなくなった、生徒はぞろりぞろりと力なく停車場をでた。
ちょうど汽車が動きだしたとき、ひとりの少年が大急ぎでやってきた、改札口が閉鎖されたのでかれはさくを乗り越えようとした。
「いけません」
駅員はかれをつきとばした。かれはよろよろと倒れそうになって泳ぐように五、六歩しざった、そうしてやっと壁に身体をもたらして呼吸(いき)をきらしながらだまった、その片手は繃帯(ほうたい)にまかれて首からつられてある。彼の胸があらわになったときその胸元もまた繃帯されてあるのが見えた。
かれはだまって便所と倉庫らしい建物のあいだへでた、そこには焼きくいの柵が結われてある、かれはそこに立って片ひじを柵においた、青黒い病人じみた顔は目ばかり光って見えた、帯がとけかけたのも、ぞうりのはなおが切れたのもいっさいかれは気がつかぬもののごとく汽車を見つめていた。
万歳万歳の声と共に校長の顔があらわれたときかれはじっと目を校長に据えた。かれの胸はふるえかれの口元は悲痛と悔恨にゆるみ、そうしてかれの目から大粒の涙がこぼれた。
かれは阪井巌である。
汽車が見えなくなったときかれはようやくさくをはなれて長い溜め息をついた。それからじっと大通りの方を見やった。そこには学校の友達が波のくずれるごとく、帰りゆく、阪井は顔をたれてしずかに歩いた。
とだれかの声がした。
「生蕃がいる」
「阪井のやつがきている」
少年達の目は一度に阪井にそそがれた、阪井は棒のごとく立ちすくんだ。
「やい生蕃」
まっさきにつめよったのはライオンであった。
「やい」
阪井はだまっている。
「きさまはなにしにきた」
「久保井先生に用事があってきたよ」と阪井はやはり顔もあげずにいった。
「きさまは久保井先生を学校からおいだしたんじゃないか、どの面さげてやってきたんだ」
「…………」
「おい、犬でも畜生でも恩は知ってるよ、おれはずいぶん不良だが校長先生の恩だけは知ってるんだ、きさまは先生をおいだした、犬畜生にもおとるやつだ」
「…………」
「きさまのようなやつはくたばってしまやがれ、きさまのようなやつがいるのは浦和の恥辱だぞ、どうだ諸君、こいつを打ち殺そうか」
「やっちまえやっちまえ」と声々が叫んだ。かれらはいま五分前に先生と悲しい別れをした、満々たる憤怒と悲痛はもらすこともできずに胸の中でうずまいている、なにかの刺激あれば爆発せずにいられないほど血潮がわき立っている。それらの炎々(えんえん)たる炎はすべて阪井の上に燃えうつった。
「やれやれ」
「制裁制裁」
激昂した声は刻一刻に猛烈になった。人々は潮のごとく阪井に向かって突進した。
「なぐってくれ!」
いままで罪人のごとく沈黙していた阪井はなんともいえぬ悲痛な顔をして、押しよせくる学友の前に決然と進みでた、そうしてぴたりと大地に座った。
「おれはあやまりにきたんだ、おれは先生にあやまりにきたんだ、おれはおまえ達に殺されれば本望だ、さあ殺してくれ、おれは……おれは……犬にちがいない、畜生にちがいない……」
繃帯を首からつった片手をそのままに、片手は大地について首をさしのべた、火事場のあとをそのままの髪の毛はところどころ焼けちぢれている、かれは眉毛一つも動かさない。
「あやまりにきたとぬかしやがる、弱いやつだ、さあ覚悟しろ」
ライオンはほうばのげたのまま、かれの眉間をはたとけった。阪井はぐっと頭をそらして倒れそうになったがじっと姿勢をもどして片手を大地からはなさない。
「畜生!」
「ばかやろう!」
「恩知らず」声々がわいた。
「なぐるのは手のけがれだ、つばをはきかけてやれ」
とだれかがいった。つばの雨がかれの顔となく首となく背中となく降りそそいだ。
「ばかやろう!」
最後に手塚がつばをはきかけた。
「手塚、おまえまでが」
巌はじっと手塚を見詰めたので手塚は人中へかくれた。
「さあ帰ろう」とライオンがいった。「最後にのぞんで足であいつの頭をなでてやろう、さあみんな一緒だぞ、一! 二! 三!」
げたの乱箭(らんせん)が飛ぶかと思う一刹那(せつな)。
「待ってくれ」
はらわたをえぐるような声と共に柳は巌の身体の上にかぶさった。
「待ってくれ、阪井は火傷(やけど)をしてるんだ、あやまりにきたものをなぐるって法があるか、火傷をしてるものを撲(なぐ)るって法があるか」

つるが病むときには友のつるが翼をひろげて五体を温めてやる、ちょうどそのように柳はどろやつばによごれた阪井の全身をその胸の下に包み、きっと顔をあげて瞋恚(しんい)に燃ゆる数十の目を見あげた、その目には友情の至誠が輝き、その口元にはおかすべからざる勇気があふれた。
「なぜ阪井をなぐるか、なぐったところで校長がふたたび帰ってきやしない、今日はぼくらが泣きたい日なんだ、先生にわかれて一日泣くべき日なんだ、人をなぐるべき日ではない、阪井だって……阪井だって……先生を見送りにきたんじゃないか、……諸君、帰ってくれたまえ、なあ阪井君も帰れよ、諸君帰ってくれ、阪井帰れよ、諸君……阪井……
柳はまっさおになって歎願するように一同にいった。もうだれも手をくだそうとするものもなかった。かれらは凱歌(がいか)をあげた、そうしてげたをひきずりひきずりがらがら引きあげた。
あとに残った柳は、屈辱と悲憤にむせんでいる阪井の頭や背中のどろやつばをふいてやった。
「さあいこう」
阪井はだまっている。
「どこかいたいか、えっ? 歩けないか」
阪井はやはりだまっている。
「さあいこう、ねえ、みっともないじゃないか、車でも呼ぼうか」
手を取ってたすけ起こそうとする柳の手をぐっとにぎって阪井は目をかっとあいた。
「柳、ゆるしてくれ」
「なにをいうんだ、過去のことはおたがいにわすれよう」
「おれはおまえに悪いことばかりした、それだのにおまえは二度ともおれを救うてくれた」
「そんなことはどうでもいいよ、さあいこう」
柳は阪井を強(し)いて立たした、ふたりはだまって裏通りへでた。
「おれはなあ柳」
阪井は感慨に堪えぬもののごとくいった。
「おれは今日から生まれかわるんだぞ」
「どうしてだ」
「おれが今までよいと思っていたことはすべて悪いことなんだ、それがわかったよ」
「それはどういうことだ」
「どういうことっておまえ、すべてだよ、すべてだ、なにもかもおれは悪いことをして悪いと思わなかったのだ、親父はおれになんでも学校で一番強い人間になれというだろう、だからおれは喧嘩をした、活動を見ると人を斬ったり賭博をしたりするのが侠客だという人だ、だからおれはそれをまねて見たんだ、だがそれは間違ってるね、悪いことをして人よりえらくなろうというのは泥棒して金持ちになろうとするのと同じものだね、そう思わないか」
「そうだとも」
「だからさ……」
阪井はこういったとき、傷がいたむので眉をひそめた。
「君の家まで送ってゆこう」と柳はいった。
「かまわない、もう少し歩こう」
阪井はふたたびなにかいいつづけようとしたが急に口をつぐんで悲しそうな顔をした。
「車に乗れよ」
「何でもないよ……ねえ柳、ぼくはおまえにききたいことがあるんだが」
「なんだ」
「一年のとき、重盛(しげもり)の諫言(かんげん)を読んだね」
「ああ、忠孝両道のところだろう」
「うん、君に忠ならんとすれば親に孝ならず、はかわいそうだね」
「ああ」
「清盛(きよもり)は悪いやつだね」
「ああ」
「重盛がいくらいさめても清盛が改心しなかったのだね」
「ああ」
「それで重盛はどうしたろう」
「熊野の神様に死を祈ったじゃないか」
「そうだ、死を祈った、なぜ死のうとしたんだろう」
「忠孝両道をまっとうできないからさ」
「困ったから死のうというんだね」
「ああ」
「ではおまえ」
阪井の語気はあらかった。
「困るときに死んでしまえばいいのかえ」
「それが問題だよ」
「なにが?」
「自分だけ楽をすればあとはどうなってもかまわないというのは卑怯だからね」
「じゃ重盛は卑怯かえ」
「理論からいうと、そうなるよ、しかし重盛だってよくよく考えたろうと思うよ」
「そうかね」
阪井は長大息をした。かれはだまって歩きつづけた。そうしてやがてしずかにいった。
「清盛が改心するまで重盛が生きていなければならなかったね」
「さあぼくにはわからないが」
「ぼくにはわかってるよ、わかってるとも、そうでなかったら無責任だ」
柳は阪井を家まで送ってわが家へ帰ってくると途中で手塚に逢った。
「やあ、いま、きみのところへいこうと思ってきたんだよ」
「そうか」
柳は手塚の行為について少なからぬ悪感をもっていたのできわめて冷淡に答えた。
「生蕃はどうした」
「帰ったよ」
「きゃつ、ぼくのことをおこっていたろう」
「どうだか知らんよ、だがおこっているだろうさ、いままできみと阪井とは一番親しかったんだろう、それをきみがみんなと一緒になってつばをはきかけたんだからね」
「だってあいつは悪徒だからさ」
「きみほど悪徒ではないよ」
柳は思わずこういった。手塚はさっと顔をあからめたがそれは憤慨のためではなかった。かれは柳に肚(はら)の中を見みすかされたのがはずかしかったのである。だがこのくらいの侮辱はかれに取っては耳なれている。かれはぬすむように柳の顔を見やって、
「きみ、活動へゆかないか」
「いやだ」
「クララ・キンポールヤングすてきだぜ」
「それはなんだ、西洋のこじきか」
「ははははきみはクラちゃんを知らないのかえ」
「知らないよ」
「話せねえな、一遍(ぺん)見たまえ、ぼくがおごるから」
「活動というものはね、きみのようなやつが見て喜ぶものだよ」
さすがに手塚は目をぱちくりさせて言葉がでなかった。だがこのくらいのことにひるむような手塚ではない。かれはこびるような目をむけていった。
「きみ、ぼくのカナリアが子をかえしたからあげようね」
「いらないよ」
「じゃね、きみは犬を好きだろう、ぼくのポインターをあげようね」
「ぼくの家にもポインターがいるよ」
「そうだね」
手塚はひどく当惑してだまったが、もうこらえきれずにいった。
「きみは生蕃が好きになったのか」
「もとから好きだよ」
「だってあいつはきみを負傷させたじゃないか」
「喧嘩はおたがいだ、生蕃は男らしいところがあるよ」
「じゃ失敬」
「失敬」二人は冷然とわかれた。
光一に送られた巌は家へはいるやいなやわが室(へや)へころがりこんだ。いままでこらえこらえた腹だたしさと悲しさと全身のいたみが、急にひしひしとせまってくる。かれは畳にころりと倒れたまま天井を見つめて深い考えにしずんだ。
かれの頭の中には停車場前において学友に打たれなぐられつばをはきかけられた光景が浮かんだ。げたで踏まれたひたいのこぶがしくしく痛みだす。がかれはそれよりも痛いのは胸の底を刺されるような大なる傷であった。
父の不正! 校長の転任! 学友の反感! 数えきたればすべての非はわれにある。
「巌、どこへいってたの?」
母は心配そうにかれの室(へや)をのぞいた。巌は答えなかった。
「おなかがすいたろう。ご飯を食べない?」
「ほしくありません」
「火傷(やけど)がなおらないうちに外へ出歩いてはいけないよ、おや、ひたいをどうしたんです」
「なんでもありません」
「また喧嘩かえ」
「あちらへいっててください」と巌はかみつくようにいった。
「なにをそんなにおこってるんです」
母はきっと目をすえた。その目には不安の色が浮かび、口元には慈愛が満ちている。
「なんでもいいです」
「なにか気にさわることがあるならおいいなさい」
「あちらへいってくださいというに」
母はしおしおとでていった。巌は起きあがって母の後ろ姿を見やった。なんともいいようのない悲しみが一ぱいになる。お母さんにはあんな乱暴な言葉を使うんじゃなかったという後悔がむらむらとでてくる。
「どうしようか」
実際かれは進退にまようた。いままで神のごとく尊敬していた父は悪人なのだ。この失望はかれの単純な自尊心を谷底へ突き落としてしまった。かれにはまったく光がなくなった。
死んでしまおうか。
いや! 平重盛はばかだ。
二つの心持ちが惑乱して脳の底が重たくだるくなった。かれはじっと机の上を見た。そこに友達から借りた漢文の本がひらいたまま載っている。
「周処三害(しゅうしょさんがい)」
支那に周処という不良少年があった。喧嘩はする。強奪はする。村の者をいじめる、田畑をあらす、どうもこうもしようのない悪者であった。あるときかれの母が大変ふさぎこんでいるのを見てかれはこうきいた。
「お母さんなにかご心配があるのですか」
「ああ、私はもう心配で死にそうだ」と母がいった。
「なにがそんなにご心配なのですか」
「この村に三害といって三つの害物がある。そのために私も村の人も毎日毎日心配している」
「三害とは何ですか」
「南山(なんざん)に白額(はくがく)のとらが出でて村の人をくらう、長橋(ちょうきょう)の下に赤竜(せきりゅう)がでて村の人をくらう、いま一つは……」
こういって母は周処の顔を見やった。
「いま一つはなんですか」
「おまえだ、おまえがわるいことをして村の害をなす、とらとりゅうとおまえがこの村の三害だ」
この話を聞いた周処は俄然(がぜん)としてさとった。
「お母さん、ご安心なさい、ぼくは三害をのぞきましょう」
周処は南山へ行って白虎を殺し、長橋へいって赤竜を殺し、自分は品行を正しくして村のために善事をつくした。ここにおいてこの村は太平和楽になった。
巌は読むともなしにそれを読んだ。突然かれの頭に透明な光がさしこんだ。かれは呼吸(いき)もつかずにもう一度読んだ。
「三害を除こう、おれは男だ」かれはこう叫んだ。
「おれに悪いところがあるならおれが改めればいい、お父様に悪いところがあるならおれがいさめて改めさせればいい、ふたりが善人になればこの町はよくなるのだ、南山にとらをうちにゆく必要もなければ長橋にりゅうをほふりにゆく必要もない、第一の害はおれだ、おれを改めて父を改める、それでいいのだ」
かれは立って室(へや)を一周した、得もいえぬ勇気は全身にみなぎって歓喜の声をあげて高く叫びたくなった。
かれは窓を開いて外を見やった、すずしい風が庭の若葉をふいてすだれがさらさらと動いた、木々の緑はめざめるようにあざやかである。
「豆腐イ……」
らっぱの音と交代にチビ公の声が聞こえる。
「チビ公だ」かれは伸びあがってへいの外を見やった。
「とうふい――」
暑い日光をものともせず、大きなおけをにのうてゆくチビ公のすげ笠がわずかに見える。
「おれはあいつにあやまらなきゃならない」巌は脱兎(だっと)のごとくはだしのままで外へでた。そうして突然チビ公の前に立ちふさがった。
「青木! おい、堪忍してくれ、なあおいおれは悪かった、おれは今日から三害を除くんだ」







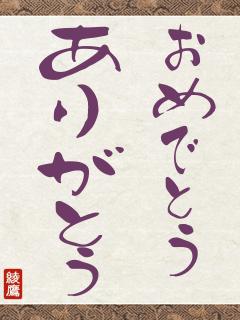











この記事への質問・一言コメントをどうぞ AIコースケと議論しよう!
回答には文字数制限があるため、制限を超えると途中で打ち切られることがあります。