公邸の裏にまわると、作戦本部といわれるテントがあり、大きなテーブルを中にして、十人ほどの警官が鋭い目で何台もの電話からはいる情報を聞いていた。
その時、私の目にちらりと赤いものがうつった。木立の向こうに配置されていたのは一台の消防自動車である。水をはった真新しいバケツが四個、窓の下におかれていた。そのブリキの光が妙に印象的であった。不安なニュースは、事前に用意された消防自動車から生じたものではないだろうか。
ワレ友ヲウシナウ
「1960.6.15. ワレ友ヲウシナウ」
樺美智子さんが殺された国会南通用門の門柱に、この文句が石でこすって書かれていた。ここにも二寸五分角の丸太が縦横に組み合わされ、その丸太に有刺鉄線がまきつけられている。有刺鉄線の上に、だれがそなえたのか、たくさんの花束がむざんにつき刺してある。あたかも、血をながした幾人かの学友を象徴するかのように、その花束の花は、一様にしおれて、首うなだれている。通用門の前の焼香台には、ひきもきらぬデモの人々が焼香と黙祷を捧げて、立ち去ろうとしない。「ご焼香のすんだ方は、あとの人に道をあけてください」と整理員がメガホンで叫ぶ。
すでに国会周辺はもちろん、チャベルセンター前、人事院わきまで、Y字形の道にはデモ隊の人々がぎっしりと押しかけて身動きもできない。
林立するプラカードと赤旗をぬって、ライトブルーの旗を先頭に午後五時、喪章をつけた東大合同慰霊祭参加者の行進が国会正門前を通って南通用門前に着く。約三百人の東大教授団、そのあとに約七千人の学生、そして一般都民が続いている。一人一人が一本ずつのカーネーションやマーガレットの花を手にしている。手から手へ、二本、三本と集められて前に送られる花は、次第に大きな花束となって、焼香台の前につみ上げられる。社会党議員にまもられた樺先生夫妻が、すずらんの花束を有刺鉄線につきさして黙藤をささげる。わっとカメラマンが夫妻をとりまく。私のところからは、もう夫妻の姿は見えない。身動きのできない学生たちはその場にすわりこみをはじめる。
官邸前は、新聞社、ラジオ、テレビ会社の車が一列に並び、各社のテレビカメラが、ものものしくやぐらの上にのっている。官邸の門柱やヘイの上には、鉄カブト姿のカメラマンがひしめいている。四機のヘリコブターは、交互に音高く国会の頭上をとんで離れようとはしない。屋台のうどんや、ジュース、あんぱん、焼きいもなどを売る、その日ぐらしの商人が右往左往している。すわりこみのデモ隊の間をぬって、アイスクリーム屋が「安保反対、えー、アイス」と、アイスクリームを売って歩く。なんという貧しい国だろう、貧しい国のあまりにも貧しい政治がうんだ、これが唯一の笑いであった。
うつぼつたる怒り
「岸君、再び戦場で会おうぜ」
次第にせまってくる夕やみの中に、ひときわ高く一枚のプラカードがかかげられている。あと五時間。
国の長い運命を決定する午前0時が刻々と近づいてくる。不思議なことに、五月十九日以来一カ月の間、常に有刺鉄線の向こうに腕をくんでいた警官隊の隊列は、今日は見えない。警官隊は建物のかげにひっそりと集まって立っている。デモ隊を刺激するなという配慮であろうか。あるいは、やるならやってみろ、という高姿勢なのか。
そのころ、また一つ不安なニュースが口から口へと伝えられた。市ケ谷、習志野、宇都宮、練罵の自衛隊員に外出禁止令が出たというのである。官邸内では閣僚会議が開かれ、白衛隊の“治安出動”が話題になっているというのだ。デモ隊の“院内突入”や“焼き打ち”にそなえ、議員会館では、“重要書類”を運び出したとか。国会議事堂内は鉄の防火トビラがおろされ、官邸内では消火栓につないだホースが、赤いジュウタンの上をはい、いつでも放水できるようになっているという。
配慮か挑発か、それを断定できるものはだれ一人としていない。空前の大衆動員の成果を決定するものは、個人の責任と良識の上にかかっていた。
学生も必死であった。教授も必死であった。各大学の教授団が、すわりこみの学生たちの間をぬって説得に奔走する。「国会や官邸へ乱入しても、安保阻止にもならなければ、岸を退陣させることもできない。それはむしろ右翼の登場をうながすだけだ。秩序正しく行動してほしい」と。
はじめて国会周辺のすさまじい光景を目にした教授の中には、うわずった声で学生たちに呼びかける姿もあった。はた目にはコッケイでも、しかし学生と教師の間には、人間として通い合う血のあたたかさがのこされている。学生たちの笑いは、教場での笑いのように、明るく余裕があった。
ついに午前0時
一方、三宅坂の国立劇場建設予定地を埋めつくした、公労協、民間労組は、デモ指揮班の「流れ解散」に反対して、一時は険悪な様相を呈した。くらやみの中に、うつぼつたる怒りとエネルギーがみなぎっていた。それはもはや、エネルギーという物理的な力ではなく、恐ろしいほど緊迫した精神を感じさせる。
「流れ解散絶対反対!」「すわり込め!」とヤミの中で叫ぷ一つ一つの声は、アジや、野次などというものではない。それは心の叫びを伝えている。指揮班の命を待たずに、すでに先頭は出発した。私は不安になった。何事も起こらなければよいが。しかし、その不安を消してくれたものは、国会正門前いっぱいにすわりこんだ高校生グループと、自発的にすわりこんだ一般都民の姿であった。「ふたたび流血をくりかえさないために」私たちはここにすわった、と紅顔の少年はいう。まだ中学生だという娘をつれた一人の母は、「樺美智子さんの死が他人事だと思えないものですから」という。
三十万人余にのぽる秩序整然たるデモは、このようにして行なわれた。「ご苦労さまです」「ご苦労さまです」とマイクを通じてよびかける社会党員のよびかけは、もはや空虚なものになっていた。国民は自分たちのために戦っているのだ。一社会党や、共産党のために戦っているのでは、決してない。自分の生活を守るために、自分の足をふみ出したのだ。
そうした国民の不安をよそに、時は一分一分と過ぎてゆく。
そして午前0時をむかえた。岸首相は、三十万、いや、二千万人近い人々の心の叫びをついに聞こうともしなかった。
携帯ラジオから流れる「新安保自然承認」のニュースは、黒雲のように、人々の頭上をおおった。
「もう一押しだったのに」とだれかがつぷやいた。はたしてそうだろうか。私たちは人間ではないものと戦っていたのではないだろうか。これほどまでの反対にあいながら、岸首相の手にのこったものは一体なんであろう。どのような約束手形が彼の手におちてくるというのだろう。私は暗い空にむかって、ふるえるような思いで立っていた。
午前三時、私は家路についた。J紙の山本満氏からの手紙が一通、机の上で私を待っていてくれた。私はその手紙を読んだ。はじめて暖かいものが私の胸にこみ上げてきた。その一節をここにのせさせていただく。
まあたらしい生命
――六月十五日夜、若ものたちの群れのなかにいて、わたしは、「子供の徴兵検査の日に」という金子光晴の戦争中の詩を、しきりと思いおこしていた。「けずりたての板のようなまあたらしい裸で立っている息子の若いいのちを、「喰い入るように眺め」ながら、詩人は、のしかかる権力の暴虐に憎しみをたぎらす。
その日、国会におしかけ、そして流血の犠牲をうけた学生たちは、みんな「けずりたての板のような」まっすぐで、感動的な若ものたちであった。未来をはらんで誇りを戦いとろうとする、「まあたらしい」若ものたちであった。“エネルギー”などという物理的な力ではない、ひとりひとりが限りなくいとおしまれなけれぱならない若ものたちであった。
かれらの翹望(ぎょうぼう)する未来を、失礼千万にも権力によって奪いとろうとするものとは、用いられる武器が鉄の警棒であろうと、あるいは「理論」と称する衰弱した観念であろうと、わたしたちは、若い友人らと、肩を組んで戦おう。そして、戦いに傷ついた友には、かれがふたたび「けずりたての板のよう」に大地にしっかり立てるよう、父親や兄のごとくに助けよう。そのような行動を通じてわたしたちは、さいごまで若ものたちの誠実な友人でありつづけることを、かれらの「けずりたての板のようなまあたらしい」生命を熱烈に愛しつづけることを、かれらに保証し、そしてそれを、わたくしたち自身にもたしかめあうことができるだろう。犠牲者への救援を組織しよう。そして、たがいに裏切ることのない友情のしるしを、結び交わそう――。
ただ平和な生活を
最後にお断わりしておく。私は反米でもなければ、反ソでもない。とりわけ親米でもないが、親ソでもない。私が熱愛するものは、平和な私自身の生活であり、この私の生活をささえてくれる美しい社会である。
そしてまた、私は日本人であることの誇りと、日本人であることの喜びを、私個人の生活の中に反映してくれる、よりよき政治を念願する一日本人である。なぜこのようなわかりきった断わり書きを書くかといえば、過日私はある知人から、「お前はいつから敵にまわったんだ」と詰問されたからである。(了)
1925(大正14)年、神戸市生まれ。岩手医学専門学校中退。48年、松竹入社、助監督となる。脚本家デビューが先で、オリジナル第一作は54年「美わしき歳月」(小林正樹監督)。監督デビューは61年、脚本作品は映画・テレビ・舞台と1000本に近い。妻は女優の故・高峰秀子、養女は文筆家・斎藤明美。映画賞は毎日映画コンクール脚本賞、ブルー・リボン脚本賞など多数。勲四等旭日小綬章受章。















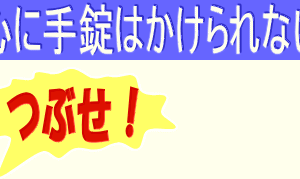


















歴史の瞬間に立って-60年安保闘争の記録より https://t.co/I74XV40ZTE @kousuke431さんから